(注意)「R落穂拾い」も「R関係文献紹介」も同様ですが,引用対象の文献は一部しか読んでないものが多いことをお断りしておきます。即ち,是非全部を読みたいと思った文献以外は,引用箇所の前後(と,まえがき・序文・あとがき+引用文が含まれている章)しか読んでいないものが多くあります。従って,付加する個人的なコメントは,そのような状況でも言うことができることや感想を述べることに限定されます。内容を的確につかみたい方は,興味を抱いた図書についてはご自分でお読みになることを勧めします。(M)
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
As I have grown older,I have realized more and more the importance my grandmother had in moulding my outlook on life. Her fearlessness,her public spirit,her contempt for convention,and her indeference to the opinion of the majority have always seemed good to me and have impressed themselves upon me as worthy of imitation.She gave me a Bible with her favourite texts written on the flyleaf.Amang these was‘Thou Shalt not follow a multiude to do evil.' Her emphasis upon this text led me in later life to be not afraid of belonging to small minorities.
* 注:'Amang' は 'Among' の誤植。'flyleaf' は原著(『ラッセル自伝』では 'fly-leaf'.
<斉藤雅久(訳)>
歳を取るにつれ,自分の人生観を形成するに際し祖母がいかほど重要であったかを益々痛感しております。祖母の勇気,他人を思いやる心,因習に対する軽蔑,多数派の意見に対する無関心は私にはいつも立派に見えた,そして見習うに値すると私の心に深く焼き付いています。祖母は私に聖書を与えてくれました,その見返しに祖母のお気に入りの聖句が記されていました。その中の一つに「汝,衆二倣イテ悪ヲ為スナカレ」(出典;『旧約聖書』「出エジプト記」23章2節)というのがあった。この聖句を祖母が重視していたおかげで,後年私は少数派に属することが怖くなくなった。
|
|
But in retrospect, as I have grown older, I have realized more and more the importance she had in moulding my outlook on life. Her fearlessness, her public spirit, her contempt for convention, and her indifference to the opinion of the majority have always seemed good to me and have impressed themselves upon me as worthy of imitation. She gave me a Bible with her favourite texts written on the fly-leaf. Among these was "Thou shalt not follow a multitude to do evil." Her emphasis upon this text led me in later life to be not afraid of belonging to small minorities.ラッセルが,最初雑誌に連載したものを,少し字句を追加・修正して『自伝』に取り込んだ,と考えるのが一番あたっているようです。しかし,そうであれば,その初出の掲載誌をあげてもらいたかったと思います。(斉藤氏は,孫引きしたために,どの雑誌に掲載されたか知らなかった可能性もありますが・・・。)
<松下(訳)>
しかし振り返ってみると,成長するにつれ,私の人生観を形作る上で祖母がいかに重要であったか,しだいに認識するようになった。祖母の恐れを知らない勇気,公共心,因襲に対する軽蔑,多数派の意見に対する無関心は,いつも私には善いことだと思われたし,模倣する価値のあることだと強く印象づけられた。祖母は,見返しの遊び紙(白紙)に祖母のお気に入りの文句が書かれている聖書を私にくれた。その中に次の文句があった。
「汝,群衆に付和雷同し,悪を為すなかれ」
祖母がこの聖句を強調してくれたことは,後になって,私がごく小さなマイノリティに属することを恐れなくさせてくれた。
(p.4) (トルストイとラッセルは)一見して,同じ平和主義者であるが,ずいぶんと対照的な一生を送った二人のように見えるかもしれない。一方のトルストイは内省的で,戦争と平和の問題を絶えず実存の問題として引き受け,自分の信仰の純粋さに専心する一生を過ごした。他方のラッセルは外交的で,同時代の政治・社会問題についていち早く発言し,世界中を飛び回って啓蒙活動に邁進する一生を過ごした。・・・。ラッセルの平和活動(特に第一次世界大戦時の反戦活動及びそのために入獄したこと)は有名でそれについて触れる方はかなりいます。また,1954年3月のビキニ水爆実験以降のラッセルの反核運動も有名で,1960年代には多くの日本国民の耳目をとらえることになり,1965年には日本バートランド・ラッセル協会も設立されました。当時,大学入試の英語の読解問題にラッセルやモームが突出して多く出題されていたこともあり,日本の多くの人がラッセルの名前を知っていました。しかし,その後,入試問題に出されることも少なくなり,ラッセル協会も自然消滅し,しだいにラッセルのことが話題になることが少なくなりました。
そのような状況が続きましたが,最近では世界史の教科書の大部分にラッセル=アインシュタイン宣言(1955年7月9日発表)に関する記述が載るようになりましたので,若い人については,ラッセルの名前を知っている人が増えてきていることと思われます。
松元雅和氏は,本書(『平和主義とは何か』)において,感情的な反応を引き起こし易い「戦争と平和の問題」について,平和主義(pacifism)に焦点をあて,論理的にわかりやすく整理して説明されています。特に,「従来の平和主義をめぐる議論の混乱の多くは,絶対平和主義(pacifism )と平和優先主義(pacifisism)との混同が原因である」との指摘は同感です。ラッセルの平和運動の批判の一つのタイプは,ラッセルに「平和主義者」(つまり平和優先主義ではなく,「絶対」平和主義者のレッテルを貼ったうえで,ラッセルは第一次世界大戦は反対したが第二次世界大戦の時は「変節」して賛成に回った!」というものです。
引用はラッセルの著書及び発言からのものが一番多く,ラッセルの平和思想 理解にも役立ちます。ただし,一般向けの本ですので,ラッセルが設立したラッセル平和財団及び太平洋平和財団のことや,ラッセルの平和活動において重要なラッセル法廷などについては一切ふれていません。その意味では,ラッセルの平和思想・平和活動の全体像をつかむことはできませんが,今後,そういったことに取り組む著作(研究者)がでてくることを期待します。
安心してお薦めできる著作です。(M)
(p.5) 本章では,こうした多様な姿かたちをとりうる平和主義の輪郭を明確にするため,そのなかに幾つかの区別を立てていく。実のところ,平和主義には様々なバリエーションがありうるし,それに応じて戦争に対する態度も若干違ってくる。本章でははじめに平和主義の定義を概観したうえで,次にそのバリエーションを,強度と範囲という二つの観点から分類する。最後に,本書全体の分析視角として「絶対平和主義」と「平和優先主義」の区別を紹介したい。
(p.6)・・・。 オックスフォード英語辞典を引くと,平和主義(pacifism)の項目には次のような説明がある。--「平和的手段を,実行可能でかつ望ましい戦争の代替物とするという信念や主張のこと。紛争解決手段として,戦争やあらゆる形態の暴力行為を拒絶する一群の教説(の信奉や主張)」。
ここでいう「平和的手段」とは,要するに非暴力手段のことである。言葉による問題解決は,いかなる場合であれ腕力による問題解決よりも'優先'されるべきである。たとえそのことで,問題解決の可能性が遠ざかり,あるいは自分にとって不利の結果に終わるとしても,非暴力を貫くことには,それだけの価値と理由があるのだ。
(p.25) ところで,以上の分類をあらためて眺めてみると,そのなかに大別して二種類の傾向を見てとることができるかもしれない。一方を体現するのはトルストイで,より実存的・宗教的・革命的な性質をもっているのに対して,他方を体現するのはラッセルで,より実利的・世俗的・改良的な性質をもっている。本章では最後に,これら二つを「絶対平和主義」と「平和優先主義」と呼び分け,次章以降で平和主義の妥当性を検討する際の手がかりとしたい。
絶対平和主義とそのルーツ
絶対平和主義と平和優先主義の区別は,一部の類似した分類を除き(久野収「二つの平和主義」),これまでわが国ではあまり一般化していないが,現在の平和主義研究でしばしば参照される重要なカテゴリーである。私見では,従来の平和主義をめぐる議論の混乱の多くは,これら二つが混同されることから生じていると思う。さらに,これは決して便宜的な区別ではない。発展史的に見れば,平和主義の多様な思想や実践のあいだには,以上の区別に基づく比較的はっきりとした一線を引くことができるのである。
・・・。
(p.84) 実際のところ,(第一次世界大戦下英国の)民主管理同盟は熱狂的に戦争へと突き進むイギリス国民を止めることはできなかった。こうした反省をもとに,ラッセルは戦時中から,人間行動の動因である「衝動」を無下に否定したり,その噴出に蓋をしたりすることなく,むしろその動力を正しい方向へと向けることが重要なのだと考えるようになる(「社会改造の諸原理」)。中立冷静に理を説くことだけが,帰結主義的にもっとも効果的なわけではない。人間がときに陥りがちな非合理性をどのように改善するかは,現在の功利主義論でも熱心に議論されている(児玉聡『功利主義入門』第五章)。
★後は,購入するか図書館で借りるかしてお読みください。
(p.iv~v: はじめに) ・・・。しかし,話がここまで(「この世に生じることには必ず時間的に先立つ原因がある,という命題」まで)進んでくると,多くの人がそう簡単に首を縦に振らないだろう。・・・。言うまでもなく,私たち(人間)の自由の問題が絡んでくるからである。
宇宙の始まりから,すべてが決まってしまっているのであれば,私たちが自由である,などということはおよそありえないこととなってしまう。・・・そうだとすれば,犯罪などというものはおよそ存在しないことになる。・・・。
しかし,むろんそういうことにはならない。人の場合は,こうした(そうした)ことをすれば,それはまちがいなく犯罪である(松下注:犯罪であるとされる)。・・・。
だが,そうだとすれば,この上なく明瞭なのである。すなわち,すべてが,宇宙の始まりから決まってしまっている,などということはないのである。・・・。
では,それは(松下注:人間の自由/因果の連鎖が存在していないところなどは)どこにあるのだろうか?
(p.vii) ・・・。こうした冒頭からの論究を支える哲学的議論の一つは,1912年のバートランド・ラッセルの論考("On the notion of cause")である。そして,もう一つが,ヘーゲルの『論理学』に展開された様相論もしくは必然性論である。(松下注:ちなみに,高山守氏の『理想』n.679(2007年)掲載の論考に「ラッセルの因果論とヘーゲル」があります。)
ラッセルには,随時論究するが,ヘーゲルの必然性論は,第5章で取り上げ,そこで,ヘーゲルが,これまでの私たちの議論をいかに先取りしていたかを見る。・・・。
本書は,こうして,ラッセルおよびヘーゲルに依拠しつつ,徹底して因果の想念を乗り越え,真に,自由と理由の世界へと至ろうとするものである。
[pp.35-41: 第1章 原因は結果に先行するのか/第4節 原因と結果は同時である--カントとラッセル]
[pp.36-37:原因と結果との間に時間経過は存在しない--ラッセル(1)]
(p.36) ところで,原因・結果との間に時間経過ははありえない,という議論を現代において正面から論じたのは,1912年におけるバートランド・ラッセルである。ラッセルは,まずはこう論じる。哲学者たちが,原因と結果とを時間的に連続したものと考えているということは疑いえない。しかし,・・・,そういことはありえないのである。もし,そうだとすると,無限小の時間間隔というものは存在しないのだから,原因と結果との間には,ある有限な時間経過 t (τ タウ) があるのでなけらばならない。しかし,このことは即座に克服不可能な問題を引き起こす。というのも,我々が間隔 t (τ タウ)をどんなに短くしようとも,その間に期待された結果を阻む何事かが起こりうるからである。(Bertrand Russell, "On the notion of cause" in The Collected Papers of Bertrand Russell, v.6(1992), p.197.)・・・。
要するに,(ラッセルは)原因と結果とは,同時でなければならない,というのである。 [pp.38-41:そもそも因果は存在しない--ラッセル(2)]
(p.38) だが,ラッセルはここで,さらに議論を一歩進めている。というのも,このようにして,原因と結果とが本来同時のものであるとするならば,それらはそもそも原因・結果ではないのではないか,因果関係だと哲学者たちに,あるいは,一般に思われているものは,実は因果関係ではないのではないか,と論じるからである。
哲学者たちが基本的であると考えていることは,ある出来事Aが,別の出来事Bを「引き起こす」[AがBの原因である]ということなのだが,このような事例とは,本当はただ,実際的な観点に従って隔離されたシステムの,もっとも単純化された実例であるにすぎない。(前出 p.204)・・・。
少々分かりにくいが,こういうことである。すなわち,物が落ちるということは,私たちの実際的な観点--つまり,目下の場合,日常的な関心--のもとで捉えられた一つの出来事である。この出来事が,他のさまざまな物事から分離されて,いわば純粋にこの出来事として取り出され,隔離される。つまり,たとえば,空気の抵抗とか,途中で何かがぶつかるとか,また手を出して落ちているものをつかんでしまうとかいうことを全面的に排除して,物が落ちるというこの一事が隔離される。するとここに物の落下に関する「等式」-- S = (1/2)gt2 (落下の法則)--が成立する。これが,ラッセルのいう「実際的な観点に従って隔離されたシステム」である。・・・。
[pp.45-129: 第2章 原因・結果とは何なのか--ダメット,マッキー,黒田亘,ハンソンへの批判的検討]
(p.45) 自然科学に,原因・結果の概念は不要である,とはよく言われることである。そこには科学法則があるのみで,因果関係なるものは存在しない。あるいは,機能しないと。ラッセルの議論も,たしかにそのような議論であると見ることはできる。しかし,問題は,単に自然科学といった限定された領域に関わるものではない。そうではなく,総じて,はたして因果関係なるものは存在するのかどうか,機能するのかどうかということである。ラッセルは,そうしたものは存在しない,機能しない,と論じるわけである。
[pp.131-160: 第3章 因果関係から理由関係へ --理由論ならびにライブニッツとの対比]
[pp.138-140:因果関係から理由関係へ(1) --ラッセルをめぐって]
(p.138)・・・。
こうしたラッセルの議論を振り返るならば,それはまさに,因果関係から理由関係への転換の主張である,ということができるだろう。重力の存在は,物が落下することの原因ではない。両者は決して因果関係においてあるのではなく,一体となって,「隔離されたシステム」,すなちち,「等式」・「関数」( S = (1/2)gt2)を形作る,とラッセルは言う。だがまた,このシステムとは,物が落下するということ,あるいは,どれだけ落下するのかということについての十分な理由にほかならないだろう。・・・。
★これでやめておきます。あとは現物図書をお読みください。
本書((社)日本図書館協会 選定図書!!)はラッセルを理解するための最重要文献の一つですが,大部なうえに高価なため,あまり読まれないことが想像されます。また,都道府県立レベルの大きな「公立」図書館ならば購入すると思われますが,地域の「公共」図書館では購入しそうもありません(購入するとしても大都市の中央館くらいでしょうか)。
そこで,以下,「恣意的」かつ「気ままな」引用となってしまいますが,少し抜書きしてみます。大部なため,引用は(「序」のところ以外は,)原則として各章2,3箇所に限定します(ただし,引用箇所の変更や修正は必要に応じ適宜行います)。
訳者や出版社に断りもなく長い引用をすることはあまりよろしくないですが,販売促進の一助ともなりますので,ご寛容いただければ有難く存じます。
購入して読みたいと思っていただける人が少しでも多く生まれれば幸いです。(松下)
序
(p.13) オットリンのエリザベス朝的雰囲気に最初に気づいたのは D. H. ロレンスだった。女王と貴婦人,このかくしゃくとした二人の老婦人のイメージに共通するのは,みごとなまでの不屈の精神と生命への愛である。(松下注:オットリンは長い間持病に悩まされたので,「かくしゃくとした」というのは肉体的なものと言うよりも精神的なものだといったほうがよいであろう。)そうしたオットリンの資質こそ,著者として私(シーモア)が本書によって伝えようとしたことであり,「破天荒な生涯」もそのための副題だった。けっして彼女が贅沢三昧の暮らしを好んだという意味ではない。オットリンが精一杯生き,挫折から学び,どんなに傷ついても体験ひとつひとつを新たな冒険として,真っ向から取り組んで生きた人間だった。・・・。
(p.17) オットリンとブルームズベリ(グループ)との結びつきは,ようやく一章を満たす程度の関係だろうが,それに対して,バートランド・ラッセルとの関係はそれだけで一書を成すに十分である。二〇世紀の名だたる恋愛事件の中で,この二人の場合は最も激しい恋愛のひとつであった。しかも,オットリンの生涯でいかなる人間関係よりも最重要な関係だった。今回,筆者がオットリンの私文書を入手できたことにより明らかにしえたことは,既発表のオットリンに関する回想録は,彼女のラッセルに対する感情の真実を読者から故意に逸らす(そらす)ものであったということだった。同時に筆者は彼女がラッセルの人生で果たした決定的な役割をこれまでになく鮮明にすることができた。ラッセルがオットリンに宛てた二千通以上の書簡は,彼の書いたものとしては最も微笑ましくかつ魅力に富む。・・・。(p.18)オットリンは,死ぬ四年前のことだが,ラッセルを人生でただ一人の精神的に絶対の信頼を寄せた相手として追想した。・・・。ラッセルの研究者は,無理からぬことだが,通常笑いの種とされた女性の影響を重視しようとしない。・・・。

(右写真:オットリンが着用したドレスのひとつ)
(p.20) さて,話を本題に戻す前に,オットリンの生涯でほとんどいつも誤解のもとになっている3つの側面(松下注:健康,業績,他者から多くの敵意を受けた原因)について触れておきたい。
・・・。オットリンの症状は10代後半に始まり,以後,死ぬまで苦痛から解放されたことはほとんどなかった。・・・。オットリンの手記を読むと,症状を友人にひた隠しにすることに誇りを感じたことが分かる。1928年,骨癌の一種で死にかかった時はじめて,友人はオットリンが耐えてきたことを知って驚愕したのだった。
(p.21) ・・・。幼少時,極端に友達が少なかったオットリン(松下注:ラッセルの幼少時と似通っている。ラッセルとオットリンとの結びつきを強めた一つの要因でもある。)は強い愛情に飢えていた。それを求めるあまり,愛する人々に相手が薄気味悪く思うくらいにやたらと贈り物をしたり,もてなしを続けた。・・・。オットリンの気前良さは,彼女が大金持ちだという誤った印象を周囲に与えただけだった。・・・。
(p.23) 欠陥だらけの回想録は,結局,『回想録 レディ・オットリン・モレルの半生』(1963)と『ガーシントン邸のオットリン,1915-1918』(1974)の二巻本として出版された。二書には,フィリップ(夫)による文章上の多くの改変と明らかな削除が目立ち,なかでも目につくのは,オットリンと娘との難しい関係,フィリップ・モレルの不貞と精神障害の問題,オットリンのヘンリ・ラムおよびオーガスタス・ジョンとの関係の実相,ラッセルとの恋愛に関する時間を追った記録などの削除である。・・・。筆者は回想録から引用を行う場合,こうした誤記を,オットリンの手になるタイプ原本と差し替えることによって,無断のまま訂正した。・・・。
enlarge(拡大する!)
enlarge(拡大する!)
伝記作家はあくまでも客観的であるよう心掛けなければならない。そこで,筆者は,最善を尽くして,オットリンに関する証拠を有利不利にかかわらず,贔屓の引き倒しにならぬように提示した。それでも,オットリンに寄せる筆者の称賛の念を本書から完全に取り除くことはできなかった。
(右のオットリンの肖像写真:The Autobiography of Bertrand Russell, 3 vols.(ハードカバー版)の第1巻掲載の写真)
第一部 ヴィクトリア朝に生まれて
一 箱入り娘だった少女時代 1873-1892
(p.29) オットリンの『回想録』第1巻でもっとも大きく立ち現れるのは父親(注:ベンティンク中将/ベンティンク家は代々ポートランド公爵家を継ぐ家系)である。・・・。(父親は)愛情のかぎりを尽くして,娘(注:オットリンは,ベンティンクが再婚でもうけた「ひとり娘」)を甘やかした。・・・。オットリンは,(父の死後)20年間,父に代わる男性を求め続けた。・・・。
(p.40) オットリンは行き届いた敎育を受けたわけではなかったから,成人した後も,人生の多くの時間をその埋め合わせに費やさなければならなかった。19世紀後半,公爵家の娘たちには上質な敎育など望むべくもなかった。・・・。
(p.47) オットリンは母から二つのものを受け継いだ。ひどく病弱な身体と宗教的熱狂を。彼女は病弱に耐える力を求めて宗教に帰依した。
二 娘から妻へ 1893-1902
(p.60) ・・・。オットリンは自分の関心に最も適うのは哲学だと決めた。公爵夫人の母(注:義母)がこの考えの味方として加わってくれたが,肝心の公爵(注:義兄)は渋々同意するだけだった。1897年(注:オットリン24歳)の厳寒の一月,オットリンはスコットランドのセント・アンドルーズに旅したが,カリキュラムに哲学がなく,リッチー教授の下で論理学を学んだ。
(p.68) ・・・。その年(1899年=オットリン26歳)の五月,(オックスフォード大学の)サマヴィルッカレッジの聴講生として,オックスフォードに移住して,オットリンは(アスキスの影響だろう)ローマ史と経済学(松下注:オットリンはイタリア好き)を学んでいた。「きっともうオックスフォードのマドンナですよ」,人のよいマクドナルド夫妻はひどく興奮気味に呟いたものだ。
第二部 自由への歩み
三 結婚,そして母親となること 1902-1907
(p.79) オットリンは,1902年(Ottoline 29歳)にフィリップ・モレルと結婚。
(p.84) ・・・。二人(注:フィリップとオットリン)を結びつけたのは激情ではなく,誠実さと優しさだったし,相互に相手を必要としたからだった。妻よりも夫の方がはるかに相手を必要としていた。夫が妻を頼りにしていることに気づけば気づくほど,オットリンは夫を保護し,外敵から守る決意を固くした。私がいなければあの人は生きていけないと確信する。・・・。
(p.92) (夫フィリップが自由党の候補となったことで)家族の不興をかったことをいやと言うほど知らされながら,オットリンはいかにも嬉しそうだった。フィリップの人生の空虚(注:フィリップが弁護士としての仕事を嫌い,生きがいを持てなかったこと)を埋める大義名分が見つかったのだ。ただひとつ気になったのは,フィリップが人前でひどく神経質にみえることだった。ローガン(松下注:ローガン・ピアーサル・スミス/=ラッセルの義兄)に連れられて,バートランド・ラッセルの自由貿易主義の講演会に出掛けた時,その雄弁に圧倒され,オットリンは夫が同じように余裕のある自信を持って演説するのを聞きたいと痛烈に思った。・・・。
四 画想を誘う女性像
(p.110) ・・・。幼い娘(注:ジュリアン)には欠陥だらけの母親だったかもしれないが,革新的なモデルを求める画家たちにとっては,抗し難い存在だった。ダンカン・グラント,ヘンリ・ラム,シモン=アベール・ビュシイ,オーガスタス・ジョン,ジェイムズ・プライド,ドロシイ・ブレット,ネヴィル・リットン,チャールズ・コンダーなど,カンヴァス上にこの女性を捉えようとした画家の名前を列挙すれば,長い長い名簿が出来上がる。・・・。「・・・。気持ちを奮い立たせるようにして,オット(オットリン)に会いに出掛けました。その美貌に圧倒されたあまり,突然,海の中にいて,岩上で横笛を奏でる人魚の歌を聞いている錯覚に囚われました。どうしてそうなったのか分かりません。でも,オットは赤みがかった金髪を豊かになびかせ,クッションのように柔らかそうな頬を愛らしい深紅色に染め,その姿態は,私の知見をこえて人魚の姿とはこういうものかと思わせる。そんな姿形で・・・ふくよかで,それでいて滑らかでした。」(ヴァージニア・ウルフのヴァネッサ・ベル宛て書簡,1917年5月22日付)
enlarge(拡大する!)
五 ブルームズベリ,愛と芸術 1907-1910
(p.117) 「因習的状況は死である」,オットリンは1907年の手記にこう記す。「おまえの人生は世の仕掛けた絆を打破しなければならぬ。この世に順応することなどゆめゆめないように心せよ」。オットリンは打破することに積極的だった。以前に変わらず夫に献身的だったとはいえ,男児の死(松下注:息子ヒューは娘ジュリアンとの2卵性双生児。出産後まもなく死亡)は夫婦間の溝の始まりとなった。ノートには,フィリップの冷やかさとともに,自分は夫の期待に背いたのだという思いに言及した悲しい記述にあふれている。「息子さえいてくれたら」とオットリンは書く。・・・。
(p.118) ・・・。オットリンはぜひとも創造的な人たちに役立つことを何かしたい,としばしばローガン(注:ラッセルの義兄)に話した。ローガンは,それならそういう人たちをお屋敷(松下注:ベッドフォード・スクウェア44番地にある建物/参考:Bedford Square に関する Wikipedia の説明)に呼んで,パトロンを紹介してあげたらいいではありませんか,と至極もっともな助言をした。
オットリンは喜んで助言に従い,1907年春,自らが主宰する例の「木曜会」の招待状の発送に取り掛かった。・・・。
(p.120) オットリンはブルームズベリー・グループのために特にパーティを催したりしなかった。自分が力になれそうと思う創造性のある人を,だれかれの区別なく自邸に招待した。・・・。
六 利己主義者を惹きつけて 1909-1911
(p.147) ラッセル夫妻はオックスフォード近郊に居を移していた。後を追うようにローガン(注:ラッセルの義兄)と彼の母ハナが引っ越した。1909年9月,ローガンはオットリンとフィリップがブラックホールにミセス・モレル(注:フィリップの母)と滞在中なのを聞いて,妹のアリス(注:ラッセルの妻)にフィリップ夫妻をバグリー・ウッドの自邸に招待してはどうかと進めた。・・・。この時,献身的なローガンは,もう顔も見るのも嫌になった女との結婚生活に縛り付けられていたバーティ(松下注:バートランド・ラッセルの愛称)が,フィリップの美貌の妻にどう反応するか,まったく考えもしなかった。・・・。
(p.148) ・・・。「バートランド・ラッセルは本当に魅惑的な人です」とその日(松下注:オットリンがラッセル夫妻の自宅を訪問した日)の夜,オットリンは書く。「こんな魅力的な人に会ったことがありません。・・・。あの方の目に止まって私は有頂天になりました。で,半時も経つうちに私の愚かさ加減が分かって馬鹿にされるのではないかと,それが気になって体がわなわな震えました。それでも気を取り直して話しかけたのは,あの方の素晴らしい機知とユーモアのお陰でした」。どんな話だったか,二人とも記録していないが,バーティは(=のほうも)すっかりオットリンの虜になって,なんとか口説いて二人だけの長い散歩をしたいと思った。・・・。
七 噴出する情熱 1911年3月
(p.170) ・・・。フィリップは(選挙区の)バーンリーにいて不在だった。・・・。二人(注:エセル・サンズとラルフ・ホートレー)は早々と引き上げ,気がつくと,オットリンは初めてラッセルと二人きりになっていた。前々からラッセルが不幸なのではないかと感づいていたが,悲壮な努力でかろうじて自制しているらしいことにもしばしば気がついていた。オットリンに向かって胸の内を明かそうとする気配がみえると,オットリンは本能的に相手に話すように促して,ありったけの共感と理解を捧げた。それは爆発的な効果を招来した。二人が帰った後,私たちは暖炉の前で夜更けまで話をしました。・・・。(p.171) ・・・。(ラッセルは)二日後,パリへ向かう列車の中でオットリンに手紙を書き,気持ちを伝えようとした。「胸がいっぱいでどこから書きだしてよいかわかりません。・・・。」
あの方(ラッセル)が不幸なのを知りました。強度の抑圧状態と厳格な内的規律の中であの方は生きているのを知りました。・・・。まさか私にあんな爆発的な激情が注がれるとは思ってもみませんでした。打ちのめされ,狼狽し,吹き飛ばされました。・・・。バーティ(ラッセルの愛称)の雄弁と激情が突然襲いかかってきて,一切を捨ててくれ,とせがむのです。われにもなくこの感情の激流に押され,フィリップとジュリアンから離れることなど考えられないと訴えても,バーティを納得させることはできませんでした。それにしても貴女が小生を愛してくれたなんて,本当にただ事ではありません。自分がすごく厳格・冷徹で,美的生活からすごく遠ざかった人間であるような気がしています。さして強靭でない理想をことごとく破壊することを約束させられた一種の論理的機械みたいです。自らの理想は自らの批判に耐え抜き,それを土壌にして実を結びます。貴女の理想も同様であると信じます。たいていの人はそうではありません。世間からは皮肉屋と思われていますが,それは表面的にすぎません。・・・。まことに堂々たる手紙である。その雄弁と決意だけでなく,ラッセルは早くもやがて二人に訪れることになる不和の主要な原因が何なのか,予見しているからである。オットリンが重視した美的生活の側面に,つまり色彩と想像力と感動の世界に彼が共鳴できなかったことは,後にオットリンがなんとしても認めがたい欠落だった。ラッセルはこの「論理的機械」を駆使して幾度となく,オットリンの宗教的信条の砦に容赦ない攻撃を仕掛けた。・・・。
(p.173) オットリンは苦悶する。「どうすればよいのか?」。この時を振り返りながら,こう手記に記す。オットリンは,アリス(注:ラッセルの妻)にすべてを話して欲しいと頼んだ(かれは実行した),それでオットリンの気が変わる。・・・。「バーティが歩んで来た,あの自己抑制の荒涼たる生活に彼が逆戻りするのをどうして黙視できたでしょう? このすばらしい価値ある人生の重荷を(私=オットリンが)引き受けることを阻むなんて,とでもできることではなかったのです」。・・・。
(p.179) バーティが同じ文学的趣向があることは,オットリンにとって大きな発見だった。・・・。二人の共通部分がいかに多いか,それに気づいて驚いた。
(p.180) ラッセルの頭を支配していたのは,オットリンに出会うまでは,数理哲学だった。1911年は,彼の言う「あの冷ややかな手応えのない愛」に捉われた幽囚の終焉(ゆうしゅうのしゅうえん)の年であり,同時に多くの人の見るところ,ラッセルも人間問題に与る(あずかる)哲学者としての一層大きな重要な生涯の始まりを劃した年でもあった。・・・。
第三部 オットリンとバーティ
八 ある恋愛の肖像 1911-1916
(p.183) オットリンとバーティは,1938年,彼女の死まで手紙を,時には一日に四通の割り合いで交換し合った。両人の恋愛を綴る内密な記録であり,オットリンに関する貴重な原資料でもある。
(p.185) ・・・。バーティの堪忍袋の緒が切れることもしばしばだった。別段驚くことではないが,長い恋愛の間には,バーティがオットリンを諦める訳では決してないのに,他の女性に気を移すこともあった。そのやり方はいつも同じだった。オットリンに実情(松下注:他の女性との恋愛関係の内容)を話す。時にはその見通しさえ話すのだった。オットリンはようやく彼が幸福になれるかもしれないと思いながら,そうした話を喜んで聞いた。(松下注:ラッセルは自分の子どもを欲しかったが,5歳年上の妻アリスは子どもを産めない身体であり,オットリンも手術後,子どもを産めない身体になった。オットリンはラッセルを愛してはいたが,ラッセルが子ども産める女性と結婚して幸せな家庭を築くことを望んでいた。)
九 信頼と背信 1911年4月
(p.196) 肉体的に強く惹かれるのは彼(ラッセル)の方であることなど(は),議論を始めるとほとんど問題ではなかったのではないだろうか。彼女(オットリン)が惚れ込んだのは,バーティ・ラッセルの肉体ではなく,精神だった。「あの人(注:ラッセル)の心の美しさ,魂の純な炎が私に影響を与え,肉体的といってよい魅力を発揮し始めて,ダン(松下注:John Donne, 1572-1631:英国の詩人,作家,英国国教会の司祭)が表現する陶酔の境に私を誘い込むのです。魅力に乏しいあの人の肉体は消え失せてしまうように思われます。すると二人の魂がひとつの炎になって結び合い,あの人の魂が私の魂に浸透してくるのです。」(『ガーシントン邸のオットリン』)
十 イプスデンの危機 1911-1912
(p.224) ・・・。バーティがイプスデン(Ipsden)にやって来てまもなく,危機が顕在化した。後日,ラッセルは宗教を巡る議論だったと釈明したが,そればかりではなかった。二人の初めての本気の喧嘩で,バーティの欲求不満とオットリンが二人の関係から何を求めるかを彼に明言する決心がその発端となった。二人はこの後にこの時のことを振り返って,この時こそ相互の愛の本当の深さを発見した時だったと述懐した。オットリンの要求にバーティが理解を示し,二人は共同して本を完成するという新計画に取り掛かる決意を固めた。執筆はバーティ,方向付けはオットリンの役,著作は彼の懐疑主義と彼女の信仰の均衡を図る狙いだった。二人はこれを自分たちの子どもとみなし,二人の間で愛情を込めた呼び方をした。・・・。
(p.225) この子どもこそが共著「牢獄」であった。もっともこの幼児は,知的および信仰に対して厳格な姿勢をもつ老境のラッセルによって,まだ幼いうちに,賢明な判断だったが,葬り去られてしまった。・・・。
「牢獄」は教義によらぬ信仰の姿勢の重要さを世人に実証して見せる狙いだったが,これはラッセルが「神秘主義と論理」(Mysticism and Logic)において再度取り上げ,大きな成功を収めるテーマだった。・・・。
(P.229) ・・・。新しく掴んだオットリンの自信は,バーティが『哲学の諸問題』(松下注:The Problems of Philosophy, 1912/邦訳書では『哲学入門』)の幾章かを彼女に読み聞かせたこと,理解し難いとか理解ができないと思った時には,かならずそう言って欲しいと求められたことが自信を与えたのだろう。(『哲学入門』の)文体の稀有の透明性は,バーティが提示する論点はすべて彼女にも理解できなければならない,疑義には明快な返答がなされなければらならないとする,オットリンの主張によることが大きかった。
十一 三角関係 1912-1913
(p.243) オットリンとバーティの戦前(注:第一次世界大戦前)の関係は,要するに,彼が二つの方向に引っ張られ続けた時期の苦難の関係だったと言える。ラッセルがオットリンの求める書き方をすれば,ウィトゲンシュタインが彼(ラッセル)の不誠実,軟弱な思考を責め立てた。もし純粋哲学に背を向ければ,ラッセルはオットリンの不機嫌だけでなく,教え子(ウィトゲンシュタイン)の判断力の容赦ない明晰性に我が身をさらすことになった。ウィトゲンシュタインの考えでは,ラッセルが能力を全的に発揮できる領域は記号論理学だった。オットリンの考えでは,彼には人類の幸福のためにその知性を活かし,「世の人が皆それぞれの生活を宗教化するのに役立つ哲学を発信する」という明確な義務があった(1912年3月15日)。・・・。
(p.265) ・・・。バーティはウィトゲンシュタインが(ケンブリッジ大学の)「使徒会」と関わりをもったことが気になって,一時的とはいえ(オットリンへの)愛を想うどころではなかった。彼はオットリンより同性愛者に対して不寛容だったから,自分の弟子がケインズやストレイチーに感化されはしまいかと気が気ではないのに,どうしてオットリンは平気でいられるのか不思議だった。(松下注:慶應義塾大学教授で評論家の福田和也氏は,ラッセルは同性愛者であるケインズやストレイチーと親しいことから,ラッセルとケインズとは同性愛関係にあった,と断言している。『ラッセル自伝』のなかにおけるぼかした記述を誤解(誤読)したのかも知れないが,想像だけで決め付けるのは研究者としていただけない。参考:福田和也『大丈夫な日本』(文春新書)について)
十二 小春日和 1913-1914
(p.293) ・・・。オットリンが彼(ラッセル)の手紙から知る限り,ラッセルは彼女(オットリン)との再会を指折り数えていたのだった。ラッセルが(米国からの)帰国直前,ダッドレーというシカゴ在住の一家族を訪問する予定であることをそれとなく伝えてきた時,オットリンはうさん臭く思ったわけではないが,それでも数年前からダドレー家の娘の一人(Helen Dudley)と知り合いだったことを伝える文面から,ひょっとすると面倒なことになるかもしれないと予感したかも知れない。・・・。
(p.295) ラッセルは自叙伝で,ヘレンへの情熱を殺したのは戦争のショックのせいだ,と主張した。手紙を見ると,すでに彼の(ヘレンへの)情熱はマッチの火程度に衰えていたことは明白である。(『ラッセル自伝』のなかの該当箇所:Helen Dudley について)その主な理由はオットリンの反応だった。・・・。
(p.298) ・・・。ラッセルは終始一貫オットリンの勇気を褒めたたえていた。戦争(第一次世界大戦)の初期の段階,オットリンは彼の砦となった。つまり,ラッセルが信念に忠実でありつづけるために,頼りにすることができる唯一の人だったのだ。ラッセルは自叙伝に,彼女は「私にとってひじょうに大きな支え,力」でしたと記した。「あの人がいなかったら,まず最初に完全に孤立無援だったでしょう。しかし,あの女性(ひと)は戦争嫌悪の点で,そして当時の世界中がどっぷり浸かっていた神話と虚偽の受容を拒否する点でも,少しも揺らぐことがありませんでした」。・・・。(p.298)ラッセルは旧友ホワイトヘッド夫妻すらが国(英国)の方向に誤りはないと考えていることを知って衝撃にたじろいだ。・・・。
十三 新しい友,新しい敵 1914-1915
(p.329) 初めからロレンス(D. H. Lawrence)の悪意があろうはずがなかった。(1915年)三月,ケンブリッジを訪問して,その地に(ロレンスが)見つけた同性愛的共同体にロレンスが嫌悪感を表した時,ラッセルはそういうロレンスを熱烈に支持し,「ロレンスは男色に僕と同じ反感を持っているとオットリンに語り,「君のせいで(同性愛者は)無害な集団だと危うく信じるところだった。僕は考えを元に戻したよ。・・・・。」
(p.331) ・・・。ラッセルの後年のさらに辛辣なロレンス観によれば,彼の血の意識の神秘哲学は「そのままアウシュヴィッツに繋がる」のだった。陰の発案者,つまり本当の悪党はロレンスの妻(フリーダ)だ,ロレンスは(妻の)代弁者にすぎないと,オットリンと同じように,確信した。
第四部 ガーシントン邸
十四 ガーシントン邸の肖像 1915-1928
(p.353) ・・・。オットリンのもてなしの心にとって幸いだったのは,(ガーシントン邸の)敷地内に数棟のコテッジと屋敷の向かい側に農場管理棟があったことで,大人数の時にはあふれた客をそこに泊めることができた。フィリップが手早くラッセルのためにフラット仕様の部屋を用意したのも,この離れの建物の中であった。フィリップのこうした寛容な対応は,その頃,妻の愛人として世間にかなり広く知られていた男性をどう処遇するかという問題の解決になった。・・・。
十五 ガーシントンの最初の年 1915-1916
enlarge(拡大する!)
(p.361) ロレンス夫妻の後に,(ガーシントン邸への)訪問客がひっきりなしに続いた。その中に,ダンカン・グラント,マーク・ガートラー,それに盲腸の術後の静養で領主館(ガーシントン邸)に四週間滞在中のメイナード・ケインズがいた。オットリンは雅量のある人間だったが,これほど強引な同性愛者に出会ったことがなかった。「あの色情狂のケインズ!」,こうオットリンは手記の中で呼ぶ。だが,ケインズは人を虜にする客人だった。オットリンは芝生のデッキチェアに寛ぐケインズのかたわらに座りながら,この人の魅力のいわく言いがたい特質をどう定義してよいかわからなかった。・・・。(右写真出典:Bertrand Russell and His World, by Ronald Clark, c.1981)
(p.376) 1916年の(英国における)徴兵制に反旗を翻した人々の英雄はバートランド・ラッセルだった。その頃,教壇から「徴兵反対同志の会(NCF)」の闘争に全身全霊で打ち込んでいた。欠席のロレンスだけが彼に軽蔑的だった(「先生の講義はいいとは思いません。もう大方おわりましたか」)。短い戦争体験から戦争支持の正当性について確信が揺らぎ,挫折感を味合わされた若い役者マイルズ・マレソンのような兵士にとって,そして兵役拒否者(松下注:兵役忌避者)にとって,ラッセルの講演は驚くほど明快だった。会場の後方に立っていたマレソンは生まれて初めて,「私の世代の殺戮はできる限り速やかに終わらせるべきである,という熱烈な理にかなった議論」に聞き入っていた。自分の(兵役に関する)審議を神経質に待っていたリットン・ストレイチーは,彼らしい皮肉屋のマスクを捨てて,ラッセルを評して,「この地上に現在これほど威力絶大な人物はいないと思います」と言った。・・・。
十六 悲しみの時 1916-1917
(p.404) オットリンにとって女性との付き合いは楽しくなかった。男ばかりの家庭で育ったから,男性相手の方がいつも気が楽だった。本当に相談したいことは女性とは話しにくかった。(女性は)話題がいつも世間の噂話か自分の考えや感情にずれてしまうのだった。オットリンは不満を口にする。「女性はいかにも個人的過ぎる。男性のように根本的な事柄を本当に強く意識することがない。退屈を感じてしまい,楽しいことや些細なことへ流されてしまう」。フィリップは,オットリンが認めるように,こうした根本的な事柄を議論することを好まなかった。・・・。
(p.423) おそらくこの不運の発覚で,フィリップは事実をオットリンに話さなければならないと決断したのだろう。(1917年)3月7日の夕方,診療所に出掛けた。明るい月のひかりがカーテンを開いた窓から差し込み,二人の顔を煌々と照らす病室のベッドに起き上がって,オットリンは,夫に二人の愛人がいること,しかも二人とも妊娠していることを知る。・・・・。
(p.426) ・・・。オットリンがフィリップの裏表を知って支払った最大の代償は徐々に侵食してくる自信の喪失だった。これはこの後の二年間の手記に明白である。自信が根こそぎなくなった。目の縁にコール墨の汚れた線を引いて,息ができないほどの厚化粧をまとって,オットリンは感情だけでなく姿までもグロテスクに人が変わってしまった。旧友はその変わりようにショックを受けた。・・・。
十七 一時代の終焉 1917-1918
(p.441) バーティはクリスマス(1917年12月)にガーシントン邸を訪れて,それを機にオットリンと仲直りした。その間,アメリカで軍隊がストライキ(の)阻止に動員され, ,成果を挙げた事実をふまえて,ラッセルはイギリスでも同じ目的でアメリカの軍隊が利用されるだろうと軽々しい発言をした。1918年1月初め,この考えを『トリビュナル』紙上で公開,現在ではありえないことと思われるが,この見解は英米両国の関係を脅かすに足る重大な発言と受け取られ,ラッセルは禁固6ケ月の判決を受けた。4月,減刑の訴えがなされたが,功を奉さなかった。外務大臣アーサー・バルフォアとラッセルの兄フランクの口添えで,ブリクストン刑務所の禁固第一組(松下注:第一部?)で刑に服すことが認められた。結果として,早期に釈放された。(松下注:「早期」というと誤解を与えやすい。ラッセルは5ケ月刑務所にいたので,「少し早め」あるいは「1ケ月短縮されて」とでも表現すべきであろう。)
enlarge(拡大する!)
十八 ダブリンとトロントとタイガー 1919-1922
(p.471) ライオネル・ゴムは,(オットリンの)手記ではつねにタイガーと言及されるが,1920年6月にガーシントン邸にやって来て,庭園の彫像の台座を修復したり,屋敷の東側の段庭の設計に従事した。経歴は不明で,わかっているのは,養母と村に(で)暮らしていたこと,オットリンは最初会った時亡霊を見ているのではないか,と動転するほど印象が強烈だった。その姿は,「まるでわが子が生き返ったみたいでした。まるで自分そのもの,自分の精神の生まれ変わりみたいでした」,とオットリンは1928年7月に(当時を回顧して)書く。
(p.483) ・・・。オットリンがロンドンにちょっとした手術を受けるために出掛けた直後に,タイガー(ライオネル・ゴム)の養母から彼が危篤だという電報が届いた。オットリンは地元の医師に電話ですぐ領主館(ガーシントン邸)に行ってほしいと依頼してから,最初の汽車で戻る。帰りつくと,タイガーは二度目の脳内大出血の後で,家畜小屋の中庭で横たわっていた。すでに意識はなかた。30分後,オットリンの腕の中で息を引き取った。
十九 母としての試練 1922-1925
(p.503) ・・・。オットリンは,夢の宿るボールゾーヴァ城(松下注:オットリンの母が女男爵となり譲り受けた古城)を別にして,ガーシントン邸をどこよりも愛していたが,いまはそれをあらゆる不幸の根源と思うようになった。愛する人(松下注:生まれてすぐに亡くなった一人息子とタイガー)が亡くなった屋敷であり,嫉妬深い友人が彼女に悪意を持つきっかけとなった屋敷だった。・・・。
(p.507) 屋敷はジュリアンの友達でいっぱいだった。オットリンは自分も年を取ったと感じるようになった。初めて,「娘や(娘の)友達はみんなほんとうに若いと思えた」のだった。オットリンと同世代の知人・友人としては,わずかにバーティが相変わらず時たま訪ねてくるだけだった。しかし,そのバーティも,ドーラ(松下注:1921年に正式にラッセルと結婚)と共同で開校させようとしている学校(松下注:Beacon Hill School) の計画に忙殺されて,オットリンの金策とわがまま娘の苦労におざなりの関心を示すだけだった。
第五部 ガウワー・ストリート10番 (Gower Street)
二〇 回想録と勇気の試される時 1925-1928
(p.511) 「太陽を背にして窓辺に座り,過ぎし日の素描のつもりで『わが人生』の執筆にかかりました。着手するのに難儀しました。・・・。」とオットリンは,1925年9月28日(オットリン52歳)に記す。
オットリンはあまり年齢のことは考えなかったが,ガーシントン(邸)の初期の年若い友人たちがいまや中年であることが彼女を回顧的にした。オットリンは来し方を振り返った時に,どうやら人生の大部分を,貴族社会にあって生き方に絶望的に不器用でありながら,まずベッドフォード・スクウェアで,次いで本人が言う「夢多き劇場」であったガーシントンにおいて舞台責任者兼演出家としての役割を見つけた女役者として,舞台の上で生きてきたような気がした(これは彼女の回想録を支配する顕著な心象である)・」・・・。
(p.513) オットリンは以後死ぬまで回想録の仕事に打ち込む。出版について聞かれると,死ぬ前は絶対困ります,と言って1936年(注:オットリンは1938年に死亡)にマーゴット・アスキス(注:英国首相をつとめたアスキスの娘)を驚かせた。しかし,コテリアンスキーには,もし公爵(注:オットリンの義兄のポートランド公爵のこと)が私より先になくなれば,考えて見ましょうと言った(ウェルベック邸の生活を意識的にお世辞抜きで描写して,公爵にあらぬ迷惑をかけたくなかった)。オットリンの思慮分別が不幸な結果に終わったことは『回想録 レデイ・オットリン・モレルの半生』と『ガーシントン邸のオットリン』を読んだ者には誰の目にも明らかだろう。この二冊はオットリンの記述どおりではなく,彼女の死後,「改善」を狙った夫フィリップの手が原稿全体に徹底的に入ったものだった。・・・。オットリン家のたっての要請に懸命にこたえて,フィリップはラッセルを匿名にし,最終的には除外してしまった。ジュリアン(オットリンの娘)は,たとえ付録であってもいいから,回顧録の中でラッセルの復権を図ることにしたが,その付録は稚拙な編集のため,ミスプリントと誤りだらけだった。・・・。オットリン本人が夫フィリップへの献身を倦むことなく強調した結果,実像を歪めることになったが,ことに隠蔽を意図した時にはそれは痛ましい限りだった。・・・。
(p.528) フィリップとオットリンがとうとうガーシントン邸を手放すことを決めたのは,1927年の10月だった。
(p.531) (1928年)最初の異常の兆しは莫迦莫迦しいほどに些細なことだった。ハクスリー夫妻やエリオット(T. S. Eliot)やアイルランドの友人ジェイムズ・スティーヴンズらを招いて茶会を開いたある時,オットリンは客の一人から顔に変な染みがあるといわれた。・・・。ハクスリーの友人ドクター・ラウは(オットリンの)口腔の壊死が相当進行している状態,局所癌の一症状と診断した。生存のためには全下歯の抜歯と顎骨(がっこつ)の一部切除しかなかった。手術後,感染部位にドレーン管を挿入したまま,二か月の入院生活が続いた。
五月,オットリンは回復して,九週間ぶりにベッドに起き上がることができた。手術による傷は治癒したものの,筋肉と骨の切除のために,「顎がぎょっとするほど変形してしまい,思わず誰も目を背けないではいられなかった」。・・・。
(p.532) オットリンの知人・友人の中でラッセルだけが,彼女の本当の苦しみを知っていた。中にはサスーンやジュリエット・ハクスリーやマーク・ガートラーのように,オットリンが健康の優れないことを苦にせず,最後まで隠し通そうとしたのを見て,感心した友人もいた。ブルームズベリーの仲間をふくめて,大半がオットリンの頭痛や通院治療や特別食事療法を金持ち女の健康不安症候群として一笑に付した。誤解だったことが判明すると,誰もが驚愕し,少しばかりばつの悪い思いをした。
二一 友情と再生 その一
(p.537) ・・・。ガーシントン邸での歳月は,知人・友人を信頼して心の内を打ち明けることがいかに危険であるかオットリンに教えた。ガウアーストリート(の新居)に移ると,手記はオットリンの唯一の感情の吐け口(捌けぐち)となった。
オットリンの死後,フィリップは妻の文書に目を通しながら,最後の二十年間妻が手記を彼に見せなくなってから,どれほど知らされないままのことが多かったか知って愕然とした。
(p.548) ガウワー・ストリートへの引越しをきっかけに,オットリンと異母兄の第六代公爵との付き合いが驚くほど息を吹き返した。
(p.549) ウィリアム・アーサ・ベンティンク公爵(松下注:第六代ポートランド公爵/ちなみに,オットリンの父親の名前はアーサー・チャールズ・キャベンディッシュ=ベンティンク)はつねに社交的な人だった。・・・。ヘンリ(弟)がこの世をさり,あわせて気のおけない最も優しい同志(妻)も世を去り,公爵は慰みと心の支えになる愛情を異母妹(オットリン)に求めたのだった。
(p.551) この変わりようには目を奪われる。かつての否定的な態度は絶対的な無批判な献身にとって変わられた。オットリンは相手に吹き込んでしまったらしい感情が分かる気がしたが,驚きだった。だが同時に,このような絶対愛に心が揺さぶられるのをどうしようもなかった。公爵は,貴女と一緒にいる時だけが僕の幸せですと告げた。オットリンの健康について医師に相談したり,治療代を払おうとしたり,底抜けに気前よく贈り物をし,相手が喜ぶだろうと思えば,どんな労も厭わずせっせと楽しい事柄を手配した。・・・。
(p.552) ・・・。オットリンの最晩年の六年間,両人はほとんど毎日手紙を書きあった。彼女が亡くなると,公爵は自室に籠って三日間ドアを閉めたままだった。
二二 友情と再生 その二
(p.595) 1928年,顎の手術を受けたオットリンは,術後顔の形がひどく歪んだのを知って,以後公衆の面前に姿を見せるのはご免だと思ったが,一年後,以前にもまして社交にかまけるようになった。死ぬような目に遭い,人生が与えてくれるものはなんでも掴もうという気になった。・・・。
(p.609) オットリンの健康は1928年の年明けとともに衰えをみせた。1936年の末頃には,病気が意志の力を上回るようになったことを認めないわけにはいかなくなった。そうなると,簡易宿泊所で行なっていたホームレスのための事業は中止せざるをえなかった。・・・。
二三 最後の一年 1937-1938
(p.611) オットリンがタンブリッジ・ウェルズに三ヶ月の入院中に見舞いに訪れた数少ない友人の一人がバーティ(注:ラッセルの愛称)だった。彼は「とても優しく素晴らしかった--昔ながらのすばらしいあの方の姿です」とオットリンは記録する。彼とピーター(松下注:パトリシア/ラッセルの三度目の妻)に子どもが生まれる時が近づくと,オットリンは(ラッセル夫妻は)お金が足りないのではないかと気になり,診療所からジョージ・サンタヤナ(松下注:ハーバード大学教授を務めていたスペインの思想家でラッセルの友人)に手紙を書いて,貴殿のロックフェラーの縁故を活かして援助できないか尋ねた。タイミングよく,援助がサンタヤナの甥ジョージ・スタージスから小切手の形で届いた。おまけに年額一千ポント支給の約束も得られた。1937年9月,バーティからそのことを聞き,オットリンは嬉しそうに「すごくよかったと思います。これで一安心です」と手記に書く。
(p.613) 1938年3月頃には,キャメロン医師(松下注:オットリンの主治医の一人)のこうした投薬に関して医学界で重大な疑義が表明された。4月20日,オットリンはキャメロン先生が亡くなったと聞かされた。実は2日前に自殺したのだった。
4月20日の夜,オットリンは最後の手紙を公爵宛にしたためる。翌朝,オットリンはキャメロン医師の助手,ガウァリアウ医師からプロントジルの注射を受けている最中に息を引き取った。享年64歳だった。死因は心不全とされた。
[1998年9月の改訂版によるシーモアの追記]
(p.625) (1933年)12月になると,公爵(オットリンの異母兄)がロンドンにオットリンを訪ねてきて,ますます執拗に肉体関係を迫るなど,オットリンは不安でならなかった(松下注:母親が異なっても兄弟であるため?)。・・・。
(p.627) 両人は1936年11月8日,ケンブリッジを再訪した。はた目には物静かな年配の,70歳代と60歳代の夫婦として,フィッツウィリアム博物館を巡り,友人を訪ねた。物静かな空気は無残にも粉砕された。その日の(オットリンの)手記の末尾には次のような文章がある。「その時から私の苦難が始まりました。・・・。。どうしたらいいか,四六時中考えています。・・・。あんなに怖かったあの兄(義兄)がいま愛人だなんて・・・あの人は眠っているときも私を愛撫しつづけたんです。」
(p.627) ・・・。彼女には相談する相手のいない出来事だった。同時にこれは,疑いもなく,フィリップ・モレルが妻の手記を人目から隠し続けた決定的な理由であり,そして編集の手が加わった原稿しか現に入手できない出来事だった。
中井久夫氏の(このエッセイを書くにあたっての)情報源はほとんど『ラッセル自伝』からですが,さすが精神病理学の大家らしく,ラッセルの人間性及びそれを形成するにあたって影響した要因をするどく指摘しています。ラッセルは3歳までに両親を失い,その後大学に上がるまで,聡明ではあるがしつけの厳しい祖母に育てられます。祖母にも孫に対する愛情はもちろんありますが,やはり実の親(特に母親)のような甘えられる愛情ではありませんでした。さらにラッセル家には精神疾患にかかる者が多く,ラッセルは自分もいつかは発狂するのではないか,と時々恐怖に襲われるとともに,悪夢を度々見ることになります。ケンブリッジ大学(トリニティ・コレッジ)に上がると,それまで孤独であった少年が人が変わったように社交的な人間に変わっていきます。しかし,幼少時に形成された性格・人格はラッセルが成人してからも影響力を発揮します。ラッセルの人間性やラッセル思想を理解するためには,以上のような事情を理解しておくことが非常に重要だろうと考えます。(また,オットリン・モレルとの間になぜあのような強い結びつきができたか,理解できます。)
以下,中井久夫氏のエッセイを長々と引用させていただきます。ちくま学芸文庫に入っていますので,容易に入手できるはずです。全文をお読みになることをお薦めします。(松下)
(p.251)・・・。
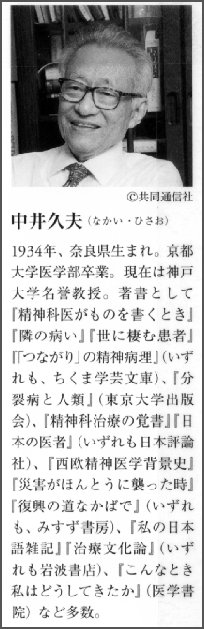
コンピューターの祖父と父
バートランド・ラッセル(1872-1970)が97歳という高齢で没するときまで急進的な平和運動家であったことを記憶する人は今日もなおすくなくなかろう。彼は戦後の世界史において国連事務総長やローマ法王にならぶ知性の法王のような権威を以て発言し,その声はキューバ危機や中印紛争においては両陣営がひとしく聴くだけの力をもっていた。
しかし彼がすくなくともアングロサクソンの世界においては二十世紀最大の哲学者とされていることを知る人は意外にすくない。彼の哲学の真髄が実は『幸福論』や『教育論』ではなく数理論理に基礎をおく分析哲学であることを知る人はさらに少ない。彼が大著『プリンキピア・マテマティカ』全3巻(ホワイトヘッドと共著)によって20世紀最大の数学者であることを知る人はいっそう少ない。
『プリンキピア・マテマティカ』が難解を以て鳴ることは有名である。それは数学をゆるぎない論理的基礎の上に据えようとしたもので「1」を定義するために第1巻の半ば以上をついやし,2×2=4 が出てくるのは第2巻のまん中あたりであるという。いかに読まれていないかは,この本が1911~1913年に刊行されてから40年もたってのちアメリカきっての論理哲学者ライヘンバッハが学会である定理を発表したとき,ラッセルが立ち上がって「それはプリンキピア・マティマティカのかくかくのページにのっている」と叫んだというエピソードからも想像できよう。(参考:「プリンキピア・マテマティカ対コンピュータ」)
ところが意外なことにウィーナーがコンピューターの父ならラッセルは祖父である。・・・中略・・・。
(p.253)・・・。ラッセルのつくった世界はあまりに閉鎖的な「論理主義者の楽園」にすぎない,という批評もでてくる。しかしそれは思わぬところで新しい芽を出す。それがコンピューターである。実にコンピューターは「論理数学の物質化」(森毅)という性格をもっている。そしてコンピューターは最近(注:このエッセイの発表は1972年)になってついに『プリンキピア』のほとんどすべての定理を解いた。かつてラッセルが「来る日も来る日も白紙を前にして考えつづけた」(『自伝』)苦渋な道のりは,弟子ウィーナーのうんだコンピューターによってみごとに跡づけられた。
しかし,論理数学の体系を完成した男とそれを物質化した男は性格も歩んだ道も全く対照的であった。二人の数学とのめぐり合いは全く異なるものであった。
(p.254~)
変わり者一家
ラッセルは英国貴族界切っての名門にうまれた。彼の中には一滴も庶民の血が入っていないといわれる。代々自由党の政治家となるべき家柄であった。ラッセルの祖父はヴィクトリア朝時代に首相・外相を歴任した。明治維新前夜に英国の暗躍は著しいがその総指揮者はこの(祖父の)ラッセル卿である。
しかしラッセルは不運な少年であった。彼の両親は自由思想家である。父はそのために国会を追われ,森の中に居をかまえて著作に耽っていたが,ラッセルの3歳のときに亡くなった。すこし前に母と姉が死んでおり,ラッセルは3歳で孤児になってしまった。
ラッセルの記憶は祖母にひきとられるためにロンドンの停車場についたときから始まる(参考:『ラッセル自伝』の冒頭部分)。祖母の住む広大な荘園ペンブローク・ロッジには(ビクトリア)女王も気軽に立ち寄られたが,しかしそこの住人は何という人たちであったろう。祖父はこのころすでに車椅子の人であったが祖母はかくしゃくとしており,仮借のない態度で周囲に君臨していた。首相・外相夫人にふさわしい教養の持主であったが清教徒的信念をもち,性や文学に対して激しい偏見をいだいていた。その他に叔父の一家と叔母がいた。しかし叔父も叔母も変わり者であった。叔父ははげしい対人恐怖のために公職につけず,科学を織りこんだ風変わりな讃美歌をつくって日をすごしていた。叔母は結婚の直前に妄想病になってしまい,そのまま老嬢となった。ただ一人残ったきょうだいである兄はのちに高等詐欺師のようになる。この兄が,ことごとにラッセルに意地悪をしかけた。もっとも無意識のきずなは強かったらしく,この兄の死の時,ラッセルは大きな衝撃を受けている。そもそもラッセル家には精神病者が多い。当時のラッセルには知らされなかったが父も時々精神病の発作を起こしており,父のすぐ下の弟は生涯を精神病院で送っている。つまり祖父母の子どもたち4人はすべて精神異常を来しているわけである。
遺伝ということもあろうが,おそらくラッセルの祖母が子どもたちを呪縛しながら,母親と子どもの間にあるべき根本的な信頼関係をつくらせなかったのではなかろうか。『自伝』その他からみる限り,この祖母の呪縛力は,感情移入しつつ読む者を魅了しかねないものである。「統合失調症をつくる母親」(フロム=ライヒマン)だけで統合失調症がつくれるものか否かは知らないが,そういう名で呼ばれたことのある女性の魅力を私は肌身に感じた。逃れるのは大変だろうな,と思った。
硬質な知性の下の深淵
3歳から16歳までラッセルは全く孤独でこの環境にあった。祖母は彼を学校にやらず,例の叔父が自然科学を,叔母が歴史を,二人の家庭教師がドイツ語とフランス語を教えた。祖母は(孫のラッセルの)両親の自由思想的な影響を子どもから取り去ろうとし,父親の指定した後見人を当局に運動して無効とした。ラッセルは高貴な血をひくと同時にいかがわしい反抗児だった人の子どもで,うまれながらに注意人物だった。
当時を知る人は「二人の子ども(注:ラッセルと兄フランク)はまるで幽霊のようであった」と語っている。ラッセルは全く反抗せずにすべてに耐えた。彼は幼児語を全く使わず,正確な大人のことばを語った。3歳にして女王や首相(注:グラッドストーンのこと)に大人として接することを強いられた体験は,後年の彼をどんな場合にも物怖じしない人物とした。しかしそれは公式の席のことで,私生活では極端なはにかみ屋だった。とくに親愛の惰を示すのに異常なためらいをみせた。
このように,小児が成長してゆく上で何よりも必要な,密接な情緒的接触という心の栄養が欠けている環境で,外界から隔離され,ほとんど全く同年輩の人間を知らず,変わり者の大人の間に住んで全く反抗を示さなかったと聞けば,精神科医はそれだけでぞっとする。遺伝負因のことなど二の次三の次で,その子が将来統合失調症などにならないかと考えてしまう。
このような場合,子どもが反抗しないのは第一に捨てられる恐怖からである。子どもは自分が無力で保護なしでは生きてゆけないことをよく知っている。彼は日々そのことを思い知らされる。この恐怖に対抗して子どもが成長という抵抗の多い冒険に打って出られるのは,母子関係に代表されるような根本的な信頼関係に支えられてはじめてできることなのである。実際,ラッセルは祖母に捨てられたとき(場合)のことを考えて慄然としたと後になって洩らしている。
ラッセルの長い生涯には発病の危機が幾度かあったと推定される。彼は50をすぎるまでたえず自殺を考えながら生きていた。80歳まで毎晩悪夢に苛まれた。あいまいさを許さない彼の硬質な知性の下には深淵があった。彼はそのことを知っていた。しかし白髪をふりたてて論戦する攻撃的な哲学者の中に過敏さと自責と自己解体の恐怖がひそんでいたことをみてとる者はすくなかった。彼はついに耐えとおした。80歳をすぎてようやく彼は『自伝』の中にそのことを告白するのである。(松下注:晩年に出版した『ラッセル自伝』はいろいろな時期に書いた文章を材料にしている。ここでは,80歳頃に書き,『自伝』に盛り込んだ文章のことを言っている。ちなみに,1921年=ラッセル49歳の時にドーラとの間に初めての子供が生まれている。)自分は「星と深海と暗い夜に属している種族である」。
彼を支えたものは知性であった。子どもと子どもをとりまく世界との間に根本的な信頼関係がないとき,子どもにとって謎にみちたものである世界はそのまま恐怖そのものである。多くのものはそこで立ちすくんでしまう。ただ少数の子どもが世界を知的に理解することによって,ありのままの世界の中で憩えない事実をのりこえようとする。世界の信頼性を世界の可解性に置換しようとする試み,知性をたよりにこの世界をのせる不動の岩盤に達しようとする試みである。
幾何学への初恋
ラッセルは幼いときすでに「絶対に確実な知識というものが存在する」という確信と「何とかしてそれを得たい」というはげしい希みが芽ばえていた。それは11歳のときにユークリッド幾何学を教わったとき,はじめて現実のものとなった。それは初恋にもまさるまばゆい大事件であったと彼は語っている。
幾何学との出会いの中にすでに彼の数学の性格があらわれている。彼は公理系そのものの基礎を問題にして,解法の熟達には興味を示さなかった。兄はそういう彼をあざわらった。しかし彼の中には数学の基礎をきわめたいという気持が油然とわきおこった。このとき彼はそれまで祖母にたたきこまれてきた宗教の教義にはじめて疑念をいだいた。彼の心の中にはじめて内面の自由がうまれた。彼はこの大秘密をギリシャ文字でノートに記した。
16歳の彼は突然孤独の世界から猥雑な少年たちの世界に投げこまれる。祖母は大学入試の準備のため,必要な古典語を学ばせようと彼を寄宿制の予備校に送った。それは軍人の卵の集団であり,彼らは体験も心の準備もない彼を性的に徹底的にからかった。彼はその頃読んだ『ガりバー旅行記』に出てくるいやしい人獣ヤフーがそのまま人間の姿であることをはじめて知った。彼はくり返し野原にさまよい出て夕日にむかって歩きながら自殺を思った。彼の足をひきとめたのは,もう少し数学を知ってからにしようという考えであったという。
ついに大学入試の少し前,彼は当時,認識論の基礎と考えられていたミル流の経験論が数学についてはまちがいであるということに気づいた。2×2 = 4 という演算は,人類が 2×2 をくり返すたびにだんだん確実になってゆくという種類のものではない。つまり 2×2 = 4 は経験的確実性をこえた真理である。この直観が「彼の数学」のはじまりであった。この素朴な啓示がいくたびかの知的危機を経ながらついに彼を『プリンキピア』の完成にまでみちびいた。
むろん数学は『プリンキピア』とともに終わったのではない。ラッセル自身80歳をこえて「絶対に確実な知識に到達するという私の目的はついに果たされなかった」と述べている。たしかに目的はついに果たされなかったかもしれない。しかしその道程は実に稔り豊かであったということができる。
以下,pp.259-266 は省略。
[pp.38-40:バートランド・ラッセル]
(p.38) こうした水爆の実験から生産,配備,運用訓練に至り,威嚇と使用におよぶ一連の事柄こそ,新たな理論の誕生を迎える前提でした。こうしたことを,まずもって,イギリスの哲学者バートランド・ラッセルの場合を例にして説明しましょう。ラッセルが率先してかかわった3つの事業を紹介しましょう。
[1つ目の事業は「ラッセル=アインシュタイン宣言」の発表]
人類初の「マイク」水爆実験のあとアメリカは,ビキニ環礁で「ブラボー」とよばれる水爆実験をします(1954年3月)。これは航空機に搭載した乾式の水爆の実験で,観測班員28名のほか,マーシャル諸島の島民多数と危険区域外の漁船数千隻余りも被曝しました。これで日本のマグロ漁船第五福龍丸の乗組員も被曝しました。日本社会は,放射能で汚染されたマグロの処分をふくむ食料汚染という事態で,一種のパニック状態になりました。核実験がもたらす放射性廃棄物,すなわち「死の灰」の暗影が世界全体に知れわたることになりました。
この年12月,ラッセルは核実験反対宣言を起草し,BBCで「クリスマス演説」をしました。翌年(1955年)には,「相対性理論」で著名な物理学者のアルバート・アインシュタインに手紙を書きました。アインシュタインが亡くなる直前に承諾をえて,ラッセル=アインシュタイン宣言を発表します。この宣言は,署名の呼びかけ人となった湯川秀樹を含む11名の教授のうち,ロートブラットとインフェルトをのぞく全員が,ノーベル賞の受賞者でした。だが,それよりももっと重要だったのは,この宣言が伝えようとしたメッセージの内容でした。およそ将来の世界戦争においてはかならず核兵器が使用されるであろうし,そしてそのような兵器が人類の存続をおびやかしているという事実からみて,私たちは世界の諸政府に,彼らの目的が世界戦争によっては促進されないことを自覚し,このことを公然とみとめるよう勧告する。したがってまた,私たちは彼らに,彼らのあいだのあらゆる紛争問題の解決のための平和的な手段をみいだすよう勧告する。核兵器は人類の存続をおびやかしている,こういう事実を世界の大衆に示した点がまず重要でしょう。このコンセプトから,いまや人類はまったく新しい思考様式をつくりださなければならない,つまり人間性に想いをいたし,戦争の廃絶と核兵器の廃絶を実現するのだという思考様式をとるべきだと提言したのです。こうした画期的な理論提言が生まれました。この宣言が発表されたのは,1955年7月9日,ロンドンにおいてでした。この宣言を直接受容するかいなかということとは別の次元ですが,実際この年8月に,日本で原水爆禁止世界大会が開催されて,世界でも同時期に反核運動が広がっていきます。
2つ目の事業は,パグウォッシュ会議(注:「科学と世界の諸問題に関するパグウォッシュ会議)の発足です。・・・(省略)・・・。
3つ目の事業は,イギリスのCND(核廃絶キャンペーン)です。CNDはイギリス政府が水爆実験を行ったあと,これに抗議する反核意識の高まりをうけて,1957年11月に誕生しました。翌年(1958年)2月17目の設立総会でラッセルが初代代表に就任することが認められました。執行委員会には,ロートブラットも加わっていました。パグウォッシュ会議では,核抑止論が有力になり始めていて,1964年の第12回会議では,最小限抑止の原則が全面軍縮に至るもっとも有用な道であるとされました。しかしラッセルは,こうした立場を批判する大衆運動の先頭にたったのでした。