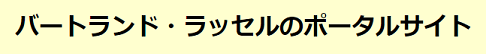
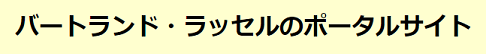
* Bertrand Russell(1872-1970)は,1872年5月18日, Wales (Monmouthshire 州 Trelleck の近く, Wye 河畔に建てられた Ravenscroft と呼ばれる家)で,英国初の女医 Dr. Garrett Anderson の手で生まれる。8ポンド3/4=約4,000g。愛称 Bertie。
ペンブローク・ロッジに着いた当日の記憶は,使用人の食堂(Hall)で飲んだお茶である。その食堂は,広く,長くどっしりしたテーブルとテーブル用の椅子と,(背もたれのない高い腰掛け一つだけしか置いてない部屋であった。使用人たちは皆この部屋でお茶を飲んだが,女中頭(松下注:日高氏は,house-keeper を「管理人」と訳されているが,ここでは後にでてくるように,ミセス・コックスという年輩の女中頭のことをさしている。ロッジ管理人は,後にでてくるシングルトン氏)とコックと祖母専属の女中(lady's maid)と執事(使用人頭)は,女中頭の部屋で上流階級を形成していた。私はその使用人たちの部屋で,お茶を飲むために高い腰掛に座らされた。そこで私が最もはっきりと覚えているのは,なぜ使用人たちはそんなに私に興味をもつのだろうかと不思議に思ったことである。その時はまだ,私は,大法官(注:司法長官と上院議長を兼務)や何人もの有名な勅撰弁護士やその他の著名人たちが私を真剣に考慮の対象にしていることを知らなかったし,また,私がペンブローク・ロッジに来る以前に起こった奇妙な出来事も,私が大人になるまで知らなかった。 私の父アムバーレイ卿は,長い間病をわずらい次第に衰弱が進み,(私がペンブローク・ロッジにつく)>直前に(1876年始めに)亡くなったところであった。母と姉(誤訳:日高一輝訳『ラッセル自叙伝』では「妹」になっているが,年上の妹はいない。)はそれより一年半ほど前(1874年に)ジフテリアで死亡していた。あとで日記や手紙でわかったことであるが,母は活発で,精力的で,機知に富み,まじめで,独創的で,そして恐れを知らない人であった。また,写真から判断すると,美人でもあったにちがいない。 父は,哲学に通じ,学問好きで,超俗的で,気むずかしい,きちょうめんな人であった。 二人とも熱心な改革論者で,そうしてどのような理論でも自分が正しいと思ったらいつでも実行にうつす覚悟をもっていた。父はジョン・スチュアート・ミルの信奉者かつ友人であり,そのミルから父母は,産児制限論者及び婦人参政権論者になることを学んだ。父は産児制限を唱えたために国会の議席を失った。母はその急進的な意見の故にしばしば,苦境におちいった。 (注:下記のケンブリッジ公爵夫人の発言は,翻訳家の植村昌夫氏による誤訳の指摘を参考に,2007年8月3日に一部修正しました。植村氏には御礼申し上げます。) クイーン・メアリー(注:ただしこの時はまだ王妃になっていない)の両親が主催したある園遊会で,ケンブリッジ公爵夫人がかん高い声でこう言った(注:当初「メアリー女王」としていたところ,植村氏から,「Queen Mary は Mary of Teck, 1867-1953 のことであり,女王ではない。またこの園遊会の時にはまだ王妃にもなっていないはず。)」とのご指摘をいただき,訂正しました。/ちなみに,「女王」とは「女性の王様」というだけでなく,「摂政裕仁親王,久邇宮良子'女王'(じょうおう・じょおう)と結婚」というように,「内親王の宣下のない皇族の女性」の意味もあります。) 「ええ,私にはあなたがどのような方かわかっています。私の義理の娘ですよ。ケンブリッジ公爵とは)。けれど,聞くところによれば,あなたが好きなのはただけがらわしい過激派とアメリカ人だけだそうですね。ロンドン中でそれが言いふらされていて,社交クラブではその話でもちきりです。私は,世間のうわさどおり急進派やアメリカ人が本当にけがわらしいかどうかを知るために,あなたのペチコートが(下品な人たちとのつきあいで)汚れていないか見せてもらわないといけませんね」 フィレンツェ(フローレンス)駐在英国領事からの次の手紙は,そのことに関する事情をよく物語っている 「拝啓 レディ・アンバーレイマッツィーニは,私の母に彼の時計のケースを贈った。それを今,私が所有している。 |
* 1908年当時のパディントン駅の写真 * (ラッセルの両親の写真の出典):Photos from R. Monk's B. Russel, the spirit of solitude, 1996. My first vivid recollection is my arrival at Pembroke Lodge in February 1876. To be accurate, I do not remember the actual arrival at the house, though I remember the big glass roof of the London terminals, presumably Paddington, at which I arrived on my way and which I thought inconceivably beautiful. What I remember of my first day at Pembroke Lodge is tea in the servants' hall. It was a large, bare room with a long massive table with chairs and a high stool. All the servants had their tea in this room except the house-keeper, the cook, the lady's maid, and the butler, who formed an aristocracy in the house-keeper's room. I was placed upon the high stool for tea, and what I remember most vividly is wondering why the servants took so much interest in me. I did not, at that time, know that I had already been the subject of serious deliberation by the Lord Chancellor, various eminent Queen's Counsel, and other notable persons, nor was it until I was grown-up that I learned to know of the strange events which had preceded my coming to Pembroke Lodge. My mother sometimes got into hot water for her radical opinions. At a garden-party given by the parents of Queen Mary, Duchess of Cambridge remarked in a loud voice: 'Yes, I know who you are, you are the daughter-in-law. But now I hear you only like dirty Radicals and Americans. All London is full of it; all the clubs are talking of it. I must look at your petticoats to see if they are dirty.'The following letter from the British Consul in Florence speaks for itself:
|
|
|