Google Alert に「バートランド・ラッセル」や「Bertrand Russell」というキーワードを登録しているため、毎日、Web上にラッセル関係の情報がアップロードされると Google から自動的にアラートが送られてきます。
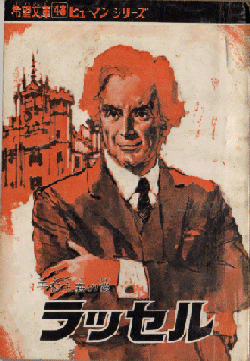
先日、某書店で「「希望文庫 48 平和主義の礎『バートランド・ラッセル』」という本を売っているとのアラートがきましたので、早速注文してみました。しかし、物理的なものとしては初見ですが、中身は私が早稲田大学教育学部のラッセル文庫に昔寄贈した 「ポケット偉人伝・第7巻・哲学思想家篇」(5分冊入)のなかの1冊(1971年7月刊)と同じものでした。つまり、残念ながら、同年4月に「希望の星」という雑誌(?)の付録としてだされたものの再販でした。
<目次> ラッセル家の家系/考える少年/兄と弟/哲学への歩み/ケンブリッジ大学へ/周囲の反対を押しきって/ふたたび数学へ/敗北/戦雲/弾圧、また弾圧/ロシア革命/バートランド・ラッセル事件/各戦争をなくすために。
(p.28)「数学と美」
わたしは十代の頃から数学に関する名言を集めている。中でも好きなのがこれだ。」「正しい見方さえすれば、数学は、真理であるだけでなく、至高の美でもあることがわかる。それは、彫刻の美のように、冷徹で無駄のない美だ」(バートランド・ラッセル『神秘主義と論理』、1918年)
これをアマゾンで購入
(pp.83-84)「ピュタゴラスとは何者か?」
・・・。ピュタゴラスのアイデアは、数学という科学が持つ三千年の歴史を経ても色褪せることがない。哲学者バートランド・ラッセルは、かつて、「ピュタゴラスは、賢明であった時期も、賢明でなかった時期も含めて、人類史上最も知的に重要な貢献を果たした人物の一人である。」と書いた。ピュタゴラスは、数を崇める宗教を創始したという点で、史上最も不可解な数学者でもある。その宗教の主な教義は、豆を食べることの罪悪視と魂の輪廻転生であり、ほかにもたくさんの奇妙な規則が定められていた。ピュタゴラス教団の信者にとって、数学とは法悦をもたらす啓示だった。
ピュタゴラス学派の人々は、現代のフラクタル研究者と同様に、音楽家に近い存在だった。彼らは、数学的真理を発見する過程でパターンと美を創造した。数学者と神学者の融合はピュタゴラスに始まり、最終的にはギリシャのすべての宗教哲学に影響を与え、中世の宗教でも一定の役割を果たし、近代のカントにまでその影響が及んだ。バートランド・ラッセルは、「もしピュタゴラスが出現していなければ、神学者が神と霊魂の不滅の論理的証明を追い求めることはなかっただろう。」と言っている。・・・。
(p.348)「古典的な床屋のパラドックス」
ラッセルが考案した「床屋のパラドックス」の紹介。引用省略。
(pp.169-181:「知的教養主義の継承--私の世代」)
さらには、戦後のわれわれの世代ですと、父親の世代とは違って、フランスのものがかなり重要な意味を持ってきました。カフカはフランスじゃないけど。サルトルとかカミュ、ジッドなどがまず一番大きな名前だったかもしれません。それから、たまたまカフカの名前を出したのは、不条理的な世界というのがフランスの現代文学とドイツ文学に描かれていて。カフカの場合はあれをドイツ文学と言うべきなのかどうかさえちょっと問題がありますね。プラハのユダヤ人ですから。カフカはこういう言葉を残していますよね。書かないことへの不自由、書くことへの不自由。彼はユダヤ人だけども自分の著作はドイツ語でしか書かない。まあイディッシュで書くということががあったかもしれないけど・・・。でも、ドイツ語で書くということ自体がカフカにとっては、ある意味ではひとつの屈辱とでも言うべきものかもしれないわけですよね。ですから、そういう不条理の中に生きたカフカや、メルロ=ポンティやカミュやサルトル、あるいは英語圏でいえばバートランド・ラッセルなどというような世界がわれわれの教養でしたね。とにかく読んでおこうよって。
では、そういうときにドストエフスキーなんかはどうだったかというと、これはある意味で言うまでもなかったんです。つまり、当然読んでおくべきものでした。だから、父親の世代はドストエフスキー読まなきゃいけないというのは義務だったと思いますけども、私たちの場合はそれは前提であって、それを読んだ上で、カミュや、サルトルの『自由への道』。これは一応翻訳がありましたから、私は翻訳で読みましたけど、そういうのが高校から大学へかけての必読書でしたし。それからもうちょっと社会学的なものだと、エーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』も、まあみんな読んでましたね。そんな世界ですね。 ・・・
(pp.224-226:「バートランド・ラッセルと『論語』」)
・・・。こうして、知と情と並べて書いてみますと、文化には、頭の文化と心の文化がある。これは何度も申しましたが、英国のバートランド・ラッセルが申しておるのであります。面白いですね。頭の文化と心の文化があると行ったのはラッセルであります。このラッセルの言葉と、この『論語』の言葉(「君子は坦らかにして蕩々たり、小人は長く威々あり」)を突き合わせてみますと、意外なところに一致点があるように思います。
丈化には頭の文化と心の文化とがある。頭の文化はどんどん進んできたが、心の文化は一向に進んでいないではないかと、今から五十年前にラッセルが申したのであります。警告を発したのであります。それと、この『論語』の言葉とを併せ考えてみますと、いかにもラッセル言う通りであります。
現在においても、文化・文化と威張っているが、肝心かなめの心の文化の方は進歩どころか、反って退化し、駄目になっているではないか。「君、坦(たい)らかにして蕩々(とうとう)たり、小人は長く威々たり」、全く、先ず全くと言って差支えないでありましょう、心の文化は遅れております。本当にそのきめ細かく言えば、知的なものも考えようでありますが、心の問題に知が関係しないとは言えないかも知れません。それよりも、先の(注:前にあげた)魚屋さんのような人が仮りに居られたとしてみると、その人は余り考えるというよりも、人生を歩んでいるうちに、そういうことを体得するのであります。これはなる程面白いと思います。私は今、黒板に字を書いて思い付いたのであります。
この「君子は坦らかにして云々」と「君子は貞にして諒(りょう)ならず」と『論語』に言っているのですが、これを先に述べたラッセルの頭の文化と心の文化に当てはめると心の文化の面を示しているのであります。ラッセルが五十年前にイギリス人に警告して、みんな威張っているが、人間として大したことはないではないか、人間というものは心の面からみると、昔より反って劣っているではないか、と申したのであります。
と申しますのは、当時のイギリス人は七つの海に太陽の没することがないと威張っていた国であります。イギリス人であるというだけで、世界を闊歩することができた時代であります。現在とは大分違います。しかし、このイギリス人に対するラッセルの警告は、実は単にイギリス人に対してのみではなく、人間全体に対する警告でもあったのであります。
何と、なる程、こうして黒板に知と情と並べて字に書いてみると分かります。今こうしてこのことがはっきりしたことは不思議な感じがいたします。こういう意味で、なる程面白いですね。
(pp.9-14:小説『神狩り』のプロローグ)・・・。俺(ウィトゲンシュタイン)は、この土地を愛していたはずなのに・・・。悲しみにうちひしがれて、彼はそう考えた。ケンブリッジ大学を辞職までして、ここにやって来たのは、この地でだったらかれ(注:「神」?)と戦えると思ったからなのに・・・。
波は後から後から押し寄せてきて、海岸の総縁(ふさべり)に立つ彼の足を濡らしていく。その冷たさが、今の彼には、なにか救いであるかのようにさえ感じられるのだった。
「ヴィトゲンシュタイン先生--」
と、ふいに横手から彼の名が呼ばれた。ゆっくりと振り返る彼の眼に、岩陰から出てくる漁師の姿が映った。毎日、彼の元に牛乳を運んできて、身回りの世話をしてくれている漁師だった。人の善いこの漁師がいなければ、最も近い村まででも15キロはあるというこの地で、彼は一日として暮らすことはできなかったろう。
「やあ、おはよう」
彼--その難解な著作と、暗鬱な容貌で生きながら半ば伝説的人物になってしまっている哲学者ヴィトゲンシュタインも、この無欲な漁師には、笑いを見せるのだった。
「おはようございます」
と、漁師も挨拶を返して、
「先生、ロンドンから手紙がきています」
一通の手紙を差し出した。
そこに書かれてある名前を見て、ヴィトゲンシュタインの表情(かお)がパット明るくなった。バートランド・ラッセル。--この手紙を、ヴィトゲンシュタインはもう一月(ひとつき)以上も待っていたのである。ひったくるようにして、漁師の手から手紙を受け取ると、
「ありがとう」
顔も上げずにそれだけを言って、開封し始めた。
ヴィトゲンシュタインの奇矯な行為には慣れているのか、別にあきれたような表情もしないで、漁師はそのまま立ち去っていった。
手紙を読んでいるヴィトゲンシュタインの髪を、海から吹きつけてくる強い風がかき乱している。・・・いや、読んでいるのではない。見ているのだ。その封筒には、ただ一枚のレター・ペーパーしか入っていない。そして、そのレター・ぺーバーには、ただ一行の文字が連なっているだけなのだ・・・。
「俺はこんな手紙を待っていたのではない」
ヴィトゲンシュタインは力のない声でそうつぶやくと、そのレター・ぺーパーを風に放した。波打際に落ち、引き込まれるように波に攫われていったそのレター・ペーパーには、こう書かれてあった。
<私は神を信じない>
ついに、ラッセルとは相容れることがなく死んでいかねばならないのか・・・海を見つめるヴィトゲンシュタインの眼には、怒りではなく、哀しみの色が浮かんでいた。・・・ラッセル教授は神を信じない。そう、だからこそ、ラッセルとヴィトゲンシュタインは決別しなければならなかったのだ。
--私は、あなたの『論理哲学論』(『論理哲学論考』)のなかに、神秘主義の影響を感じます・・・。
28年前、ラッセルが寄こした手紙のなかにあったその一節を、ヴィトゲンシュタインは今もまざまざと思い出すことができる。
ラッセルとヴィトゲンシュタインは、トリニティ・カレッジで師弟の関係にあった。だから、ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論』が出版されるにあたって、ラッセルが長大な序文を書いて寄こしたのも、ごく単純な師弟愛からだったはずなのだ。
ところが、ヴィトゲンシュタインは、その序文を強く拒否した。その序文のなかで、自分の思想がラッセルの『論理的原子論』の方向に歪められている、と感じたからである。--以来28年、両人はついに顔を会わせることさえなかったのだった・・・。
だが、今の俺は師ラッセルをこの上もなく必要としている・・・ヴィトゲンシュタインは頭のなかでそうつぶやいていた。だからこそ、傲慢な自分自身を無理矢理に説きふせて、一通の手紙をラッセルに書かせたのではなかったのか。その返事がこれだ・・・。私は神を信じないこれだけなのだ。
ヴィトゲンシュタインは眼を閉じて、海岸に立ち尽していた。そうしていると、遠くに響いている海鳴りが、まるで誰かのつぶやく呪詛 (じゅそ) のように聞こえる。
呪詛の声こそ、俺には相応しい。
ヴィトゲンシュタインはそう思った。彼は、自分が呪われている、という確信を持っていた。彼の4人の兄のうち、3人までが自殺している。・・・その狂的な血と、彼自身の哲学との両方によって、呪いを受けているのだ。
呪いがそれほど怖いか。
ヴィトゲンシュタインはかっと眼を見開いた。
--語りえぬことについては、沈黙しなくてはならない。
かつてヴィトゲンシュタインが、『論理哲学論』の最後に著した言葉である。だが、今、その語りえぬことについて、語らなけれぱならない時がきたのだ。たとえ、そのために新たな呪いを受けることになろうとも・・・。
正直、彼独りの手には余る仕事だった。だからこそ、ラッセルの救けを求めたのだが・・・。こうなったからには仕方がない。独りでやるしかないのだ。
やり抜くことができるとは思えない。ここ数年、彼は腹に異物感を感じていた。父親を癌で失い、姉もまた癌によって失いかけている彼にとって、その異物感がなにを意味するものなのかは明白だった。
後3年、もしかしたら2年ともたない生命かもしれないのだ・・・。
だが、これはやらなければならない仕事なのだ・・・。ヴィトゲンシュタインはそう自分に言い聞かせた。俺が挫折することになっても、きっと誰か仕事を受けついでくれる人が現れるに違いない。
重い雲がちぎれかけて、海にうっすらと陽が差している。
その海を見つめるヴィトゲンシュタインの眼に、ようやく和やかな光が浮かび始めていた。
それから3年後の1951年4月、ヴィトゲンシュタインは、ケンブリッジで62年の生涯を閉じた。死因は癌腫であった。(プロローグ終わり)
(pp.256-261:「チキン」)
バートランド・ラッセルは、この「チキン(弱虫)」(チキンゲームのチキン)に、核戦争の手詰まり状態の一つの比楡を見た。1959年出版の『常識と核戦争』(Common Sense and Nuclear Warfare)のなかで、ラッセルはこのゲームについて(以下のように)説明しているだけでなく、このゲームを実際に地政、国政レベルで応用している人々に対し、忌憚のない意見も書いている。ちなみに、ラッセルが解説した方のゲームが、今では(少なくともゲーム理論の世界では)「正統的」なチキンゲームとされており、映画の崖から落ちる方のチキンゲーム(例:ジェームス・ディーン主演の映画『理由なき反抗』のなかのチキンゲーム)とは区別されている。核の手詰まり状態がはっきりして以来、東西の政府は、ダレス氏(米国国務長官)の言うところのいわゆる「瀬戸際政策」を取り始めた。この政策の名称は、不良青年たちのやる一種の遊びのイメージから取られたものと聞いている。この遊びは「弱虫!(チキン!)」というゲームだ。まず中央に白線の引かれている長いまっすぐな道路を選び、左右の端に分かれた2台の車を同時に発車させ、猛スピードで互いに接近していく。どちらの車も、左右の車輪のどちらか一方は、白線の上を走らせなければならない。2台の車か接近するにつれて、正面衝突の危険も増大していく。もしどちらかが、先に白線からはずれて相手をよけたら、その相手はすれ違いざまに「弱虫!(チキン!)」と叫び、よけてしまった少年は軽蔑の対象となる。・・・。
無責任な少年たちがこのゲームをやれば、頽廃的で不道徳たと言われる。だが、その場合危険にさらされるのはゲームをやっている当人たちの命だけだ。しかし、有力な政治家たちがこのゲームをしたらどうだろう。当人の命のみならず、何千万もの人命が危機にさらされることになるのに、どちらの側でも、自分の側の政治家は、その高度な知恵と勇気を示しているのであり、相手側の政治家だけが非難の対象だと思っている。これは無論ばかげたことである。こんなに危険なゲームをやるというのは、両者ともに責任がある。悲劇が起きずに過ぎることもあるかもしれないが、そのうちに、面子(メンツ)を失いたくないという気持ちの方が、「核による絶滅の恐怖」に勝ってしまう時が遅かれ早かれ来てしまう。相手方から「弱虫!」と軽蔑の言葉を叫ばれることが、もうどうしても嫌だと両者ともに思う時が来てしまう。その時、両国の政治家の手で、世界中が破滅へ突入するのである。
(pp.59-86:第2章「若きウィーナー」)
(p.64) そしてウィーナー青年は、ケンブリッジ(大学)でそれ以上のことを学んだ。あの威厳ある高度な知性と衰退する貴族階級の砦の周りに、特異さを芸術の域へ高める、幅広い奇抜さを見た。有名なトリニティのおかしなお茶会(注:マッド・ティー・パーティ → 通常「気狂いティー・パーティ」)を構成する3人の哲学のドン --ラッセルと、新しい「常識」の哲学者G・E・ムーア、イギリスでへーゲル観念論に抵抗する最後の人物J・E・マクタガート(注:原文が間違っているのか、誤訳なのか不明/マクタガートは有名なヘーゲリアン)--は、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』からそのまま出てきたような人物だった。おかしな帽子屋(→気狂い帽子屋)と言いえばラッセル以外にはなく、ブルームズベリーの群集(注:誤訳では?)と戯れ、魅惑的なイギリスやアメリカの女性との顰蹙を買うような色恋に戯れる、ひょろっとした、野性的な貴族だった。・・・。(参考:N. ウィーナー「解放-ケンブリッジ、1913年6月~1914年4月」)
(pp.362-387:第12章「ある科学者の反乱」)
(pp.382-383) 『人間の人間的利用--サイバネティックスと社会』(注:邦訳書名は『人間機械論』(みすず書房))は、『サイバネティックス』に対して向けられたすべての非難に開かれていて、当たっているものもあった。おおざっぱな構成で、社会批判については遠慮がなかった。それでも、欠点と見えるところが、1950年代初めの、不安な大衆の心には感じるところがあり、本はよく売れた。読者も書評も、ウィーナーほどの科学者が、切迫した普遍的な重みをもつ問題について、これほど力強く声を上げることに、密かにぞくぞくしたらしい。ウィーナーのかつての気難しい恩師で、すでに80歳に近く、前年にはノーベル文学賞も受賞したバートランド・ラッセルも、言うことをきかなかったかつての学生に高い点数を与え、イギリスの一般誌で温かく支持した。「人間は必要か」という題の文章で(注:Are human beings necessary? In: Everybody's Weekly, 15 Sept. 1951, p.13.)、ラッセルはウィーナーの本を、「とてつもなく重要な本」と喝采した。ウィーナーが、「人類がその労働と、他の巧妙な人々の労働の結果としてつきつけられる危険を、ゆゆしい口調で」出した功績を認め、「この新しい[産業]革命が、広大で例のない悲惨をもたらさないとすれば、世界が文明の始まり以来その上に乗って進んできた基本的な前提をいくつか変えなければならないだろう」と請け合った(ママ)。
(pp.100-102:組み合わせを変える)
(p.101) ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker, 1909年-2005年11月11日)は、新しい組み合わせによって開発された代表的な例としてコンピュータをあげる。コンピュータは6つの異なる分野の知識が結びついて開発されたものだ。
17世紀末に「二進法」が発見されて、あらゆる数字は1と0で表現できるようになった。19世紀のはじめに「計算機の概念」が生まれ、人口を調査するために「パンチカード(機械式統計機)」が発明された。1906年(明治39年)に「電子スイッチ」と「真空管」が生まれた。1910年(明治43年)にバートランド・ラッセルが、はっきりしたデータとして示されたあらゆる概念は、1と0(オンとオフ)ですべて表現できることを発見し、「論理は数学的に処理できる」ことが分かった。コンピュータが発明されたのはそれから35年後である。1946年(昭和21年)に、それまで発見された6つの異なる知識が一つにまとめられたのである。パソコンが普及したのはさらにそれから40年後のことである。・・・。
(p.181)耳で聞き、耳で読む

イギリスの世界的哲学者だったバートランド・ラッセルの自伝を読んで、おもしろいことにぶつかった。「耳で読んだ」というのである。どうして、耳で読めるのか、というと、読み手がいて、読んでもらって、それを聞く。それで、「耳で読む」となるのだ。読み手は夫人が当たった。ところが、この奥さんがたいへんなタバコのみだったそうで、タバコを吸う間は、読むのが中止される。ラッセルは、それを待っていたという。注目すべきは、こうして耳で本を読むようになってから、書く文章がよくなったとラッセル自身がのべていることだ。もともとラッセルは文章家であったが、いっそう磨きがかかったというのであろう。晩年の文章は清澄で深さをたたえる名文である。・・・。
(p.185)未知を読めば
・・・。漢学の素読ができなかったのは、時代のせいでしかたがないとあきらめてはいたが、残念であった。しかし、それに近いことを毎日のお勤め(注:読経)でしていたのだと気がついたとき、妙にうれしかった。すくなくとも、耳で読むことを覚えた。バートランド・ラッセルの自伝でつよい感銘を受けたのも、いくらかそれに通じる経験がこちらにあったからであろう。・・・。
<第7章:教区学校に対する援助をめぐって--公正さを探求する>
(p.418)
・・・。また同じ時期、リベラルなアメリカ人知識層とカトリック高位聖職者の間の公的道徳をめぐる論争は、検閲および学問の自由という具体的争点をめぐって表面化し、両者の関係をより悪化させることになる。バートランド・ラッセルが、1940年に性と結婚に関する自らの見解を糾弾されて、ニューヨーク市立大学の職を追われたとき、ラッセルは、この処遇がカトリック政治勢力によってもたらされたとみなした。これはもっともであった。たとえば、主要なカトリック雑誌や、大司教フランシス・スペルマン Francis Spellman は、ラッセルの「反宗教的見解」を問題視し、執拗に攻撃したのだ。ただし、この事件では他の宗教指導者も同じように関与していた。事実、ラッセルの第一の論敵は、むしろ英同国教会であった。ただし、リベラルな考えを持つカトリックの高位聖職者や知識人が、ラッセルの弁護のために声を挙げることがなかったのも確かである。したがって、リベラル派がアメリカの政治生活におけるカトリック・ヒエラルキーの影響力に懸念を持ち、教区学校が検閲を支持する教育を行っているのではないかと疑いにかかったのも、それ相応の理由がないわけではない。実際に、思慮分別をもった多くの人たちが以下のような結論に到達したのである。すなわち、かりに最高裁が教区学校の存在を容認するとしても、少なくとも私たちだけは、教区学校に対するほんの僅かの公的助成にも断固反対の立場をとるべきである、と。・・・。
(pp.5-13:はじめに)
(p.5冒頭) 1948年のバートランド・ラッセルからはじまった由緒あるリース講演(Leith Lecture)に、初の医師・実験心理学者の講演者として2003年に招かれたのは、私にとって名誉なことでした(注:ラッセルの第1回講演 Authority and the Individual は1948に出版されている。また、南雲堂から1959年に『権威と個人』という訳書名で出されている。全6回の講演(肉声)の録音の視聴)。リース講演は過去50年間、イギリスの知的・文化的に名高い場所で開催されており、また、招待を受けた私にとっては、ティーンエイジャーの頃にその業績から大きな影響を受けた、そうそうたる歴代の講演者たち、ピーター・メダワー、アーノルド・J・トインビー、ロバート・オッペンハイマー、ジン・K・ガルブレイス、バートランド・ラッセルほか多数のリストに、仲間入りができるのもうれしいかぎりでした。
しかし、歴代の講演者たちが、私たちの時代の知的風潮を決定づけるのに重要な役割をはたした偉大な人びとであるだけに、そのあとに続くのは容易なことではないという認識もありました。さらにリース卿(BBC初代会長)がこの事業を始められたそもそもの趣旨に沿って、専門家だけでなく「一般のひとびと」にもよくわかるような講演をしなくてはならないという手ごわい課題もありました。・・・。
(pp.10-11) ・・・。このような探究--ヴィクトリア朝時代人のような着想--は、現在の私の専門分野である神経学や心理物理学とは、まるでかけ離れています。しかし子ども時代に夢中になったこれらのことごとは、消すことのできない刻印を残し、「おとな」としての私の人格にも、科学を実践するスタイルにも、大きな影響をおよぼしているにちがいありません。・・・。たぶん自分だけの世界に逃げこむことを、孤独だとか、「おかしい」とか、変わっているとか、そんなふうに感じるのではなく、自分は特別だというふうに感じていたのでしょう。おかげで私は、退屈さと単調さ-ほとんどの人が「普通の生活しと呼んでいる、つまらない生活-を超越し、ラッセルの言う「高尚な衝動が、実世界という流刑地から逃避できる」場所に行くことができたのです。
(pp.64-65)・・・。Alan Wood の Bertrand Russell; the passionate sceptic, 1957 (Unwin Books, 1963)は,そう面白くはなかった。彼(アラン・ウッド)は、批判的にラッセルを理解しているが,反対の立場をのりこえて暖かい気持ちで彼について記述している。この本に,さほど魅力を感じなかったのは,これより4年前に,碧海純一(訳)『バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家』(みすず書房,昭和38年2月/昭和41年1月=第9冊)を読んでいたためであろう。もっとも、翻訳に感激したというよりも、同時に内容にも感動していたのだと思う。・・・。
(松下注:誤解を生じさせそうな書き方となっている。秋山氏が言いたかったのは「碧海教授の翻訳はすぐれており、アラン・ウッドが書いた内容もよかったので最初読んだときはとても魅力的な本だと思った。しかし、4年経過して読み返してみると、「新鮮さ」が減り、最初に読んだときほど良いと思わなかった。」ということであろうが、上記の書き方ではそのように受け取らない人がいそうである。
因みに、秋山氏のラッセル関係の論文等に、他に、以下のものがある。
・「D.H.LawrenceとBertrand Russellの人間的思想的相違について」[『八幡大学社会文化研究所紀要』v.7(1980)
・「(研究ノート)Bertrand Russell の翻訳に見られる誤訳などについて」[『八幡大学論集』v.33,n.3(1982年9月)pp.132-162]
・「同上その2」[『八幡大学論集』v.33,n.4(1983年3月)pp.117-142]
・「Bertrand Russell の思想に関する覚え書き」[『八幡大学論集』v.35,n.4(1985年3月)pp.117-142]
・「Bertrand Russell 書誌」[『教養研究』(九州国際大学教養学会)v.12,n.3(2006年3月)pp.111-132]
(pp.254-256:抽象的で厚みのない哲学のテクスト)
(p.254) まず,B.ラッセルの『数理哲学序説』(Bertrand Russell, An Introduction to Mathematical Philosophy(London: Allen and Unwin, 1919. repr. London and New York: Routledge, 1993)から,英語の原文とそれに対応する日本語の訳文を挙げます。
[平野智治(訳)『数理哲学序説』(岩波文庫,1974年)pp.25-26]
再び数の定義に帰ろう.数は,ある種の集合すなわち与えられた個数の要素をもつすべての集合を,1つの束にまとめるための手段である.吾々は2つの要素からなるすべての集合を1つの束に,3つの要素からなるすべての集合を別な束にまとめ,この方法を順次続けると,要素の数の同じ集合がみな同じ1つの束にまとめられ,その結果いろいろな集合の束がえられる.各々の束の要素はみな集合であるから,束はいわゆる集合の集合である.
ラッセルが用いる英語の単語や構文は平易ですが,こうした話題になじみのない読者には、引用した箇所は抽象的で難解な文でしょう.ですが,この文のもつ抽象性は,英語という一言語や英語圏の文化にのみ特有なものではないし,英語で表わされた思想だから難解というのでもありません.'number'(数),'co11ection'(集合),'term'(要素),'bund1e'(束)といった概念や,これらの概念の組織は,日本語の文法や語彙体系に移されることによってもあまり影響を受けない.数についての論理的な解明というような「厚みのない」話題については,英語でも日本語でも同じ事柄を表すことが可能なのです。ですから、訳文のような比較的自由な訳も、「同じ事柄」を伝達しえている限りは、許されることになります。
(pp.245-246)きょうは、バートランド・ラッセルが1922年に公にした『中国の問題』*1についてお話ししたい。・・・。以下省略。
*1:Bertrand Russell, The Problem of China(London: George Allen and Unwin, 1922; reprint, 1966), 260pp. 邦訳としては、牧野力訳『中国の間題』(理想社、1970年)。この訳書には、「バートランド・ラッセルと中国」と題する新島淳良氏による解説(全55頁)が収められている。なお、本稿においてラッセルのこの書物から引用する場合は、冒頭にモットゥとしてかかげた三つの引用文をふくめて、ぺージ付はすべて英文原書の1966年リプリント版による。
本書は彼の中国・日本での旅行体験をふまえて書かれたものであるが、単なる印象や場当りの思いつきを記したものではない。行動的な哲人ラッセルの欧米近代社会に対する辛辣で機智に溢れた批判にしっかり裏打ちされた歴史的・比較文化論的な発想を理論的な粋組として書かれたすぐれた「同時代史」である。中国を主たる対象としているが、全15章のうち4章を日本にあてている。ところで、私のねらいは、この本の内容について詳しく述べることではない。むしろ、この本を歴史の流れのなかにおいてみること、そして、ラッセルその人の思想および行動と関連させて、それを背景において位置づけてみること、-いわばこの本を額縁に入れてみるという*2ことである。
*2:ラッセルの人と思想については碧海純一『ラッセル』(動草書房、1961年、全247頁)がよい参考になる。また、彼の思想ないしは中国における活動が、どのような影響を中国に残したかという点については、訳書にある新島氏の解説がすぐれているので、その方に譲って、本稿では触れない。 ・・・。
(pp.254-255) 当時の国立北京大学は1917年依頼、蔡元培(1867から1940)が総長をしていた。彼は1926年まで在職したが、教授陣に大いに人材を集めた。新進気鋭の士もあれば、保守的な老大家もあるというわけで、北京大学は軍閥政治の暗黒な政治世界のただなかにおいて、学問の砦を成していた。学生数は今日の感覚で考えると非常に少なくて、300名から400名程度であった。ここが有名な文学革命の中心であって、五四運動のデモの中心になったのもここの大学生たちであった。それ以後のいわゆる五四運動の中心になったのがこの北京大学である。まさにこの五四運動の燃えさかっているときに、ラッセルはここで講義をし、セミナーをし、ことにセミナーで親しく学生たちと接触したわけである。・・・。
(pp.279-280) また、日本人と中国人とを対照させて次のように述べている。「中国人は何か一つの命題を、それが真であることが証明されるまでは疑い続ける。日本人は、それが虚偽であることが証明されるまでは、信じ続ける。」(『中国の問題』p.169)
[pp.104-106: バートランド・ラッセルの波乱万丈]
(p.104) まず、バーティの愛称で呼ばれたラッセルをみよう。彼はジョニー(=フォン・ノイマン)より前に集合論の公理化を手がけた。むやみに長々しい形の公理化をし、そんな形は必要なかったとあとでわかっても頑固に非を認めなかった。」
(p.106) ラッセルはやがて、見たところ順調な万事にしじゅうかみつく人になる。1950年代はアイゼンハワーの政策に異議を唱えた。戦後はイギリスの一方的な核廃棄を要求する旗を振り、1961年にはケネディ大統領とマクミラン首相を「ヒトラーどころか・・・史上最悪のやから(注:・・・の省略も原文のママ)」とこきおろす。まだ講義をしていたころのラッセルは、紳士のはずなのに、彼より賢くない人にも理不尽とわかることを頭ごなしの調子で学生にまくしたてたらしい。」
(p.109) こうした事実を暴いたからといって、浅はかな保守主義者のように、ラッセルやウィーナーやその他たくさんの数理科学者の知性をおとしめるつもりはない。とはいえ、庶民としては、ラッセルみたいに暴風のごとき感情に襲われ、ところかまわず吹き飛ばされ、苦悩の深海を越えて絶望の断崖にぶち当てられる感情的な学者よりは、目の前の事実を冷静にみつめながら動く科学者のほうが安心できる。
(p.124) 1901年、神経衰弱の寸前からなんとか立ち直ったラッセルは、「存在する万物の類(クラス)」の内部矛盾を解消しようとして大著の執筆にかかる。ホワイトヘッドと書いた『プリンキピア・マテマティカ』は1910~1913年に出版され、おおかたの矛盾はつぶせたものの、冗長で、一部は無用の長物だし、大戦のあと外国人嫌いになっていたドイツ人たちは、いかにもイギリス的で阿呆くさいとみた。ジョニーは『集合論の一公理化』(1925年出版。執筆はそれ以前)で当の問題に取り組み、学位論文『集合論の公理化』(1928年出版。これも執筆はずっと前)で仕上げた。高価な『プリンキピア・マテマティカ』を買って格闘するのに二の足を踏んでいた学生にとって、ジョニーの論文は天の恵みだった。ドイツやアメリカの教授に言わせると、ジョニーは大著の中身をたった1ページの公理に置き換えたことになる。
(p.125) (ジョニーはすぐにゲーデルの正しさと価値を認めたのに、おおかたの研究者はできなかった。)ラッセルの反応はどうだったのか。大いに興味がある。35年後に書いた自伝のなかで、あの育ちならさもありなんといった反応を見せている。・・・。」
[pp.192-194:「デモクラシー思想からラッセル、モームへ」]
(p.193) ・・・。この本(原仙作『英文標準問題精講』)は1933年の初版以来5回改訂されているから、それらを比較すると(入試英語の)出典の変化がわかるわけだ。拙著『日本人は英語をどう学んで来たか』(研究社,2008年)に掲載した分析結果をもとに,頻出作家を年代順に並べてみよう。
(『英文標準問題精講』の)1954年(昭和29)年版までは戦前と同じような傾向だったが、1962年版からはバートランド・ラッセル(15大学)、サマセット・モーム(12大学)、オルダス・ハックスレー(10大学)などの現代作家の作品が圧倒的な人気を誇るようになった。・・・。
話をもとにもどすと、表5-3のすべての時期を累積すると、1930年代以降の入試に頻出の作家ベスト5は次のようになる。
一位:ラフカディオ・ハーン(39回)/二位:バートランド・ラッセル及びロバート・リンド(33回)/四位:チャールズ・エバレット(27回)/五位:サマセット・モーム(25回)・・・。
[pp.111-117:「我慢できない大知識人-バートランド・ラッセル」]長くなりましたので、引用はここまでとします。全文をお読みになりたい方は、図書館で借りるなどしてください。
(p.111) 大知識人はしばしばとんでもなく好色漢であったりする。ヴォルテールがそうであり、サルトルがそうであった。そしてケンブリッジの先生の代表としてはバートランド・ラッセルがいる。
・・・。ポール・ジョンソンが『インテレクチュアルズ』で知識人批判を行ったのは1988年であった。(別宮貞徳(訳) 共同通信社 1990年)。そこではもちろん、ラッセルに一章が割かれている。・・・。
(p.113) ラッセルはアリスの影響で社会主義に興味を持った。結婚生活ははじめはうまくいったように見えた。しかしやがて、あまりに欲望の強いラッセルはまじめな妻にあきてきた。
1901年、彼は先輩のアルフレッド・ホワイトヘッドの妻イヴリンに恋した。この時から彼は性的欲望の解放に目覚めたという。自由恋愛を実践するようになる。特に人妻が好きであったという。
1910年、彼はレディ・オットリン・モレルに恋する。・・・。
アリスと離婚したラッセルは、夫のいるオットリンの恋人になり、性の快楽に目覚めた。
1914年の最初のアメリカ講演旅行の時に、彼は突然、プレイボーイに変身した。すでに40歳を過ぎた教授は、出会うアメリカ女を片はしから口説き出した。しかも、彼はそれらの情事を、他の愛人たちにかくさず報告した。彼の愛人は、彼の浮気を認めていたようである。ラッセルは人妻が好きであったが、彼女の夫たちもそれを認めていたらしい。
(p.115) ドラ・ラッセルは『タマリスクの木』(山内碧(訳) リブロポート 1984年)という素晴らしい自伝を書いている。そこで彼女はラッセルについて、かなり厳しく書いている。「・・・。このような男性が生きていく上で、多数の人々を傷つけるのは避けられないことだが、悲劇的な欠点は、彼がその避けられないことに対して、何の感情も持たないことだった。・・・。」
(私の下記の引用の仕方はかなり恣意的です。興味のある方はぜひ本書をお読みください。残念ながら、6月15日現在、アマゾンでは売っていません。)
・・・。
(p.155-156)オットリーヌ・ヴァイオレット・アン・カヴァンディッシュ・ベンティンクは、一八七三年六月、陸軍中将アーサーの第五子として生れた。父親のアーサーは、軍人としての俸給のほかに第五代ポートランド公爵の従兄から定期的に収入を得、第六代の爵位継承の日を待ちながら安楽な生活を送っていたが、五十九歳の年に急死した。一八七九年十二月、第六代ポートランド公爵の位を襲ったのは、二十一歳になる先妻の一人息子アーサーである。ダーピシャー、ノッティンガムシャー、ノーサンバランド等に広大な所領を有する新公爵は、異母妹と義理の母親を疎んじることなく、三十一歳で結婚したのちも、物心両面にわたる援助を惜まなかった。オットリーヌには実に千五百ポンドの年収が保証された。・・・。
彼女は風変りな女性だった。『キリストの顰(ひそみ)にならいて』を愛読して宗教的情熱を燃やし、ウェルベックの大邸宅で使用人のための聖書教室を開いた少女時代、社交界と上流社会を嫌って家族を絶望させた思春期、親族会議の許可を得てスコットランドのセント・アンドリューズ大学で論理学を学んだ二十四歳の春の決断、その経歴のどれをとっても、およそその出生にそぐわない、どこか現実との蝶番(ちょうつがい)がはずれたような女性である。面長だがふっくらとした可憐な少女が、身の丈六フイート近い(約一八三センチ)おどろおどろしい女性に生育し、長い鼻で衆人を圧倒したのもその一つの現れなら、蝶の舞うような筆跡も奇抜である。・・・。
(p.156)一九〇二年二月、二十八歳の年に、彼女はオックスフォード大学の顧問弁護士の職にあったフィリップ・モレルと結婚し、一族郎党を安堵させた。・・・。一九〇六年一月、英国選挙史上に残る自由党大逆転の総選挙で、フイリップは大方の予想に反し、自由党候補として当選したのである。
オットリーヌは下院議員夫人になったが、議員夫人の地位は彼女には何ほどのものでもなかった。この年の五月、娘ジュリアンを産んだ産後の肥立ちが悪く、そのためヒステリー症状を呈し始めた彼女は、翌年二月婦人科医による手術を受け生涯子供の産めない体になると、むしろこれを僥倖として、ロンドン社交界にサロンを形成する大望を抱き始めた。世のため人のためという大義は、思春期の社交嫌いを過去の挿話に変え、当時有閑階級に属する女性の間でその能力を発揮する最古かつ最も贅沢な手段としてもてはやされたサロン形成の願望に合体したのである。・・・。勇名を馳せつつあったジプシー・スタイルの画家オーガスタス・ジョンを手始めに、ヘンリー・ラム、ロジャー・フライらとの間に生まれた熱烈な恋愛と書簡の交換、相手を食傷させるような贈り物による攻勢、その帰結としての関係の冷却等、いかにも「お人好し」のオットリーヌにふさわしい出来事には枚挙に遑(いとま)がない。・・・。
(p.160)・・・。一九一〇年一月、三十七歳のラッセルが折から実施された総選挙で自由党議員フィリップ・モレルの応援に立ったとき、彼の人生を画する新しい事件の伏線が敷かれることになった。翌一九一一年三月、ソルボンヌ(大学)から講演依頼を受けた彼が出発前のロンドンでの投宿地にベッドフォード・スクウェアのモレル家を選んだ夜、選挙区に発ったフィリップを欠いた邸でオットリーヌと話し込むうちに二人は親密さを増し、明け方の四時頃には実質上の肉体関係が生れていたのである。
ラッセルの青春はこの日から始まった。以降おそらく四年間のうちに彼がオットリーヌに宛てた書簡は二千通、オットリーヌの返書は千五百通に上ったという。オットリーヌの伝記作家は、テキサス大学の収蔵するこの書簡を多数引用して二人の愛の推移を辿っているが、そこから判断する限り、時に哀願し時には喧び泣いて二人の愛を繋ぎとめようと試み、ついに絶望して自殺まで考えなければならなかったのは彼女ではなくラッセルの方だった。・・・。ラッセルはまた、妻のアリスに年収の半分を提供する条件を示して離婚話を持ち出したため、彼女から逆にオットリーヌの名を公けにして醜聞沙汰にすると脅された。・・・。
ラッセルはやがて彼女以外の女性との恋愛を楽しむ術を体得したから、ロレンス夫妻がベッドフォード・スクウェアに招かれた頃には、再び彼らは平穏な交遊関係に戻っていたのである。
〔ロレンスとラッセルという〕二人の情熱家は最初からお互いに好意を砲いた。自動車で〔グレタムから〕戻る途中、バートランド・ラッセルは、「驚くべぎ男だ。底の底まで人を見抜く」と叫んだ。「その通り。だけど本当に間違っていない?」と私〔オットリーヌ〕は尋ねた。「絶対に。彼は無謬だ」というのがバーティ(ラッセル)の返答だった。「エゼキエルか、旧約聖書の他の預言者が、まるで予言をしているようだ。むろん非国教徒の先祖の説教者の血が濃いんだが、何でも見通していていつも正しいんだ」
二月八日、オットリーヌが記録したラッセルの言葉は、五十年余りのちに書かれた彼の『自伝』の中の、「私は民主主義の確たる信奉者だったが,ロレンスは政治家達に先立ってファシズムの全哲学を展開していたのだった」という類の文章からは想像することもできない。しかし最初の対面から半年ほどの間、ラッセルはロレンスの思想に共鳴し、ロレンスも十三歳年上のラッセルから大きな影響を受けた。・・・。
(pp.195-212 ケース・スタデイ9「92歳にして立つ」)
[富永氏の情報源は『ラッセル自伝』と思われるが、少なからず事実誤認(誤読・誤訳や勘違い)や不正確な記述等があるが、書かれていること自体は的外れではない、と思われる。]
・・・。
さて、一体バートランド・ラッセルは、偉大なる人類の先導者なのか、それとも、非難されるべき好色漢なのか? ・・・。
彼が偉大なのは、メリット賞(注:メリット勲位)やノーベル賞(注:ノーベル文学賞)を受賞するに相応しいだけの業績を持つ人間であるにも拘らず、いかにもその賞に相応しい偉人タイプに自分を描かなかった、公正さにある。(注:『ラッセル自伝』の記述の率直さについて言っていると思われる。)・・・。
オットリーンとのことも、コレッティとのことも、最終的には狂気に陥ってしまったあのシカゴの娘のことも、彼自身が伝記の中に詳細に書いていることなのである。こういう事実の顛末を、功なり名を遂げた人間の誰が、自分で書くだろうか?
誰しも神様ではない。失敗もするし後悔もする。若気の過ちも、壮年の愚考も、老いの間違いもある。なぜなら、我々は皆人間なのだから。・・・。そういう、人に知られたくない事実を、これだけあからさまに描くことこそ、偉大と形容するに値するのではないか。・・・。
最後の質問に入ろう。バードランド・ラッセルは何歳で始めたか? ・・・中略・・・。 だから、私は確信して疑わない。1970年2月2日、北ウェールズはプラスペンリンの山荘で、エディス夫人に看取られつつ、97歳の生涯を全うしたバートランド・ラッセルは、その時、決して死ぬことではなく、断固として生きることを、また新たなるスタートを切る時のことを、考えていたに相違ない、と。
(pp.9-12 はじめに)
・・・。
「愛はエゴの固い殻を破る」と、バートランド・ラッセルは言った。愛を知ることによって人間は思いもかけない変身を遂げるというわけだが、師もまた恋人と同じように、人間を変えさせ、独善の殻を打ち破ってくれる。その場合、師には若者の生硬な批判をガッチリと受けとめる大きさが、そして若者にはハネつけられても食いついていくしぶとさが何よりも要求される。・・・。
(pp.374-375 クリスマス・キャロル)
・・・。
何時の世にも、善きもの、美しいものは、なかなか眼に入らないのだ。そうであるとすれば、寒々とした出来事ばかりが眼について、心がはずまないなどと嘆くのは、こちらの眼がわるいのかも知れぬ。つまり、心あたたまるものを求めながら、何時の間にか、心あたたまるものに対する自分の感受性が荒れてしまっていて、見るべきものを見ず、感じるべきものを感じないのであろう。考えてみると、それもあながち否定はできないようだ。
かのディケンズの描くところの冷血強欲なスクルージ老人のもとへは、幸いにしてクリスマスの晩、過去、現在、末来の降誕祭の精霊が訪れてくれた。そのおかげで、スクルージ老は感受性と人間らしいあたたかい心を取り戻すことができたのだが、さて、待てども待てども、私たちのところへは、精霊さんも現れない。・・・。
バートランド・ラッセルがある時、「もし死んだ後で、創造主に出会ったら、何といいますか」とたずねられたところ、彼はためらわずに「神よ、何故あなたは、ご自分の存在の証拠を、こんなに不十分なままにしておおきになったのですか--というでしょう」と答えたということである。さすがにラッセル卿らしい答えであり、イギリス的自由人の面魂すら感じられるが、さて「神」がこのラッセルの問いをいかに受け止め給うたかは--ラッセル卿は亡くなってすでに久しいが--知る人とてもない。
どうやら無心で心貧しき人にのみ、クリスマス・キャロルは届くようだ。(1985年12月24日)
[pp.132-158: 20世紀の経験主義-ラッセル、エイヤー、ウィトゲンシュタイン他]
((p.132)・・・。(哲学の)大衆化に努めたほかの哲学者と同じように、バートランド・ラッセルもまた、厳格さでは彼にまさる --そして知性では彼に劣る-- 同業者たちからは疑いの目で見られることもあった。しかし、ラッセルに刺激された聴衆のなかにはその後、学問の世界で文句のつけようのない成功をおさめた人もいる。そのなかの一人、一筋縄ではいかない著名なアメリカの現代哲学者、ウイラード・ヴァン・オーマン・クワインは聴衆の哲学者たちを前にしてこのことを証言した。「わたしの仲間の多くは、ラッセルの本に感化されてこの道にはいりました」。影響力の大きさで言えば、『哲学の諸問題』(The Problems of Philosophy, 1912)ほど重要なものはない。これは一九一二年に初めて出版されて以来、大学生の哲学入門書としていまだに推薦される本だ(松下注:ウィトゲンシュタインは、ラッセルの『哲学の諸問題』(邦訳書書名は『哲学入門』)を「三文小説」であると言って非難した。哲学観が異なるとその評価も雲泥の差が生ずるよい例です。)。
ラッセルと(クマの)プーの類似点ははっきりしている。いま僕たちがしているのは、「偉大なるクマ」の哲学的知識と理解のはばの広さを手短に描き出すことだ。だから、プー物語にあるラッセルの哲学は多種多様でたくさんあるが、ここではプーが説明しているものからひとつだけをとり出すことにした。集合論である。集合とはその集合の元、つまり要素であるものの集まりということだ。次にあげる五つの文を見てほしい。・・・。
(p.58) バートランド・ラッセルについて語ることにはかなりの逡巡と忍耐を必要とする。というのも、彼が読者にそれを強いるような書き方をするからである。(松下注:当初、4月号に掲載される予定だったらしいが、「逡巡」の結果、5月号掲載になったらしい。)例えば、一九四六年(松下注:米国では1945年に出版されており、1945年の間違い)に書かれた彼の『西洋哲学史』第二十五章「ニーチェ」の項では、「ニーチェの超人は、ギリシャ語を知っているということを除けば、ジークフリードに酷似しているのである。これは変に思えるかもしれないが、別にわたしが悪いわけではないのである。」(市井三郎訳『西洋哲学史3』みすず書房、一九七〇年)と、ニーチェを放り出すような書き方をする。かと思えば、序説のところで南欧イタリアのルネサンスに対抗し、「宗教改革は-ローマの新しい支配に抗する北方諸国の反逆であった。」(同書1)とか、欧州南北比較の瞠目(どうもく)すべき鋭利な視点を提示するかに見える。注がないので、ラッセルの独創だと思うではないか。だが次のように、ニーチェの本歌取りだったりする。 ・・・。(後は、図書館などでお読みください。/読書会会員用(要パスワード))
(p.12)・・・。
長滝 選択のミスが起きた(笑)。
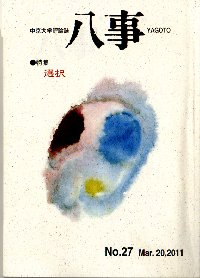
三浦 そう、選択ミスが起きましたね。これは事前にリサーチしなかったのがいけなかったんですが・・・。仕方がないので、川本皓嗣(1939~。欧米と日本の詩の研究。現在、大手前大学学長。学士院会員。主著『日本詩歌の伝統』)という詩の先生に付きました。形だけ付いたということです。それで修士論文は哲学を扱えないので、しょうがないからバートランド・ラッセルの評伝に取り組みました。大正時代に来日したときから晩年の平和運動まで、つまり人物研究ですね。そういうことで修士論文は書きました。
(p.14)
長滝 なるほど。そうすると、小説の方は学部生の頃から投稿していて、実際に本になったのは就職されてからですか。
三浦 そうです。就職一年目のときに投稿したのが雑誌に載って、それから本が出るようになりました。最初に雑誌に載ったのは三十(歳)のときです。それ以前にラッセルの平和運動のことを書いたりして、ちょこちょこ原稿料はもらっていましたけどね。初原稿料はラッセルでした。
長滝 そうですか。ラッセルに関しては何年か前に岩波新書から本を出されましたね。
三浦 ええ、あれはもう哲学ですね。今年(2010年)、イギリスから寄稿依頼があって、戦前・戦後の日本とラッセルとの関わりを論じたエッセイを書きましたが、ラッセル評伝は二十年ぶりで・懐かしい気分でした。だいたい今はラッセルを論じるとしたら「ラッセルのパラドクス」とか「記述理論」とか、数学や哲学の話題が主になっています。
(pp.125~134:ヨーロッパから学ぶこと)
(p.126~ )・・・。1965年にヨーロッパをまわった時のことを思い出す。
イギリスの労働党政府はポンド不安の問題とマレーシアの安全保障問題があるので、ベトナム政策については、公式にはアメリカとぴったりくっついていた。しかし、中国政策についてはアメリカのそれと全然違っていた。ロンドン・シティで財界人などと会うと、「アメリカのベトナム政策はまったく狂気のさたではないか。いったいどこに解決のメドがあるのであろうか」と語っていた。労働党の左派も批判的だった。それだけの冷静さがあった。
経済力が弱ったからといって、「西欧の没落」とか「英国病」とかいってバカにする風潮があるが、ヨーロッパの奥の深さをあなどってはいけない。文化、伝統というものを評価しながら付き合うことが大事だ。民主主義にしても、イギリスには、王権に対する個人の権利を保証するための長い歴史がある。若い時ジュネーブでバートランド・ラッセル(イギリスの哲学者)に会った時、「イギリスの民主主義は三百年の経験がある」と言われたのを思い出す。イギリスは、王様に対する個人の権利を保証する長い歴史があったので、それが根づいて、個性のある民主的な社会が出来上がった。その点、日本はまだまだ時間が足りない。
(pp.38~68:上山春平「中江兆民の哲学思想)
(p.41) 西洋におけるすぐれた哲学思想とキリスト教思想との関係について、さらにバートランド・ラッセルのばあいを検討してみよう。彼は、近著『私の哲学の発展』(みすず書房,1961年)という哲学的自伝の中で、哲学的思索の出発点にふれ、「私の思考を促した感惰的推進力は主として宗教の根本的な教理についての疑いであった。」と書いている。「根本的な教理」とは神の存在と霊魂の不滅の思想に他ならない。1888年3月3日から6月3日(注:ラッセル16歳の時)にかけての日付のある手記からの摘録によれば、彼は神の存在をニュートン的な仕方で辛うじて肯定し、霊魂の不滅を否定している。私たちには想像もつかないことだが、当時のイギリス社会ではこうした考えでさえ危険思想であった。「私は私の神学上の疑いを気に病んだ。というのは、私はそれまで宗教の中に'慰め'を見出していたためばかりでなく、また、もしこれらの疑いを人にうちあけるなら、人に苦痛を与え、またその嘲笑を招くであろうと感じたためでもある。そこで私は大変孤立し、孤独になった。私は16歳の誕生日の直前と直後とに、自分が信ずることと信じえぬこととを書き記した。人に知られぬようにギリシャ文字と発音通りの綴りとを使って・・・」とラッセルは書いている。彼は当時まだ神の存在を否定する所まではいっていなかったが、まもなくその地点に到達する。「私は神の存在を信じなくなり、18世紀フランスの哲学者たちの主張にちかいものに進んだ。私は合理主義の熱情的な信奉者であるという点で彼らに一致した。」
これがラッセルの哲学思索の出発点であった。それは兆民の『続一年有半』の見地とほぼ一致するが、兆民にはラッセルのばあいのような神学思想との血みどろなたたかいが欠けている。おそらくこうしたたたかいを通してはじめて、ラッセルのたくましい理論的な思索力がきたえ上げられたのに相違ない。
(pp.432~68:鶴見俊輔×河合隼雄×埴谷雄高「文学の無限性」
(p.432~) 闇の奥を究極まで突っ走る人間
埴谷 僕は80歳になりました。よく今まで生きましたね。『世界』の対談中、大岡昇平に言われた。「しゃべり始めたら、おまえ、止まらない」って。たしかに年をとってきたらそうですね。僕は若いときは黙っていて一応威厳があったけれども、今はどんどんおしゃべりになって、威厳喪失で、老人性饒舌症と言われても、どうしようもない。
河合 今度は『死霊』に、饒舌狂の人が出てくるんじゃないですか(笑)。
埴谷 『死霊』の初期時代は僕がおしゃべりじゃない時代に書いた。おしゃべりの作中人物は、黙っている僕の反対表現だ。ところが、今度は自分がおしゃべりになってしまった。作中人物はみな僕の分身ですけど、作中のどこへでも自分が入ったみたいで、これは弱りましたね。無限の大宇宙のなかへ入ったおしゃべりですから、とても止まらない。作品のほうは進まないけれど。
鶴見 もう50年ぐらい前になりますが、私はバートランド・ラッセルからこういう話を聞いたことがあります。すべてを疑うということは、命題としては矛盾が生じて成り立たない。けれども、「すべて疑わしい」という感情を否定することはできない。感情のなかに「すべてを疑う」というひらめきがあると。
この話を聞いて私は、ラッセルという人は論理学者であるだけでなくて哲学者であると思ったんです。神秘と境を接しているという感じがあるんですね。事実、『神秘主義と論理』という著作もあります。
埴谷さんの『死霊』を読んでいると、感情のひだのなかに、命題にできない「疑う」ということがいくつも出てくる。それを論理の感情学というか、論理の形而上学が貫いているということを感じます。・・・。
(pp.228~238:直接話法を掘り起こす)(p.234) これなどは,直接話法を持ちこむという発想は,なかなか思いつかないかもしれない.しかし,太字にした名詞句の部分に持ちこんでみると,意外に効果があるのではないかと思う.
The man who feels himself unloved may take various attitudes as a result. He may make desperate efforts to win affection, probably by means of exceptional acts of kindness. In this, however, he is very likely to be unsuccessfu], since the motive of the kindness is easi]y perceived by their beneficiaries. The man, therefore, becomes disillusioned by experience of human ingratitude.
-- Bertrand Russell
(pp.83-84) 生活の中に品位を求める>
・・・。彼(柳宗悦)が民芸品の美を発見しその保存の重要性を訴えつづけなかったら、日本の手仕事の多くはすでに空しく失われてしまっていたに違いない。その意味で柳宗悦は日本の手仕事を守った大恩人なのだが、今度出た『柳宗悦随筆集』(岩波文庫)を見るとそういう運動へと駆られた人のふだんの素顔がうかがわれて興味深い。
彼はたとえば、近頃美しい言葉遣いが聞かれなくなったと歎じ、バートランド・ラッセルの講演を思い出して(松下注:宗悦は1921年7月28日に慶應義塾大学大講堂で行われたバートランド・ラッセルの講演を聴いている。)、「その品位ある言い廻しや音の美しさに大変打たれた。人格が言葉を生むともいえるが、言葉はまた人格を変える。」と言っている。こんなところにも生活の中に品位を求めた彼の心がうかがわれ、それがすなわち民芸の美の発見につながっていたかとわかるのだ。・・・。
(pp.189-200) 第2節 バートランド・ラッセルの生涯と嫉妬
(pp.189~190) 他方、ノンフィクショナルな嫉妬の経験的事例は、数理哲学者であり、1950年ノーベル文学賞の受賞者でもあった B. ラッセルが、その『自叙伝』にきわめて率直に記している。
実はアメリカ文学者・文芸評論家の佐伯彰一が、ラッセルと親交の深かった9歳年長の哲学者 G.サンタヤーナ(George Santayana、1863-1952:1907年~1911年までハーバード大学で哲学の教授を務める)のラッセル評を次のように紹介している。「私のすべての友人の中で、いやおよそ私の世界に属するすべての人々の中で、最もずば抜けた人間といえば、バートランド・ラッセルにとどめを刺す。彼には生れの良さ、天分、学識、不屈の熱意と精神力、ブリリアントな知性、そして断乎たる誠実と勇気があった。彼の正義愛は、そのユーモアのセンスに劣らず鋭かったし、数学、自然科学、そして歴史にも通暁していた。重要な外国語はことごとくよく出来たし、政治と文学の世界の現状にもすこぶる詳しかった、と[佐伯『自伝の世紀』p.282]。このように評されるラッセルと少なくとも十数名の女性との間に展開された衝撃的な「嫉妬」の事実を、ほかならぬベン・ゼエヴの論文中のごくわずかな言及によってわたしは知らされた[Ben-Ze'ev, 1990, pp.510-511]。これをきっかけとしてわたしは彼の『自叙伝』を中心に、彼の随想や、少しばかりの関連文献を手にしてみた。
ラッセルは、98年に近い生涯の間にアリス、ドーラ、パトリシア(愛称ピータ)、エディスと、4人の妻を持ち、このほかに多数の女性との間に「恋」や「情事」をくりかえした人であった。
(以下、「ラッセルの生涯」の詳しい紹介あり → 省略)
さて『自叙伝』を中心としたラッセルの年譜的紹介が長くなりすぎた。わたしがここに示したかったのは、峻厳にして孤高の人とさえみえた数理哲学者の並みはずれた英知の展開と、彼が愛した女性に対する情動との信じがたいまでの対比である。スキャンダルめいたラッセルの女性遍歴を -すでにラッセル自身が告白しているのだから- ここであばいてみたかったわけでは決してない。
はじめにサンタヤーナのラッセル評を、佐伯に依拠しながら紹介したけれども、その書き出しから受ける印象と異なり、実はサンタヤーナは媚びたラッセル評をしたわけではない。このラッセル評(サンタヤーナがこれを書いた時はラッセルはまだ存命中)は、長年の交友からえられた行き届いた配慮と観察にもとづくものだが、まだあとに続く手厳しい文があったと佐伯彰一はいう。仕事ぶりが「先細り」であったかどうかはわたしには評価できないが、率直で、透徹した合理主義者とみなされたラッセルは、理性をかなぐり捨てたかのように嫉妬の情動をわれわれの前にことごとく露呈してみせた。例えば、下院議員フィリップ・モレルとその妻オットリーンとラッセル自身の三者の関係をふり返ってみよう。「ラッセルは指導者となり、幅広い名声と影響力をふるって然るべき人物であった。実際、彼は数学と論理学において鮮やかな足跡を残し、・・・卓越した人物とひろく認められもした。しかし、彼の能力に比してみれば、総体として失敗者であった。彼の仕事ぶりには、先細りの趣がある。彼は時間と精力、さらには金までも、つまらぬ対象に浪費してしまった。ホワイトヘッドと協力して書いた『数学原理』をべつとすれば、彼の能力を十分発揮して、歴史にのこるような記念碑的な作品は、何一つ残さなかった」と(サンタヤーナは)いい切ったという[佐伯『自伝の世紀』p.283]。
以下省略
(pp.117~118)
私は、バートランド・ラッセルの哲学の講義にも出た。彼がケンブリッジで教えた最後の年で、聴講する学生の数は大変なものだった。ある講義の後で、私は彼の著作の一冊を持って教壇に近づき、自分のペンを差し出してサインしてほしいと頼んだ。ラッセル卿は私のペンを使って、ほかにもサインを頼むために列を作っていたすべての学生の本に署名した。一通りそれが済んだ後、彼は私を待たせたことに気づき、詫びた。そして、私をビールに誘ったのだった。私は、天にも昇る気分だった。ラッセル卿が夕食に出かける時間が来るまで、私たちは一緒に飲んだ。帰り際に、彼はこう言ったのだ、「お若いの、君と話すのは実に楽しい。今学期、講義が終わるたびに一緒にビールを飲もうじゃないか」。
ラッセル卿と肩を並べて通りを歩いている私を見かけた誰かが、あんなに嬉しそうな顔をした人間は見たことがないと言った。ラッセル卿は、その語彙と機知の両面で十八世紀を思わせる英語を話した。恋愛したことがあるかどうか、私に尋ねたことを覚えている。そして、「かりになかったとしても、別に驚かないがね」と付け加えた。ラッセル卿がしゃべったことを、すべて書き留めておけばよかったと思う。当時、私が書いた手紙の中に、ラッセル卿が話した逸話が一つだけ残っている。それは、彼の知り合いの若い中国人に関するものだった。その若者の中国での恩師は叡智の人として知られ、また、一度も風呂に入ったことがないことで有名だった。その恩師が死んだ時、誰かが先生の亡骸(なきがら)を風呂に入れて、さっぱりさせたらどうだろうかと言った。しかし、若い中国人は反対した、「だめだ、先生は、'まるごと'そのまま葬るべきだ」。(PDF版要パスワード)で読売新聞掲載の紙面(イラスト付)を読む)
(pp.197~198)
・・・。しかし、実際には、努力してもなかなか報われないという現実がある。特に、貧しい親の元に生まれた人、それほど能力がない人は、「努力しても」、なかなか豊かな暮らしには到達できない。そこで出てきたのが、マルクス主義に代表される革命思想である。貧しい労働者が団結し、生まれながらの金持ちである資本家たちと闘争していけば、将来の時点で革命が起こり、労働者が最も豊かな生活ができる時期が来ることを約束する思想である。これは、哲学者バートランド・ラッセルによって、キリスト教の教義とそっくりであることが強調された(ラッセル『西洋哲学史』)。少なくとも、共産主義思想は、貧しい人々に希望を抱かせるという機能を果たしていたことは確かである。
それゆえ、1990年前後の社会主義諸国の体制崩壊によって、貧しく生まれた人の「合理的」宗教が崩壊したといえなくもない。すると、来世に希望を求めざるを得なくなり、その結果、過激なイスラム教やキリスト教のファンダメンタリズム、そして、オウム真理教のような過激な新宗教に惹かれる人々が出てくる。振り返ってみれば、社会主義思想やそれを教義とする政党は、現世に希望を持ちにくい人が非合理的な行動に走るのを防ぐ防波堤の機能を果たしていた。中国が「社会主義」という看板を捨てられないのは、革命によって前近代的宗教を破壊した後に、社会主義を放棄すれば、貧しい人々に心理的救いがなくなってしまうことに指導者たちが気づいているからなのだ。ソ連が崩壊した後、ロシアをはじめとした旧ソ連構成国は、宗教や民族を基盤とした数々のテロに悩まされているではないか。バートランド・ラッセルが今生きていたら、同じ見解をもつであろうと信じている。
こんにち、狂気といふことが成功を奏するといふことは、現代の特異性の一つであり、うまく成功を収める型の狂氣は、殆んど、権力に対する衝動から出てくるものばかりだと云つても過言ではない。紙数が少ないから先を急ぐけれど、民族主義は、実はファッシズムにとって二次的なものであり、その基礎は'唯我哲学'の拡張にすぎなかった。バートランド・ラッセルも言っているように、「人種とナショナリズムに対する信念は、このようにして唯我哲学の心理的に言って当然の帰結」であった。日本の右翼がファッシズムと相渉るのは、主としてこの二次的な面である。ジェンティーレか、他の識者のように、ファッシズムを社会民族主義という範疇に入れず、民族主義と全体主義との間に、本質的差異を認めたのは正しかった。民族主義はもっとも利用しやすい武器である。・・・。
バートランド・ラッセル『権力(論)』
(pp.1~-14 序章 歴史教科書への問いかけ)
(p.1)歴史教育の機能
(子どもたちは)自分たちの国家が行なった戦争はことごとく防衛のための戦争で、外国が戦った戦争は侵略戦争なのだと思うように導かれる。予期に反して、自国が外国を征服するときは、文明を広めるために、福音の光をともすために、高い道徳や禁制やその他の同じような高貴なことを広めるためにそうしたのだと信じるように教育される。
バートランド・ラッセルは『教育と社会体制』(松下注:Education and the Social Order (London; Allen & Unwin, 1932))のなかで、このように述べている。
これはヨーロッパの帝国主義諸国を念頭に置いての発言だが、いわゆる教科書検定のみならず、政治家・知識人による過去を美化する発言をたびたび耳にしてきた日本国民には、容易に実感をもって受け止めることができるであろう。確かに侵略戦争は悪いことだが、朝鮮半島から大陸への進出は、ロシアの脅威に対して自衛するうえで必要不可欠の措置であり侵略戦争ではなかったと考える人々、そしてそのように次世代の日本国民に信じさせたい人々は、いまも少なからず存在している。こうした現象は、「教科書問題」という言葉が示すように、戦後の日本社会の未解決の問題として取り上げられる例が多いが、ラッセルのさきの言葉は、国家による自国史の美化という行為が、必ずしも日本に限られるものではないことを示している。それは、むしろアメリカやヨーロッパ諸国にもかなりの程度に共通した現象と認められるであろう。
(p.168)これまで妻・浜子にふれる機会がなかった。妻は昨年(1985年)3月22日、東京神田の三井記念病院で肝不全のためなくなった。67歳であった。
(pp.168~169)・・・。妻が逝って半年ほどして、妻と大変仲の良かった私の姪の富谷照子が亡くなった。名古屋の料亭・桜明暮の女将をやっていたが、何かといえば妻と二人で出かけたり、おしゃべりを楽しんだりしていた仲であった。大変元気だったのに、妻の後を追うようにして急に逝ってしまった。
先日、現在はユニバーシティー・オブ・アリゾナで天文学を専攻している孫の佐藤光宏から電話があり、「おじいちゃん、バートランド・ラッセルの『西洋哲学史』の第1巻259ぺージを読んでよ」と言われた。早速、その本を買い求めて読んだが、ギリシャの哲学者、ポセイドニオスの説として、こんなことが書かれてある。「真に有徳なひとの魂は星辰輝く天球まで上昇し、星が回転するのを眺めて時を過ごす」。
私の悲しみを思いやって、わざわざ国際電話をかけてきたのはうれしかったが、妻も今は天の星となって、私のこの「履歴書」を読んでくれているような気がする。
(松下注:石田氏はこのエッセイを発表した翌年の1987年に亡くなっている。/上記の引用は、いうまでもなくラッセルの考えではなく、ポセイドニオスの説である。)
(pp.231~243:第14章 クニヒト山麓にて)
(p.231)1961年、バートランド・ラッセルとその他およそ一万二干の人々とともに、(著者ホブズボームが)トラファルガー広場で有名な反核の座り込みをして、幸いにも警察に逮捕されないで終わってからまもなく、友人で(ケンブリッジ大学の)「使徒の会」の会員でもあったロビン・ガンディから、疲れた顔をしているから2,3日、彼とともに北ウェールズですごさないかという誘いがあった。・・・。その平地は、19世紀初めにマドックスという人が壁を造成して排水するまで、海の入江になっていた。ポートマドックという新しい港の名前は、彼の名前を取ったものである。この事業は進歩的な訪問客から大いに誉められたが、詩人のシェリーもその一人だった。・・・。
(p.236)・・・。ケンブリッジの大物たちの名前が、いろいろな意味でクラフ王国とすでにつながっていた(クラフ・ウィリアムズ=エリス Clough Williams-Ellis:ポートメイリオン(→ポートメリオン)に理想郷を創った建築家で、ラッセルの友人→ 参考)。哲学者のバートランド・ラッセルはポートメリオン半鳥に、ノーベル賞を受賞した物理学著パトリック・ブラケットは、引退後に、クロイソルの娘の家からあまり遠くないブロンダヌの少し上にある休日用の田舎家だった家に定住し、中国科学史の偉大な研究者ジョゼフ・ニーダムは、一人ないしは二人の女性とともにきまってポートメリオンで休暇をすごした。・・・。
(p.239)・・・。しかしそれは、外部からやって来た者の喜びだった。北ウェールズのわれわれの地方は、外部からの永久的、半永久的な定住者というか、民の奇妙な一群を引きつけていた。フリーランスのもの書き、ソーホーにいられなくなったボヘミアン、不定期の低収入の中で精神的な救済を求める人、風変わりな無政府主義の知識人などがそうした人々だった。反核闘争を代表する高齢の導師バートラン・ラッセルがクラフ王国にいることから、多くの人々がこの地域に集まった。ラッセル自身のうまくいっていない家族の人々は数に入れないとしても。若いアメリカ人の闘士で、当時この哲学者に対して異常な影響力を持っていたラルフ・シェーンマンは、決して地元民の一人になることはなかった。彼はラッセルの名において世界を救うことを唱えて、忙しく飛び回っていた。・・・。1962年のキューバ・ミサイル危機の後に、彼はラッセルが世界平和を救ったことに感謝するデモ行進をポートメリオンで行なったが、それはフルシチョフがラッセルヘの電報で危機の終結を公式に発表したからだった。(これは、フルシチョフにあてたラッセルの電報への返事だったが、キンゼーはラッセルの電報は自分が原稿を書いたと称している。)
ラッセルが晩年に住んだプラス・ペンリン
山荘からポートマドック方面を望む
拡大する!(enlarge)
(pp.178~179:「バートランド・ラッセル(著)『西洋哲学史』)
九番目。どういうわけかは知らないが、私は何度も何度も、自分がバートランド・ラッセルを(愛読書に)入れなければならないということを思い出す。私と彼がかけ離れていることはよく知っているが、いつもこの人を愛してきた。実際は、我々は180度反対だ。おそらくそのためなのだろう。対極は互いに引き合う。また私の目に浮かんでいる涙が見えるかね?- これはバートランド・ラッセル、友だちの間では「バーティ」として知られていた彼のためのものだ。九番目の本は彼の『西洋哲学史』だ。
西洋哲学に関する限り、彼以前にこんな仕事をした者はいない。哲学者にしかこんなことはできない。歴史家は試みたことがある。だから哲学史はたくさんある。だがその歴史家たちの一人として哲学者ではなかった。これはバートランド・ラッセルほどの哲学者が歴史書(『西洋哲学史』)も書いたという初めての例だ。しかも彼は実に誠実で、その書を『哲学史』とは呼んでいない(松下注:東洋も含めた「世界」哲学史ではなく、「西洋」哲学史と言っているということ)。自分が東洋哲学については何ひとつ知らないことをよく知っているからだ。彼はただ謙虚に自分が知っていることを述べ、しかもそれが全哲学史ではなく、アリストテレスからバートランド・ラッセルに至る西洋的部分にすぎないことを言明している。
私は哲学は愛さない。だがこのラッセルの本は歴史書に止まらずひとつの芸術作品だ。それは非常に体系的、かつ美的で、実にすばらしい。おそらく根本的にはラッセルが数学者だったからだろう。
インドはいまだにインド哲学とその歴史を書けるバートランド・ラッセルのような人を必要としている。哲学史はたくさんあるが、それは歴史家によって書かれたもので、哲学者によって書かれたものではない。そしてむろん、歴史家は歴史家にすぎない。彼には思想の流れの豊かさとその内なるリズムは理解できない。ラダクリシュナンが『インド哲学史』を書いており、多分これがバートランド・ラッセルの本のようなものになることを願ったのだろう。だがこれは'盗作'だ。この本はラダクリシュナンによって書かれたものではなかった。これは彼、ラダクリシュナンが審査官になった一貧乏学生の論文だった。その論文のすべてを彼は盗んだ。ラダクリシュナンは訴えられて訴訟になったが、その学生はあまりに貧しかったので、訴訟を闘うことができなかった。彼はラダクリシュナンから充分な金を渡されて黙らされた。
さて、こんな人たちにインド哲学を判定することなどできるはずがない。バートランド・ラッセルのような人が、インドと中国によって必要とされている。・・・。特にこのふたつの国だ。西洋はバートランド・ラッセルのような革命的な思想家を持つことができて幸運だ。彼はアリストテレスから自分自身までの西洋思想の全発展をこの上なくすばらしい物語として描き上げる能力を持ち、そして実際に描き上げた。
(なお、p.236には、ラッセルの『プリンキピア・マテマティカ(数学原理)』がごく簡単にとりあげられている。)
(pp.185~193:「怠」-「1日4時間労働」の夢[ラッセル『怠惰への讃歌』])
(p.186)・・・。ラッセルはなぜ、「仕事は良いものだ」という世間一般の常識を批判し、「怠惰はよいものだ」という主張をしたのか。人びとが生きるうえで大切なのは、「閑」(ひま)である、という思いがラッセルの主張の根幹にある。
勤労は神聖であり、働くことはすばらしいものだという考え方は、支配者、富裕階級が、働く者にそう思いこませるために言いつづけ、その企みが一般にもひろまったとラッセルは考える。
少数の特権階級は、他人の労働のおかげでたくさんの閑な時間を享受している。自分たちの快適な閑を守るためにも、特権階級は働く人に向かい、「働くことは大事なこと」と言いつづけてきた。
「私が本当に腹から言いたいことは、仕事そのものは立派なものだという信念が、多くの害毒をこの世にもたらしているということと、幸福と繁栄に到る道は、組織的に仕事を減らしていくにあるということである」
ラッセルはそう書いている。・・・。
(p.187)しかし近代社会では、閑をもつことは、少数の特権階級の特権ではなくて、社会全体を通じて、公平に分配されるべきものになった。働く人たちも、閑を求める権利をもつようになった。
ラッセルは、閑こそ文明にとってなくてはならぬ大切なものだという。近代の技術をもってすれば、閑を公平に分配することもできそうなものだ、と考えた。
そこから、ラッセルの「1日4時間労働」という夢のような発想が生まれる。「閑」を生むには労働時問の思い切った短縮が必要だろう。
長い間、長時間働きつづけてきた人は、突然、閑ができても、閑をうまく使いこなすことができず、閑をもてあます日々を送ることになるかもしれない。ただ、人生のもっともすばらしいものと縁がなくなるのは、閑な時間がないためだということをラッセルは指摘する。・・・。
(p.188)働くことでくたくたになっていては、たのしみは受け身のものになる。仕事に精力を吸い取られたものは、スポーツの試合を見る、刺激の強い映画を見る、といった受け身のたのしみにすがることになるのだ。
だれも、一日に長時間働くということを強いられない世の中では、そしてたとえば一日の労働時間が4時間以内ということになれば、たくさんの閑を得た人びとは、より創造的な活動に飛びこむことができるようになる。ラッセルは、1930年代の著作のなかでそう考えている。・・・。
(p.189)ラッセル論文(松下注:これは論文というよりは「エッセイ」)の主眼は、「労働時間を短縮して、閑を創ろう」というところにある。その目的は怠けることを勧めるというよりも、むしろ閑な時間をたくさん持って、人問らしい暮らしをする方向を探ろうということなのだ。
(p.193)ラッセルに学ぶことの一番人切な点は、「閑を創る」ことは「文化を創る」という点だ。多くの人が、いらいら、あくせく、せかせかの状態にあって、どうして豊潤な文化を創ることが可能だろう。おおいに閑を創るために、私たちはもっと貧欲でなければならぬ。
(p.2)
[斉藤] 僕のイギリス小説との出会いというのは、『英語のたくらみ、フランス語のたわむれ』の対談のときにも話しましたが、基本的に語学なんですね。中学のときから英語が好きで、その自然の流れで文学作品を読むようになって、高校時代に原書で読んでというようにね。一番にはまったのは、最初は小説ではなくてバートランド・ラッセル(1872~1970)の随筆だったのですが、その同じ関心でサマセット・モーム、ジョージ・オーウェル、ジョン・スタインベック、純文学ではないけどアガサ・クリスティとかね。そういう作家の小説なんかを読み始めて、なるほど英語の学習の延長線上にこういう文学の愉しみがあるんだなと感じて、大学では英文学を専門にしようと自然に思いましたね。ただ、東京大学の駒場キャンパス(主に一・二年生の教育に当たる)ではいろんな新しい学問を目にするから、多少浮気心が出てきたんだけど、幸か不幸か(三・四年生への)進学振り分けの点数がそんなによくなくてね(笑)。
(p.210)
[Q] チョムスキーさんには、ヒーローといいますか、賛嘆の念を覚えて仰ぎみるような方がどなたかいらっしゃいますか。
[A] ええ、おおぜい。本当のヒーローたちもいます。ただ、彼らは一般にはほとんど知られていません。著名人のなかでは、バートランド.ラッセルです、知性の点でも、公人としても、すばらしい人物です。ラッセルとアインシュタインに対する世の中の見方がどう違うか、その違いに着目するとちょっとおもしろいですね。このふたりは、ほとんど同じ思想を抱いていました。そして最後には、ふたりとも核兵器に深く関与したのです。ふたりとも社会主義者でした。ところが、アインシュタインのほうは偶像となったのに、ラッセルはまったく違います。この差は、アインシュタインが請願書に書名し、それから書斎に戻って物理学に没頭したという点にあります。ラッセルのほうは、請願書に書名し、それから町に出てデモに加わったのです。