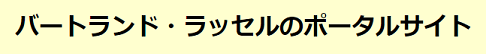
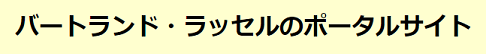
第2章 コペルニクス的革命(コペルニクス的転回)n.17 - 神学者と彗星神学者たちは,ガリレオに対する悲惨な「勝利」の後,この例で示したような公的に明確な態度をとること(official definiteness)は避けた方が賢明であると気づいたけれども,科学に対して敢えて 啓蒙主義 をとることに反対し続けた。(注:「they continued to oppose obscurantism to science as far as they dared」のところを,荒地出版社刊の訳書で津田氏は「できるだけ科学に対し非教化主義をとることをやめなかった」と訳出している。津田氏は「非教化主義」をどういった意味で使っているかわからないが,そのままとれば意味が逆であろう。この一文は,「神学者たちが民衆に知識を与えずに無知のままにしておこうという「蒙昧主義をとることには反対し続けた」ととるべきであろう。因みに,obscruntism 蒙昧主義とは,「意図的に曖昧な言い方をしたり,またある問題を明るみにすることを妨げるような態度のこと」であり「啓蒙思想に対するカウンターとしての反啓蒙主義とは異なる」 。即ち,神学者たちはコペルニクス説には反対したが,蒙昧主義の立場をとらなかったということを言っていると解釈すべきであろう。) これは(このことは),彗星の問題に対する彼ら神学者たちの態度によって例証されるかも知れない。現代の人々には彗星の問題は宗教と余り関係がないことのように思われるだろう。けれども,中世の神学は,-それ(中世の神学)は不変・不易である(immutable)と意図された唯一の論理体系であるという理由だけから- 必然的に,ほとんど全てのことに関して明確な見解をもつことは避けることができず(注:あいまいな見解や態度を示すことができず),従って,科学の最前線の全てにおいて(最前線の全てにおいて)闘いに従事する傾向があった(しがちであった)その(神学の)古さのせいで,神学の多くは単に組織化された無知であるに過ぎず,神学はその多くは文明開化の時代に生き残り続けてくるべきではなかった(いろいろな)誤謬に神聖な香り(the odor of sanctity 聖者のおもかげ,高徳の誉れ)を与えた。彗星に関して,(キリスト教の)聖職者たちの見解には2つの源泉があった。一つは,法則の支配は,我々(現代人)がそれを考えるようには考えられなかったことである(注:科学的な自然法則ではなく,神の定めた法則)。もう一つは,地球の大気より上にあるものは全て不滅で(indestructible)なければなならいと考えられていたことである。 |
Chapter 2: The Copernican Revolution, n.16
|