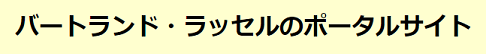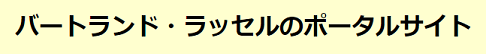けれども,私の幼少時代の始めの年月は幸せであった。そして'孤独'であることが息づまるように感じられるようになったのは青年期が近づいた頃だけであった。私にはドイツ人とスイス人の(女性で住み込みの)家庭教師がついていた。私は彼女らが好きだった。私の知性はまだ,私の身近な人々(訳注:my people ここでは家族だけでなく,自分の家庭教師を含めて身近な人々のことを言っていると思われます。)がこうした知性の面で欠けているからといってそれを苦慮するほど十分には発達していなかった。しかし私は,両親が生きていてくれたらよかったのにと思っていたのを記憶しているので,ある種の不幸を感じていたに違いない。ある時 - 私が6歳のとき - この感情を祖母に話した。すると祖母は,両親が亡くなったことは私にとってたいへん運の良いことだと語りだした。その時,祖母の言ったことはとても受けいれがたい印象を私に与え,祖母がそういうことを言うのは'嫉妬'からだろうと思った。もちろん私は,ビクトリア朝時代の物の見方からすれば,そうした発言にも十分な根拠があるということがわからなかった。(訳注:ラッセル両親は無神論者であり,父は死ぬ間際,遺児に無神論者の2名の後見人をつけようとしていた。また,両親は自由恋愛論者であった。)
祖母の顔は非常に表情に富んでいた。そうして,偉大な世界に住んでいるその経験にもかかわらず,自分の感情を隠す技を修得していなかった。'精神異常'のことにふれると,彼女は発作的に悶え苦しむことに気づいた。そこで,どうしてそうなるのだろうかと,その理由をいろいろ推測した。祖母が一人の息子をある保護施設に預けていることを発見したのは,ずっと後になってからのことであった。彼は精鋭な連隊に入隊していたが,その2,3年後に発狂した。完全に正確であるかどうかは請けあうことができないが,私が聞いた話では,彼があまりに'清純'であったので同僚将校たちが彼をいじめたということであった。彼らは連隊のペットとして一匹の熊を飼っていた。ある日のこと,彼らは,ふざけてその熊を彼にけしかけた。彼は逃げ,ショックで記憶を失った。そうして,田舎をさまよい歩いているところを発見され,身許がわからないまま,(英国救貧法上の)労役所附属診療所に収容された。その夜半,彼は,「熊! 熊!」と叫びながら飛び上がり,そうして隣りのベッドに寝ていた放浪者の首を締めて殺害した。彼はついに記憶を回復しなかった。けれども80歳以上になるまで長生きした。
|
The early years of my childhood, however, were happy, and it was only as adolescence approached that loneliness became oppressive. I had governesses, German and Swiss, whom I liked, and my intelligence was not yet sufficiently developed to suffer from the deficiency of my people in this respect. I must, however, have felt some kind of unhappiness, as I remember wishing that my parents had lived. Once, when I was six years old, I expressed this feeling to my grandmother, and she proceeded to tell me that it was very fortunate for me that they had died. At the time her remarks made a disagreeable impression upon me and I attributed them to jealousy. I did not, of course, know that from a Victorian point of view there was ample ground for them. My grandmother's face was very expressive, and in spite of all her experience of the great world she never learned the art of concealing her emotions. I noticed that any allusion to insanity caused her a spasm of anguish, and I speculated much as to the reason. It was only many years later that I discovered she had a son in an asylum. He was in a smart regiment, and went mad after a few years of it. The story that I have been told, though I cannot vouch for its complete accuracy, is that his brother officers teased him because he was chaste. They kept a bear as a regimental pet, and one day, for sport, set the bear at him. He fled, lost his memory, and being found wandering about the country, was put in a workhouse infirmary, his identity being unknown. In the middle of the night, he jumped up shouting: 'The bear! the bear!' and strangled a tramp in the next bed. He never recovered his memory, but lived till over eighty.
|