下村寅太郎「バートランド・ラッセルのこと」
* 出典:みすず書房版「ラッセル著作集・月報」より(第1巻付録)
* 再録:下村寅太郎『精神史の森の中で-研究ノート』(河出書房新社、1972年8月)
* 下村寅太郎(1902‐1995):京大哲学科卒。西田幾多郎、田辺元に師事。1945年に東京文理科大学(現・筑波大学)教授となる。
* 参考:下村寅太郎「バートランド・ラッセルのこと-ノーベル文学賞受賞に因んで(1951年)」
「イギリス人はアマチュアの国民である、政治家も、軍人も、科学者でさえも」、と学僧イングが『イギリス論』の中で言っている。常識や良識をその考え方や行動の根底とすること、「原理」を建ててそれを強行することを好まないのはイギリス人の国民性である。ラディカルでないことは彼らの性格である。原理や理念に強制されるのは自分で作ったものに支配されることである、原理や理念はこれを支配すべきもので、これに支配されるべきものではない、-これが彼らの信条である。これがイギリス思想の伝統である「経験主義」「功利主義」になる。実際にこれによって最も均衡のとれた社会や生活を維持しているのはイギリス人であろう。適当に論理的で適当に妥協的である。これは謂わば「大人」の哲学である。プラトン哲学を何よりも政治哲学として理解するのもイギリス人である。これは決して無節操な現実主義ということではない。堂々たる一種の貴族主義である。近世の革命思想はイギリスが発祥地であり、その指導者であったではないか。而もその革命も狂信的でなく、節度をもっている。革命「理念」に支配されない。乱に到らない。
この性格を哲学思想として形成した経験主義は単なる「学者の哲学」ではない。社会人の哲学である。アメリ力人の「プラグマティズム」は論理的にはイギリスの経験主義よりはラディカルである。しかし逆説的であるが、それだけ現実的でないところがある。というのは我我の実際の経験は決して単にプラグマティズムではないからである。
イギリス人がアマテユアの国民である所以は、アマテユアが積極的に勇敢に自分の意見を主張し、同時にアマテユアの意見が寛容に傾聴されることである。G.B.ショウのような劇作家が経済学や社会学の法則を建てたり、H. G. ウェルズのような小説家が近代社会の新しきユートピアを設計したり、ラッセルのような数学者が児童教育論や結婚問題、政治哲学や幸福論を開陳する。そしてイギリス人は寛容に、或は熱心に、これに耳を傾ける-というのはこれらの人々の著書が何れも甚だ広く読まれているからである。しかしこれらの意見が現実のイギリスの政治や政策に作用したり影響したりしたことはない。これも亦イギリス的である。その影響は専らイギリス人のものの観方や態度に力を及ぼしているのであろう。ということは却って政治や政策以上に大きな、重大な影響を及ぼしているということになる。結極、緩慢に或は悠然と経験の中に摂取されて行くのであろう。ショウとウェルズとラッセル-漫然と挙げられたわけであるが、しかしこの三人の思想家には何れもイギリスの思想家としての共通の性格がある。合理主義的批評的な性格に於て、進歩的革新的な意見に於て、それから幅の広さに於て-しかし深さの乏しい点に於ても、ラディカルではない点に於ても、甚だ同型的である。イギリスに於て最もポピュラーであることは、最も典型的にイギリス的である所以でもある。
そういえば、ラッセルが真に専門家的であるのは極端な言い方であるが、数学者(「論理学者」という方が精確であるが)としてだけであるかもしれない。哲学者としては、もしドイツ流の講壇的哲学者を標準にして言えば、寧ろアマテユア的である。ラッセル自身これを哲学の本領としている。専門家にしか理解されないなら哲学の価値の大半を失うとすら言う。もっともそれがイギリス哲学の性格でもある。哲学者としては、ラッセルよりは寧ろホワイトヘッドの方が遥かに哲学的である-洞察の広さや深さや精繊さに於て。思想家としてのラッセルは寧ろヴォルテールの型に似ている。バートランド・ラッセルは「合理主義者」である。しかしその合理主義の性格が問題である。ラッセルはある文章の中で、自分は懐疑論者である、しかし英雄的な懐疑論者でなく、妥協と節度を愛するイギリス・ホイッグ党である」、といっている。
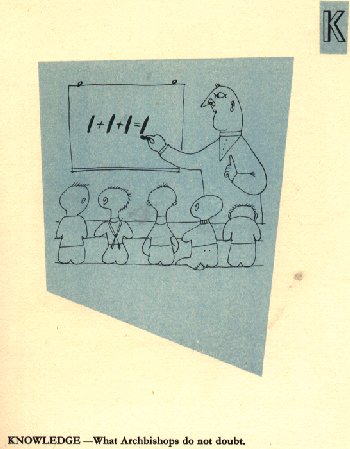 徹底した懐疑主義というのは実際は却って合理主義的ではない、寧ろ甚だ合理的(注:非合理的?)なのである。実際的には誰も疑っていないものを理論的に疑わねばならぬとする者だから。ラッセルは論理的に処理出来ないものをきっぱりと哲学の埒外に追い出す。論理的に言えるものとそうでないものとを明晰に区別して、論理的なものだけを「哲学」の問題とする。ところでその謂うところの「論理」は数学と同質な論理-形式論理であって、矛盾を統一したり止揚したりする弁証法のような論理ではない。弁証法は形式論理で処理出来ない-例えば、無限とか絶対とか、矛盾の一致とか三位一体とかの問題(右イラスト出典:B. Russell's Good Citizen's Alphabet, 1953)を、合理化するために余儀なく編み出された論理である。ラッセルでは、何らかの意味でこのような論理を必要とする社会哲学や道徳哲学や歴史哲学や宗教哲学は実際は「良識にもとづく意見」であって、「哲学」と言わるべきものではない。例えば彼はヒュームの哲学には同感するが、その政治論には反対である、という。ヒュームの哲学とその政治論との間には必然的なつながりはないと言うのである。現代に於ても未だ哲学と政治とが直結しているのは、「革命前までは未だ中世的であったロシアと、チベットだけ」である、という。ラッセの哲学とラッセルの道徳哲学・歴史哲学・宗教哲学とを区別し、それらの間に論理的結合のないことを指摘した批評を自ら「親切な」批判と言っている。このようなラッセルの哲学は、極めて明快で明朗で健康で晦渋さや陰影がない。その限りでは甚だ常識的である。ラッセルの合理主義はかかる性格のものである。ドイツ流の哲学者の所謂「悟性的」な哲学である、ドイツ哲学に慣れた日本の学界ではラッセルがこれまで-数理哲学以外では-比較的興味をもたれなかった理由である。しかし同時に、これが戦後我が国でラッセルの読者が増えて来た理由である。しかしラッセルに関心がもたれる限り、その合理主義の根底になっている真直な太い背骨を身につけることが必要である。ラッセルの合理主義には何処か貴族的なものがある。自ら「妥協と節度を愛する」者と言うが、実際にラッセルが曖昧な妥協をしたことはない。第一次大戦では非戦論を固守して大学から追放され、投獄されている。自説の結婚論や教育論を敢て世評に抗して実行して憚らない。
徹底した懐疑主義というのは実際は却って合理主義的ではない、寧ろ甚だ合理的(注:非合理的?)なのである。実際的には誰も疑っていないものを理論的に疑わねばならぬとする者だから。ラッセルは論理的に処理出来ないものをきっぱりと哲学の埒外に追い出す。論理的に言えるものとそうでないものとを明晰に区別して、論理的なものだけを「哲学」の問題とする。ところでその謂うところの「論理」は数学と同質な論理-形式論理であって、矛盾を統一したり止揚したりする弁証法のような論理ではない。弁証法は形式論理で処理出来ない-例えば、無限とか絶対とか、矛盾の一致とか三位一体とかの問題(右イラスト出典:B. Russell's Good Citizen's Alphabet, 1953)を、合理化するために余儀なく編み出された論理である。ラッセルでは、何らかの意味でこのような論理を必要とする社会哲学や道徳哲学や歴史哲学や宗教哲学は実際は「良識にもとづく意見」であって、「哲学」と言わるべきものではない。例えば彼はヒュームの哲学には同感するが、その政治論には反対である、という。ヒュームの哲学とその政治論との間には必然的なつながりはないと言うのである。現代に於ても未だ哲学と政治とが直結しているのは、「革命前までは未だ中世的であったロシアと、チベットだけ」である、という。ラッセの哲学とラッセルの道徳哲学・歴史哲学・宗教哲学とを区別し、それらの間に論理的結合のないことを指摘した批評を自ら「親切な」批判と言っている。このようなラッセルの哲学は、極めて明快で明朗で健康で晦渋さや陰影がない。その限りでは甚だ常識的である。ラッセルの合理主義はかかる性格のものである。ドイツ流の哲学者の所謂「悟性的」な哲学である、ドイツ哲学に慣れた日本の学界ではラッセルがこれまで-数理哲学以外では-比較的興味をもたれなかった理由である。しかし同時に、これが戦後我が国でラッセルの読者が増えて来た理由である。しかしラッセルに関心がもたれる限り、その合理主義の根底になっている真直な太い背骨を身につけることが必要である。ラッセルの合理主義には何処か貴族的なものがある。自ら「妥協と節度を愛する」者と言うが、実際にラッセルが曖昧な妥協をしたことはない。第一次大戦では非戦論を固守して大学から追放され、投獄されている。自説の結婚論や教育論を敢て世評に抗して実行して憚らない。
ラッセルのあの明快で直裁的で合理的な断言には何者をも怖れず、何事にもものおじしない太い無遠慮な叛骨的なものがある。これは我が国の所謂進歩的な思想家の軽快な合理主義とはいささか違ったものがあることに注意されてよい。ラッセルの合理主義には、たしかに、先きに「貴族的」と言ったように、強豪な性格がある。よく知られていることであるが、実際に彼の家系はヘンリー八世以来の古い名門である。彼の祖父はヴィクトリア朝時代の進歩的政党の首領であって、早く、二、三歳で両親を喪った彼はこの祖父母の許で育った。祖父は間もなく世を去ったので、祖母から最も強い影響をうけた。この祖母は道徳的に厳格なスコットランドのピューリタンで、酒や煙草を罪悪視し、食事に無関心で、愉楽を蔑み、生涯顕栄な生活の裡に居ながら全く非世間的で、子供や孫に世間的な成功や「よい結婚」を望まず、ひたすら「有益な有徳な生活」をすることのみを望んだ。自己自身の判断や個人の良心の至上性を信奉するプロテスタント的精神の主で、ラッセルの十二歳の誕生日のプレゼントに聖書を与え、愛誦(唱)の聖句を自ら記した-「汝、悪をなす多数に従うなかれ。」「強くあれ、勇敢であれ、怖れるなかれ、又狼狽するなかれ、汝の神、汝の到る所に常に汝と共にいますべければなり。」ラッセルは今もこの聖書を愛蔵し、これらの訓言が彼の生涯に深い影響を与えたこと、そして「私が神を信じることを止めた後も猶お若干の意味を保持しているように思えた」と告白している。そして「……人間よりも偉大なものを認めないヒューマニズムの宗教を作ろうとする人々は私の情緒を満足させない。而もなお私は、この世の中に私が人間や況んや動物以外に重んじうる何ものかが存在することを信ずることは出来ない。星空でなく、それを知覚する人間へのそれの効果がすばらしいのである。宇宙をそれの大きさの故に讃嘆するのは奴隷的で不条理である、非人格非人間的な真理は迷妄であるように見える。かくて、私の情緒は激しく反抗するが、私の知性はヒューマニストと行を共にする。この点に於て、『哲学の慰め』は私には存しない。……」と自伝を結ぶのである。(東京教育大学教授)


