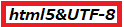書評:「隠された面にも照明、人間愛と抵抗精神の源(バートランド・ラッセル)
* 出典:『読売新聞』1970年6月27日掲載* 日高一輝(著)『人間バートランド・ラッセル-素顔の人間像』の書評
* 鈴木芳郎は、日高一輝氏の本名らしい
多彩なラッセルの活動をささえていた核心は何であろうか。著者はそれを、「愛への熱望、知識の探究、苦悩する人類のためにそそぐ無限の情熱と、あくまでも自己に忠実に生きようとする姿勢」とに求めている(松下注:これはラッセルが『自叙伝』の冒頭で自ら述べているもの)。ラッセルは晩年にこう語ったという。「愛と知識は、その可能なるかぎりでは、高く天国に達した。しかしいつも人類にたいする憐欄(れんびん)の情がわたしを地上にひきもどした。かれらの苦悶(くもん)の叫びがこだまして、わたしの胸にひびくのである。飢えに泣く子どもたち、圧迫者に苦しめられる犠牲者たち、孤独と貧困と苦痛の世界全体が、社会の現実として存在している。わたしはこの社会悪を減らしたいとねがう。しかしわたしにはできない。そしてわたしも苦悶する。これがわたしの人生である。わたしはこの人生を生きるに値する人生だと思っている。そして、もしもチャンスがあたえられるならば、もう一度喜んでこの人生を生きようとおもう」(松下注:これも『自叙伝』冒頭に出てくるラッセルの言葉)。
この率直な告白は、われわれの心に訴えかけるものがある。
ラッセルは人類の未来を青年に託して、今年(1970年)の二月、ほぼ一世紀にわたる孤高の生涯を閉じた。深い人間愛が、みずからに対するきびしい生活規律に裏づけられていたこと、そこからラッセルの妥協を許さぬ抵抗の精神が現われてきたこと、無神論者あるいは不可知論者で反宗教的というレッテルをはられがちなラッセルが、真理を求めて疑いを重ねつつ、実在するもの、永遠なるもの、生命の根源なるものに近づこうとしていたこと、少年時代から何回も自殺をしようと考えるような内向性をもち、秘密主義がラッセルを最後まで苦しめたことなど、あまり知られていないラッセルの一面(これらは『自叙伝』にすべて書かれていること。書評者は、明らかにラッセルの『自叙伝』を読んでいないと推察。)が、本書では生き生きと描きだされている。
本書は人生をいかに生きるか模索しつつある若い人々に一つの指針をあたえるであろう。(講談社、420円)