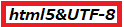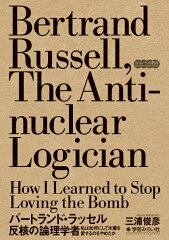湯川秀樹「核廃絶の道を求めて-第25回パクウォッシュ・シンポジウム開会講演(1975年8月26日)」
* 出典:『核軍縮への新しい構想』(湯川秀樹・朝永振一郎・豊田利幸(共編),岩波書店刊,1977年8月刊)pp.1-4.* 湯川秀樹「バートランド・ラッセルと世界平和」 / ラッセル=アインシュタイン宣言の着想
*(参考)日高一輝著『世界はひとつ,道ひとすじに』
* 湯川秀樹(1907~1981:明治40年~昭和56):1929年に京大理学部を卒業。1932年同大講師となる。湯川スミと結婚し,湯川姓となる。1934年大阪大学へ移り,1935年『素粒子の相互作用について』を発表し,中間子の存在を予測。1939年京都大学にもどる。1947年,ポーエルがパイ中間子を発見し,中間子論が実証され,1949年日本最初のノーベル物理学賞受賞。1955年,ラッセル=アインシュタイン宣言の共同署名者となる。パグウォッシュ会議へ参加するとともに,科学者京都会議を組織。また,世界連邦世界協会会長もつとめる。
核軍縮への道を妨げてきた最も重要な因子の一つは,核抑止という考え方であります。これについてはさまざまな議論がありますが,核抑止の考え方に基いた政策が常にポジティヴ・フィードバックを結果することは明らかであります。これは超大国の核軍備が無限大を指向することを意味します。これは核軍縮が原理的にゼロヘの方向を指向しているのと完全に背馳しています。核軍縮実現のための方策とは,ネガティヴ・フィードバックの繰返し以外のものではありえないはずであります。
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
その代りに,人類の将来についての私の個人的なヴィジョンを述べて私の話を結びたいと思います。人類の存続のためには核軍縮の達成が必要でありますが,核軍縮はわれわれが達成しなければならないことの一部分にすぎないことも明らかであります。それは全面完全軍縮の重要な一部分でありますが,後者ですらわれわれの目的のすべてではありません。最終の目標はすべての国の安全がそれぞれの国の軍備を必要とすることなしに保障されるような,世界システムを樹立することであります。この点に関して,私はラッセルやアインシュタインと世界連邦のヴィジョンを共にするものであります。
しかしながら,このようなヴィジョンを持っている・いないにかかわらず,われわれはすべて核軍縮達成の必要性について意見が一致していると思います。われわれはすべて,核兵器はわれわれ共通の敵であり,すべての核兵器を地球から完全になくすことがわれわれの目標であるという点で一致していると信じます。私はこれからのセッションで行われる具体的な幾つかの提案が,核軍縮達成に有効な寄与となることを心から希望し,ここに第二十五回パグウォッシュ・シンポジウムの開会を宣します。