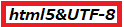市井三郎『バートランド・ラッセル』(講談社版・人類の知的遺産 第66巻)-第1章冒頭
* 出典:市井三郎(著)『バートランド・ラッセル』(講談社、1980年2月刊 7,368,4p 18cm. 人類の知的遺産 第6巻6/箱入り)* (故)市井三郎氏(1922-1989)略歴
I バートランド・ラッセル思想 - 1 思想と生涯の素描(冒頭部分)
これからその思想と生涯とをたどろうとするバートランド・ラッセル(Bertrand Arthur William Russell)は、英国のヴィクトリア朝時代、つまり1872年5月18日に生れ、98歳に近いとき、つまり1970年2月2日に、自然死のような最後をとげた。
だがその生涯は、最後にいたるまで波瀾にみちていた。40歳代のなかば頃まで、ケンブリッジ大学に(一時の断続はありながら)教籍をもって、高度に専門的な学問に従事してはいたが、そのあいだにも彼は、数学・数理哲学という専門領域をこえて、『ドイツ社会民主主義論』とか、『自由人の信仰』『ライプニッツの哲学』といった著述をものしていた。
第1次世界大戦にさいして反戦の言論だけでなく、実践をも開始した彼をケンブリッジ大学は追放処分にふした。それいらい彼は、どの大学の定職にもつくことなく、在野の思想家として、人間社会にかんして考えうるほとんどあらゆる分野で著述をし、かつ実践しつづけたのである。(ついでながら断わっておく。書斎での執筆活動もひろい意味の実践であるが、ここでいうのは、著述活動をこえた社会的実践の意味である。)
純学問的な分野におけるラッセルの貢献が何であったか、それはおいおい語ることにするが、以上に示唆した彼のはばひろい活動がいったい何であり、何をもたらしたのか、という点にかんして、最初にひとつの鳥瞰図を描いておきたい。これはあくまでわたしの見方を素描するのであるから、ラッセルの生涯にまつわる多くの固有名詞は、ここでは可能なかぎり省くことにする。
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
さらに西欧ではとっくの昔に社会慣行になっていたはずだ、とわが国で信じられがちな民主主義なるものも、国内の政治制度としては(たとえば英国でも)ようやく前世紀終りころに労働者階層にまで選挙権がひろげられた。だがそれも男性に対してだけで、イギリス成人女性がすべて参政権を得たのは、よりおくれて1928年(フランス女性の場合は1945年)である。さらに国際的な民主主義となると、ずっとおくれる。西欧諸国の政府が権力政治的(power politics)な外交政策を強固にとりつづけたのは周知のとおりであり、一般人民のものの見方も、自国内の民主主義的慣行を国外にまでひろげて考える、といった姿勢からは長く縁遠かったのである。
その一般人民の考え方に変化が起り始めたのは、きんきん過去半世紀あまりのことにすぎない。まさにバートランド・ラッセルは、今世紀のその数十年のあいだに、英国の一般の人々の考え方や慣行に以上のような変化を起させるために、最大の闘いをたたかった思想家・実践者だったといえるだろう。