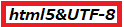バートランド・ラッセル『私の哲学の発展』あとがき
* 出典:バートランド・ラッセル(著),野田又夫(訳)『私の哲学の発展』(みすず書房,1960年8月 364+ii pp./ラッセル著作集別巻として1963年1月刊)* 原著:My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell
*野田又夫(1910~2004.04.22):デカルト研究で有名。バートランド・ラッセル協会設立発起人の一人。京大名誉教授で、2004年没。
本書は Bertrand Russell, My Philosophical Development, 1959 の訳である。「まえがき」にのべられているように、巻末に付録としてアラン・ウッドの「ラッセルの哲学」の断片がつけてあるが、これも一緒に訳出した。(なお、アラン・ウッドが生前に発表した伝記『バートランド・ラッセル、情熱の懐疑家』は現在、木鐸社から刊行されている。1979年8月追記)
★ラッセル『西洋哲学史』
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
この書物はラッセルが自分の哲学の原理的部分の発展をのべたものである。原理的部分というのは、主として論理学・数学・物理学にかかわる哲学的分析の仕事を意味する。ラッセルの著作活動のもう一方のもの、すなわち政治・社会・歴史・倫理・教育・宗教についての仕事は、内容的にとりあげらてはいない。これはかれの、哲学についての厳格な考え方にもとづくものと思われる。かれは、政治や文化の批評を、論理学や認識論と同格の学問的仕事とはみとめないのである。それで、さきに挙た「自叙伝のこころみ」や「私の精神の発展」とはちがってこの書物は、かれが哲学的分析において真とみとめえた理論を次々に要約して示した、いわば総計算書の趣きがある。自分の学問上の仕事はこれだけだがこれだけはやったのだ、というのである。そしてその要点を、改めて読者にわからせようとする老人の親切もつよく出ている。たとえば第6章で、数学的論理学の核心が何であったかを説いているところを読んで目の覚めるような感じをもつ者は訳者だけではないであろう。
「ラッセルのこの書物に似たものを過去に求めるとやはりデカルトの『方法序説』がそれだといわねばならないであろう。哲学そのものの性格からいってもラッセルはデカルトと問題を共有している。青年時代にデカルトを解析幾何学の創始者としてしか知らなかったとき、すでに哲学者デカルトの問題に出会っていたのだ、とみずからのべているとおりである。
これはわれわれにははなはだ便利である。
訳者は、昨年この本を読んで異常な同感を覚え、たまたま求められて喜んでこれを訳した。翻訳は解釈だと思うので、自分の取りえたかぎりの意味ははっきり伝えようとつとめたが、1,2意味を取りかねて文字だけを辿ったところがある。たとえば第8章のはじめ(p.110)に「テキサス州人(Texans)云々」というところはどういう人々のことを言うのかわからなかった。いま気になるのはこの類いのことであるが、しかしもっと重大な解釈上の誤まりを、知らずにおかしていないともかぎらない。お気づきの方はどうかお教え願いたい。なお市井三郎氏には若干の疑点を考えて頂き、みすず書房の富永博子さんからはゆきとどいたお世話をうけた。いずれにも厚く御礼申し上げる。 1960年8月 野田又夫
こんど再版にあたって、初版で脱落していた文章を補い、誤字誤植を正した。これらを親切に御指摘下さった、猪狩佳久氏、土井邦夫氏に厚く御礼申上げる。 1962年12月 野田又夫