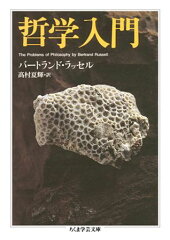バートランド・ラッセル(著),中村秀吉(訳)『哲学入門』
* 原著:The Problems of Philsophy, 1912)
* (故)中村秀吉氏(1922~1986)は、東大数学科卒。金澤大学の教員を経て、千葉大人文学部教授。ラッセル協会設立発起人の一人。
訳者あとがき(1964.01.30 九州旅行先にて)
本訳書の原典(The Problems of Philsophy, 1912)についてラッセルは次のようにいっている。|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
「『数学原理』(Principia Mathematica)を書く仕事が終るとすぐ、その本がまだ印刷中に、私の哲学の概要を通俗的なことばでのべた本を『家庭大学叢書』(Home University Library)のために書いてはどうかと,ギルバート・マレー(著名な古典学者、ラッセルの友人)からすすめられた。このすすめは都合のよいときにあたえられた。わたしは、記号的演繹推理の厳格さから逃れるのをうれしく思ったし、また、わたしの当時の考えはそれ以前にも以後にもなかったほどのすっきりした明確な形をもち、簡明にのべることが容易だったからである。この本は大きな成功をおさめ、いまでも広く読まれている。たいていの哲学者たちはいまでもそれを、私の考えを十分にのべたものだと考えているように思われる。」(ラッセル『私の哲学の発展』野田又夫訳、p.129)
がんらいラッセルは幼児から数学、とくにその厳密な論証の筋道を愛好し、これをあらゆる学問の模範と考えた人であったが、決して論理に一方づいて生れた人ではなかった。かれが数学や論理学に嫌気がさしたのは一度にとどまらない。その第1はケンブリッジ大学の卒業試験のあとであった。かれは烈しい訓練を強いる計算や論証の技術のためまったく数学が嫌になり、数学の本を全部整理してしまおうと思ったほどであった。その第2の機会は、師であり友人であったホワイトヘッドとの協力に成る『数学原理』の仕事を終えたあとにおとずれた。おそらくラッセルは、世紀の変り目から1910年頃までというものは、その巨大な頭脳を休めるいとまもなくこのモニュメンタルな仕事に従事したのであったろう。その仕は事の成果を出版所に持ち込んだあとでは、野にいて枯草を食むような数学・論理学の仕事から解放されて、もっと生き生きとした哲学の分野のことをやってみたい思いに駆られたことであったろう。それがこの文章にのべられている彼のいつわりない気持であったようである。本書の生彩に富んだリズミカルな文章は一つにはこのようなことに原因があるように思われる。
もちろん本書の内容のすばらしさはこのようなことにのみよるのではない。がんらい彼には哲学者としてのすぐれた問題意識とその解決法がある。かれの哲学思想はどのようにして形成されたであろうか。
19世紀後半、初めてドイツ哲学は英国に強い影響をあたえ、とくに、ラッセルの師であったブラッドリー(F. H. Bradley, 1846-1924/ Oxford 大学教授)やマクタガート(J. M. E. McTaggart, 1866-1925)はへーゲルの決定的影響を受けた包括的・一元論的世界観によって当時の若き哲学学徒を魅了した。若きラッセルやその友人ムーア(G. E. Moore, 1873-1958)もその仲間であった。
ブラッドリーによれば、人間による一切の知識は不完全であり、古典的英国経験論のよりどころとする知覚判断といえどもその例外ではない。われわれの知識が感覚の世界に依存することはこれを認めなければならないが、絶対確実な感覚判断・知覚判断はなく、知識の真理性の判定規準は整合性と包括性である。ある段階の知識は一応の整合性をうることにとって真と判断されるが、それは新しい知識との乖離(かいり)によって整合性を乱され、ふたたび整合性を回復するためにはみずからを越えて進まなければならぬ。知識はありうるかぎりの包括性を要求する。しかしそれにしても有限的人間には限度があり、したがって整合性も絶えず破られる。したがってわれわれの要求する絶対的真理(the Truth),実在(the Reality)に到達することは不可能である。しかし絶対的真理・実在たるものが存在することをわれわれは心(heart)によって知っている。とはいえ、かかる絶対者を判断によってとらえることはできない。われわれの判断は原理的に不完全・あやまれるものだからである。絶対者は一切の判断を拒否し、時間・空間中にもない、区別なき一者である。
1912年に出版された本書の思想は,このようにして多くの点でムーアのそれと規を一にしている。もちろん、独創的思想家であるラッセルはこの当時といえどもムーアと完全に思想を同じくするものではない。とくにラッセルには、古典学の教養のみを哲学以外の背景としているムーアには到底及びもつかない、数学・論理学・数学的自然科学の教養がある。この方面を背景とする多くの独創的な論理学的・認識論的思想が彼にあるのは当然のことである。また、一生のあいだ基本思想を変えなかったムーアと較べて、ラッセルの哲学思想には相当の変化があったことにも改めて注意する必要があろう。
しかしそれにしても訳者がとくにムーアの名前を挙げるのは、ラッセルが認識の出発点として絶対不動の直接所与を認め、これを純粋な感性的経験内容であるとして,これにムーアと同じく感覚与件なる名前をあたえているからである。彼らがこのように感覚与件なるものを考えるにいたった動機として、ブラッドリーによる絶対確実な知識判断の否定に対する反発があるが、独欧学派のブレンターノやマイノングの影響があるといわれる。独欧学派の人達は認識における作用と内容とを峻別できるものとする。ムーアとラッセルはこの見解を受け容れたが、とくにムーアは両者の区別を強調した。感覚(sensation)とは多義的な語で、それは感覚する働き・心的作用(mental act)と(これによってとらえられる)内容=感覚与件とに分けるべきものであるとした。色感のばあいでいえば、見る働きは見られる色とまったく違うというのである。この区別を徹底させて彼は、見なくても感覚与件としての色が存在することは考えうるとまでいう。本書を書いた当時のラッセルは「感覚与件」なる語でムーアと同じものを指してはいるが、その理解はムーアよりも常識的で、1914年に発表された『感覚与件と物理学との関係』では感覚与件の所与性を強調し、たとえば見られない色は所与としてあたえられていないから感覚与件ではないとしている。このためかムーアが最後まで感覚与件に固執したのに対し、ラッセルの方はしばらくしてこの見地を放棄している。
その萌芽はすでにいまあげた1914年の論文に出ている。ラッセルもムーアも実在論者であるから、感覚与件を存在物として認めるともう一つの存在物である物質的対象との関係を論ずる必要にせまられる。ムーアは物質的対象の存在を確信しながら、感覚与件との関係を十分論ずることができなかったようにみえるが、ラッセルはこの確立に苦慮し、次第に物質的対象を感覚与件から構築(construct)できるものとして考えるようになった。このとき困るのは,見たり、聞いたりしていないときの物質的対象のあり方である。これは見たり聞いたりしていないときに感覚与件が存在していないのでは治まりがつかない。そこでかれは前記の論文で感覚作用のないときにも存在する、感覚与件と同種の「感性体」(sensibillia)なるものの存在を仮定するにいたる。しかしこのことはすでに感覚与件の立場を踏み超えていることを示すものであろう。
ここで本書の基本的立脚地であるラッセルの実在論を振り返ってみよう。ラッセルは現象主義の方に傾いたこともあったが、いままでの長い生涯を通じて基本的には実在論であった。しかし多少なりとも現象主義に染まっている彼の実在論が、一番徹底したのは本書においてであるということができる。もっとも感覚与件を確実な存在として認める以上、これと物質的対象との関係をどのように考えるかが一番重要であり、またわれわれの関心を有するところである。ラッセルは同一対象を感覚するばあいにすらいえる感覚与件の個人的差異をムーア以上に強調し、それぞれの人がそれぞれのばあいにもつ感覚与件を原理的に異なった私的なものであるとし、その時間・空間的規定もまったく私的なものであるという。ここに青年時代に彼の好んだライプニッツの単子論の影響がみられる。しかしライプニッツと違ってかれは、すべての人に共通なものとしての物質的対象をも認めるわけである。いかにしてわれわれはこのものの存在を知るのであろうか。本文にみられるように、ラッセルはその存在の合理化を基本的には本能的信念に求めている。われわれから独立した外界の存在は論証によって得られたものでなく、もともと所有している信念であるというのが彼の見解である。この信念なる考え方は,ヒュームの思想の発展とみられるが、この本能的信念なるものはこの時代のラッセルよりも後期ラッセルにおいて一層重要な役割を果たすようになる。彼は厳密な論理的証明の不可能なところに、しばしばこの生物学的・心理学的概念の助けを求めている。
しかしラッセルは物質的対象の存在の拠りどころをたんに本能的信念に求めているのではなく、その論理的補強として単純性の原理をもちこんでくる。われわれは変転きわまりない感覚与件の流れ,むしろ交替,だけでは実際問題として到底現実世界を記述することはできない。それは複雑、無法則に過ぎるからである。外界の名残りは物質的対象を仮定して初めて合法則的に捉えられるというのである。ここにわれわれはカント的問題が別の論理によって定式化されているのをみるであろう。ラッセルにおいても、カントの物自体と同じく、物質的対象そのものの色・形・大きさ等は捉えられず、またこのような考えは意味をもたないものとされる。ただ捉えられるのは感覚与件との対応関係である。物質的対象間の空間的・時間的諸関係は、われわれが直接感知できる感覚与件間の空間的・時間的諸関係と同じものであるか、またはこれに対応するものであるとされる。こうして近代数学・近代論理学で主役を演ずる対応の思想が、ラッセルの認識論では表面に出ている。もっとも彼には、客体としての物質的対象を感覚与件の原因の一つ(もう一つはわれわれ人間)として考えるような素朴な思想もある。
しかし物質的対象が外界の法則的把握に必要だといっても、感覚与件を物質的対象と並べて基本的存在としたのでは、(ぎこちない)存在の多重化と写らざるをえない。この多重化はラッセルが論理学者としてモットーとするオッカムのかみそりに抵触し、また引いては彼自身主張した単純性の原理に反することにもなりかねない。こうして彼は自身重要な寄与をして自然数の定義の方法や、ホワイトヘッドのおこなった空間点・瞬間・粒子の構築法を援用して、物質的対象そのものを構成的に定義しようと企てるにいたるのである。(前掲『感覚与件と物理学との関係』および『外界に関するわれわれの知識』1914年) ここにいう定義は既知の要素からの対象そのものの構成法を教えるのでなく、求める対象と同型(isomorphic)の意味で同じあり方をすると考えられる対象の構築法をあたえるのである。それは論理的に導き出されるという意味で、ムーアや本書のラッセルの立場とは異なってくる。本書のラッセルにおいては、物質的対象はたんに感覚与件から推認されるだけで直接導出されるものではなかったからである。
ラッセルの認識論でとくに独創的なものは、知識を見知りによるものと記述によるものとに分けることであろう。その理論は1911年に初めて明確な形で発表されたものであるが、1905年に出た、かれの著名な記述理論をその論理的背景としている。後者は当時においてはその重要な意味を理解されなかったが、その後、彼とウィットゲンシュタインによる論理的原子論や論理実証主義・意味論等の展開によって、その重要性がきわめて高く評価されるようになった。見知りによる知識と記述による知識とを区別することは、従来の経験主義的知識論の狭い枠を打ち破って,知識を理性的・普遍的方面にまで拡大するものである。しかし一方、いかなる知識が見知りによってえられるかについては、ラッセル自身決め手をもたないようにみえる。かれは感覚与件・記憶内容・感覚与件の感知を見知りの対象としているが、感覚与件そのものは彼の協力者ムーアにおいては知識とはなりえないものであった。知識・認識の対象となるものはムーアにおいては命題のみである。しかしこの時代のラッセルは命題のみならず事物も知識の対象となるとし、第11章の終りで論じているように、知識を事物の知識と真理の知識とに分けている。もっともラッセル自身、現象主義の時代には感覚与件を所与として知識としては考えないようになった。また感覚与件の感知、たとえば「わたしが太陽を見ること」は1つの心的作用であり、このようなものを否定する『心の分析』の立場からすれば、それは見知りの対象というわけにはいかない。また彼は、「わたし」との見知り、ある種の普遍との見知りという考えをもっていてこれにも問題はあるが、ここでは論じないことにする。
本書の帰納理論について一言すれば、帰納理論はヒューム以来、英国哲学のもっとも得意とするところであるが、その基本的観点はヒュームのそれをあまり出ていない。本書の理論もその例にもれず、ただ帰納原理を明確に定式化したにとどまっている。しかしこの方面におけるラッセルの思想はその後かなり発展をみた。それは帰納を因果系列の把握と結びつけ、この把握を基本的には,例の本能的信念に基づくものとして考察するのである。それは1948年の『人間の知識』(Human Knowledge)などに主として論じられている。
本書では帰納原理の考察から一般原理が問題とされ、さらに先験的知識・その要素としての普遍に論述が及ぶという順序になっている。ラッセルが古典的な経験論者と違う、すぐれた点は、感性的・経験的なものと並んで論理的・理性的なものを独自なものとして認めたことにある。個別的なものに対して普遍的なものの独自性を認めたことにある。それは、彼が何よりもまずすぐれた論理学者であることによったのであろう。
一般原理・普遍的真理についていえば、ラッセルはここでとくに論理学の命題の性格について語っている。論理法則・論理原則はわれわれの思考を支配する法則ではなく、いかなる事実をも支配する事物の法則だというのが彼の基本的観点である。しかし同じく事物を支配する法則といっても,経験法則からは区別されなくてはならない。なぜなら論理原則そのものの正しさを経験によって証明することはできず、かえって一切の経験的命題は論理原則を前提とすることによって初めて証明されるからである。この意味で、経験論者と理性論者との論争は基本的に理性論者が正しい。一切の知識は特殊経験を機縁としてえられるものであるが、論理学や数学の命題は経験を起源とするものではない。こうして、論理学や数学の命題が属する先験的知識の正しい理解が必要となってくるのである。ラッセルはカント的な先験的判断に関する見解を排除するが、先験的判断そのものの存在を確認していることに注意せねばならない。
しかし先験的真理に関するラッセルの透徹した論述にも、将来(本書執筆以後)の見解の変化を予知する意見の矛盾が萌芽的に含まれている。それは、彼が論理原則すら事物そのものについての法則と考えておきながら、一方では先験的知識は一切仮説的なもので、特殊事物に関する経験がなければ現実世界について少しの立言もできかねるとしていることである。たとえば論理原則はすべて、「かくかくであればかくかくである」と教えるにすぎず、端的に「かくかくである」ということはできないというのである。ここに重大な見解の分裂がみられるのであるが、ラッセル自身は論理法則を次第にたんなる言語規則としてみる見地に移行していったのである。
ラッセルは「先験的知識」なる語をカントから援用したかにみえ、先験的なものと分析的なものや綜合的なものとの関係は、本書では大体カントをそのまま踏襲しているようにみえる。それは、1つにはかれが「分析的」,「綜合的」なる概念について十分の反省もなくカントの用法をそのまま用いていることに基づくのであろう。同様に、先験的真理と論理的真理との関係も本書でははっきりのべられてはいない。しかし『数学原理』完成の直後に書かれたという本書成立の事情から推察すれば、両者は基本的には一致しなければならないようにみえる。それとも彼は帰納原理や道徳的原則のようなものを考慮して両者は異なっていると考えるのであろうか。ともあれ、この問題は最近の分析哲学できわめて活発に論じられた問題である。
ラッセルはカントの先験的論理学のみならず、先験的なものを一種の心的なものとみなす一切の理論を排除したが、彼自身は、第10章でのべているように、一切の先験的知識をもっぱら普遍間の関係を扱うものと考えた。その普遍のなかで主役を演ずるのは関係である。関係の理論はラッセルの論理思想のなかでとくに重要な位置を占めるものであった。そもそも普遍なるものは経験主義者が考えたように心的なものでは決してない。それは心的世界・物的世界とは別の第3の世界、あるいは心的・物的世界を1つの感覚的世界としてまとめれば第2の世界を構成する。前者が可変的なものに対し後者は不変的である。このような思想においてラッセルはほとんどプラトンの現代版である。しかし従来の哲学・論理学では形容詞または名詞に対応する普遍のみが論ぜられて、動詞または前置詞に対応するものが無視されてきた。この動詞または前置詞に対応する普遍としてラッセルが考えているのは関係である。関係はそれまで性質に従属的にのみ論ぜられる傾きがあったが、スピノザやブラッドリーの一元論も、ライプニッツ風の多元論も、その根拠はこの普遍の誤認にある。こうしてラッセルの重要な哲学・論理学の寄与である、関係の理論が展開されたのである。
このようなラッセルのプラトン的普遍論はどのように特殊と普遍とを関係せしめるか。そこに後天的なものと先験的なもの・感性的なものと理性的なもの・事実的なものと論理的なものとの関連の仕方が問題となる。それはラッセル哲学の基本的問題の一つであるが、彼はこの問題を十分説得的には論じていない。しかし彼自身本書の普遍実在論的立場を少しずつ変えて、次第に唯名論的傾向を示すようになったことに注意しておく必要がある。
なおラッセルはある種の知識を直観的に自明なものとし、またすべての知識に蓋然性の程度を帰属せしめている。これについても論ずべき問題は多いが、ここではこれ以上論じないことにする。
最後に哲学の価値について論じているが、哲学を実用のために学ぶという考えを排し、哲学によってせまい人間の視界を拡げ、人間を宇宙の市民たらしめ、このことによって真の人間的自由を獲得せんとの考えをのべている。真理への愛とともに人類平和への努力に一生を献げてきた彼の信念としてまことに興味深いものがある。
本訳書は、市井三郎氏のお薦めによって完成したものである。とくに記して感謝の意を表をわしたい。また訳出にあたっては先学・柿村峻氏の本文庫での訳文を参照し、被益するところが多かった。厚くお礼を申し上げたい。なお術語翻訳について相談にのって下さった武田弘道氏、訳者の口述を筆記して下さった中本昌年・藤田晋吾の両君、種々ご迷惑をお掛けした杜会思想杜の星野和央氏・伊藤友乃氏の諸氏にもあわせて謝意を表する次第である。