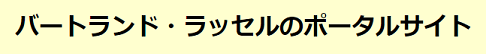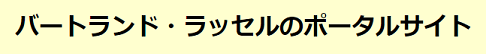第12章 意識と経験 n.2 - 主観は論理的虚構
この問題は、当初、見かけ上そう思われた以上に重要なものであった。我々は経験によって学習するということは明らかであり、しかも少なくとも私には、学習が単にある種の行動の仕方を獲得することだけで成り立っているだけでなく、また「知識」と呼ぶことのできる何かを生みだすことで成り立っていることは明らかであると思われた。そしてこのことは、私が感覚は関係的事実であるとする説(関係説)に固執している間は困難を生じなかった。この説によれば、あらゆる感覚(感覚するもの)全ては、それ自身一つの認識であり、それは私が 「感覚所与(sense-datum センス・データ)」と呼んだものの意識(ものを意識すること)で成り立っていた。(しかし)『精神の分析』(1921年) において、私は「感覚所与(センス・データ)」という考えを明示的に捨てた。私はこう述べた、「感覚は、明らかに、我々自身の身体を含めて、世界についての我々の知識の源である。(従って)感覚はそれ自身一つの認識であると見なすことは当然であると思われ、私も、最近まではそう考えていた。(たとえば)知人が街で私に近づいてくるのを見る時、あたかも単に見ることそれ自体が知識であるかのように思われる。もちろん、知識は見ることを通して得られることは否定できない。しかし私は、単に見ることそれ自体を直ちに知識であると考えるのは誤まりであると考える。もし仮に、見ることが直ちに知ることではないと考えるならば、我々は見ること(もの)を見られること(もの)とを区別しなければならない。 たとえば、我々がある形した一片の色を見る場合、その一片の色と、我々がそれを見ることは、別々のことであると言わなければならない。けれども、この見解(見方)はさきに(『精神の分析』の)第1項で論じた意味における『主観』(主体)ないしは『作用』を認めることを要求する(注:The Analysis of Mind は、1919年と1920年にロンドンで公開講義がなされている)。そしてもし仮に主観(主体)があるとするならば、主観(主体)はその色の一片に対して一つのの関係すなわち意識(awareness)と読んでよいような一つの関係を持つことが可能である。この場合、ひとつの心的事象(event)としての感覚は、色の意識で成りたっており、一方、色そのものは全く物理的なものであって、これを感覚と区別するために、感覚所与と呼んでよいであろう。けれども、主観(主体)は、数学的な点や瞬間と同様に、一つの論理的虚構であると思われるのである。 主観なるもの(論理的虚構)が導入されるのは、観察がそれ(その存在)を明らかに示すからではなく、そうすることが言語上便利であり、明らかに文法上必要とされるからである。こういう名目的な存在は、現実に存在するかも知れずまた存在しないかも知れないが、それが存在すると想定すべき十分な理由はない。そういう名目的存在が果たすと見える機能は、集合や系列(series)やその他の論理的構成物によって常に果たすことが可能であり、これらは(主観などの)名目的存在ほど疑わしくないもので成り立っている。我々が全く無根拠な想定(perfectly gratuitous assumption)をすることを避けるべきであるとしたら、我々は世界の実際の構成要素の一つとしての主観をなしですまさなければならない。 しかしそれをやめると、感覚を感覚所与から区別する可能性もまた消え去る。少なくとも、私はその区別を保存する方法を知らない。従って、我々が一片の色を単純に見るときにもつ感覚は、その一片の色そのものであり、物理的世界の現実的要素であり、物理学がとり扱うものの一部である。 一片の色は確かに知識ではなく、それゆえ、我々は単なる感覚が認識的であると言うことはできない。感覚は それの生み出す心理的効果(結果)により、認識の原因となる。 それは、或る場合にはひとつの感覚がそれに関連する他のものの記号となることによってであり(たとえば視覚は触覚と関連する)、またある場合にはその感覚が消えた後に心像(イメージ)や記憶を生じさせることによってである。 だが、単なる感覚はそれ自身では認識ではないのである。」(pp.141-142)
|
Chapter 12: Consciousness and Experience , n.2
The issue was more important than might at first be apparent. It is obvious that we learn by experience and it at least seemed obvious to me that learning does not consist merely in acquiring certain ways of behaving but also in the generation of something that may be called 'knowledge'. So long as I adhered to the relational theory of sensation, this offered little difficulty. Every sensation, according to this view, was itself a cognition which consisted in awareness of what I called the 'sense-datum'. In the Analysis of Mind (1921) I explicitly abandoned 'sense-data'. I said: 'Sensations are obviously the source of our knowledge of the world, including our own body. It might seem natural to regard a sensation as itself a cognition, and until lately I did so regard it. When, say, I see a person I know coming towards me in the street, it seems as though the mere seeing were knowledge. It is of course undeniable that knowledge comes through the seeing, but I think it is a mistake to regard the mere seeing itself as knowledge. If we are so to regard it, we must distinguish the seeing from what is seen: we must say that, when we see a patch of colour of a certain shape, the patch of colour is one thing and our seeing of it is another. This view, however, demands the admission of the subject, or act, in the sense discussed in our first lecture. If there is a subject, it can have a relation to the patch of colour, namely, the sort of relation which we might call awareness. In that case the sensation, as a mental event, will consist of awareness of the colour, while the colour itself will remain wholly physical, and may be called the sense-datum, to distinguish it from the sensation. The subject, however, appears to be a logical fiction, like mathematical points and instants. It is introduced, not because observation reveals it, but because it is linguistically convenient and apparently demanded by grammar. Nominal entities of this sort may or may not exist, but there is no good ground for assuming that they do. The functions that they appear to perform can always be performed by classes or series or other logical constructions, consisting of less dubious entities. If we are to avoid a perfectly gratuitous assumption, we must dispense with the subject as one of the actual ingredients of the world. But when we do this, the possibility of distinguishing the sensation from the sense-datum vanishes; at least I see no way of preserving the distinction. Accordingly the sensation that we have when we see a patch of colour simply is that patch of colour, an actual constituent of the physical world, and part of what physics is concerned with. A patch of colour is certainly not knowledge, and therefore we cannot say that pure sensation is cognitive. Through its psychological effects, it is the cause of cognitions, partly by being itself a sign of things that are correlated with it, as e.g. sensations of sight and touch are correlated, and partly by giving rise to images and memories after the sensation is faded. But in itself the pure sensation is not cognitive' (pages 141-142).
|