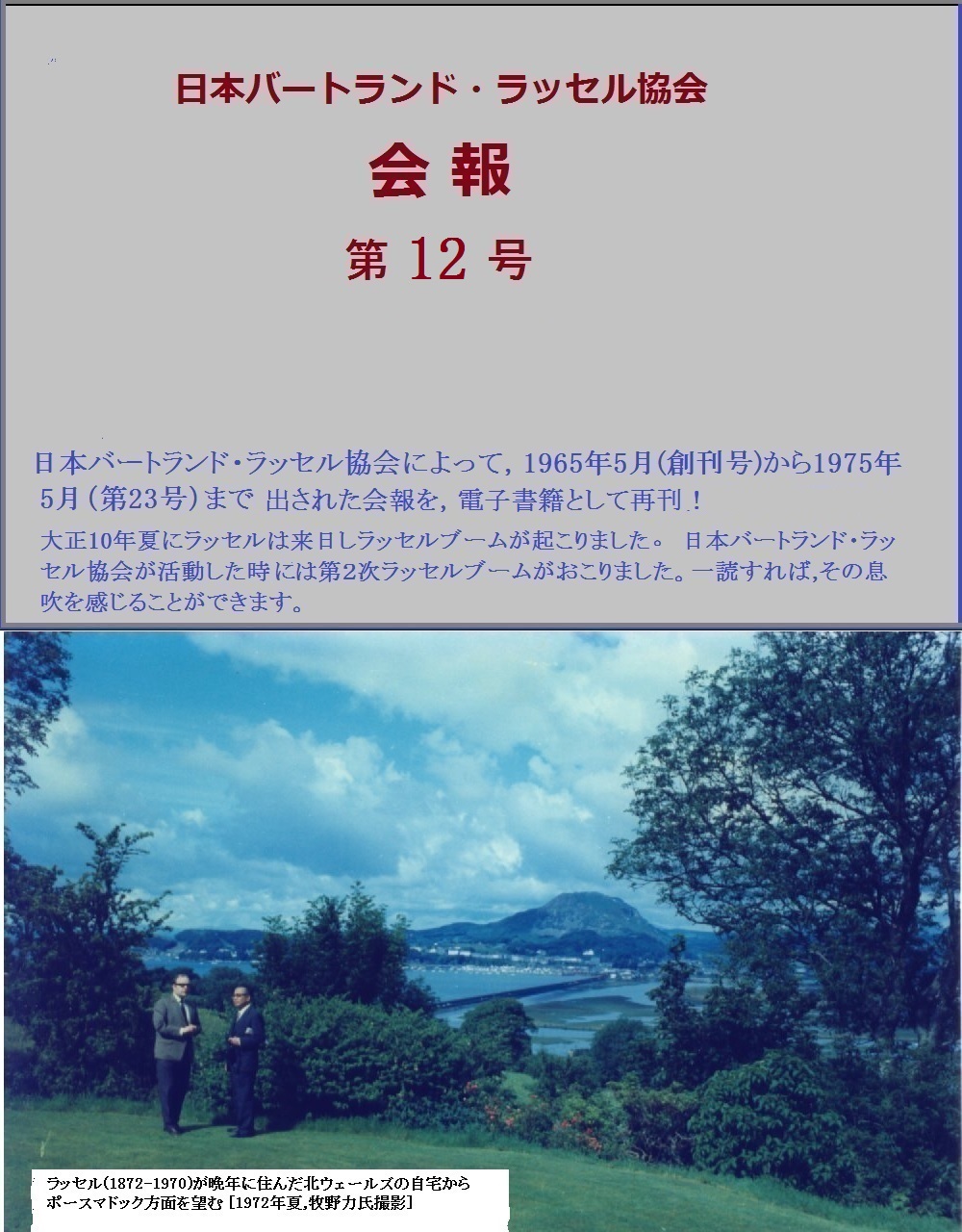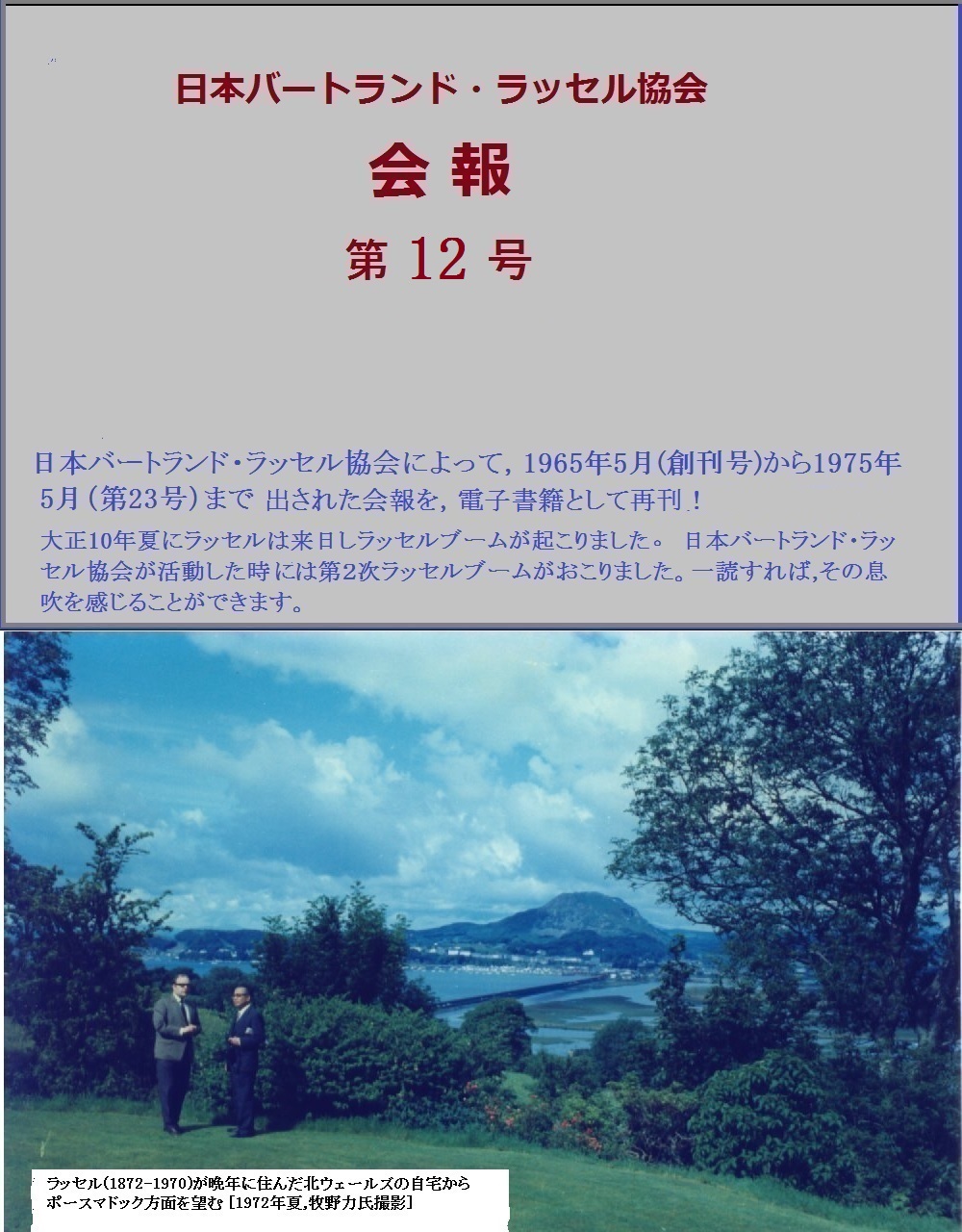吉田夏彦「(ラッセルの) 哲学と論理学」(日本バートランド・ラッセル協会_第4回研究会講演要旨_
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第12号(1969年4月)pp.2-3,& 5
* 吉田夏彦氏(1928~2020)は当時、東京工業大学助教授。なお、目次(p.1)では「ラッセルと哲学の方法」となっている。
1.ラッセルの精神
ラッセルの哲学上の功績の一つは、論理学が哲学にとって持つ意義を強調した点であろう。この論理学はいうまでもなく、古い論理学ではなく、ラッセル自身がその発展に大きく寄与した現代論理学である。20世紀の始めには伝統的論理学と現代論理学とのちがいについての認識はまだ普及していなかったから、このちがいを強調することに十分な意味があった。ラッセルの努力も、しばしば、この点での啓蒙にあてられたのである。
しかし、現代論理学についての知識もようやく普及しだした現在では、このちがいのことばかりに重点をおいて話をするのは、得策ではないと思われる。特に哲学との関連でいえば、古代ギリシア以来、西洋の哲学者がその解決に心をくだいてきたさまざまの問題に対し、有力な武器を提供してくれるところに、現代論理学の一つの意味があるのだから、それと過去の伝統とのつながりの面にも、ひとの眼をむけるようにしなくては、話が片手落ちになるおそれがある。
また、ラッセルは、1930年代に、論理学の研究を止めてしまったが、論理学は、その後も、めざましい発展をつづけている。その発展の中でえられた新しい成果の中には、哲学的にも重要な意義を持つものが少くない。そうして、そういった成果にてらしてみると、ラッセルの予想があたらなかったとしなくてはならない点も多数ある。たとえば、彼は、いわゆる集合論の二律背反をさけるため、タイプ理論をとなえた。しかし、今日ではタイプ理論は、数学の全体系を再生するためには、弱すぎるものであると考えられ、むしろ、彼のライバルであったツェルメロの創始した公理的集合論の研究の方が盛んである。また、彼は、集合の概念を原理的には除去してしまい、属性の概念の方を基本的なものとすることをこころみたが、現在からみれば、このこころみは成功しなかったといえる。
そこで現在において論理学と哲学との関係を論ずるのには、ラッセルが、かつて同じ主題についておこなった議論をじかに追っても、あまり意味はないことになりそうである。それよりも、論理学や哲学の現在の発達段階に即した話をした方が適当である。しかし、こうすることは、ラッセルが、20世紀の始めに情熱的におこなった議論のいわば精神ともいうべきものを受けつぐことにはなると思う。特に、哲学研究者の間に、論理学が哲学にとって持つ意義がまだ十分に浸透しているとは、いえないのが現状であることを考えると、なおのことそういえると思う。いいかえると、5,60年前のラッセルの主張のこまかい点に通じている哲学史家はふえても、当時のラッセルが当時の論理学の発達状況をふまえてこの問題をとりあつかったのと似たことを現在においてこころみる哲学者の数は、依然として少いのが現状である。
しかも、哲学者の大部分が論理学の発達に眼をふさいでいる間に、大局的な意味で、ラッセルの正しさがうらがきされるような状況もひらけてきた。つまり、ラッセル自身は集合の概念に対して懐疑的になった時があるけれども、集合論的な枠が論理学や数学を統一するものであるということは、彼が終始いだいていた信念であった。そうして、昨今のブルバキズムの流行などに、技術的なこまかい点はぬきにすればこの信念が正しかったことをしめしているといえる。
ここでは以上のことをふまえ、現代論理学と哲学との関係を、現在において妥当と考えられる見地から、解説することをこころみたい。
2.論理学のカテゴリ
集合の性質については、現在でもよくわからない点が多い。また集合については、よほど気をつけてものをいわないと、矛盾を生ずるという危険は、依然として存在する。しかし、集合概念がその問題性にかかわらず、論理学や数学において、かくことのできない基本的なものであるということは、今日、大多数の論理学者や数学者によってみとめられているところである。
さて、集合とは、ひらたくいえば、一つの条件をみたすものの全体を、それ自体、一つのものとしてあつかうことが許される場合の、ものとしての全体である。たとえば、「清和天皇の子孫で源姓を名乗っていた」という条件をみたすものの全体は、清和源氏という集合になる。「美」ということばは、「美しい」という条件に対応する集合をあらわしていると考えられることもある。
この、あとの例からわかるように、集合は、むかしの哲学で考えた普遍者に大体、対応するものと考えてよいのである。
つぎに、むかしの論理学では、定言判断、すなわち
・・・は ・・・である
というかたちの文を基本的なものと考えたが、この点は、現代論理学においても同じである。ただ、伝統的論理学では、定言判断のうちでも、包摂判断、つまり一つの集合とその部分集合とのあいだの関係をあらわす文を一番基本的なものとしたのに対し、現代論理学では、一つの集合とそのメンパー(元)とのあいだの関係をあらわす帰属判断を、一番基本的なものと考える。
詳しくいうと、
・・・は ・・・である
というかたちの文は、
1)・・・は ・・・の部分集合である
2)・・・は ・・・の元である
3)・・・と ・・・とは同じ一つのものである
の三通りのかたちのどれかに解釈できるが、このうち第一のかたちを基本的なものと考えるのが伝統的論理学であり、第二のかたちを墓本的なものと考えるのが現代論理学である。なお、
・・・は ・・・の元である
というかたちは、記号をつかい
∈
と書かれる。
基本的な文から出発して複雑な文をつくる操作として、現代論理学は、つぎのようなものを考える。
否定 文Aから 「Aではない」をつくる
連言 A,Bから 「AでB」をつくる
選言 A,Bから 「AかB」をつくる
仮言 A,Bから 「AならB」をつくる
全称 変項(というのは代名詞を一般化したようなもの)xをふくむ文Axから、「すべてのxについてAx」をつくる。
存在 変更xをふくむ文Axから、「Axをみたすxがある」をつくる。
以上のものがあれば、原理的には、現代論理学が分析する論証は、すべて表現できる。そこで、現代論理学の基本概念(カテゴリ)は、つぎのようなものだということになる。
集合
∈(帰属関係)
否定、連言、選言、仮言
変項
全称、存在
これ等のカテゴリの大部分は、昔から知られていたものであり、のこりのものについても、その有力な前身ともいうべきものが考えられていたことは、さきにのべたとおりである。つまり、カテゴリにおいて、現代論理学は、特に眼新しい点は、少いのである。
しかし、この少数の、どちらかといえば昔からおなじみのカテゴリだけをもちいて、論理学や数学において必要な概念のすべてが定義できるということの発見は、現代論理学の重要な成果の一つなのである。この成果をもたらすのには、ラッセルも大いに貢献した。
なお一時、関係の概念がカテゴリとして必要であるとされ、関係をカテゴリとして認める点こそ現代論理学と伝統的論理学とを区別する重要な点である、と考えられたことがある。しかし、ウィトゲンシュタインやクラトウスキによリ、順序対の定義が考えだされてからは関係をカテゴリとする必要はなくなった。このことが、かなり古いことであるのに哲学者には必ずしも知られていないのは、注意を要する点である。
3.論理的分析
この、ごく少数のカテゴリだけで、きわめて多くの概念の定義が可能であるという事実に、ラッセルは非常な感銘を受けたようである。そこで、このやり方を論理学や数学の領域から、哲学の領域にまでおしひろめようとして、彼が唱道したのが、いわゆる論理的分析の方法である。この方法は、経験科学や日常生活、あるいは形而上学などに登場する概念についても、少数のカテゴリにもとづく定義が可能であることを示そうとこころみるもので、特に定義のし方については、論理学や数学のそれに範をおこうとした。
ラッセルは、この分析のプログラムを立てただけで、実行の方には少数の例を示した他はあまり手をそめなかったが、1920年代から1930年代にかけてのカルナップは、かなり精力的にこのプログラムを実行した。また、この分析により哲学古来の難問がとけるであろうとする見込みについて、説得的な議論を展開した。そうして、カルナップの主張は多くの論理実証主義者をひきつけたのである。
しかし、1940年代前後の後期ヴィトゲンシュタインを中心とする日常言語派の反撃により、論理的分析の有効性に対する信仰は、哲学者のあいだでは、ようやく勢いをうしないだしたのである。
日常言語学派の、ラッセル、カルナップ批判には、もっともな点もある。特に、この二人の哲学者が、新しい論理学によってひらけた可能性の大きさに酔ったあまり、独断的ないいかたをしていた点をついた批判は、正しい批判である。けれども、論理的分析に関する二人の議論がゆきとどかなかったのは、当時、論理学の発達がまだ十分なものではなかったことによる面も大いにあるのである。したがって、かつてのラッセル、カルナップの主張が批判されるべき点を多々ふくんでいたことが事実であるということから、論理的分析の方法が無効であるということは、必ずしもでてこないのである。それどころか、現在における論理学の発達状況を背景において考えれば、かつてのラッセル達の予想よりさらにひろい範囲で、大いに有効であると考えられる。
たとえば、論理的分折の方法は唯名論にとって有利な結論を保証するものであるかのように、一時は考えられた。けれども、現在になってみればこの方法は、世界観において中立的なものであり、さまざまな立場の哲学者により、使用可能なものなのである。だから、今では、むしろ、実在論的な傾向の人により、好んでもちいられたりしているのである。また、科学基礎論の領域では、たとえば測定の問題に、この方法が応用された結果、多くの混乱が除去されているのである。
4.普遍論争
古くからの普遍論争に、論理的分析の方法が新しい光をあててくれることを指摘したのは、ラッセルとカルナップとの弟子になるクワインである。彼は、存在の問題を、論理学における存在の概念によって考えるべきだとするラッセルの主張にしたがった結果、この指摘に達したように想われる。
クワインの存在論をめぐっては、賛否さまざまの意見が、多くの哲学者によって表明されているが、論理学のことを少し深く考える場合には、彼の議論に、きくべき点の多いことがわかると思う。
以上、とりあげた点の具体的な説明や、ここでは論じ残したいくつかの点は、近く当協会から刊行予定のモノグラフにのせる、この小文と同名の文章のなかでおぎなうことにしたいと思う。(了)