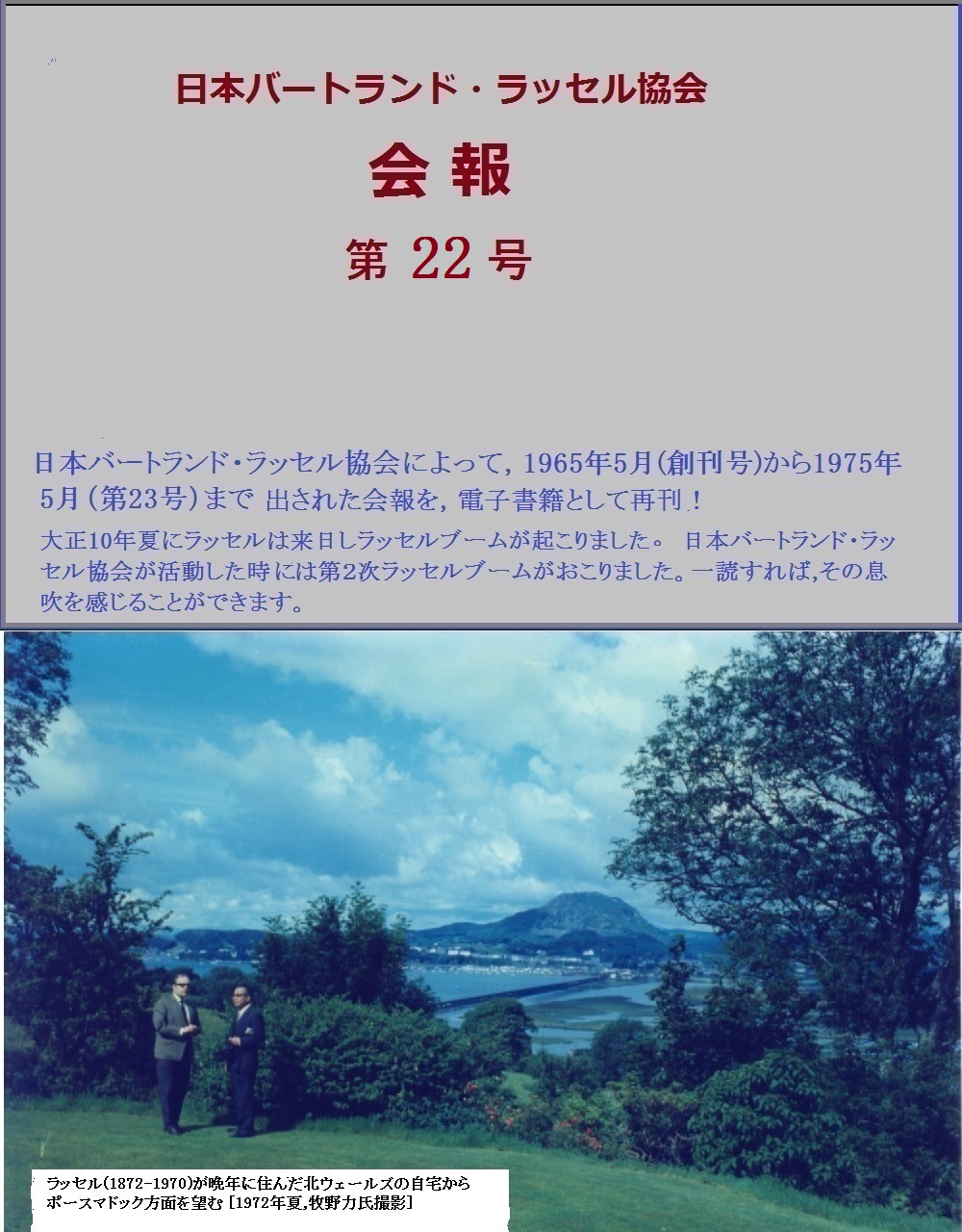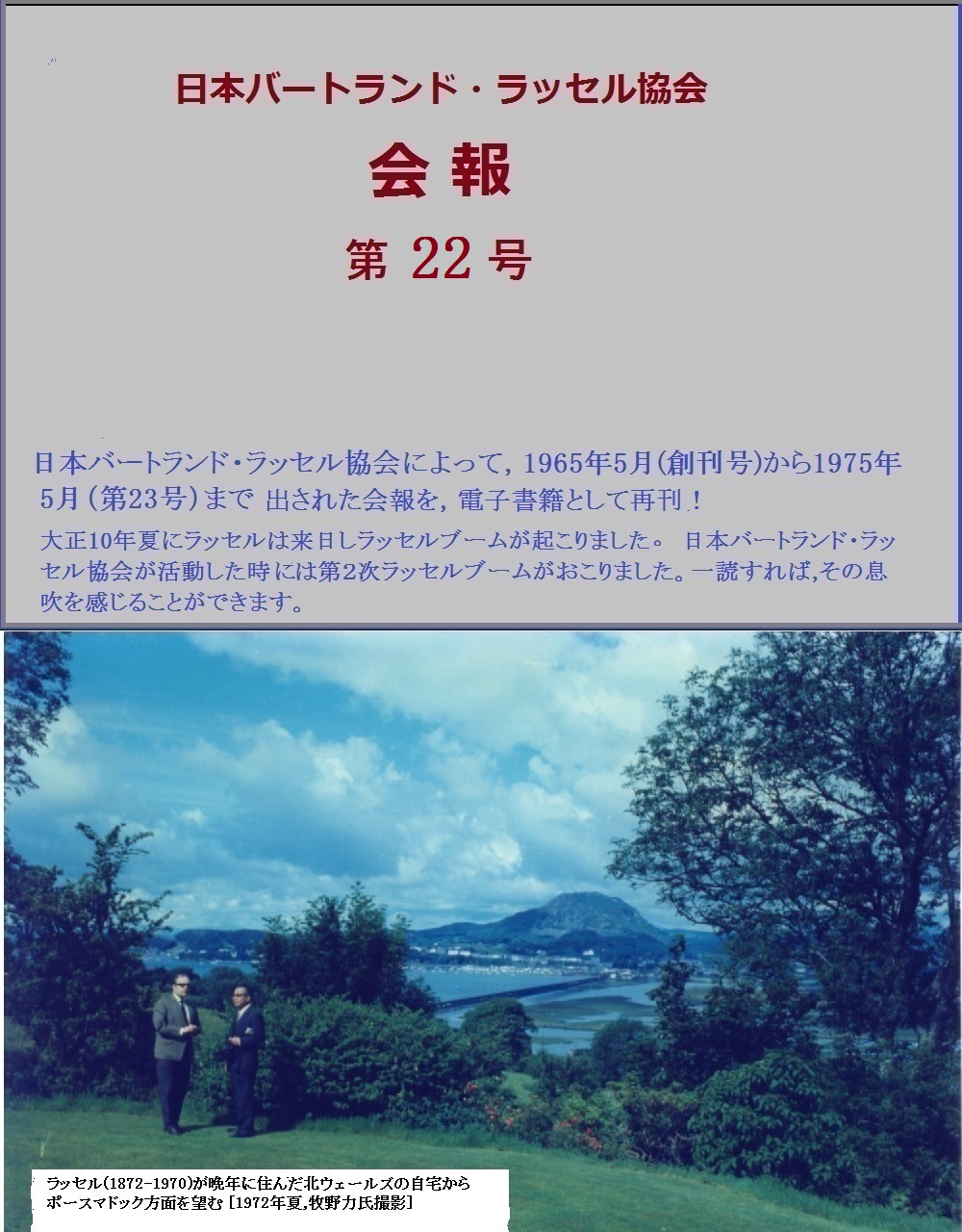谷川徹三「自由人ラッセル」- バートランド・ラッセル生誕百年記念講演要旨
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第22号(1973年9月)pp.1-2.
* 谷川徹三 氏は,当時,ラッセル協会第2代会長
 ラッセルは,哲学者としては,数理哲学や論理学の領域に最も大きな業積を残しています。しかし政治や社会の問題,宗教や教育や性の問題についても哲学者として大きな発言をした人です。そのころの人としてはラディカルな自由恋愛論者で,生涯に四人の女性と結婚するということをしています。自由といえば,一九〇二年に「自由人の信仰」という論文を書き,翌一九〇三年に雑誌に発表しています。今日はこの問題を中心に述べてみようと思います。
ラッセルは,哲学者としては,数理哲学や論理学の領域に最も大きな業積を残しています。しかし政治や社会の問題,宗教や教育や性の問題についても哲学者として大きな発言をした人です。そのころの人としてはラディカルな自由恋愛論者で,生涯に四人の女性と結婚するということをしています。自由といえば,一九〇二年に「自由人の信仰」という論文を書き,翌一九〇三年に雑誌に発表しています。今日はこの問題を中心に述べてみようと思います。
自由とは何か・…。フリーマンとかリベラリストというのは,元来は政治上又は経済上の自由主義者を意味するより,フランス語のリベルタントのように,ヨーロッパにおけるキリスト教の正統的信仰をもたない人という意味でした。日本においては,自由という言葉は古くは精神の自由ということで,特に禅宗では,「随所に主となる」とか,「応無所住而生其心」(まさに住するところなくしてその心を生ずべし)というような境地をさす言葉として使っていました。つまり,何ものにもとらわれない精神の自由で,これを最も高い精神の境地と考えたわけであります-こういう意味の自由の概念は古くから日本にもあった。しかし,そのうち自由という言葉が,ほしいままに振まう,勝手なことをするというような悪い意味にもっぱら用いられるようになりました。そこへ,明治になって,新しく西欧の自由の概念が入ってきたわけです。西欧における自由の概念は,人間の生きる道の探求と共に政治・経済・社会の諸問題に関連した思考をふくんでいた。ただ,英語では,リバティーとフリーダムとがちがうように,そこに二つの問題があった。リバティーは,ローマ時代に,奴隷という身分から解放された者について使われたラテン語の法律用語リベルタスから来ている。そこで,何らかの束縛から解き離されること,一般的にいって,「-からの自由」を意味するのに対して,フリーダムのフリーは古代英語のフレオンからきている言葉で,これは愛することを意味する-したがって友人(フレンド)とも語源を等しくしている。ですからフリーダムとは,「-からの自由」ではなく,「-ヘの自由」または「-である自由」であります。そこでフリーマンとは,ただ束縛から解放された人を意味するだけでなく,人生において積極的な態度を示すような意味をもっているのです。リバティーは価値の条件であって,それ自身価値ではない。おもしろいことに,英語では今もってリバティーとフリーダムとを区別するけれども,同じヨーロッパの大国であっても,フランスにはフリーダムにあたる言葉はありません。英語のリバティーにあたるリベルテしかないのです。またドイツにはリバティーにあたる言葉はなく,フリーダムにあたる意味のフライハイトがあるのみです。
これはフランスの政治的・社会的伝統が人権と結びついて,人間を古い権力から解放する努力に専ら向けられて来たからでしょう。それに反してドイツにおける伝統は,精神の自主性・理性の自律を深めることに重点をおいている。そこに国民性のちがいが見られると言ってよい。イギリスにおいては,両方の概念が存在している。ラッセルがフリーマン・自由人と言っているのには,こうした背景があると私は思っています。リバティーについて西欧人が考えの第一にすることは,キリスト教の正統的な信仰を否定することと結びつけて考えるのが普通です。ですから,ラッセルの「自由人の信仰」も,キリスト教的信仰をもたなくなった者が,キリスト教に代わるものとして,何を精神のよりどころとするかという問題をとり上げたのです。
科学の教える世界は無目的で無意味で,無限の世界である。人間は,いろいろな原因が,予見することなしに作り出したものである。自然は人間を計画的に作り出したわけではない。人間の起源と成長,人間の希望や恐怖も,愛や信念も,アトムの偶然の配列の結果にすぎないのです。歴史の各時代のあらゆる営みもあらゆる献身も,太陽系の壮大な自然と共に消滅する運命をになっている。人間の業績の輝かしい伝統は,不可避的に宇宙の瓦礫の中に埋もれないではいられないのです。すべてこれらは確実なことなのです。いかなる哲学もこのことを無視することはできません。心のよりどころと言ってもすべてはこの枠内でしかうちたてられないのです。しかしこうした自然の恐ろしい非情の実相の認識から,自主性や知恵が生まれ,新しい生活が生まれるのです。大前提は,人間などというものを考えて人間を作ったのではないということです。またそういう自然にしても,天地から作られたのであって,人間は関知しなかったのです。それにもかかわらず,あるいはそれなればこそ,人間と生まれたからには,人間社会でいっさいのことを考えていなければならないのです。この大きなプロセスの中核となっているものは何か。人間と社会とのあらゆる問題の中心にすえられているのは何か。それは結局,普遍的な愛としての人間愛である。ラッセルはここに注目したのです。この人間愛は,知識や知恵と結びついたものでなければなりません。知恵のない愛では,創造のいとなみができない。キリスト教の愛や仏教の慈悲は,ここで言う普遍的な愛にあたるものです。ニーチェは,この普遍的な愛を軽蔑したのでありますが,ラッセルは,この愛こそ,世界について願われるあらゆることに対する起動力であるといっています。
ラッセルはまた,『私はなぜキリスト教徒でないか』という著書を出していますが,その中で,自分がキリスト教徒でないのは,キリスト教には人間愛の知恵と結びついた発現を妨げる教会という組織があったり,魔女狩りや宗教裁判にみられるような憎しみの教義があるからであると述べているのであります。ラッセルは,古くから理論的社会主義者の集まりであるフェビアン協の一員でありましたし,ロシア革命には初め希望を抱き,一九二〇年,イギリス労働党員の一行と一緒にソ連を訪れているが,自分はなぜ共産主議者にならないかについて,それは,キリスト教と同様に憎しみの教義があるからだと言っています。晩年にいたって,ベトナム戦争をアメリカの戦争犯罪行為として告発した情熱にしても,この限りない人間愛の精神,自然にしてかつ純粋な自由人としてのラッセルの姿が見られる思いがいたします。