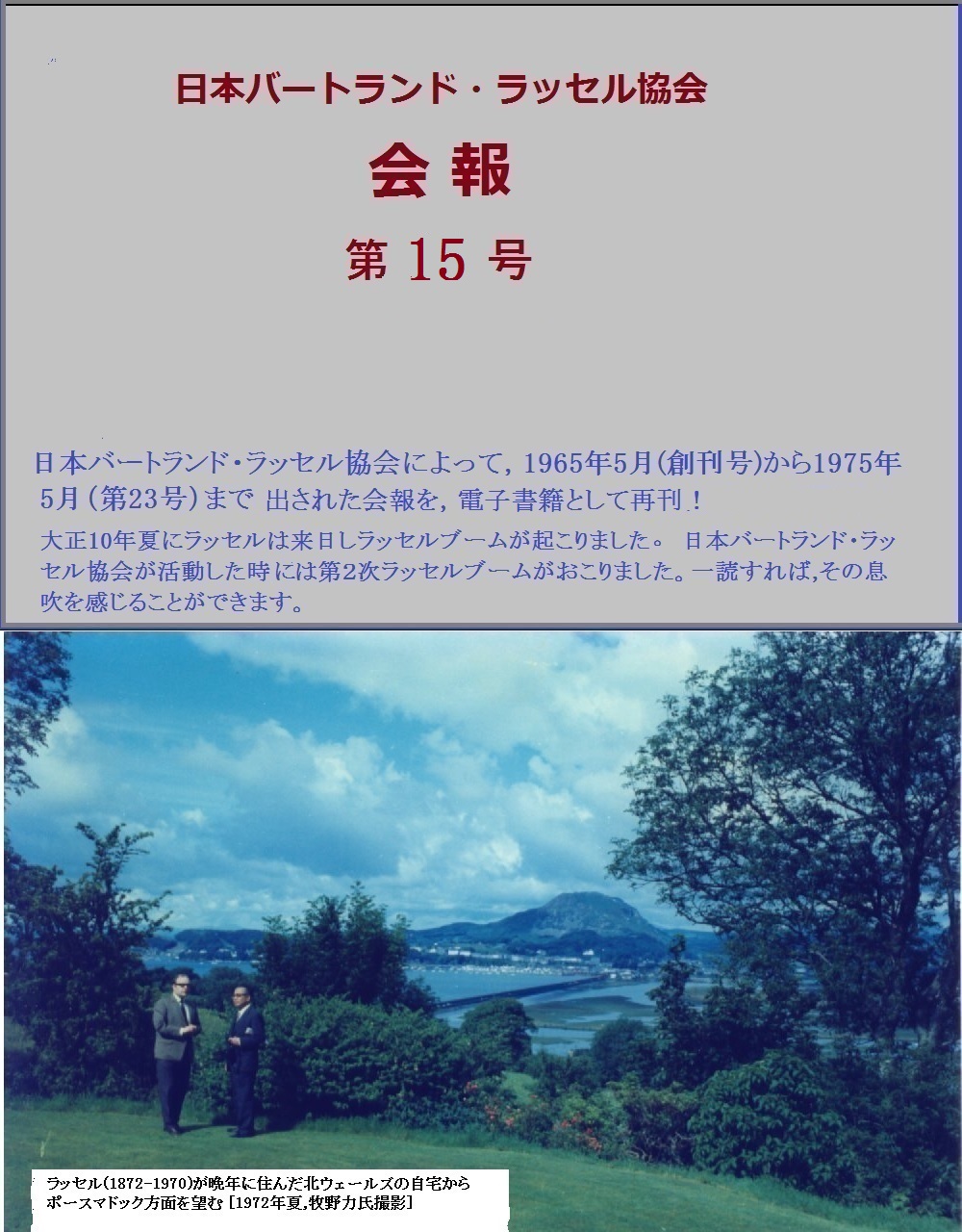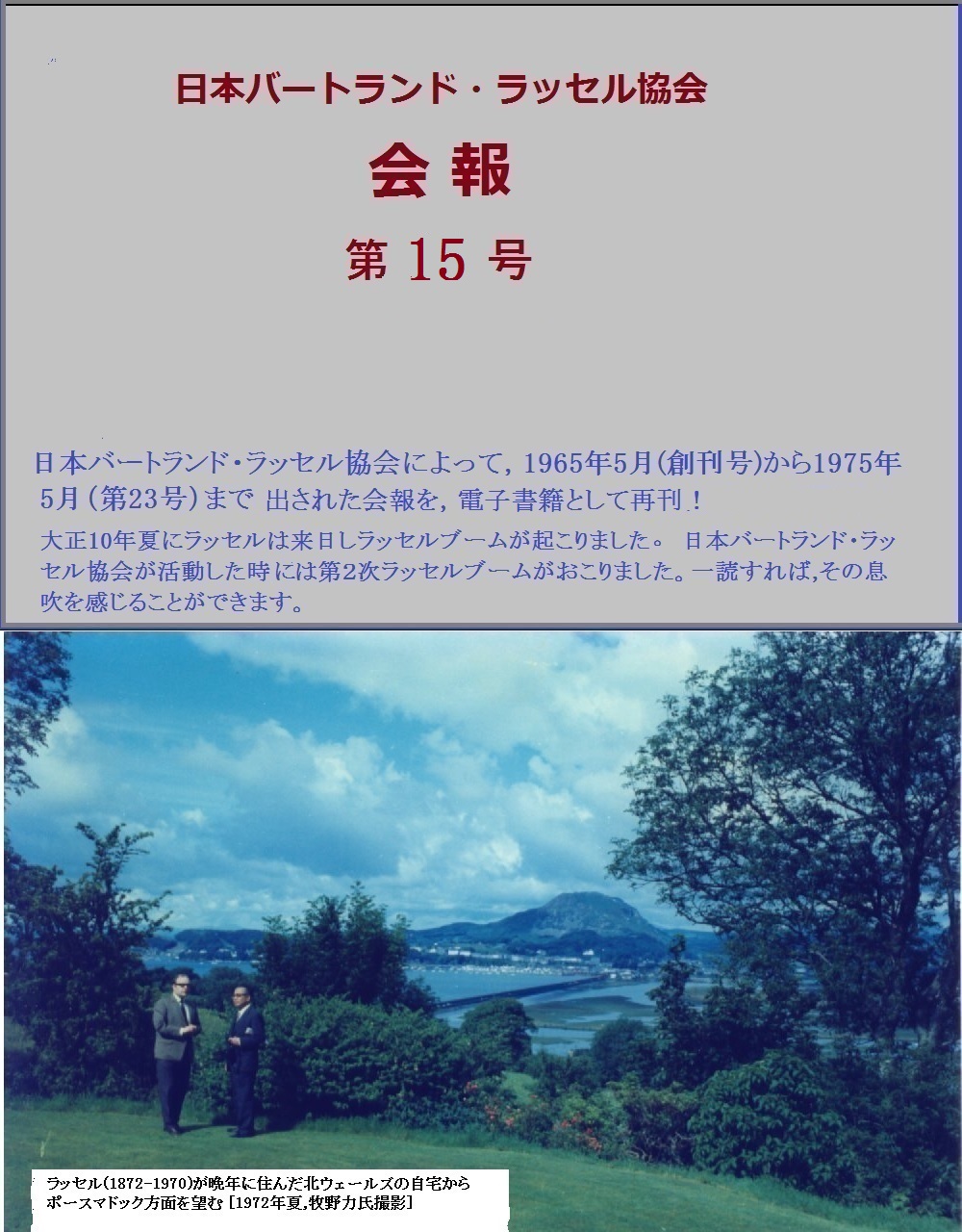島康晴「'地球の良心'(バートランド・ラッセルを)悼む」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第15号(1970年5月)p.9
* 島康晴は、日本バートランド・ラッセル協会会友(大分県、自由業)

バートランド・ラッセルはいわば、現代'地球の良心'であった。百才まで生きると豪語したこの巨星も遂に倒れたが、凡人からみればまさしく天寿を全うしたかの観がある。だがその生涯は決して平坦なものではなかった。或る時は投獄を、或る時は離婚を、或る時は講義のボイコット(松下注:ニューヨーク市立大学教授就任取消訴訟のことを指していると思われるが、ラッセルの講義が学生によってボイコットされたり、自分で講義をボイコットしたりしたわけではない。)や、或る時は飛行機事故で九死に一生を得る等、いわば波瀾の生涯であったともいえよう。
物理学にエネルギーがあるごとく、彼は社会科学のエネルギーとして「権力」を考えた。それはフロイトが「性(リビドー)」を、マルクスが「生産関係」を考えたのと同じである。そしてこの「権力への抵抗」こそは彼の全生涯であった。我々がラッセルに抱く魅力の一端はその反骨精神、野党精神にあるのかもしれない。事実彼は第一次大戦反戦運動でケンブリッジ大学を追われて以来ずっと野にあって活躍を続けて来た。
ベトナム戦争はこれを民族の独立戦争とみ、「アメリカ人よ、かつては君達も独立戦争を戦ったではないか」といって反省を求め、トラファルガー広場を埋める群衆を前にしては、「一エーカーの他人の土地を荒らすことが罪ならば、百万エーカーの他国の領土を荒らすことはその罪が百万倍重い。一人の人間を殺すことが罪ならば百人の人を殺すことはその罪が百倍重い。私は哲学者としてでなく、ノーベル賞受賞者としてでなく、一人の人間として訴える。(核戦争によって)人類を滅してはならない……」といって演説した。
かつてラッセルは日本ではあまり重視されない時があった。それは難解なドイツ流の観念論を有難がり、イギリス風の常識や経験論をあまり重視しなかった日本思想界の伝統によるのかもしれない。つぎにかかげるラッセルの文章は社会科学や平和運動に献身し、神や宗教を否定してきた人のそれとしては非常に意味深い味のあることばである。
「人生において、本当に価値あるものは個人であって、決して戦場や政治上のことがらではない。社会の組織的な生活は必要であるけれども、それは「機構」として必要なのであって、決してそれ自体に価値があるわけではない。人生に於て最大の価値をもつものは、古代の偉大な宗教家が説いてきたことにむしろ近いものである。…」(Power、1938)
私がラッセルに感心したことの一つは、私のどのような手紙にも必ず返事を寄こしたということである。或る時は「全学連と共にやれ……」とか、中ソ論争では「……如何なるイデオロギーの勝利より人類生存の方が大切だ……」とか、「現代に於て核戦争に対する闘争よりさしせまった問題はない……」とか非常に過激だと思われるような時もあったが、ラッセルからみれば当然なことであったのかもしれない。
おそらく後世の史家達は、二十世紀初頭から後半にかけて、最大の哲学・思想家として、はたまた核戦争反対への果敢な闘士としてながく、その名を史上にとどめるであろう。