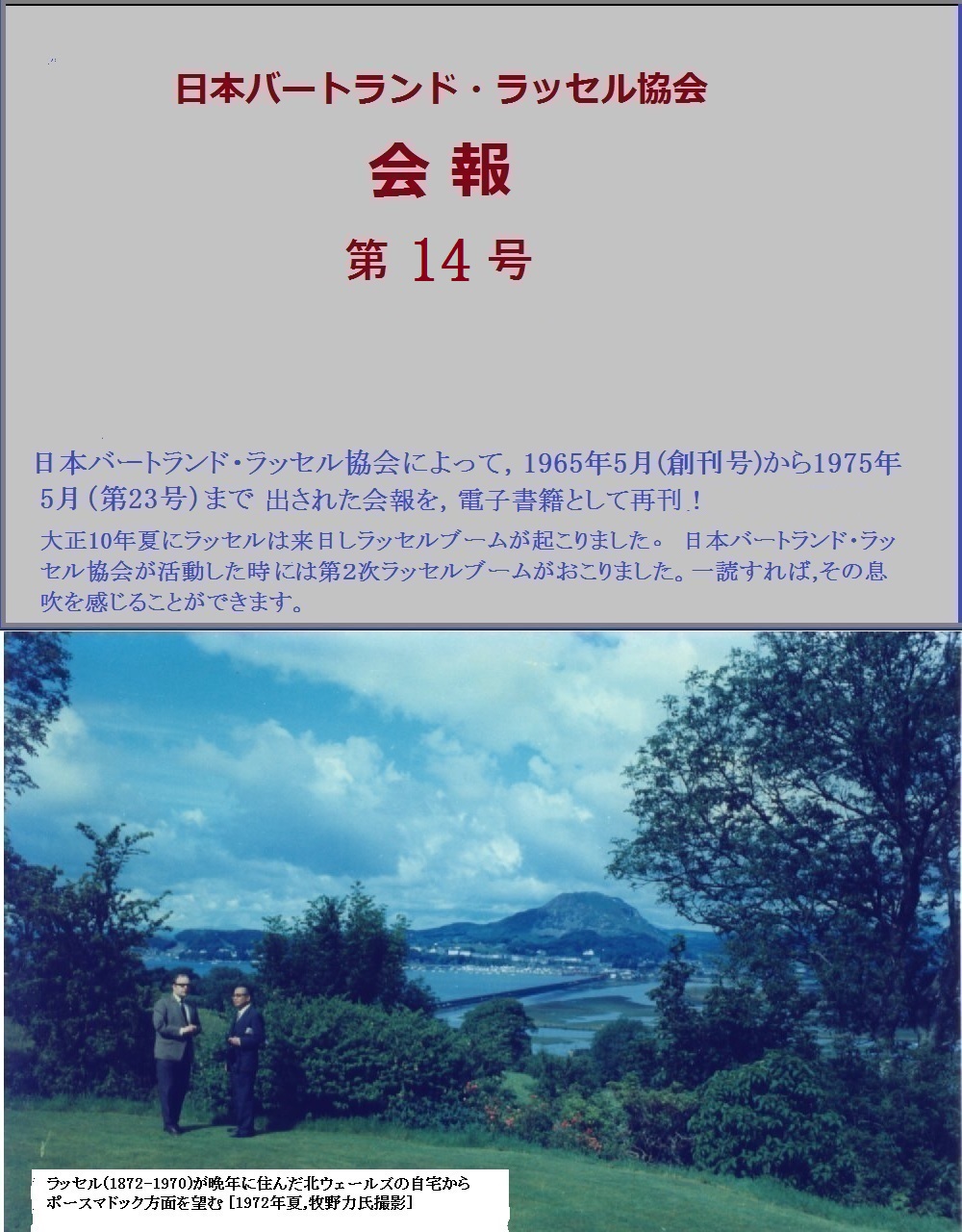
ラッセル協会会報_第14号
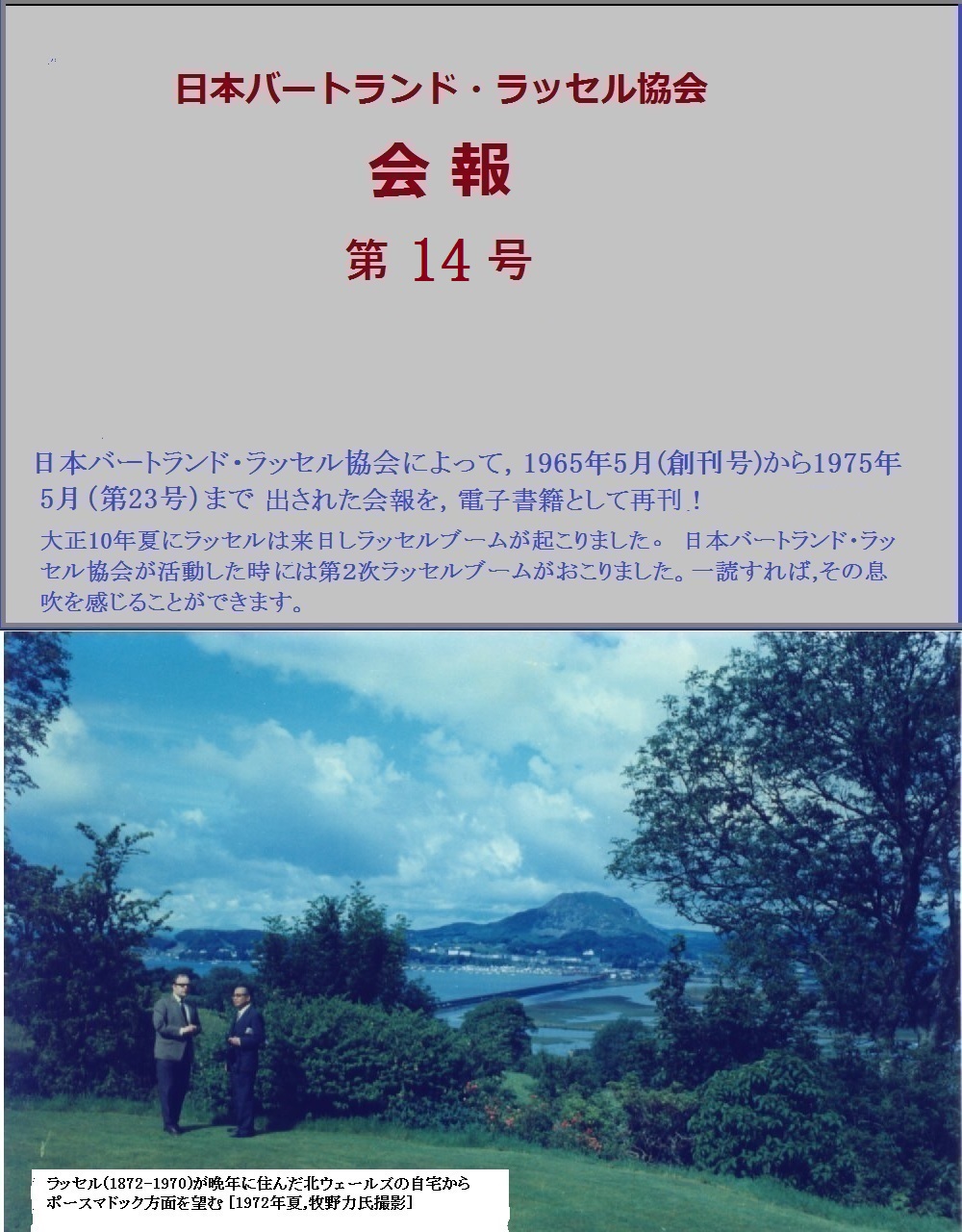 ラッセル協会会報_第14号 |
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
「金曜日の晩,ハーバードの教え子であったエリオットとその花嫁と一緒に食事をしました。エリオットがつかみどころのない男だから妻もすごいのかと思ったら,さほどでもありませんでした。彼女はきゃしゃで,いささか俗っぽいところがあり,アヴァンチュール型で,元気のよい女性で-彼は彼女が画家といったかと思いますが,女優のほうが適わしいと思いました。彼はこった男で,おちつかない様子でした。彼女は彼をふるいたたせるため結婚したけれども,なかなか思う通りには行かないと言っています。明らかに彼は刺激を受けるために彼女と結婚したのでしょう。わたしの考えでは,彼女はそのうち彼に倦くでしょう。彼女は潜水艦(松下注:ドイツのUボート)がこわいので,良人の親戚に会いにアメリカに行くことを拒んでいます。彼は彼女との結婚を恥じていて,彼女に親切にしてくれる者があれば誰にでも感謝しています。彼女はミス・サンヅ型です。(ミス・サンヅというのは,教養の高いニュー・イングランドの人で,画家でヘンリー・ジェームズやローガン・ペアサル・スミスの友人でした。)ラッセルは若いエリオット夫人の暗い将来を感じていたようでもある。(了)