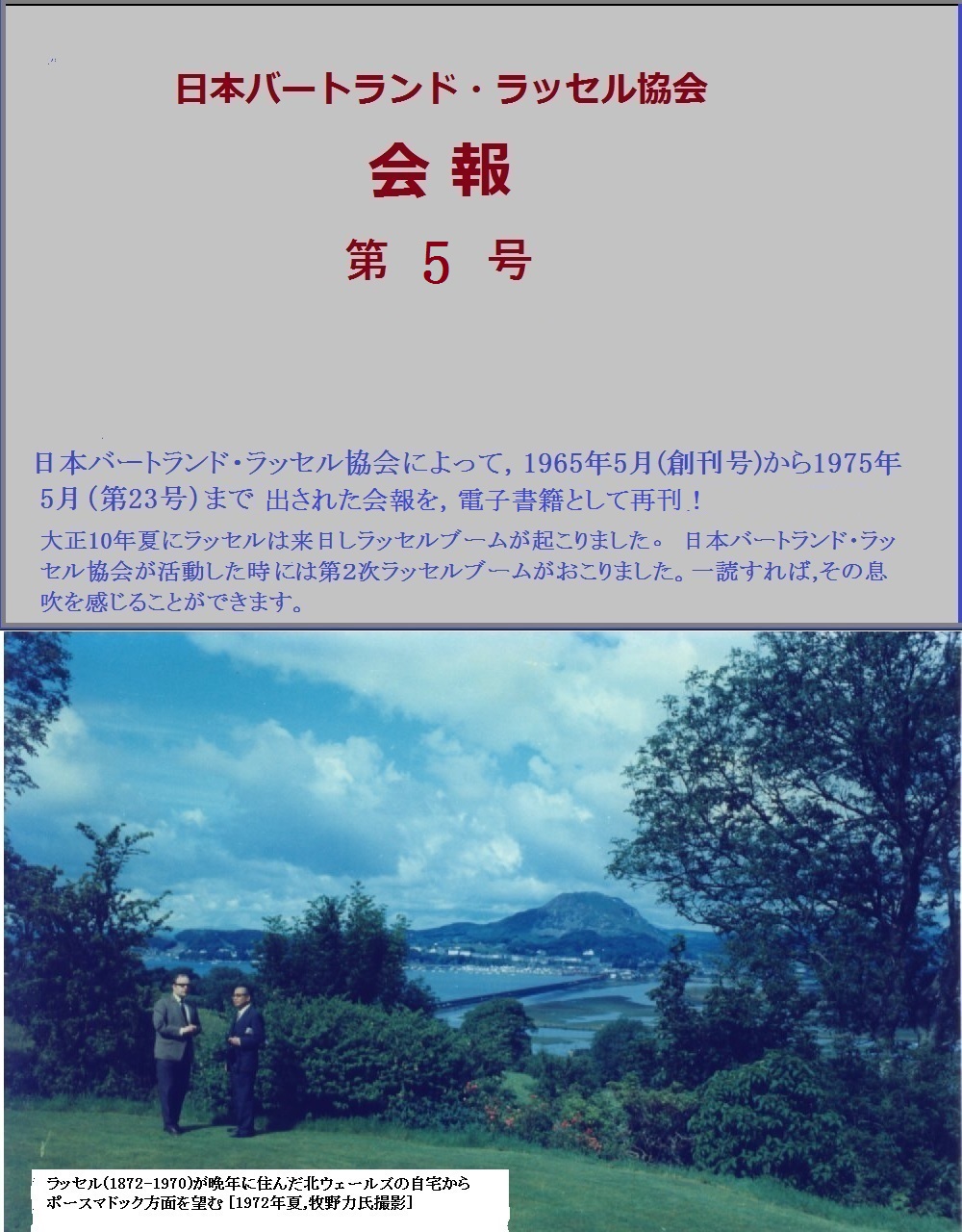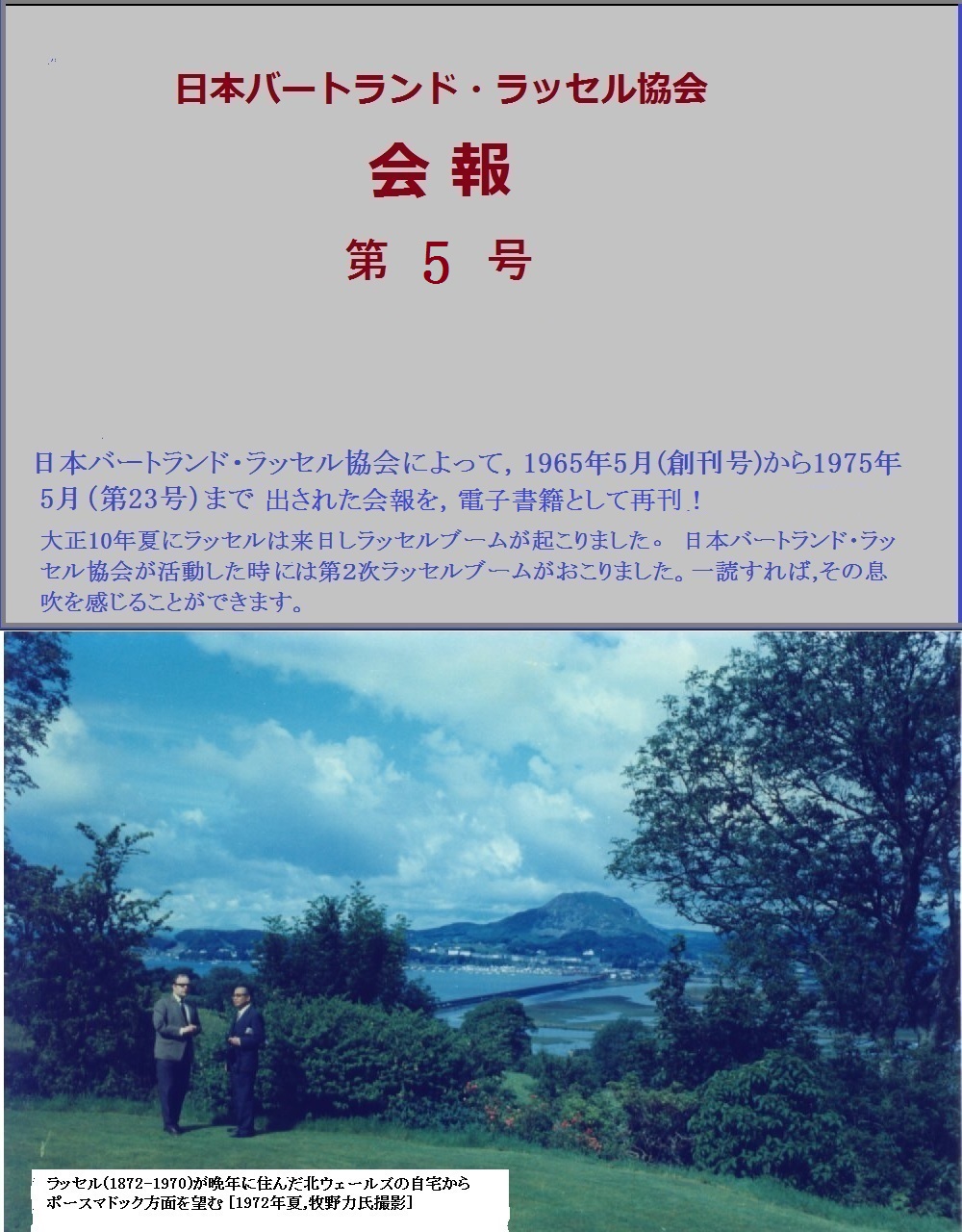永井成男「バートランド・ラッセルの無限論と論理主義の立場」
出典;『日本バートランド・ラッセル協会会報』第5号(1966年7月)pp.8-11.
* 本稿は,拙著『現代論理学の基礎』(昭和39年,有信堂)のpp.160-175,および「存在仮定のない論理学 -Principia Mathematica の体系から存在仮定を除く試み-」(科学哲学大会実行委負会編『科学哲学年報』第3巻,昭和38年)に発表した私の研究の一部を解説したものである。私の主張の厳密な論拠については同論文を参照されたい。(筆者は当時,東洋大学助教授)
* 永井成男氏(1921~2005):ウィキペディアの記事
数学基礎論の代表的な立場に論理主義,直観主義,形式主義の3つがあるがラッセルに代表される論理主義は大体次のような根本主張を指している。論理学は記号論理学として数学に属し,あらゆる数学に共通な基礎部門であるというにとどまらず,さらに論理学以外の他の全数学(応用数学を除く)は,結局は論理学に還元できるのであり,論理学のみから全数学を論理的に導出できるというのである。ホワイトヘッドとの共著『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』(1910-1913)全3巻は,この主張を厳密に論証した画期的な大作であるが,そこでは論理学からは導出できない3つの公理を新たに仮定しなければ数学を導出することができないという,ラッセルの論理主義の限界をも明らかにする結果となった。しかし後継者たちの努力によって,この欠陥は一応は除かれ,論理主義の立場は維持できるのであるがこの点については数学基礎論の専門家の問でも案外に知られていない。いや,表面的には知られていても十分には理解されていないというべきかも知れない。
『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』はその後の論理学と数学基礎論の出発点であり源泉であることが立場の対立を越えて一般に認められてはいるが,今日では数学の側からの論理学と数学基礎論の研究において,論理主義は形式主義や直観主義ほどには重視されていないのは否定できない事実である。この分野で世界の学界をリードしつつある米国においてはそれほどではないが,わが国では論理主義に対してほとんど無視に近い軽視が支配している。今日では論理主義は歴史的な価値しかなく,時代遅れであるというような偏見が専門家の間で常識化される傾向さえ見られる。論理主義が数学基礎論の現況においては主流になり難いということならば,それ相当の正当な理由が指摘できる。だが,論理主義が時代遅れの思想であるという一部の専門家の見方は偏見にすぎず,哲学と科学の正常な相補的関係を知らない哲学嫌いの頑固な一部の数学者の科学主義的謬見なのである。この偏見を打破し,論理主義の正しい理解と今後の発展に多少とも寄与しようとして本小論が書かれた。読者の御批評が得られれば幸いである。
ラッセルの無限論を取り上げたのは『数学原理』の論理主義の限界の一つである「無限公理」について具体的に議論を展開するのがこの目的に相応しいと思うからである。
論理主義によれば,科学は論理学と経験科学に二大別される。むろん数学は論理学に属する。論理学と経験科学の区別は真理の性質上の相違に基づく。科学の命題は,もしもその命題を構成している表現の意味を分析しただけで真であることが判明するようなものであれば分析命題(恒真命題)とよばれ,もしも意味を分析するだけでなく,さらに事実について経験的に確かめなければ真偽の判定ができないならば,総合命題(事実命題)とよばれる。論理学のすべての真な命題(公理や定理)は分析命題であり,経験科学の真な命題(記述命題や法則命題)は総合命題である。ラッセルは論理主義の思想から,数学の真な命題は分析命題であり,従って論理学のみから導出することができると予想したのであるが,「無限公理」という総合命題を仮定しなければ自然数の算数でさえ導出できないことを知った。無限公理は,「現実の世界には無限に多くの個体が存在する」という'経験的な主張'をふくんでいる。例えば,この世にはn個という有限個数の個体しか存在しないとする。nはいかに膨大な数であってもよい。すると,+1の操作によって n から n+1 の基数をつくったとすると,通常の算数では,むろん n+1 は n よりも一つだけ大きな有限の基数になり,n+1≠nであるが,このような算数の自明に思えるような知識も無限公理を仮定しなければ主張できない。それで初めに仮定したように現実の世界の個体の総数がn個であるとすればn+1=nという,つまりnに1を加えてもnより大きくならないという奇妙な算数を認めなければならなくなる。しかし奇妙ではあっても決して不合理ではなく全く合理的なのである。現実の世界の個体の総数は極めて膨大ではあるが有限なのであるか,それとも無限なのであるかは論理的にはわからないし,事柄としては本来実証的に判定すべきものではあるが,少くとも現行の経験科学では実際上判定できない。もしも将来,有限説が実証されたとしたならば,奇妙と思われても世界の個体の総数nに1を加えてもより大きくならない算数に改めなければならなくなる(松下注:たとえば,世界が1,000億の1,000億乗のそのまた1,000億乗の固体(それをn個とする)からなっていると仮定すると,それに1を足しても,世界の個数の総数以上にはなりえないので,n=n+1となってしまい,算数はそれを認めなければいけなくなってしまう。)。だが,現状では無限説を採っても科学に反しはしない。そこで(ラッセルは)無限説を公理として仮定することにより在来の数学の成果を維持する処置を選んだのである。すなわち,「nがいかなる数であっても,nが有限の基数であるならば,n≠n+1」と仮定する。ラッセルは「有限の基数」の代りに同義語の「帰納的基数」を用い,記号で "NCinduct" と書き,今言葉で述べたことを記号で次のように定式化する。
(n)(n∈NCinduct ⊃ n≠n+1)
これが無限公理の一つの表わし方である。将来無限説が実証的に否定され,世界の個体の総数がある有限基数(帰納的基数)のn個であることが実証されたとしたならば,n=n+1となるから,無限公理は偽となり棄てられ数学は修正される。すなわち数学は経験科学に依存し左右される。この結論は論理主義の本来の思想とは全く対立する。論理主義者ラッセルが論理主義の立場からは不都合な結論をも敢えて認める,この科学的態度ば偉大である。却って論理主義者でない普通の数学者や素人は容易にこの考えを受け入れないに違いない。たとい現実の世界の個体の総数が有限個であっても,数学としては+1の操作によってnよりも一つだけ大きい基数n+1を認めることができると確信するに違いない。例えば,デデキントはカントールと共に集合論の思想に達した大数学者であるが,「集合Sはそれ自身の真部分集合に相似ならば無限である」という命題を「無限」の定義として用い,「無限集合は存在する」という主張を数学上の定理として証明しようとした(デデキント『数について』岩波文庫,p.80-82)。もしもこの証明が正しいならば,例えば,0から出発して+1の操作によって0,1,2,3・・・・・・終りのない無限の数列が考えられるし,それらの数の無限集合も考えられる。しかも無限が数学的に存在するために何も現実の世界の個体の総数が無限であるという無限公理を要請する必要はない。だが,ラッセルはデデキントを始め同種の論法はすべて誤りであると批判し,数学的無限は無限公理を仮定していると頑強に主張し続ける。必ずしも現実の世界を論じているのでない数学では,現実の世界の個体の総数とは独立に数学的無限を考えることができるという常識は,結論を先に言えば,一面では健全である。しかし他面では非科学的な偏見であることを自覚しなければならない。わが国の代表的な独創的哲学で私自身も大きな影響を受けている西田哲学と田辺哲学では,デデキントの線に沿って,数学的無限は論理必然的なもので反省的思惟の本性に根拠があるとして哲学的に基礎づけようとしている。それは真理の一面を把えていると私は信ずるが,しかしラッセルの無限論の半面の真理を認めていない点で誤っていることを以下に明らかにする。
デデキント流の無限論は,数学の基礎部分である論理学に関しては自然言語(ドイツ語,日本語など)を用いているという点が重大である。しかるに,『数学原理』を初め数学基礎論においては,論理学の部分もまた数学と同様に記号言語という一種の人工言語を用いているという重要な相違がある。ラッセルの無限論は人工言語を用いる記号論理学の論理文法に従って展開される。数学基礎論では数学でも論理学でも,そこで用いられる人工言語の使用のための文法規則は,すべて論理文法の原則として人為的に規約される。数学で用いられる論法も,実はすべて意味論または構文論の立場をとる論理文法の規則に従う手続きなのである。例えば,公理や定理が分析命題であることを示す手続きは表現の意味用法を規約する意味論の規則に従って遂行される意味分析の手続きであり,定理の証明とよばれる推論は,若干の式から一つの式を導出することを許す変形の規則に従って公理から定理を導出する式の変形の過程で,構文論的手続きである。以下に示すが,通常の記号論理学(述語論理学)の論理文法に従って数学を展開する限りラッセルの無限論は正しいのであり,デデキント流の反省的思惟の無限論によってそれを論駁するのは不当である。
内部に部分として命題をふくまない最も単純な命題を原子命題というが,原子命題は主語として固有名(個体の名前)をとり,述語として個体の性質や個体間の関係を表わす記号から成る "Pa", "Rab" のような形の命題である。"Pa" は「個体aはPという性質をもつ」 "Rab" は「個体aはbに対してRという関係にある」という意味である。ところで,"a"や"b"などの固有名は現実に存在する(過去の存在もふくめて)個体の名前である。従って,記号論理学の論理文法では,固有名 "a" や "b"などの記号を導入する際には,それによって指示される個体が現実の世界に存在していることを仮定しなければならない。現実の世界の個体の存在を無視して勝手に固有名を導入してはならない。換言すれば,aとかbとかいう個体を現実世界の個体とは独立に論理的(ア・プリオリ)に創作してはならないのである。論理学の経験科学への依存は,実はここにはじまっている。ところで,例えば,「すべての個体xがPという性質をもつならば,Pという性質をもつ個体xが存在する」ことを意味する"(x)(Px)⊃(∋x)(Px)"というような命題が記号論理学の定理としてふくまれている。この命題は自明な分析命題であるとみなされて論理学がつくられたが,ラッセルを初め幾人かの論理学者は,後で,それらの命題は分析命題ではなく,「現実の世界には少くとも一つの個体が存在する」という経験的な主張をふくむ綜合命題であることを発見した。
もしも一個の固有名,例えば"a"を用いてよいとすれば,それらの命題は真となる。しかし,"a"を用いることは,それによって指示される個体が現実の世界に存在することを仮定することであるから,分析命題ではない。もう少し厳密に説明しよう。現実の世界における個体の存在に関しては,大別して次の3つの可能な場合がある。(1)個体が存在しない。(2)個体が有限個存在する。(3)個体が無限個存在する。これ以外の場合は考えられないし,現実の世界はそのいずれかの場合である。しかし論理的(ア・プリオリ)にはわれわれの世界はそのいずれであるかはわからない。分析命題は,論理的に可能なあらゆる場合のどの場合にも成り立つような命題である。例えば,明日の天気について雨が降る,雨が降らないという2つの場合を考えると,あらゆる可能な場合が尽されたことになる。そして,「明日は雨が降るか降らないかどちらかだ」と言えば,この予言は必ず適中する。明日の天気について可能なあらゆる場合に成り立つ分析命題だからである。だが明日の天気について事実的な情報は全く伝えない。占い師が将来起り得るあらゆる場合を想定して,どの場合にも成り立つような,予言をしておけば,百発百中となるが客の未来の出来事について実質的には何も語ってはいない分析命題である。そこで個体の存在に関わる命題が分析命題であるためには,個体が存在しない場合にも,有限個存在する場合にも,無限個存在する場合にもすべて成り立つような実質的に無内容な命題でなければならない。しかるに前述の"(x)(Px)⊃(∋x)(Px)"のような命題は,個体が有限個存在する場合と無限個存在する場合には成り立つが,個体が存在しない場合には,ここでは説明の余裕がないが,成り立たないのである。従って分析命題ではなく,「少くとも一つの個体が存在する」という事実的情報を伝える綜合命題なのである。そこでかような綜合命題をふくむ通常の記号論理学は,分析命題の理論としての論理学の理念に反し,論理主義は数学を記号論理学から導出する以前に,当の記号論理学のところで破綻したのである。この事情を理解していない一部の数学基礎論の専門家は,論理主義の破綻は記号論理学から数学に移るときに初めて起る -無限公理など綜合命題の3公理を仮定するので- と誤解している。この誤解に基づき,分析命題から成る記号論理学と綜合命題を仮定する数学との間に明確な境界線が引けるという誤った結論を引き出している(例えば,『岩波数学辞典』増訂版の論理主義の項目にはこの誤った結論が説かれている)。論理主義は時代遅れであるという数学者の偏見は,実はこの誤解に発している。
ところで論理学の論理主義的理念に反する記号論理学はどのように修正されたか。「現実の世界には少くとも一つの個体が存在する」という仮定を論理学に属さない綜合命題の公理として記号論理学(詳しくは一階述語論理学)に導入し,丁度,『数学原理』において無限公理を数学に導入したのと同じ手法が理論上は許される。だが,この方法は採用されなかった。その理由を説明しよう。「現実の世界に少くとも一つの個体が存在する」という命題は論理的には真でも偽でもないが,直接的に実証されるつまらぬ綜合命題であるから,現実の世界に個体が存在しないというような事態は,われわれの世界では現実には起り得ない。論理的には可能な事態ではあるが,そのような場合が論理的に不可能であるかのように扱ったとしても,科学には実害を生じない。数学では,厳密に論理的に可能なあらゆる場合を挙げ尽して理論を構成すると理論が複雑となるとき,実害のない限り,論理的には考えられる可能な場合であっても,実際には起り得ないとみなして,人為的に可能な場合から除いて理論を単純化する手法をよく用いる。例えば,確率論において,貨幣を投げた場合に起り得るすべての可能な場合を,表が出る,裏が出るの,2つの場合で全部尽されたかのように単純化する。厳密に論理的に考えれば多くの可能な場合がある。しかしこのように単純化しても実害はないので利用される。これと同じ手法を記号論理学は用いたのである。個体の存在に関しては,個体が存在しない場合も論理的に可能な場合であるが,その可能性を除いて,個体は有限個存在するか無限個存在するか,そのどちらかの場合で全部尽されたかのように単純化する。こうしても実害は生じない。単純化された論理的可能性の下では,「投げた貨幣は表が出るか裏が出るかそのどちらかである」という命題が,あらゆる可能な場合に成り立つ分析命題となるように,個体が存在しない場合を除いて単純化した論理的可能性の下では,"(x)(Px)⊃(∋x)(Px)"はあらゆる可能な場合に成り立つ分析命題となる。このように厳密に論理的可能性を考えないで実用上の考慮から実害のない人為的処置を採ることにより,記号論理学を論理主義的な論理学の理念に合致させることができたのである。同様の手法は,理論上は数学の場合にも適用できる。個体の存在に関する論理的可能性をさらに人為的に制限して唯一の可能な場合は個体が無限個存在する場合であるかのようにみなして単純化すれば,この論理的可能性の下では,無限公理を表現していた"(n)(n∈NCinduct ⊃ n≠n+1)"は分析命題となり,数学は論理主義の理念と合致するようになる。ではラッセルは何故にこの処置を採って論理主義を徹底的に維持しないのか。
この世の個体の総数がゼロである可能性を排しても実害はないが,有限である可能性を排することは実害を生ずる危険があるからである。相対性理論により,物理的空間の有限説が科学的に支持されている。個体の総数の有限説が科学的に支持されるようになる余地は大いにある。従って,個体の総数が有限である可能性を排する数学は非科学的な独断論となる。論理主義でありながら,科学を尊重するラッセルは論理主義の理念とは矛盾する無限公理の仮定という処置を選んだのである。論理学と数学とは個体の存在の問題に関して理論上は全く同一の立場にあることが示された。厳密に論理的に考えれば,現実の世界の個体の総数についての仮定をふくみ,論理学も数学も経験科学に依存する。人為的に論理的可能性を制限して理論を単純化すれば論理学も数学も経験科学から独立させることができる。論理学と数学の相違は理論的なものではなく,人為的な理論の単純化の処置が実害を伴うかどうかという実際的なもの,プラグマチックな相違にすぎない。
ところで論理学と数学が経験科学に依存するのは何故か。原子命題が固有名をとるような固有名言語を用いるからである。この論理文法に従って論理学と数学の理論を構成する限り,個体の存在仮定の難問を避けることができない。
しかしかような論理文法に従う固有名言語を用いなければ論理学と数学は構成できないのであろうか。ラッセルの論理主義の有力な後継者の一人であるカルナップは,原子命題の固有名の代りに位置の,名前(座標)を採る座標言語を用いて論理学と数学を構成すれば,個体の存在仮定の難問を避けることができ,記号論理学では,"(x)(Px)⊃(∋x)(Px)"なども人為的制限を加えない厳密な論理的可能性の下で,あらゆる可能な場合に成り立つ分析命題となるし,数学では無限公理も不要になることを示した。ラッセルの論理主義の破綻は救われ,論理主義は大きく前進した。だが残念ながら,カルナップの業績は一般に理解されず,その画期的な成果も正当に評価されていない。記号論理学と数学基礎論の定評あるシリーズの一冊として刊行されたフレンケルとバーヒレルの共著『集合論の基礎』(1958)では,この点に関するカルナップの業績を正当に評価すると共に,「この分野の大部分の著者たちは未だ十分に考慮に入れていないように思われる」と語り(p.167),数学基礎論の専門家の間に支配的なカルナップ無視の偏見を指摘している。わが国ではこの偏見は一層甚だしい。ところで,私自身はラッセルとカルナップの論理主義を学んだ上で,固有名言語とも座標言語とも区別される個体名言語の論理文法を規約し,カルナップの方法よりも自然な,自然言語の文法に従う通常の論理感を満足させる新しい方法を提案した。
原子命題の固有名や座標の代りに,論理的な個体名を用いる方法である。現実の個体の名として固有名 "a", "b"……を導入する通常の記号論理学の固有名言語に対し,カルナップの座標言語は,現実の個体とは独立に位置を論理的に考え,0の位置から出発して,次の位置を0'とし,0,0',0'',0'''・・・のように位置の無限系列を構成する。この構成は論理的に可能で,現実の個体の存在を考慮する必要はない。固有名言語では,現実の個体の存在を無視して論理的に個体aから出発して,a1,a2,a3…のように個体の無限系列を構成することはできない。個体の無限系列は無限公理を仮定してのみ構成し得る。しかるに私の個体名言語では,座標言語と同様に,現実の個体とは独立に,論理的に可能な思考の対象としてa1という個体から出発し,a1,a2,a3…のように論理的個体の無限系列を構成する。われわれの反省的思惟がこのような論理的個体の無限系列を構成し得ることを自証する。記号論理学の人工言語を用いない通常の数学は,実は,固有名言語を用いず個体名言語を用いているのである。デデキント流の無限論は固有名言語でなく個体名言語の論理文法の下で正当に成り立つ。ラッセルが固有名言語に執着する理由は,彼の思想が唯名論の存在論に傾斜していることに関係があるが,この点については後日改めて解説したいと思う。(了)