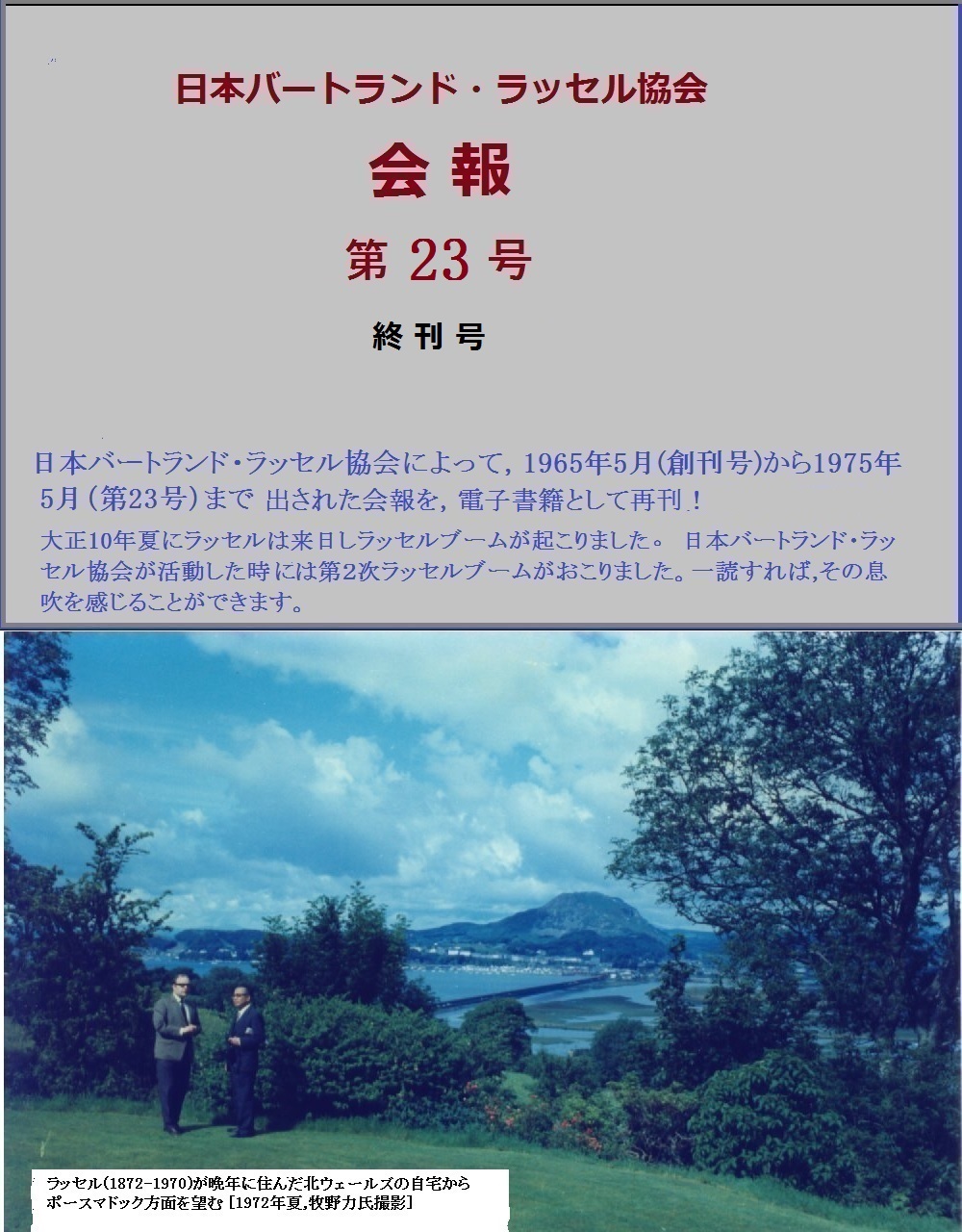金子光男「バートランド・ラッセル研究の姿勢と課題」
* 出典:『バートランド・ラッセル協会会報』第23号(1975年5月)pp.14-15.
* 金子光男は当時、東京家政大学教授
ラッセル逝いてすでに4年、巨星も時代とともに忘れ去られたかのごとく、あまり記事にも話題にも聞かれなくなったのであるが、さる10月末の朝日新聞に、久しぶりに彼のことが書かれていて救われた気がした。そこには、狂気の時代には、正気なことをいうものが狂気じみた人間にされるために、ラッセルも異端者とみられたのであるが、彼がさいごに遺したことばの、「人類が生き残ることはすべてに優先する、文明も繁栄も、自由主義も社会主義も、それは人類の生存が前提である。そして人類がこの地球に生き残りたいのならば、核兵器を全廃しなければならない」(という部分)こそ永遠に光を放つものであろうと記されていた。
不滅の光を放ってひとびとを導いていたラッセルの名があまり聞かれなくなったのは、人心日々にうとく、いかに偉大なる巨星であっても、ひとたび地に墜ちれば、もはや過去の歴史上の人物にすぎなくなってしまうものかという観をもつのは、私だけのひがみであろうか。東西古今の偉大な思想家の研究は、いつの時代になってもこれで終わったということはない。ましてラッセルのごとくあまりにも厖大な思想的領域をもっている哲人の研究は永遠に終わることはないであろう。たしかに彼についての研究は、その翻訳書をしらべただけでも相当の数にのぼっている(もちろんまだまだ翻訳されていない重要な著書も残っているが)。ましてや彼の思想を独自の立場でまとめたり、その行動をつぶさにしらべるということは容易なことではない。
 私も、全国にひろがっている無数のラッセル研究者のひとりとして、こつこつと牛歩のごとく彼の思想の足跡を辿ってみた。ラッセルという巨大なる思想の連峰は、いくつもの領域の峰を集めて峨々として聳えている。そのひとつの峰を登ることさえ至難の業である。すでに過去に、数名のクライマーがいくつかの峰に登ってその山容の思想の内容を紹介されている。私もそういった先達の案内書をてづるにして、苦節10年、なんとかザイルやピッケルを使いながら、「倫理」というひとつの思想の峰を登るという冒険を試みた。そして『ラッセル倫理思想研究』(酒井書店)としてガイドブックをまとめることができた。しかしこれはあくまでも私のたどたどしい足跡であって、自分で倫理の峰に登ったと思っていても、それは案外裾野のまわりをぐるぐる廻っていたのかもしれない。それほど彼の思想は厖大であるからである。
私も、全国にひろがっている無数のラッセル研究者のひとりとして、こつこつと牛歩のごとく彼の思想の足跡を辿ってみた。ラッセルという巨大なる思想の連峰は、いくつもの領域の峰を集めて峨々として聳えている。そのひとつの峰を登ることさえ至難の業である。すでに過去に、数名のクライマーがいくつかの峰に登ってその山容の思想の内容を紹介されている。私もそういった先達の案内書をてづるにして、苦節10年、なんとかザイルやピッケルを使いながら、「倫理」というひとつの思想の峰を登るという冒険を試みた。そして『ラッセル倫理思想研究』(酒井書店)としてガイドブックをまとめることができた。しかしこれはあくまでも私のたどたどしい足跡であって、自分で倫理の峰に登ったと思っていても、それは案外裾野のまわりをぐるぐる廻っていたのかもしれない。それほど彼の思想は厖大であるからである。
しかし私は、多くの研究者の方々が、それぞれの志向した峰に向かって登はんを敢行して、その峰々で呼びあい、またそれぞれの山容を紹介して、ラッセル思想そのものを全体的にまたいろいろの角度から検討していただきたいと思う。もちろん、いままでもかなりそのことはなされてきたのであるが、その仕事はまだまだこれからである。これはこれから何年も何年もかかって継続されていかなければならないことであろう。まだ山容の紹介されていない峰がいくつも存在しているのだから。少なくとも私ども研究者は、そういった「姿勢」をもたなければならないのではないだろうか。
次に、私は、ある外国の思想家の思想および行動を研究するということは、その人だけの思想と行動をしらべるということだけではなくて、それを通して、さいごには日本にとって、それがどのように対応し関係するかということと結びつかなければならない。つまりラッセルの思想は、どのような日本にとって「課題」をもっているかということが究明されなければならない。そうなってはじめてその思想の問題が、自分の問題となり、日本の問題となるからである。この問題は、まだまだ充分な研究がなされているとは思われない。しかも私は、いまの日本のかなり多くの思想的・文化的諸領域において、ラッセルの思想と行動のひとつひとつは、じつに日本のもっている課題と直結しているものが多いことを感ずるのである。いまの日本の社会は、あまりにも正常から離れた様相を呈している。だからこそ、このような時代には、彼のような異端の徒こそ必要なのではないだろうか。その点でも、彼は現代における人間の生き方について重要な課題を示唆しているということができるであろう。
これからは、ラッセルの資料の入手はますます困難となるであろう。しかし私は、だからこそ彼に対する研究が倍旧の努力を積み重ねて加えられてゆくことを切望し期待してやまない。われわれは、ラッセルをただ研究のために利用したというようなことであってはならない。ラッセルは、利用の対象ではなくて、学びの対象である。そしてそうすることによって、ラッセルはこれからもなお生きつづけることになるであろう。われわれは、改めて彼に対する研究の姿勢を問い直し、彼の残した日本への課題の追究に力を注ぐべきであろうと思う。