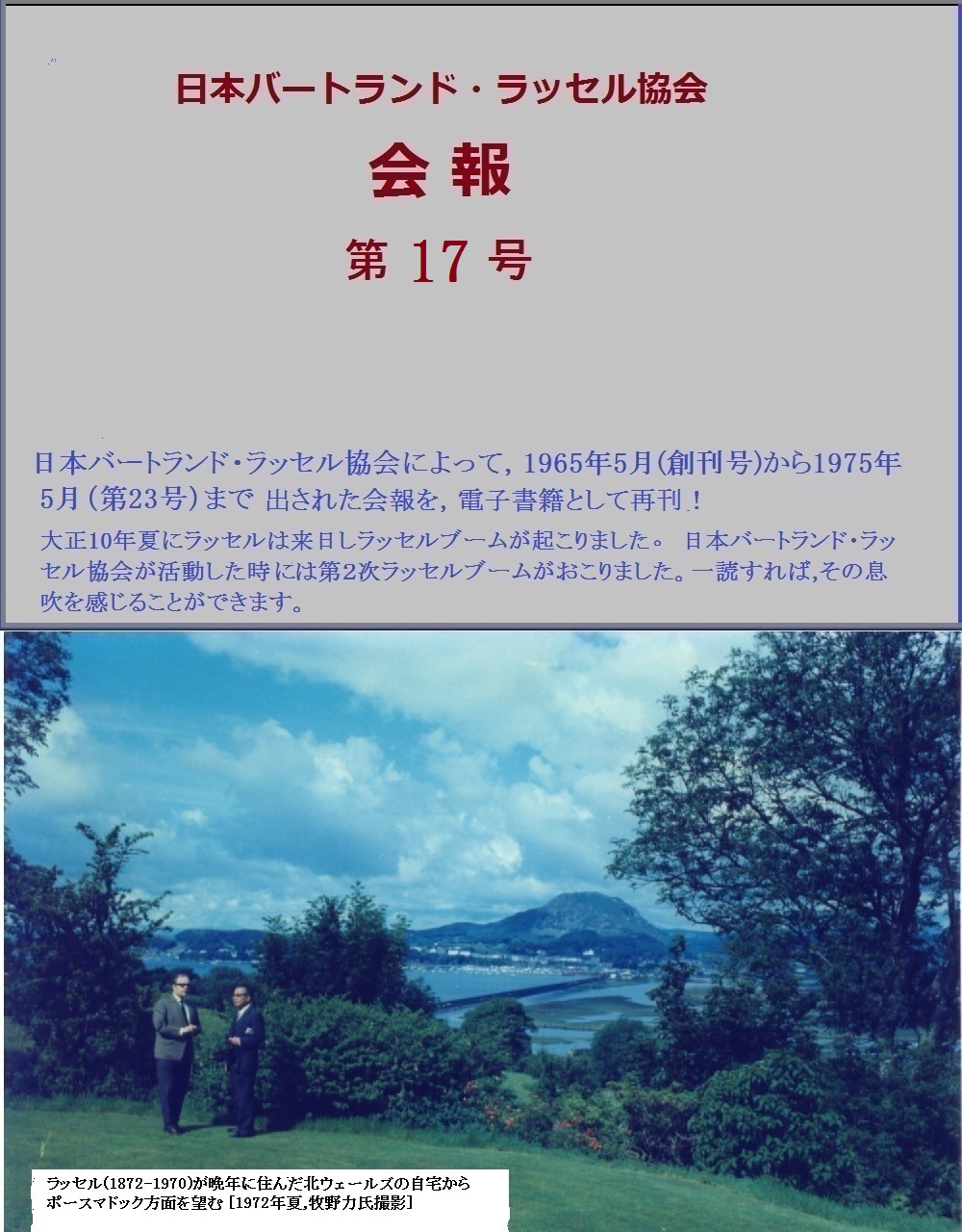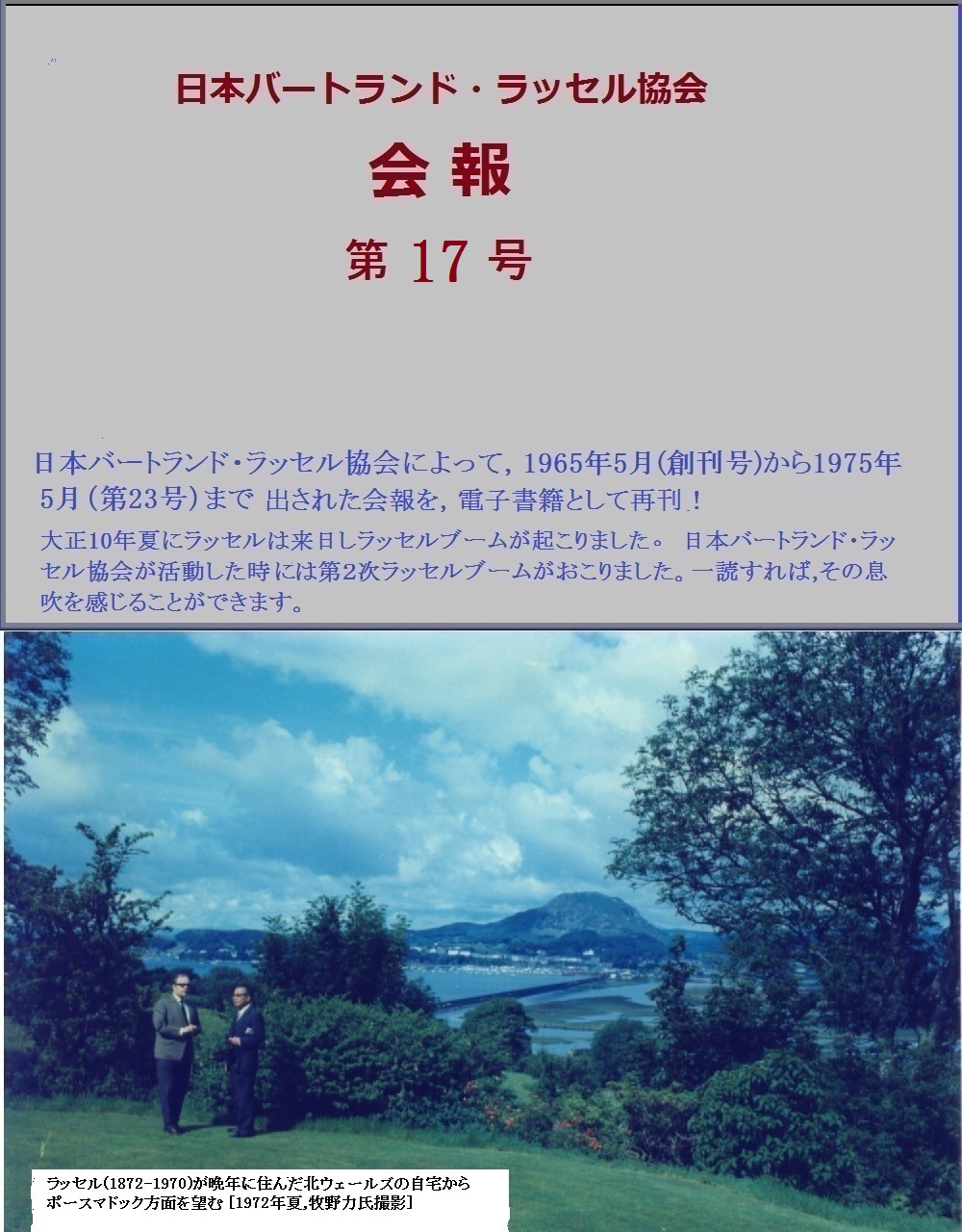(猪俣津南雄の遺稿から)「バートランド・ラッセルはロシア革命をどう見ているのか(藤田悟訳)
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第17号(1971年2月)pp.6-11.
* 猪俣津南雄(いのまた・つなお、1889-1942):マルクス経済学労農派の論客
* 藤田悟
[訳者(藤田悟)まえがき]
わたしの時代の矛盾を全面的に生きることをわたしは求めているのだ。その矛盾は皮肉から真実の条件を創りだすことができる。(ロラン・バルト)
1.猪俣津南雄について
ここに訳出した文章は、猪俣津南雄(一八八九~一九四二)がアメリカ合衆国に留学中、妻ベルタの親戚ないしは知人と思われる女性に出したと考えられる手紙の下書きの断片である。これの書かれた時期は内容からみて一九二〇年の後半、つまりラッセルのロシア訪問の報告がセンセイションをまき起こしていた頃と思われる。原文は英語で、1~6の見出番号は便宜のため訳者がつけた。
本文中にも言われているように当時の猪俣は真剣にボルシェビズムを「研究」していたようである。ソヴェト組織のシステムを相当詳細に研究していた形跡が当時のメモなどにもみられる。しかし「研究」ばかりでなく、在米日本人社会主義者団の中核となり、一九一九年に合衆国共産党が結成された際には、そのオリエンタル・ビューローに属し、実際的な活動でも活躍していたようである。当時の合衆国は亡命者のたまり場的な様相を呈していて、トロツキーは一九一七年一月から三月にかけてニューヨークに滞在しており、またブハーリン、コロンタイも活動しており、猪俣がかれらと接触していたことはほぼ確実である。ついでに言っておけば、ベルタという女性はユダヤ系ポーランド人で、ニューヨーク時代のトロツキーの秘書であったとの説もあり、また片山潜年譜(『わが回想』徳間67?の巻末)には「一九二一年三月、この頃、鈴木茂三郎が猪俣津南雄の紹介で社会主義者団に入る。同月下旬、ベルタ・猪俣を秘書としてメキシコに渡る。」とある。また「・・・マルクス経済学を学び、やがて一九年にはニューヨーク滞在の日本人社会主義者グループにレーニン『国家と革命』を講ずるほどになっていた。」(林健久)という。こうしたところからみると猪俣はすでに立派なボルシェビキだったのである。
猪俣の合衆国留学は一九一五年一〇月から一九二一年一〇月まで、まずウィスコンシン大学で主として農業経済学を学び、一九年には『農耕の最適集約度に関する典型的諸理論の分析』を提出、Ph.Dの学位をとっている。さらにシカゴ大学、コロンビア大学に学んでいる。当時の論文としては『社会主義思想の流れ』『ジョン・ステユアート・ミル』等があり、この意味ではボルシェビズムを「研究」していたといえよう。一九二一年、モスクワ経由でコミンテルンと連絡をとり帰国、早大講師としての職を得て農業経済学と経済学史を講ずる一方、翌年の日本共産党創立大会では議長をつとめるなど、活動家として思想家として理論家として、つまり稀有のトウタルな革命家として、日本マルクス主義の構築にとりかかるのである。後の著作には、『現代日本研究』('29)、『金の経済学』('32)、『農村問題入門』('37)などがある。
ここで猪俣の生涯をたどることはできないが、関心を持たれる方は、『日本のマルクス主義者』(風媒社・'69)所収の玉城素氏の論文、『日本のマルクス経済学・下』(青木書店・'68)所収の林健久氏の論文を参照されたい。また最近はじめられた猪俣津南雄研究会では不定期刊『猪俣津南雄研究』(連絡:東京経済大学・高島喜久男)を発行している。
2.ラッセルのロシア革命観と猪俣
ラッセルは、ロシア訪問後ボルシェビキに反対の立場をとったと一般に言われているようである。例えば 'Bertrand Russell's Best" の編者ロバート・E・エグナアは "Since his visit to Russia in 1920 he has been a consistent opponent of Communism in both theory and practice' と述べている。
ところが猪俣は必ずしもそうは考えていないようである。かれは『国家と革命』を講義していた程だから、ボルシェビズムに相当の信頼を寄せていたはずであり、ボルシェビキとしては、ラッセルの報告に反発していないのは不思議ともいえよう。しかし本文では猪俣はきわめて冷静に筆を進めているようである。
ラッセルはロシア訪問前、ボルシェビキにいくらか好意的だったのだろう。またボルシェビキもラッセルに好意的だったのだろう。しかしラッセルはボルシェビキ万歳を叫ばなかった。というのも、かれは知り得る限りの現実にまず忠実であることが、かれが望む科学的・理性的であることの第一歩であることを自覚していたのだ。ラッセルは以下の諸点で科学的、理性的たろうとしていたと言い得る。
(1)ロシアの現実がボルシェビキの公式発表ほどには好ましいものではないことを眼にし、それを敢えて公表したこと。
(2)しかしラッセルが好ましく思わない武装闘争、権力集中もロシアのおかれている条件のもとでは必要で不可避なものであると認めたこと。
(3)認めたとはいえ、それの孕む危険性について警告を発し、外国のプロレタリアートにボルシェビキ方式の安易な引き写しを戒めたこと。
ラッセルはこうしたことを、長い眼で見れば、ロシア革命のためにも世界のためにもなると考えて行ったのであろう。猪俣は政治的にはボルシェビキであり、ロシアのボルシェビキを支持する立場にあった。しかし猪俣は、現実に反したプロパガンダによってつくられたイリュージョンのうえに現実の革命を遂行できるとは考えなかった。ミスティフィケイションはかれの最も憎んだものだ。そしてかれはミスティフィケイションを許さぬ鋭い眼差を持っていた。そうした現実感覚に裏うちされた稠密周到な分析総合力が、猪俣をして、ラッセルを反共イデオローグ扱いする大方の見方と、ボルシェビキの「反共イデオローグ・ラッセル」に反対するプロパガンダの狭間に、真実に近づくことを可能にしたのである。半世紀を経た現在、ラッセルの警告が杞憂でなかったことは明らかである。当時の共産主義者はこの警告に充分に耳を傾け、充分な回答をすることができたであろうか。現在ではどうであろうか。ともあれ猪俣は、回答の心構えは持っていたようである。一九二〇年に、ラッセルは四八歳、猪俣は三一歳であった。
ラッセルはロシア革命をどう見ているのか
親愛なるジェニイ様、グレイシャ様
1
みなさんが具合よくやっていらっしゃるのを知っていつも嬉しく思っております。わたしがどうしてあなたがたに手紙を書かないのかとお尋ねのこと、ベルタからよくいわれます。わたしは、「書くよ、そのうちいつかね。」といっていたのですが、その「いつか」がやっとまいりました、そして今こうやって書いている次第です。
 ベルタは、あなたの手紙を読みはじめたとき、「ジェニイもラッセルのことを書いているわ!!」と大声をあげました。たまたま休暇でここに来ていた友人のギーガー君も「ウェー、どこでもみんな奴のことを話していやがる、けしからん」とぶつぶつ言っておりました。こちらでもみんながみなラッセルのことを話題にしておりましたので、それ以上聞きたくなかったのでしょう。というのもかれはそれは活動的な共産党員ですので、わたしが、本当にラッセルが議論したかったのは何なのかを話して聞かせようとしていましたが、ラッセルの文章の多くはやはりかれを傷つけていたのです。わたしはここへ来てからというものずっとボルシェビズムを「研究」してきました。つまりボルシェビズムとは何なのかを相当注意深く見てきたつもりです。そこでわたしは、ラッセルの文章は、資本家、ボルシェビキの双方の陣営から意識的かどうかはともかく見落されてきたいくつかの重要な点に触れていて、むしろ示唆的でさえあると思うのです。
ベルタは、あなたの手紙を読みはじめたとき、「ジェニイもラッセルのことを書いているわ!!」と大声をあげました。たまたま休暇でここに来ていた友人のギーガー君も「ウェー、どこでもみんな奴のことを話していやがる、けしからん」とぶつぶつ言っておりました。こちらでもみんながみなラッセルのことを話題にしておりましたので、それ以上聞きたくなかったのでしょう。というのもかれはそれは活動的な共産党員ですので、わたしが、本当にラッセルが議論したかったのは何なのかを話して聞かせようとしていましたが、ラッセルの文章の多くはやはりかれを傷つけていたのです。わたしはここへ来てからというものずっとボルシェビズムを「研究」してきました。つまりボルシェビズムとは何なのかを相当注意深く見てきたつもりです。そこでわたしは、ラッセルの文章は、資本家、ボルシェビキの双方の陣営から意識的かどうかはともかく見落されてきたいくつかの重要な点に触れていて、むしろ示唆的でさえあると思うのです。
ここがどんなところで、わたしたちの生活がどんな具合かはベルタがお伝えしているでしょうから、わたしはそれらには触れずに真直ぐにラッセルの話に入ろうと思います。この手紙はいくらか長くなるかも知れません。(右イラスト出典:B. Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953)
まずわたしの読んだラッセルのロシアについての記事ですが、『ネイション』七月三一日号と八月七日号にのったふたつです。あなたはお読みになっていないかも知れませんので、原文をお読みになりたいのでしたら入手してさしあげられます。かれはロンドンの『ネイション』にも書いているようですが、わたしの読んだのはニューヨークの『ネイション』だけです。
ラッセルの記事は、資本家の手先と報道機関によって大変歪められています。ロイド・ジョージは下院で演説したとき大騒ぎをおこしました。ニューヨークの大新聞のひとつ『ザ・ワールド』はかれの記事の一部を再録して一ペイジ全面をそれにあてました。かれらの手口は御存知のとおりです。見出しは、「レーニン=トロッキー恐怖支配下のロシア・言論報道の自由の完全な弾圧・英国のラディカルの指導者、反ボルシェビキになる」-こういう調子なのです。これは非常に巧妙な歪曲で、よほど注意深く読まなければ、ラッセルが本当にそう言いたかったかのような印象を受げることでしょう。わたしは、しかし、ラッセルが言いたかったのはそういうことではないと思います。『ソヴェト・ロシア』のハートマンがラッセルについて記事を書いています(八月一四日号)。これを読んで、わたしは、ハートマンの反対しているのはラッセルではなくて、実は資本家の報道機関によって説明(歪曲)されたラッセルに反対している、つまり資本家のプロパガンダに反対しているのだと思いました。
ハートマンの記事は、それをプロパガンダに対するものとしてみるなら、立派なものです。しかし、これはラッセルの主張に対しての批判としては問題になりません。
その他にもラッセルの記事について書いたボルシェビキがいますが、その評者は論点をひとつひとつ批判することをせずにただラッセルをプチ・ブルジョアと断じて、ロシアの革命はラッセルのような人間の理解を越えたことなのだと言っております。あなたのお手紙で触れられた批評家も、ラッセルはロシアにたったの一ケ月しかいなかったとか、反ボルシェビキとばかり会見したのだとか言って同様のことをしているようです。あとの方はもちろん嘘で、ラッセルはボルシェビキの指導者とも十分話合っています。ロシア滞在一ケ月というのは本当です。ラッセルがなにか誤った印象を得た可能性はないとはいえません。でもかれの言うことが、ロシアに六ケ月いた人の言うことと喰い違うからといって、一般にかれの言うことが真実でないと言い切ることはできません。観察は頭の問題なのですから。またボルシェビキの同情者が、公にされたばあいボルシェビキのプロパガンダと鋭く対立することになるようなロシアの状態を敢えて口にはすまい、とわたしは確信します。たとえばアーサー・ラムスンはそうした効果について述懐しているでしょう。そしてまた、もしラッセルの言うことがボルシェビキを持ち上げることばかりだったら、ボルシェビキに押しつけられたのだとしか考えられませんし、かれの文章の真実性も問題にならなかったことでしょう。わたしは、ラッセルがロシアで好ましい印象を受けることを心から望んでいました。そしてラッセルはすぐれた観察眼の持ち主であると考えていました。残念ながらかれの受けた印象はわたしが期待していたほどには好ましいものではありませんでした。しかし、わたしはそのためにすぐラッセルの観察眼はあやしく、かれの言ったことは嘘にちがいない、などと言うつもりはありません。かれがわたしたちに伝えることは、ロシア人とその指導者たちを天使としてではなく、生の人間として考えるなら、それはロシア革命と関連してきわめてありそうなことです。わたしは、ロシアの状態についてかれが言っていることのほとんどを信用し、かれの受けた印象も正当なものだと考える用意があります。まず最初に、ラッセルが革命の方法としてのボルシェビズムを扱う際にどういう立場に立っているかをはっきりさせましょう。たしかに、かれはプチ・ブルジョアであるかも知れません。共産主義者でもなく、社会主義者でさえないかも知れません。でもこういうことが起ったらどうでしょう-中国人がキリスト教の宣教師のところへやって来て、キリスト教徒はあれこれのことをやったと聞いたが、と言ったとする。宣教師は機嫌を悪くしてせっかちに問う、「誰がお前にそんなことを言ったのだ。」中国人は誰それですと答える。宣教師は勝ち誇ったように言う、「お前、奴を何者だと思うね、ユダヤ人だよ。」
ラッセルはたしかに、ボルシェビキの支配について「いじわるい」と見えることをいろいろ言っています。例をあげると-
「ボルシェビキは国内的には官僚主義的であり、国際的には好戦的である。」
「共産党員は社会の他の成員より幸福で快適な生活を送っている。」
「もし自由選挙が行なわれているなら、都市部においても地方においても共産党員が多数を得るような選挙単位はほとんど考えられない。」
「すべての権力は共産党の手中にあって、総人口一億二千万のうち約六〇万の手中にある。」
「モスコーとペトログラードは、国家の民間及び軍のすべての力を、それらの必要に供して生きのびている。」
「言論報道の自由は全面的、完全に抑圧されており、(ソヴェトに反対する)効果的異議申し立てはまったく不可能である。」
この六つの短文は『ザ・ワールド』が抜き出して眼につきやすいところに別にして印刷されてあります。これと前にわたしが引用した見出しが全体のイメイジをつくりあげているのです。もちろん、このように、かれがこれらの点について述べたことと切りはなしてのせるのは大間違いです。たとえばかれが、こういうことが起っているが、それは革命をやりぬくにはどうしても必要だ、といっているとしたらどうでしょう。そして、事実かれはそうしているのです。例えば、共産党員の「より幸福で快適な生活]についてはこういっているのです。
「しかし、こうしたことがらも、結局は、政府の要員の健康や重要性を考えに入れれば必要なことで、正当化し得るものである。かれらは、たしかに西方勢力の政府のばあいよりもずっと長い時間、しかもずっと強大な圧力の下で働いているのである。」
ラッセルの文章を読むばあい注意しなければならないことのひとつは、かれがこれら「いじわるい」ことを書いたのは、ボルシェビキを非難するためではなく、何かほかの目的で議論しているのだ、ということです。かれはこうしたことをロシアで目にすることを好みません。それはボルシェビキとて同じことです。ボルシェビキは、ほかのどの人間がやっただろうよりも、ロシア内のボルシェビキ以外のどのグループがやっただろうよりも、よく全力を尽して、与えられた状況の下で努力した、しかしこうしたことは、起るべくして起った、とラッセルは考えます。この点をはっきりとさせなければなりません。
というのもこのラッセルの立場が、かれをブルジョア資本家とその弁護論者から、つまりボルシェビキのやったことは間違っていて、ボルシェビキの政府はくわせものだ等々と言っている連中と区別するものだからです。ラッセルの立場は、また、いわゆるリベラルな人々-かれらのある者は市民的自由と国民投票による政府はいかなる状況の下でも必要である、なぜならそれらは善なるが故に善なるものだから、という議論をしている-とも違います。ラッセルはこうした議論がブルジョア・デモクラシーのみせかけの雰囲気にまどわされたものであることをよく知っています。
ラッセルの記事をあわてて読むなら、わたしがこれまでお話してきた違いを見落す可能性は大いにあります。かれを評した多くの論者のように。わたしは、評者の側ばかり責められるべきだとは考えていません。ラッセルの記事は、かれの立場をはっきりわからせようとしていません。ロシアの多くの事実を報告し、それについてのかれの評価を加えながら書きすすめるという、「ところで、ついでですが」という書きっぶりですから、かれ自身の立場についての記述はあちこちに散らばっています。ですから、読者はそれらを注意深く集めつなぎ合わせなければならず、殊に一見洞察をあまり伴ってないようにみえるそっけない観察には、注意をはらわなければなりません。それは気楽な読者にとってはきわめて困難なことです。もうひとつの誤解の原因は、かれがあまりに多くのことを一度に言おうとしたことにもあります。事実、外国の革命家たちは何をなすべきか、資本主義政府はどうすべきか-。しかし、かれの本当の立場を理解することのもっとも大きな困難は、対象の性格、つまり革命ロシアそのものの性格からきます。親ボルシェビキの心理状態も反ボルシェビキのそれもきわめて張りつめたものになっていて、自分の立場を誤解されずにロシアについて何かを言うことは、ほとんど人間の能力の限界を越えることなのです(かれがまったくの部外者でない限り)。
ここまで、わたしはラッセルの立場がどういうものでないかを述べてきました。これからは、できるだけ上手に、かれの立場がどういうものであるかを述べてみたいと思います。そのなかでわたしは何度かかれの言うことから離れなければならないかも知れません。かれがロシアヘ行く前にいったことを引き合いに出すかも知れません。かれはロシアヘ行って考えを全面的に変えてしまったかも知れないから、それはなんの役にも立たない、という議論をすることはできます。わたしとしては、考えを変えたかも知れないし、そうでないかも知れない、というほかありません。しかしここでかれの思想を全体として扱うにあたっては、かれの新しい文章と直接的に矛盾しないものはまだ有効であると考えたいと思います。
ジョンはヘレンを愛していて大学を出たら結婚すると言っていたとしましょう。しばらくして、かれは学校を終えてカリフォルニアですてきな娘に出逢ったと伝え聞きます。ヘレンはシカゴにいます。かれは考えを変えたかも知れないけれども、でもわたしは、かれのヘレンへの愛情と直接矛盾することを耳にするか、かれがさらに何か言ったことを聞くまで、依然としてジョンはヘレンを愛していると考えるのはむしろ当然でしょう。・・・。
2
お手紙で、ラッセルは大変な反ボルシェビキだといわれているとおっしゃっていますが、本当にそうでしょうか。わたしの答えは「然り、そして否、見方によります。」
ラッセルがロシアに住んでいたとしたら、かれはボルシェビキに反対したでしょうか? いいえ、もちろんそうではありません。反対にかれ自身、ボルシェビキ政府を支持し、そのために働いただろうと言っております。その第一の理由は、現在のレーニン・トロツキー政府が、ロシアの現在発展しつつある産業と向上しつつある経済状態一般の要求に最も適したものである、ということです。そして、政府の独裁的な面については、政治的戦争によって生み出された経済的混乱と反革命の圧力、また経済状態がいまだ遅れていて、人民が恐ろしく搾取されてきた状態が必要としたのだ、と言っています。
ラッセルは、イギリスの反ボルシェビキたちがそうであるように、干渉を弁護したでしょうか。これは問題外です。かれは、この干渉はこれまでもずっと愚かしく犯罪的であったし、もし続くなら、資本家側にも、また理のある共産主義の側にも悲惨をもたらすことになろう、と言っています。ボルシェビキ政府は不安定なもので、外国の資本家たちの好みに合うような政府をロシアにつくるのは容易なことだ、などと考えるのは大変な間違いです。干渉によってロシア政府に起こし得る変化は、共産主義政府内の変化にすぎません。共産主義者は権力の座にとどまり、外部からの軍事力に対しては、執拗な軍事力をさらに強力に行使するでしょう。ロシアのボルシェビキにはふたつの道しかありません-降服か、勝利か。ボルシェビキは勝利への道を選ぶでしょう。ボルシェビキは干渉国側を打ち破るに十分な力量を具えており、そしてヨーロッパの大陸部の資本主義は倒壊するでしょう。だがそうした軍事的勝利からは共産主義は生まれない。・・・。
3
かれは他のイギリス人のように干渉を好ましく思っているでしょうか。いいえ、はっきりと反対しています。ではかれは、ロシアの革命はロシアのことでひとりロシアにだけやらせておけばよいと考えている中立派のひとりでしかないのでしょうか。そうでもありません。かれはロシアに革命を、それも最少の犠牲でやりとげてほしいと願い、一日もはやく自由で幸福なロシアを実際に目にしたいと願っています。そのためかれは、世界のプロレタリアートがボルシェビキと協力することを望んでいます。もしそうだとすれば、かれが反ボルシェビキだなどと言うのは、実に変なことです。ところがかれの記事を読んだ者は誰れもかれもかれが本当に反ボルシェビキだと思ったのです。
ラッセルがボルシェビキと意見の合わない問題は、ロシア外のプロレタリアートがどういう風にロシアの同志を助けまた自らどう闘うべきか、ということです。ボルシェビキは、ロシア外のプロレタリアートが自分自身を解放しロシアの同志を解放するには、武力によって現存の資本家政府を打倒する以外に道はないと主張します。かれらの準備のガイドラインとなる原則は、自らを効果的に武装すること、そしてかれらの武力が資本家政府の軍事力を打ち破りブルジョア支配者から奪った権力を維持できるほど強力と考えられるものになったら、ただちにことを起すことです。
ボルシェビキは、革命が単に資本家政府を打倒することに限られないことをよく知っています。革命とは、もっと大きなもの、つまり共産主義の自由で幸福な社会、友愛と個人の人格的発展と社会的富の増大との全面的な可能性の開かれる社会を築くことです。ボルシェビキは、しかしながら、こういう新しい社会の建設は、武装した労働者による資本家政府の打倒後、ソヴェト組織あるいはプロレタリアートの独裁の時期を経ることによってのみなされ得ると考えます。これをボルシェビキ方式と呼びましょう。ボルシェビキは他の国々のプロレタリアートもこの方式をとることを主張し、ラッセルはそうは考えません。
4
つづめていってしまえば、権力の集中はボルシェビキ革命には必要だったのです。それは共産主義とは反対の社会に属するとみなされているものとはいえ、またボルシェビキは戦争という方法を好まなかったとはいえ、ボルシェビキは共産主義社会をつくるにはそれ以外に道はないと考えていたから、それに固執したのです。この方法は悪い。だが目的は良い。だからその方法をとることは正しいことだ。こうかれらは考えたのです。しかしラッセルは、この方法は目的そのものをあやまらせる危険が非常に大きい、と考えます。ラッセルは現在のボルシェビキの指導者がその権力を乱用するとは考えていませんが、他の国の共産主義者の指導者や後継者が、現在のロシアの指導者ほどに有能で良質であるといえる保証は何もない、と疑問と不安を提出しています。
戦争に勝利をおさめるには権力の集中が必要です。ラッセルはロシアで、人口一億二〇〇〇万のうち六〇万の共産党員、とくにそのうちの指導者が、すべての権力の所有者で、みなが政治の領域ばかりでなく経済生活においても厖大な権力を手中におさめようとしているのを見ました。経済の領域では、産業の労働者管理はもはやなく、また政治面では労働者と農民の投票は共産党員をソヴェト内の多数者にするよううまくあやつられている。さらに最高の権力機関とされる全ロシア・ソヴェトはめったに会議をひらかなくなり、ますます形式的になっていて、そのただひとつの機能は、政府内の共産党指導者たちによってあらかじめ決定されたことに議論なしで賛成することになってしまっている。
こういういろいろなかたちでの権力の集中を、ラッセルはロシアでは不可避で必要であると考えます。そして、他の国でもボルシェビキ方式をとるなら同様になるだろうと考えます。そうした革命の時期は、戦争状態となるわけですが、熱狂の渦中にいて革命家たちが考えるよりも往々にして長期にわたる可能性があります。そして「すべての経験の教える如く、大いなる権力の保持者はめったに信用すべからず」なのです。ほとんど誰でも権力を愛するもので、大きな権力を行使するのになれてしまったら、そのすばらしさに酔ってしまってめったに手離そうとはしないものです。たとえ誠実で人民の利益のみを考えている人々であっても、権力の甘い誘いは恐しいもので、自分たちの権力がもはや公衆にとって必要でなくなっても、まだ必要だと考えるだろうことは想像に難くありません。いずれにしても一度権力をその手に握ってしまった者は、強制されない限りは進んで権力を手離すことはないでしょう。
富の公正な分配と同様に権力の公正な分配はきわめて重要です。それなしには、自由と自由意志による協力とは考えられません。さらに相当期間政治的権力が少数の手に委ねられることになれば、権力を握った者は自らの経済的利益のためにそれを行使しがちなもので、ここでもまた富の不公正な分配ということになります。
5
・・・。ボルシェビキ方式をとれば、人々は何年にもわたる内乱の世に生きなければなりません。絶えず警戒心を鋭くして見はりに立っていなければ革命は奪いとられてしまうかも知れません。隣人をいつも疑っていないと反革命の仲間がいるかも知れません。もし誰かが反革命に加担する隣人の犯罪をみつけたりしたら、かれはその隣人を憎悪し罵り、こうした感情は飢と義務労働によっていやがうえにも強化されるでしょう。またその隣人はかれを憎悪し罵るでしょう。疑い-疑われる、憎悪し-憎悪される、罵り-罵られる、こうした状態が長いあいだ続いたらどういうことになるでしょう。このようにとラッセルは考えます。
このようなばあい、役人の手で、自由な友愛の世界を創造することは、どれほど困難なことになるでしょうか。このようなわけで、ラッセルは理想社会がボルシェビキ方式、あるいは戦争という方法で創り出され得るかどうか疑問をいだいています。もうひとつの理由がありまして、そちらの方がわたしには強いように思われますので、しばらくかれの議論に耳を傾けましょう。
6
…ラッセルはこのように考えますから、ボルシェビキの考えるように、ボルシェビキ方式以外ではそういう社会をつくり出すことは決してできない、とは考えません。そして他の国々のプロレタリアートがより少い弊害しか伴わない別の方法、つまりより少い流血と辛苦と権力集中しか伴わない方法をとることを望みます。そしてまたかれは、少くともイギリスでは、プロレタリアートがボルシェビキ方式を採用しないなら、これら弊害を伴わずにそういう社会をつくり出すことができると思っています。
それでは、ロシアで起っているすばらしいことを見て来て、どうしてかれがこう考えるようになったのでしょうか。それは、ロシアでの見聞の結果、かれは、ボルシェビキ方式を唯一とするかれらの議論がそれによる革命後の状況によって証明されてはいないと考えるにいたったからです。
ラッセルはこれらの弊害が、資本家の手先やプレスがいっているように、ボルシェビキの残酷さと自己本位、そして無能によるものではないと確信しています。その逆に、それらは資本家たちの残酷さと自己本位、そして無能によるものであり、資本家の戦争によるものであり、資本家のサボタージュ、介入、そして封鎖によるものであり、さらにまたボルシェビキがいうところの「ブルジョアジーの追従者」、つまり多くの労働者や農民の無関心によるものだとさえ考えているでしょう。ラッセルは、しかし資本家たちに、より愚かでなく、下劣でなく、流血を好まなくなるよう期待することはナンセンスだと、そして厖大な労働者たちにもっと社会主義の理想に忠実に、意識的になれといったところでしようがないと思っているでしょう。
ということは現在の状態では、どの国ででも、少数の意識的なプロレタリアートあるいは共産主義者が、かれらの武力が資本家の政府を打倒し、政治権力を維持して新しい社会を建設するのに十分なものだと考えて、その理由だけで革命を試みようものなら、(ロシアと)同様の流血と辛苦と少数者の手への権力の集中が起らざるを得ない、ということです。
また、他の国はロシアほど経済的に自給できませんから、他の国における辛苦が軽いものになるという可能性はほとんどありません。そして恐しい辛苦が革命に続くなら、なんらかの処置がとられねばならず、そこにロシアの共産党のリーダーたちほどに有能で、誠実で、すぐれた革命家たちが得られるかどうか、まったく疑わしいかぎりなのてす。革命戦争の只中で建設の仕事がなされねばならないとするなら権力は少数者の手へ集中されねばならず……。
★故猪俣氏(未発表)書翰掲載の弁
ラッセルが革命直後のソ連邦を視察した結果生れた『ボルシェヴィズムの理論と実際』(一九二〇年)への書評は、出版された当初、必ずしも良くなかった。一部の人々の間では、その悪評は誤解であるとも言われた。ところが、その一部の人々が共産主義者の外側に在る人々であると説得力に限界が生れよう。
その後、『権力』(一九三八)が出た。これとの連関で読むと、判りのよい点も多く出ているし、ラッセルの真意もうなづける公算が多い。
ラッセルはソ連に悪口を言っていると評するのは、自叙伝第二巻を読むと、早合点のような気がする。というのは、中国に招かれて乗船した船中で、英米仏人の船客から、ソ連視察談を要請されて、革命後のソ連について、講演した。
その時の心境として、次のことをラッセルは記している。(要旨)
聴衆は社会主義とか共産主義とかの真意を知らない連中なのだから、ソ連は希望のつながるよい国だという視点でよい面だけあげて話した。ところが、後でわかったが、聴衆の一人が上海の英総領事に宛て、ラッセルは「赤」だから、上陸させるなと、おせっかいな電報を打った。その男はサイゴンの動物園で、象にバナナを買って与えるのを断わり、一張羅の美服に、象に汚物を吹きつけられた。云々。
どうも、ラッセルの上記の問題の著書は、後で出た権力論で語られている「権力」衝動と権力の魔性について深く洞察していたからで、地上の一角に現われた貴重な社会主義国の幹部に"忠告"したのではないかという気がする。
ところが、今回、大山郁夫、鈴木茂三郎などと共に米国で社会主義の研究をした一人、日本共産党初代議長であった故猪俣津南雄氏の遺稿を整理中発見された同氏の私信のあることを教えられた。それを読むと、ラッセルの同著述を、唯悪評するのではなく、権力論に語られたような考え方がうかがえるような気がした。これは知名の実践家たるボルシェヴィクからの発言故に、注意を払う意味で、ここに全訳を掲載する次第であります。
尚、念の為、同原文が事実、故猪俣津南雄氏の自筆であることはその自宅の筆蹟によって確認されたことを、申添えます。(編集部M)