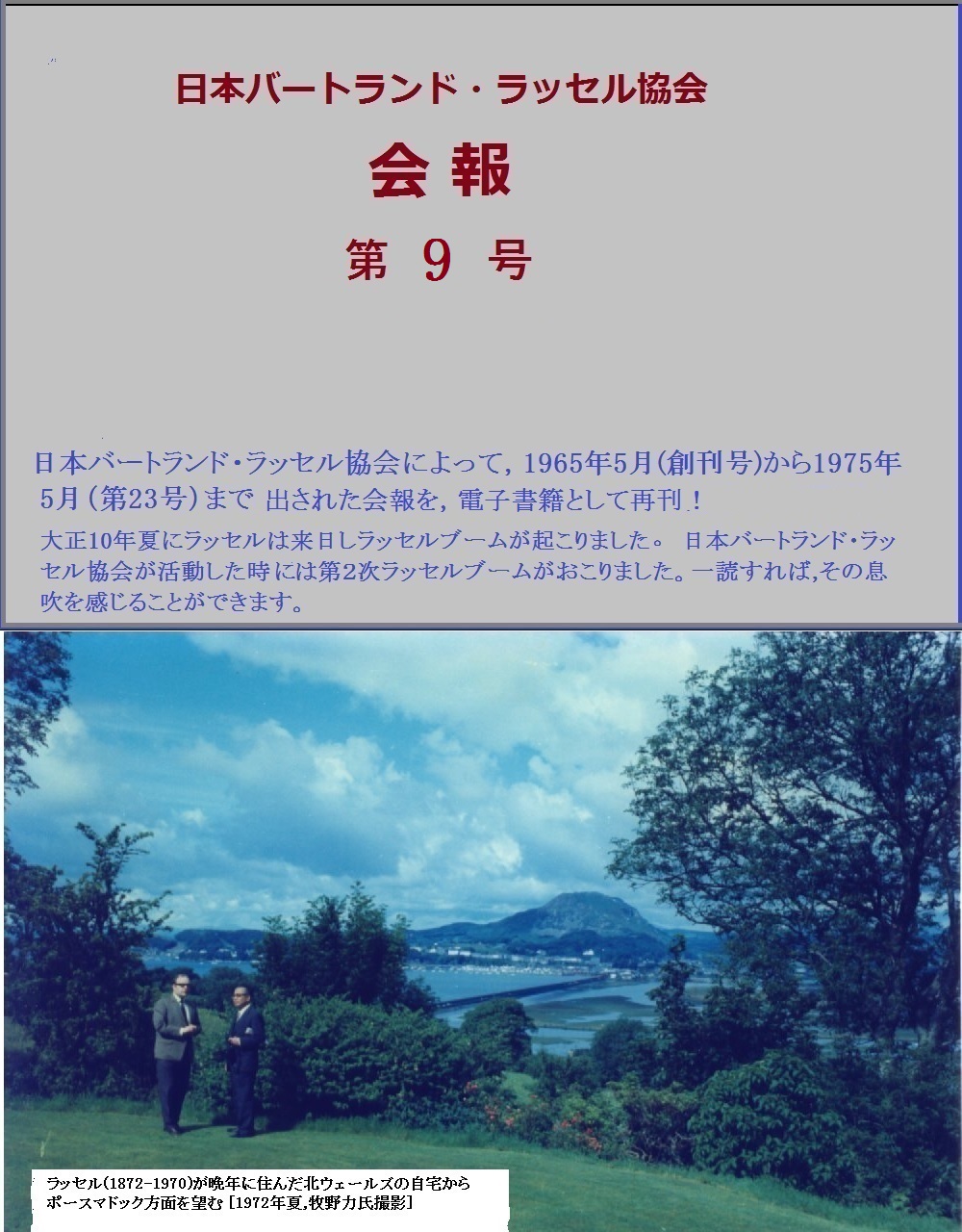日高一輝「バートランド・ラッセルの人間性」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第9号(1967年12月)pp.2-3
* 日高一輝は当時、ラッセル協会常任理事
ラッセルの哲学、論理学、数学ならびにその社会思想、さらには世界平和のための発言とその行動については、それぞれ専門の立場から研究もされているし、賛否はともかく、非凡な業績として高く評価されている。それと並んで、非常に興味もあり、またそれだけの意義もあると思うのが、ラッセルの人間性の研究である。ラッセルという人間にじかに触れて、かねてからその思いを深くしていたことではあるが、このたび『ラッセル自叙伝』を翻訳することによって、いよいよ感を深くさせられたのである。
或は、ラッセルは天才か狂人かと言い、或は、彼の発言と行動は自家撞着ではないかと言う。しかしわたくしの眼に映じたラッセルは、無類に正直で、純真で、天衣無縫である。心的過程をそのまま表明する、胸奥に去来するイメージを率直に吐露する。信ずるところに情熱をかたむけ、志すところに生命をかける。権力に諂う(へつらう)ことをしないし、身を売ることをしない。世の毀誉褒貶にとらわれない。すでに高名を世界に讃えられ、90才を越える老齢の身でありながら、逮捕投獄を覚悟の上で、街頭を行進し、国防省前に坐り込みをする。自由世界からの非難を承知の上で、ヴェトナム戦犯国際裁判を提唱する。それにもまして驚かされるのが、恥も外聞もかまうことなくすべてを告白する『自叙伝』の姿勢である。

青年時代の自慰行為、友人たちの同性愛、また、最初の妻アリスとの性交が年1回にすぎなかったこと等を、あからさまに述べている。妻アリスの兄の親友フィリップ・モーレルの夫人オットリーンと恋愛に陥いる。それでもオットリーンが、夫フィリッブにたいして純真な愛情をいだいていることを知って、その感情をいたわり、妻アリスがラッセルとの離婚理由にオットリーンの名をあげようとするのに反対する。それでも強行しようとするならば死をもって反対するといって迫る。親友のホワイトヘッド夫人は、あの時、ラッセルはほんとうに自殺したであろうと言っているし、今日でもラッセル自身が、あの時はほんとうに死ぬつもりだったと語っている。「一夜のためにそれだけの代価を払ってもよい」と言い、恋にも生命をかける彼であった。

「プリンキピア・マテマティカ(数学原理)」と取り組んでいるとき、想い、煩い、悩み、また難問が解けずにずいぶんと苦しん
だ。そして幾度か死のうと思いつめた。或る夜のごときは、鉄道の上の陸橋に佇んで二条のレールをみつめ、明朝こそはここに投身して自殺しようと決心したりする。
その大著を完成した直後は、政治に志して国会の選挙に立候補する。ベッドフォード選挙区が彼を公認するに当って、英国国教の慣例による試問の儀式をする。英国国教を信奉するか、時には教会に出席するかと問う。ただ形式的なものであったから、イエスと言っておけば公認されるのに、ラッセルは、ノー! と答え、国教の信徒ではない、教会に出席するつもりはない、自分は自由思想家だとはっきり言う。公認は駄目になり、立候補は出来なくなり、せっかく最高点当選疑いなしと目されていたチャンスを自らつぶした。
ラッセルの書くこと、態度、行動は、すべてこうした調子である。その正直さ、純真さは、その学問思想の偉績にも匹敵して無類非凡であると言えよう。世の自伝、日記、書簡、エッセイ等にして、はたしてラッセルほどあからさまにその真実をぶちまけているものがあるであろうか。心底の汚濁を適当に匿して、表面を絢麗に糊塗する「偽善なるパリサイの徒」を美徳といい、胸奥の真実をありのままに露呈して世に問うを「矛盾撞着・奇人狂人」と呼ぶのだろうか。ともあれラッセルの人間性は多くの研究課題を提供していると思う。