バートランド・ラッセル落穂拾い-中級篇(2011/2012)
2013年 2014年 2015年 2016年 2019年 2020年 索引(-出版年順 著者名順 書名の五十音順 )
<R落穂拾い(中級篇 )>は,ラッセルに言及しているもので「初心者向けでないもの」や「初心者向けではないかもしれないもの」を採録。 初心者向けは
R落穂拾い をご覧ください。
鎮目恭夫『性科学論』(みすず書房,1975年6月刊) * 鎮目恭夫 (しずめ・やすお,1925-2011.7.28):科学評論家。日本バートランド・ラッセル協会設立発起人の一人。
[pp.182-186:自我と世界] 問題の核心 はこうである--量子力学の基本理論 によれば,宇宙の任意の一部分も全体も,任意の時刻に,種々の物理学的観測(ある粒子の位置の観測とか,ある光の波長の観測とか等々)に対して,いく通りもの値を与えうる状態にあり,観測の結果それらの値のどれが得られるかは予め決定されていない。シュレーディンガー方程式 に従って時間の経過にともない連続的に変化する。ところが,そのような状態に対して観測操作 が加えられると,観測される対象が突然不連続的に変化し,ネコの場合なら生か死かのいずれか一方の状態への飛躍がおこる。したがって,もし(アインシュタインが信じたように)客観的世界の存在性 にそのような不確定性 を許さないなら,量子力学の世界像 は,バートランド・ラッセル 瞬間の唯我論(solipsism of the moment) と呼んだ思想とのみ論理的に両立しうる。この唯我論は,「現在只今の瞬間の自分自身のみが,宇宙に存在するもののすべて」であって,今の自分にとって外界の事物や過去の事物のようにみえるものは,「今の自分」の頭の中にそのようなものとして存在しているにすぎないという思想である。唯我論 は,極度に独断的・独善的な自己主張と自己正当化の支柱または口実になりうるものであり,かつ前記のような意志の絶対的自由を排除する古典的決定論 にもとづく宿命論的諦めの場合に劣らず人々に責任の放棄を促す危険がある。量子力学の世界像 は論理的に大変うまい世界像である。すなわち,観測する自分自身の自我をも含めた世界 の存在性を,自我を除いた世界 の存在性と同次元のものと考えることは,集合論におけるラッセルのパラドクス に当然ぶつかることだが,量子力学は,フォン・ノイマンが1932年の著書『量子力学の数学的基礎』で示したように,観測者の自我を観測対象に含めることを禁ずることによって,ラッセルのパラドクスが自動的に回避されるような
理論構造をもっているのである。私が今なお奇妙に思うこと に,アインシュタインも,その論敵だったボーアはじめコペンハーゲン学派(量子力学解釈の主流派)の人たちも,ノイマンも,ラッセルも,上記の問題点をついに一度も明確に指摘しなかった。
青木育志『河合榮治郎の社会思想体系-マルクス主義とファシズムを超えて』(春風社,2011年6刊) * 青木育志(あおき・いくし,1947~ ):1971年に大阪市立大学法学部卒。会社勤務のかたわら,河合栄治郎の社会思想を中心に研究。1994年に『河合榮治郎研究文献目録』出版。また,格差を肯定する「新自由主義」を否定し,平等に配慮した「自由主義へ」を主張(擁護)して『新自由主義』を2010年に出版。河合榮治郎 (かわい・えいじろう,1891-1944):社会思想家,経済学者で,自由主義知識人として著名。1920年東京帝大助教授,1926年に教授,1936年に経済学部長となる。なお,東大経済学部内における派閥闘争については立花隆(著)『天皇と東大』に詳述されている。
[pp.314-316:ラッセルとの比較(=河合栄治郎とバートランド・ラッセルの社会思想との比較)] 主要な違いは実在論と観念論という哲学上の違いだけ である。妻は四人に対して一人という小さな違いはある。社会に果たした学者としての役割はすこぶる似ている。 小さな共通点として,タバコ好きではあるが,酒は一滴も飲まなかったことがある。(松下注:いつ頃からかはよくわからないが,ラッセルは,年をとってからはレッド・ハックルというスコッチ・ウィスキーを愛飲している。→「レッド・ハックル(ウィスキー)に感謝 」) (「在欧通信」『全集』第17巻所収)」 。また,短時間ではあったが,わざわざ会ってもいる。相手陣営の論客に会うとは普通では考えられない。相当意識していたのであろう(注:すぐ直前では「意識していなかった」と書かれているが・・・?) 。「バートランド・ラッセルに会ったのはほんの一寸であった。何れゆっくりと思って,その次手紙を出したときには,アメリカヘ往かれた,という夫人の返事であった」。実際に会うだけではない。河合はラッセルの本をかなり読んでいる。ラッセルの本で河合が読んだものとしては,日記などで確認できるものとして,『自由と組織』(Freedom and Organization, 1934) のマルクスの部分,マルクス主義批判の二書などである。(German Social Democracy, 1896) を,ロシアのマルクス主義に関して,『ボルシェヴィズムの実際と理論』(The Practice and Theory of Bolshevisu, 1920) を出している。また,『西洋哲学史』(A History of Western Philosophy, 1945) の中のアウグスティヌスの章において,カソリック教会とマルクス主義との有名な比較 を行っている。いずれの著書においても,マルクス主義批判の筆致は鋭く,痛烈であった。他方,ファシズム批判に関しては,ラッセルは少し鈍かったようだ。ファシズム批判では,わずかに「ファシズムの祖先」[the Ancestry of Fascisum: 『怠惰への讃歌』(In Praise of Idleness, 1935) 所収]を著しているにすぎない。ラッセルがファシズムに大した批判を浴びせなかったのは,イギリスにファシズムは育たなかったし,身近に脅威を感じなかったからかもしれない。(松下注:「ファシズム(全体主義)」という言葉をタイトル中に含んだ著書はないが,いろいろな著書や論文・エッセイなどでファシズム(全体主義)をラッセルは批判していると思われるがいかがであろうか? それから,青木氏があげている『怠惰への讃歌』の第6章には「前門の虎,後門の狼-共産主義とファシズム-」が含まれている。単純な見落としと思われる。) ラッセルは自由主義を説き,社会主義的な社会改造に熱心であり,マルクス主義を批判し,ファシズムを批判し,平和主義に徹してきた。河合の行動に瓜二つではないか。 ともに知的勇気 あるいは知的率直さ (真理への妥協のない誠実さ,intellectual candour or integrity)の所有者であった。知的勇気とは,知的探究の結果,その結論の正しさを確信するならば,その結論を世間一般に公表して,世間一般の批判を招き,自己の立場が危うくなることが分かっていたとしても,その公表をためらわない勇気,率直さのことである。ともに「千万人といえども我行かん」(松下注:ラッセルが祖母から与えられた座右銘と同じ) の精神の持ち主であった。ラッセルは第一次世界大戦で一人その戦争に反対し,投獄もされた。投獄される危険が予知されたにもかかわらず,敢えて反対表明した。国を挙げての戦争熱の中,多くの友人を失った。『ボルシェヴィズムの実際と理論』によるロシア共産主義批判によって,世界中の社会主義者の支持を失った。それでも自説を曲げることはなかった。河合は二・二六事件のとき,幾多の危険が降り注ぐのを覚悟の上で,軍部を批判した。そして出版法違反事件で起訴され,大学からも追放された。それでも自已の主張を改めることはなかった。
上野正道『学校の公共性と民主主義-デューイの美的経験論へ』(東京大学出版会,2010年3月刊) * 上野正道(1974~ ):現在,大東文化大学文学部専任講師。教育学博士。
[pp.316-327:1940年の教育の公共性をめぐる到達点] (1)バートランド・ラッセル事件 教育と公共性に関するデューイ (John Dewey,1859-1952:米国の教育哲学者)の関心 は,新たな難問に直面することになる。それは,民主主義の危機 ファシズム やナチズム が進出し,すでに高度の緊張を孕んでいた。・・・。バートランド・ラッセル事件 ニューヨーク高等教育委員会 (New York's Board of Higher Education)がニューヨーク市立大学 (College of the City of New York)の哲学教授に招聘するプランを発表したことを受けて勃発した。ラッセルは,論理学や数学,哲学の分野で名声を博していたばかりでなく,『社会改造の原理』(一九一六年),『結婚と道徳』(一九二九年),『幸福の獲得』(一九三〇年)などの著書を出版して,真実に生きるための恋愛,結婚,離婚の自由に関する主題についても頻繁に論じていた。ところが,宗教的権威 が強く作用し,因習的な結婚観が支配しがちな当時の時代状況 において,恋愛や結婚に関するラッセルの考え方は,斬新で衝撃的な内容を伴うものであった。キリスト教界がニューヨーク高等教育委員会の決定に対する非難と攻撃を開始 した。ニューヨーク聖公会司教のウィリアム・マニング (William T. Manning, 1766-1949)は,ラッセルを姦通の容認者であり,宗教を破壊し道徳を撹乱する者 だと公然と非難した。これによって,カトリック,プロテスタント,ユダヤ系,アイルランド系を中心に,ラッセルヘの激しい攻撃 が展開され,任命撤回を求める反対運動がアメリカ全土に波及 した。反ラッセルの奔流 は,女子学生を娘に持つ母親でカトリック教徒のジーン・ケイ(Jean Kay)がニューヨーク最高裁判所 (New York Supreme Court)にニューヨーク高等教育委員会を相手に告訴し法廷に持ち込まれたことで,頂点に達した。ニューヨーク最高裁判所のジャン・マックギーン裁判長(John E. McGeehan, 1880-1968)は,原告の主張の正当性を認め,ラッセルの任命撤回の判決 を下した。・・・。だが,裁判の実態 は,マックギーン裁判長自身がアイルランド系のカトリック教徒であり,ニューヨーク市当局もカトリックの影響を強く受けていた ことから,利害関係の一致したある種の裏取引のような危うさを曝していた。ラッセルは,アメリカの情勢に愕然(がくぜん) とした。背筋が凍りつく想いで判決を聞いたラッセルは,控訴を求めたが要求は却下され,市立大学への彼の任用は反対勢力によって阻止されることになった 。彼を支持する活動 もまた熱心に行われ,任命の正当性を訴え出る動きが活発に見られた。ラッセルと親交のあったデューイは,早くから鋭敏に反応し任命を擁護する中心的な役割 を果たした・デューイのほかにも,アインシュタイン,ロバート・ハッチンス,ホワイトヘッド,ホーレス・カレン,アルバート・バーンズ,ドイツの小説家トマス・マン(Thomas Mann, 1875-1955),イギリスの小説家オルダス・ハクスレー(Aldous Huxley, 1894-1963)などが支持を表明した。・・・。デューイは,批判の只中にあったラッセルを擁護する論考を寄せた。彼は,ラッセル事件について二つの問題を提起 している。第一 は,ニューヨーク州法に従って設立された行政委員会の行為を覆し無効化する裁判所の法的権威に関わる事柄であり,第二 は,「社会的に非常に重要な問題について論じた著作の内容を高等教育機関で教授する「権限」を「著者」から剥奪できるのかどうかという問題である。 彼(デューイ)は,第一の点に関して,裁判所がこうした「権力」を持つと仮定するならば,教育行政機関は「権力」だけでなく「責任」も剥奪されることになるであろうし,第二の点について,マックギーン裁判長の判決を支持するとすれば,教授内容(注:ラッセルが教えるのはあくまでも理論哲学)の専門性と直接関係しない主題について,「大学教員の口を封じる」こと になるであろうと非難している。さらに問題なのは,ラッセル氏が実際に何を主張したのか,そしてどのような真意でもって彼が主張したのか」という「疑問」について,適切な調査や接近がなされていないことであった。・・・。一九四一年には,デューイとカレンの編著で,『バートランド・ラッセル事件』が出版された。 執筆に貢献(→寄稿)したのは,デューイ,カレン,バーンズ,フックなど,一〇名の研究者たちであった。同書の「序」を執筆したデューイによれば,出版の企画を立案したのはバーンズ であった。バーンズは,メリオンのバーンズ財団でラッセルを西洋哲学の講師として雇用する関係にあった。ラッセルをバーンズに引き合わせたのは,デューイであった。デューイの「序」は,バーンズ財団でのラッセルの講義が,それを聴いたすべての出席者たちを満足させるものであったと伝えている。また,バーンズは,ニェーヨーク最高裁判所のラッセル事件の判決に対して,「宗教的寛容と知性的自由」を求めて闘うだけでは納得せず,事件に関わる「公的な記録」を残すべきであると考えていた。デューイは,書物の公刊がそうしたバーンズの提案 によって実現したものであると述べている。・・・。絶望の淵に追いやられたみずからのアメリカ生活を回顧 して,事件の最中にバーンズ財団の講師として雇用されたときの記憶を次のように綴っている。
たくさんの進歩的な考えの教授たち が抗議をしてくれた。けれども彼らはことごとく,わたくしが伯爵だから,遺産をもっていて,裕福に暮らしているにちがいないと想っているのだった。ただ一人だけが,実際にことを運んでくれた。それはバーンズ博士であった。・・・彼はわたくしに,その[バーンズ]財団で哲学の講師をするよう五年間の契約を与えてくれた。これがわたくしを非常に大きな不安から救ってくれたのである。彼がこの約束をしてくれるまでは,当面の難渋をどう切り抜けたらいいか,わたくしにはわからなかったのである。わたくしは英国から金を取り寄せることが出来なかったし,さればといって英国に帰ることも不可能であった。たとえもし,三人の子供たちを英国にかえすための乗船券を入手することが出来たとしても,電撃戦の行われているさ中にかえしてやる気には,わたくしはどうしてもなれなかったのである。またその切符そのものも,たとえ買えるとしても実際に手に入れるのには長いことかかったにちがいないと思う。それやこれやで,ジョーンとケートを大学から退学させ,親切な友人たちの慈悲にすがって,出来るだけ切り詰めた生活をすることが必要であるように思われた。こうした矢先に,わたくしは,バーンズ博士によって窮境から救われたのである。
ラッセル事件をめぐって,デューイとバーンズは協調して行動した。恋愛,結婚,離婚についてのラッセルの見識は,学問の道徳性に関わる穏やかな黙約を打ち破り,市民の社会生活の安寧を脅かすというスティグマ(注:他者や社会集団によって個人に押し付けられた負の表象・烙印/ネガティブな意味のレッテル) を負わされ,唾棄されて然るべき内容のように扱われた。ラッセルヘの攻撃は,緊迫した社会情勢を前にくすぶる市民たちの不安を代弁していた。 これによって,ラッセルは,ニューヨーク市立大学への任用を妨げられることになった。一方で,デューイ,バーンズ,カレン,フックらは,裁判の不当性 を主張し続けた。彼らが危倶したのは,恐怖に支配された市民が批判的な思考と判断を喪失し,正義が損壊していくことであった。それは,茫漠とした思考停止状況を招くことによって,均質的な空間のなかに他者が溶解し,異質な主張や考え方が除去され消滅していく事態を意味していた。 → (1)バートランド・ラッセル事件の 全文を読む! (2)教育の査察的統制と蹂躙される権利
それは,異質な考え方を均質的な包囲網のなかに溶解し,他者の存在を消滅させることを意味していた。ラッセル事件や学校への査察的統制は,高度に緊張を孕んだ世界情勢によって不安を煽られ恐怖に駆られた一般市民 の当惑を映し出していた。その恐怖は,教育の自由と自立性を封じ込める容赦のない攻撃となって教育機関に発せられた。ラッセルやラッグを「破壊分子」とみなす考え方は社会全域に拡大し,彼らは世間から集中砲火を浴びる ことになった。一連の状況を前にして,デューイは,人びとの批判的な思考と判断の喪失 が招く遮断された視界と閉域的な要塞を解放し決壊させる前途を探った。彼にとって,教育の自由と民主主義 を保障し,公衆たちの足枷(あしかせ) のない議論と対話による開かれた正義を実現することは,公共的な事柄であった。 ・・・。
マーガレット・A.ボーデン(著),野崎昭弘・村上陽一郎・廣松毅(監訳)『人口知能と人間』(サイエンス社,1986年4月) (2012.8.3)* マーガレット・A.ボーデン (Margaret Boden,1936~ ):医学,哲学,心理学研究の背景をもつ,心理学の哲学の分野の第一人者。
[pp.335-358:例による学習] ハンプティ・ダンプティとバートランド・ラッセル は,外見上はまったく異なるが,例による学習に関する意見 では似ている。つまり両者は,姿かたちはまったく違っているが,例による学習の本質に関する前提 (この前提は,一般に行きわたっているものでもある)についてだけみれば,きわめて似ている。ラッセルの「習得による知識」(松下注:→「直接知」)と「記述による知識」の区別 を,常識的に表現したのが,次のハンプティ・ダンプティのアリスヘの返事 にほかならない。(松下注:「習得による知識」の原文は 'knowledge by acquaintance'。「習得による知識」という訳語はしっくりいかない。高村夏輝氏は岩波文庫版『ラッセル哲学入門』において「面識による知識」という訳語を,中村秀吉氏は社会思想社教養文庫版『ラッセル哲学入門』で「見知りによる知識」をあてておられるが,知覚だけでなく,五感すべてによって直接的に得られる知識のことをいうので,角川文庫版の旧版の生松敬三氏の訳語「直接知」がいちばん適切であると思われる。なお,語感がおかしいかもしれないが,私は「直知(じきち)」という言葉を使っている。 )
[それから,『咆囀する(ほうてんする) 』って,なんですか?」(ほえる) 』と『囀る(さえずる) 』の間で,まん中に,一種のくさめがはいったようなものさ。が,その声はお前も聞いたろう--向こうの森の中で--一度聞いたら,もうたくさん,というやつだ。・・・」ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』 岡田忠軒訳,角川文庫,p.94より。)
同種の区別は,「抽象的」な視覚的描写 と「具体的」な視覚的描写 を対比した第9章においても行った。そこでの議論は,これら2つのいずれにおいても,ある概念を「例によって学習する」 ということは,「伝聞による学習」 とはきわめて異なっていると同時に,それ以上のものであるということであった。実際,ラッセルは「習得による知識」(→「直接知」)をその直接性のゆえに「記述された知識」からは独立であり,かつそれよりも前の段階にあるとみなしている。つまり彼によれば,「例による学習」とは,抽象化や記述の痕跡のまったくないものであり,事実いかなる解釈も介在しない直接的な理解 を意味するものなのである。(出典: Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, 1912, chapter 5./原注:ラッセルを正しく評価するならば,「習得による知識」(→「直接知」)という彼の概念は,今日一般に使用されている「例による学習」より狭いものである ことがわかる。彼ならば,「咆囀する」の説明を聞くことを,知識と直接かかわる実例による学習のケース とみなすことであろう。しかし,一方で,彼は,例えば,「共産主義者の二枚舌」という直接的な(first hand)知識は,「習得による知識」(→「直接知」)を構成するとは,いわないであろう。その理由は,彼の説は次の点で,エイベルソンと一致しているからである。つまり,「共産主義者の二枚舌」と何かに名祢をつける(そしてそれを経験する)ことは,経験を解釈するのに幅広い,記述的な概念の背景を必要とするからである。) 「咆囀する」の説明を聞いてアリスが満足 したのも,なるほどもっともであろう。しかし,それはハンプティ・ダンプティの挙げた例 が記述すべきことをすべて明らかにしているからではない。むしろ例とは,彼女が前もって行っていた概念化をテストするとともにおそらくはそれを改良をすることを可能にするもの である。彼女は,「咆囀する」が「囀り」よりも「しゅうしゅう」という声により似ていることを学習し,それによりハンプティ・ダンプティの'記述を改める'ことまでもしたかもしれない。 要するにに「目的領域の習得」は,その知識を増大させるが,「習得する」とは目的領域と表現領域の間の特定の解釈の連結(つまり手がかりと図式の関係づけ)を考えつき,それを改良することであって,「習得する」ことによって,一般に表現領域があり余るほど豊富になることはない。人口知能 も,目的となっている意味のある現実の表現をある程度生成し改善することによって,例(そして反例)による学習を行うことができる。・・・。(後略)
安川悦子『アイルランド問題と社会主義--イギリスにおける「社会主義の復活」とその時代の思想史的研究 』(御茶ノ水書房,1993年2月) (2012.07.20)* 安川悦子 (やすかわ・えつこ,1936~ ):名古屋市立大学名誉教授。1982年に『イギリス労働運動と社会主義 「社会主義の復活」とその時代の思想史的研究』で名古屋大学から経済学博士号授与,同年同書で労働関係図書優秀賞受賞。
[pp.432-446:補論3 「イギリス社会主義をめぐる二つのオールタナティヴ --都築忠七(編)『イギリス社会主義思想史』を読んで--」(初出:『ロバート・オウェン協会年報』v.13号(1988年)所収)] 二つの相対立する「イギリス社会主義思想」の伝統 が,けっして自覚的に調整されることなく「オルタナティヴ」として提起され,時には,一方が他方の「オルタナティヴ」を否定するままにされていることに原因がある。一つの伝統 は,「労働の復権」の系譜,いいかえれば「サンディカリズム」の伝統をうけつぐもの で,労働者が自らの労働の場を確保し,労働過程を自分の手に収めることに主眼をおくものである。ラッセルの「非革命的サンディカリズム」への共感 などが,ポジティヴな「オルタナティヴ」としてここでは析出される。労働の喜びと労働の自由の確保という労働者の主体的側面 がこの伝統においては何よりも問題にされる。もう一つの伝統 は,「サンディカリズム」に対置していえば,「コレクティヴィズム」とでも名づけうるもの で,「経済の計画化」に力点がおかれる。・・・。官僚的統制と計画を否定する「サンディカリズム」的態度 と,一九世紀末チェンバレンが提起したような,集権と計画と統制を求める「コレクティヴィズム」的態度 とは,たがいに相容れる構造をもたない。価値のベクトルは逆をむいている。イギリス社会主義のこの二つの伝統をひきついだところで抽出される二つの「オルタナティヴ」をどううまくかけあわせて,一つのポジティヴな「オルタナティヴ」とするか。編者・都築に期待されたのはこのところであった。・・・。ロイドン・ハリソン は,この「サンディカリズム」と「コレクティヴィズム」という二つの対立するキイワードを,バートランド・ラッセルにおける「自由主義」と「社会主義」 というキイワードにおきかえて,二つの間の関係を明らかにしようとした。一九世紀末から二つの世界大戦をとおりぬけて活躍するラッセルの思想の本質は何であったか。「自由主義」と「社会主義」を対立する概念とみなした上でラッセルを「自由主義」の文脈にひきよせて評価するアレヴィに異をとなえたハリソンは,ラッセルを,「自由主義」も「社会主義」も手ばなさなかったヒューマニストとしてつかまえ,ラッセルの曲折にみちた思想の軌跡をあとづけながらラッセルにおける「自由主義」と「社会主義」との関係を明らかにしている。 一九二〇年にラッセルは次のように書いた。「私は,(第一次)大戦の結果,自由主義から社会主義へ移った者のひとりだが,それは,私が自由主義の理想 の多くを賛美しなくなったためではなく,社会の経済構造の完全な変革のあとでなければ,その理想を実現する機会がほとんどないように思われた からである。 ・・・。私が社会主義というのは,気のぬけた体制ではなく,徹底的な改革のことである。・・・。仕事における自治,自律が,征圧すべき自由のあらゆる形態のなかでもっとも重要なものである。 人の仕事は,もっともふかいところでその人にふれるものだからである」とラッセルは,「自由主義」の理想を実現するために「社会主義」,つまり「社会の経済構造の完全な変革」を必要とするとみなし,手に入れるべき「自由」とは,なによりも「仕事における自治,自律」であると考えていた ことが明らかにされる。ラッセルの「社会主義」は,アレヴィが定義するような「社会主義」(つまりシドニー・ウェッブやレーニンの文脈の中にあるのではなく,「ロバート・オーエンやウイリアム・モリス,コールやトーニーの文脈の中にある(一五四ぺージ)とハリソンは説明する。「非革命的なサンデイカリズム」(一五六ぺージ)こそがラッセルの到達した思想的地平であった
リチャード・ノートン・スミス(著),村田聖明,南雲純(共訳)『ハーバードの世紀--アメリカを作った名門大学』(早川書房,1990年1月) (2012.07.08)* Richard Norton Smith(1933~ ):1975年にハーバード大学卒業。
[pp.105-168:偉大な同化主義者] ローエル (Abbott Lawrence Lowell, 1856-1943: 1909~1933までハーバード大学総長) の果断さは誰の目にも明らかだった。1920年代の不安定な光の中で,不思議に精彩を欠いていたのは,彼のビジョンである。政治的弾圧と人種的迫害とが争って新聞紙上をにぎわした時代,苛立つ少数派集団が長い間ひきのばされてきた平等を要求し,スウォースモア大学やオベリン大学のような男女共学の大学が女子教育に新しい時代を開こうとしていた時代 に,ハーバードは黄金の殻の中に引きこもったように見えた。たとえば哲学科に空席ができたとき,個人的性格を重視するローエル は,バートランド・ラッセルの任命を拒否 した。哲学科主任がアメリカで最も著名な哲学者として尊敬していたアーサー・ラブジョイ を,ローウェルは「悪さをする人物」としてしりぞけた。ラブジョイの悪さの主なものは,全国大学教授協会の設立を積極的に支持したことらしかった。ローウェルは,ジョン・デューイ (1859-1952) を年齢のゆえに断わり,最終的には,アルフレツド・ノース・ホワイトヘツド (Alfred North Whitehead, 1861-1947) に落ち着いた。・・・.ローウェル総長に関する記述 )。
『丸山眞男集6 1953-1957』(岩波書店,1995年12月) (2012.06.24)* 丸山眞男 (まるやま・まさお,1914-1996.8.15):(故人)政治学者,東大法学部名誉教授。松沢弘陽 (まつざわ・ひろあき,1930~ ):政治学者,北海道大学名誉教授。
(pp.361-382)「松沢弘陽による『丸山眞男集6』の解題 現存体制の側とそれに対する革命運動の側との両方に通じる,制度論・機構論的な政治権力論を克服しようとする時,丸山の拠り所になったのは,丸山が学部学生・助手の時代から親しんだバートランド・ラッセルの権力論 (Political Power, 1938 など)(松下注:正しくは, Power, a new social analysis, 1938 ) であった。しかし,ラッセルらの権力論は,政治権力の制度論的・機構論的な見方に対して,政治権力を含むさまざまな「社会権力」一般の実態 を明らかにする上では有効だったが,「社会権力」一般から区別された政治権力の特質をとらえるには不十分だった。これに対して,政治権力の固有の性格 をとらえる上で丸山の手がかりになったのは,とりわけこれも戦前から親しんでいた マックス・ウェーバー やカール・シュミット と,戦後に知ったラスウェル であった。・・・。
掛川トミ子「『ジャパン・クロニクル』とロバート・ヤング」 [「内村鑑三全集・月報n.32」(岩波書店,1983年5月発行)] (2012.5.27)* 掛川トミ子 (1931~ ):関西大学名誉教授。専攻は,ジャーナリズム・思想史。
(p.69 本全集には,内村鑑三 が『ジャパン・クロニクル 』紙(The Japan Chronicle)の "Correspondence" 欄に投稿した英文論稿が十七篇収録されている。日露開戦後,日本の新聞がのこらず,「暴露贋懲」(ばくろようちょう) の雄叫びのなかに埋没し,新聞の中枢的機能を果たさなくなっていたときに,戦争そのものについて根本的な考察 を加え,鋭い批判の光を投じていたのがほかならぬ『ジャパン・クロニクル 』であった。コーべ・クロニクル 』主筆ヤングは非戦論をめぐって,『クロニクル』紙上でのフォーラムの形成をつうじて,新たに出会うことになる。そこで本稿では『クロニクル』の略史と主筆ロバート・ヤングの略歴を紹介し,読者の参考に供することにしたい。・・・。ジャパン・クロニクル 』は,英国人ロバート・ヤング (Robert Young, 1858-1922)が,一八九一年十月二日,神戸市の居留地で創刊した英字紙である。創刊時の題号は,新聞を発行した地域の名まえを頭に冠せて,『コーべ・クロニクル 』と称していた。・・・。さらに一九〇五年一月五日付から,地方紙を超える意図をもって『ジャパン・クロニクル 』と改題し,廃刊時までその題号を用いた。・・・。ブラッドロー (一八三三~一八九一)であった。一九二一年七月,バートランド・ラッセルが中国からの帰途,日本に立ち寄った際,神戸で下船してまっ先に訪ねたのはロバート・ヤングであった。ラッセルは『自叙伝』に,ヤングの印象を「まことに気持のよい人物」とのべ,ヤングの書斎にはブラッドローの大きな肖像画が掲げられていたことも記されている。ヤングは,ラッセルに宛てて,定期的に週刊版の『クロニクル』を寄贈しており,ラッセルは同紙を,「自分がこれまで読んだもののなかで,もっともすぐれた新聞」だと評している のが関心を惹く。また,『クロニクル』の創業資金には,ヤングが植字工として働きながら蓄わえた一〇ポンドが当てられたことも記載されている。 (『ラッセル自伝』の該当箇所 ) ヤングは一九二二年に死去するまで,ほとんどひとりで,毎日社説を書きつづけた 。かれは,それがどれほど貧弱なものであろうとも「支配者の最良の統治よりも,自治」の方に価値を見出し,西欧列強が日本に課した治外法権を撤廃することには積極的に賛意を表し,日本のために,力づよい論陣を張った。が,同時に,同じ原則に基づいてなされる,日本の朝鮮・台湾統治にたいする鋭く厳しい批判は終始かわらなかった。その「筆鋒の鋭利なるは骨を刺すが如く,其皮肉の痛刻なるは肺腑を抉るが如く・・・」(R. Young 厨の追憶」)と山県五十雄 が評しているように,日本政府および日本人の不正・偏見等,とりわけ日本の,ミリタリズムにたいする批判と洞察力 の鋭さゆえに,かれとその新聞は "anti-Japanese" とみなされたのである。・・・。
J. L. ボルヘス(作),鼓直(訳)『伝奇集』(岩波書店,1993年11月刊/岩波文庫・赤792-1) (2012.5.11)* J. L. ボルヘス (Jorge Luis Borges, 1899-1986):アルゼンチン出身の作家・詩人で,幻想的な短編作品で有名。
[pp.53-69:『ドン・キホーテ』の著者ピエール・メナール] <注:これは一種のパロディ作品ですが,わかりにくいので,下記の引用を読む前に,まず Wikipedia の説明(『ドン・キホーテ』の著者,ピエール・メナール) をお読みになってください。> (p.53) この小説家(注:ピエール・メナール) が残した「目に見える」作品は容易に,しかも簡単に列挙できる。したがって,アンリ・パシュリエ夫人がその誤りの多い目録のなかで犯した脱落や,よぶんな追加は許しがたいものがある。プロテスタント 的な偏向をだれ知らぬ者のないある新聞などはこの目録を,無分別にも,その哀れな読者ら --この者たちはごく少数であって,仮りにフリーメーソン会員や割礼を受けた者でなくとも,カルヴァン教徒である-- に押しつけた。メナールの親しい友人たちはこの目録を目にして驚き,いささか憂鬱にさえなった。わたしたちが墓所の大理石の前,痛ましい糸杉の茂みのかげに集まったのは,あれは昨日のことなのに,早くも「過誤」が彼の「追憶」をくもらせようとしている。・・・。簡単な訂正が是非とも必要だろう。・・・。(p.54) ・・・。すでに述べたとおり,メナールの目に見える作品は簡単に列挙できる。彼個人の文書を丹念に調査した結果,それは以下のものからなっていることが確認された。(a) ・・・。(p.56) ・・・。 (m) 有名な「アキレスと亀の問題」の解答を年代順に論じた作品,『ひとつの問題をめぐる多くの問題』(パリ,1917年)。この本については現在までにふたつの版が出ている。第二の版はエピグラフ としてラィプニッツの忠告「すこしも恐れることはない。たかが亀である」を掲げ,ラッセル (p.64~) ・・・。いくつかの章を取りあげて考えるとき,われわれはやはり驚かされる。たとえば,「ドン・キホーテが武器と文学について語った奇妙な話を扱っている」第一部の第三十八章を検討してみよう。周知のとおり,ドン・キホーテは(ケベードが『万人の時』の,時代はさがるが類似の章のなかで行なったように),文学を断罪して武器を弁護している。セルバンテスは元兵土だから,その判決は納得がいく。しかし,ピエール・メナール --彼は,『僧侶の反逆』やバートランド・ラッセル 転写 を見る。ド・バクール男爵夫人は二ーチェの影響を認める。この第三の解釈--反論の余地なしとわたしが判断するもの--にたいして,ピエール・メナールのほとんど神のごとき慎しさ--彼が好むものとは正反対の考えを公けにするという,その諦念と皮肉にみちた性癖--にぴったり合った第四の解釈を,果たして付け加えるべきかどうか(ここでふたたび,ジャック・ルブールの短命なシュール的断章に見られた,ポール・ヴァレリーにたいする彼の酷評を思いだそう)。セルバンテスのテクストとメナールのテクストは文字どおり同一であるが,しかし後者のほうが,ほんど無限に豊かである(彼を非難する者は,より曖昧だと評するかもしれないが,曖昧性は豊かさというものである)。
与謝野寛+与謝野晶子『鉄幹晶子全集・第19巻』(勉誠出版,2005年8月刊) (2012.4.29)* 与謝野晶子 (よさの・あきこ,1878-1942):明治を代表する歌人で,女性解放運動家。日露戦争の時に歌った『君死にたまふことなかれ』は有名。* 与謝野晶子は,ラッセルが Principles of Social Reconstruction, 1916 で述べた(所有衝動をできるだけ少なくしていき)「創造衝動をできるだけ増やす努力をする生活」の重要性について言及しています。(同書まえがき より:「最良の生活とは,その大部分がさまざまな創造衝動に基づいて築かれた生活であり,最悪の生活とは,その大部分が所有欲に発しているような生活である,と私は考えます。」)
。出典は書かれていませんが,下記はあきらかにその一つです。
[pp.113-117:与謝野晶子「欲望の調節」(1918年9月)] 欲望 に単一なものがあり,複合的なものがあり,それが無限に新しく起伏するのですから,厳密に分類することは不可能ですが,学問上の便宜 から之に対し学者に由っていろいろの分類があります。シユモラア (Gustav von Schmoller, 1838-1917:ドイツの経済学者) は(一)自存衝動,(二)性的衝動,(三)行動衝動,(四)認識衝動,(五)競争衝動,(六)営利衝動の六種に分け,露西亜のツウガン・バラノヴスキイ (Mikhail Ivanovich Tugan-Baranovsky,1865-1919:ロシアの経済学者) は(一)自己保存並に感覚的快楽を求むる生理的欲望,(二)性欲,(三)同情的衝動,(四)利己・利他的衝動,(五)無関心的衝動の五種に分けました。また英国のバアトランド・ラッセル は(一)創造衝動,(二)所有衝動の二種に大別 して,最も多く創造衝動が働き,最も少く所有衝動が働いておる処に最も好い生活が開展して行くと,云って居ります。 バラノヴスキイの謂ゆる五種の分類の第一である生理的欲望の実現を直接の目的として,物質の生産及び分配を条件とする経済行為が社会生活の死命を制するまでに法外に優勢を加へつつある現代は,欲望造化の過程に於てまだ非常に低い生活時代にあると,云わねばなりません。現代の生活は,ラッセル に従へば,所有衝動が最も多く働いて居る生活 です。シユモラアに従へば自存衝動と営利衝動との上に築かれた生活です。バラノヴスキイの謂ゆる無関心的衝動が抑圧され,シユモラアの謂ゆる行動衝動と認識衝動とが沈滞してゐる生活です。他の欲望の手段とならず,欲望其れ自身を目的として其れの満足を以て終結するもの ラッセルの創造衝動 と云ひ,シユモラアの行動衝動とは之を云ふのです。・・・。
梅棹忠夫「文化分析の構想」[加藤周一,久野収(編)『学問の思想』(筑摩書房,1971年6月刊/戦後日本思想体系v.10)] (2012.4.27)* 梅棹忠夫 (うめさお・ただお,1920-2010):故人。生態学者・民族学者。京都大学名誉教授,国立民族学博物館館長を務める。1994年に文化勲章受賞。『文明の生態史観』や『知的生産の技術』はとても有名。
[pp.169-188:梅棹忠夫「文化分析の構想」] (p.170) 3 要素と集合 文化の数学的モデルの可能性 を考えるために,まず,数学 というものの,一般的な構造を検討してみよう。数学 は,一般に数または図形に関する学問であると考えられている。しかし,今日の数学 は,その研究対象を,数または図形に限定していない。あるいは,今日の数学 は,その研究対象を何ものにも限定していないというべきであろう。B. Russell の有名な表現によれば,数学とは,"それが何であるかわからぬものについて語り,また,その語っていることが真であるかどうかわからないような"学問なのである。 つまり,数学における研究対象は,何でもいい,何かわからないところの,エレメント,要素,あるいは元素とよばれるものの集合である。そして,その要素の性質は,証明によらないところの公理系によって与えられるというのが,今日の数学の一般的なすがたである。数学の語るところは,すべてその公理系に帰着し,その公理系は証明によるものではないから,真であるかどうかはわからない,というのである。数 」は,もちろんそういうふうな要素の集合である。また,図形 というのも,点とか線とかよばれる要素の集合にほかならない。そのほか,数や図形でなくても,要素とその集合という形のものでさえあれば,数学の対象 は何であってもよい。 ・・・。
『西田幾多郎全集第23巻(書簡V)』(岩波書店,2007年9月刊) (2012.3.28)* 西田幾多郎 (にしだ・きたろう,1870-1945):日本を代表する哲学者。下村寅太郎 (しもむら・とらたろう,1902-1995):哲学者,科学史家。末綱恕一 (すえつな・じょいち,1898-1970):数学者。昭和10年東京帝大教授。戦後,統計数理研究所所長。整数論のほか,西田哲学をもとに独自の数学基礎論の確立をこころみた.[PDF]華厳経に魅了された数学者末綱恕一 。野田又夫 (のだ・またお,1910-2004):京大教授を務める。デカルトの研究で有名。ラッセル協会設立発起人の一人。* 松下注:宛先の住所を見ればわかるように,下村寅太郎の家と末綱恕一の家は近くにある。
●1943年(昭和18年)8月5日付,下村寅太郎宛 (東京市杉並区和泉町四七五)<はがき>Russell 有難う御座いました よく読んて見たいとおもひます(旧字体のママ/以下同様) ●同年8月23日付,末綱恕一宛 (東京市杉並区和泉町六二)<はがき>下村君から Russell, Introduction [(数理哲学)入門]をかりて読んでみました 併し何だか浅薄の様に思はれます 文部省の会にてお話しのものは別にお書きになりませぬか●同上年8月24日付,下村寅太郎宛 <はがき>ラスセル 難有御座いました 教へられる所はありますが何だか浅薄の様におもひます●同上年9月1日付,下村寅太郎宛 <はがき>ラッセル 御落手下さつたことと存じます●1944年(昭和19年)1月27日付,下村寅太郎宛宛 <はがき>私は数学は公理主義だけからも直観主義だけからもダメだと思ひます 末綱君の云はれる如きことを私の論理にて裏附けた様なものです Russell の implication[含意]の論埋ではだめとおもひます indiscernible[不可識別]の論理でなくては ●同上年1月28日付,末綱恕一宛 <封書>今度「論理と数理 」といふものを書いて見ました これは全く学兄の御考を論理[的]に裏附けようとして試みたものなるがどうも数学といふものが分らぬのでだめです 三月の「思想」に出るつもりですが出たら色々御高教を願ひたいとおもひます 直観論者でも公理論者でも数といふそのものがどういふものかといふ問題については私共には不明の様に存じますが ラッセル の implication[含意]の論理ではやはり唯抽象的一般者の論理であれでは数理を基礎附けられない様におもひます 物理について書きましたものは一月の「思想」故 近日出るかと存じます 出ましたら一冊さし上げます これも御教へ願ひたいと存じます これは随分思ひきつた大胆な考です 随分物笑ひとなるものかも知らぬが量子力学の世界はどうもここまで行かねば徹底せないとおもひますので兎に角考へて見たのです●1944年(昭和19年)10月28日,野田又夫宛 (大阪府泉北郡高石町羽衣一六七)<はがき>私の論理といふのは学者先生から頭から馬鹿にせられ相手にせられないのですが 数学の如きもラッセル ではどうかとおもひますが
碧海純一「社会秩序とことば」[芳賀綏(編)『社会の中の日本語』(大修館書店,1976年11月刊/日本語講座・第3)所収] (2012.3.26)* 碧海純一 (あおみ・じゅんいち,,1924年~ ):本論文執筆時は東大法学部教授(法哲学専攻)。碧海氏はラッセル協会設立発起人の一人で,常任理事を務めた。
(p.132) ・・・。このように自然現象の知覚においてすら各国語の個性が人々の世界像を大きく左右するのであるならば,社会的状況の把握とそれにもとづく社会的行動とが,言語によって強く影響されることは,容易に理解できるであろう 。親族名称の問題 は,人類学においても比較言語学においても好んで取り上げられるトピックであるが,この分野において,言語と人間の社会的行動との間の緊密なフィードバック関係は最も端的な形で現われる。"brother, sister"(英),"frère. sœur"(仏),"Bruder, Schwester"(独)などのような西欧語に対応する表現が日本語にはなく,日本人が「兄」や「妹」について語るとき,親族語彙上の強制によって,「長幼の序」を明示せざるをえないこと,双生児のばあいのように本来「長幼の序」をつけることができないばあいにも,無理に「兄」と「弟」とを区別する我が国の習慣 ,などから,人類学者や社会学者は,日本の家族制度,相続制度,その他多くの社会制度や習俗に関して多大の情報を得ることができる。また,こうした制度や習俗を或る程度まで理解することなしに,日本語の「兄」や「弟」の意味を正確に捉えることは不可能である。バートランド・ラッセル によれば,西洋の宣教師が母系制社会における布教に成功しなかった一因は,かれらが「神は父である」と説いたことにあった。宣教師たちは,「神は母方の伯父である」と説教すべきだったのである。(松下注:もちろん,半分皮肉ですね。)
嶋津格『問いとしての<正しさ>』(NTT出版,2011年10月刊) (2012.3.7)* 嶋津格 (しまず・いたる,1949~ ):千葉大学大学院専門法務研究科教授で法哲学専攻(法学博士,1982年)。2012年現在,千葉大学理事,日本法哲学学会理事長。トマス・モア (1478-1535):『ユートピア』の作者として有名。
[pp.139-162: 「ユートピア論の射程--知的構想力と秩序の問題」] (p.142) 学生B ・・・。それに,女性にとって深刻なのは,(トマス・モアの『ユートピア』においては) 「衣服は・・・全島を通じて同じ型で(但し男子と女子,既婚者と未婚者とはそれぞれ違った衣服を着ている),殆ど常に流行は変らず・・・冬にも夏にも適している・・・」というところね。これじゃまるで,いつか見学にいった刑務所 みたいだわ。とにかくこれだけはなんとかしてほしいわね。教師 「これだけ」直せば我慢できるかどうかはともかく,この部分はさっき少し話した,奢侈品(しゃしひん/必需品以外のぜいたく品) の生産をやめて資源の利用を節約しようという発想 からくる一つの帰結だろう。1969年に私が東ベルリンに行ったとき,店で売ってるのは決まった型のライトブルーのジャンパーばかりだった,というのを想い出したよ。・・・。これらは,市場におけるいわゆる「消費者主権」に批判的な発想といえるかもしれない。でも生産の決定において,すべての人間の欲望がその目的として無差別に並列される,という市場による体制の評価 は,現代でも結構議論のわかれるところだろう。それから,Bさんが指摘したそれ以外の要素は,ギリシャ的というか,常にポリスまたは国家の中で,一体性をもった集団の一員として生きなさい,という思想の現れ だ。その意味では反個人主義といっていいね。たしかに今ならこんな社会を理想的と考える人はあまりいないだろう。「全体主義」的だものね。実はモアはギリシャ古典の教養が豊かな人で,この本の中でもあちこちで,プラトンの『国家』 に出てくるアイデアを利用している。これは,ギリシャ古典の文脈では,スパルタ・モデルに依拠する「アテナイ」批判 といってもいいかもしれない。「共同食事」の制度なんてまさにスパルタ的といえるだろう。ちなみにギリシャ思想史の研究者では,アテナイ(注:現在のアテネ)が好きな人とスパルタが好きな人とに大体はっきりと分かれるね。『西洋哲学史』の中でスパルタヘの厳しい見方を語っているバートランド・ラッセル はアテナイ派で,私もこっちだね。プラトンはもともとスパルタ派の代表だが,後の時代ではルソー なんかがこの派の典型だろう。この種のプラトン流反個人主義 は,西欧政治思想史の一大系譜をなしていて,モアもこれに悼さしているということだ。これは,自由主義・個人主義・民主主義の間の複雑な関係を理論の中でどう整序するか,という現代でも未解決の問題にもかかわっている。ユートピア共和国でも選挙をするのだから,民主主義のタイプ論といってもいいかな。民主主義と全体主義は論理的に排斥し合わないということは,思想史的には常識だけど,現代政治の中では忘れられることが多いね。 ・・・。
小林一郎『田山花袋研究-「危機意識」克服の時代(2)』(桜楓社,1982年6月刊) (2012.3.7)* 田山花袋 (たやま・かたい,1872-1930):自然主義の代表的作家の一人。2009
[pp.562-588: 小林一郎「花袋の随筆について」] 評論としては,バートランド・ラッセルに対する本間久雄,中沢臨川,中村星湖の論を批判している。 ・・・中略・・・。臨川の「ベルトランド・ラッセルの立場」 は,九月の「中央公論」にのり,本間の「無抵抗主義の疑ひ」は,十月の「早稲田文学」でそれぞれ論じたものである。・・・。次に,中沢臨川が書いた評論「ベルトランド・ラッセルの立場」に対する評 である。「文壇」と「労働問題」の中間に居て,それを考えていることを多としている。が,本間久雄が,中沢臨川の「無抵抗主義」を論じている考え方は,「無抵抗」ということが,まだよく分っていない。したがって,中沢の考え方を本間は理解出来ていない というのである。悪人 なるものが別に我々人間以外にあるものと思ってゐるらしい。そしてさういうものは飽迄撲滅しなげればならないと思つてゐるらしい。そしてその人の悪たるものが本間氏自身の血の中にも混じつてゐるといふことは,ちつとも考へてゐないやうだ。惜しむべきことだ。
大塚金之助『解放思想史の人々-国際ファシズムのもとでの追想,1935-1940』(岩波書店,1949年4月/岩波新書no.1) (2012.3.5)* 大塚金之助 (おおつか・きんのすけ,1892-1977):経済学者で,一橋大学名誉教授。1950年から1977年まで日本学士院会員。 * 下記に引用したものは大塚金之助が1936年6月 に『中央公論』に発表したものであるが,国家や軍に批判的な表現は検閲により,削除されている 。たとえば,「そして(ラッセルは)・・・ のかどで監獄に旅する。」の,削除された「・・・ 」の部分は,「反軍国主義的プロバガンダ 」であったと,戦後(1948年)に追記している。ラッセルとアインシュタインとの関係 は,ラッセル=アインシュタイン声明(宣言)の関係で一般にもよく知られているが,アインシュタインがラッセルの著書 Political Ideal(1917年刊)のドイツ語版(1922年)に寄せた序文や,ラッセルが1925年に出版した The ABC of Relativity を読めば,「宣言」の30年以上前から両者は互いに注目していたことがわかる。
[pp59-80:アインシュタイン教授の一面(1936.5.5)] * 『中央公論』v.51,n.6(1936年6月号)掲載の,アインシュタイン教授の新選集『私は世界をどう見る』の紹介として。 平均をたもっているぐらつき教授 (wackeliger Professor)ではなくて,言わば偶然にそのなかへ生れおちた時代とは独立に立っている・決断的な個性の一つである。・・・。その道を,彼(注:バートランド・ラッセル) は,彼の態度が自分にもちきたす諸結果にかまわずにあるいている。一殉致者の身ぶりもせずに,彼は,教職を奪わせ,そして・・・ のかどで監獄のなかへ旅する。(注:ラッセルは第一次世界大戦時に反戦活動をしたためにケンブリッジ大学を追放され,1918年に約5ケ月間,ブリクストン刑務所に収監された。) 』(アインシュタイン教授がラッセル教授の『政治的理想』ドイツ版・1922年* へ書いた序文の一節。) * Bertrand Russell. Politische Ideale. Aus dem Englishen übertragen und eingeleitet von E. J. Gumbel. Mit einem Vorwort von Prof. Albert Einstein. Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichete, 1922. 201 S.
『小泉信三全集・第2巻』(文藝春秋,1968年9月) (2012.3.4)* 小泉信三 (こいずみ・しんぞう,1888-1966):1933年~1946年まで慶應義塾長。父の小泉信吉も1887年-1890年まで慶應義塾長を務めた。
[pp231-251:人性楽観と社会主義] (人性=人間性)(p.? 本を図書館に返却したため不詳) 国家社会主義に対する不満 が様々の形を取って現われつつあることは,たしかにその一つだといって差支えないであろう。物質上の安楽よりも自由に重きを措き,人間の隷属 slavery をもって一切諸悪の根源と認めるギルド・ソシヤリズム は,英本国においてもわが邦においても,共に漸く賛成者を加えようとしている。思量打算を絶したる人間の創造衝動を尊重して,「政治上の最高善は自由なる」こと,「最善に通ずる路は自由の路なる」ことを力説するバアトランド・ラッセル (注:「バートランド・ラッセル」の大正時代日本における表記の一つ) は,その『社会改造の原理』を著わしてから読書界の寵児 となった。 而して近頃ギルド・ソシヤリストやラッセル等が,推重措かざる詩人ウィリヤム・モリス は,一八八○年代の英国に,マルクスとヘンリイ・ジョオジ等の影響を受けて社会主義が復活したその頃から,夙くも(はやくも) 属僚的国家社会主義を嫌って,マルクス系統のハインドマン一派とも,比較的多くヘンリイ・ジョオジの影響を受けたフェビヤン協会一派とも絶縁して,別に一旗幟を翻えした人であった。モリスの理想とする境地 が如何なるものであったかは,彼れが規律井然たる公有公営主義の社会を描いたベラミイの『回顧』に反対して,人間が殆ど何等外力の強制を受けず,その意の赴くままに生活する(というよりも嬉遊する)状態を想像して書いた News from Nowhere によって窺うことが出来よう(本巻三九五頁以下参照)。このモリスの主張に比較すれば,遥かに着実穏当なフェビヤン社会主義 の方が,久しく実際的なイギリス人の喜ぶところであったのは決して不思議でない。然るに今日,労働党の為すなきに失望し,芳ら(かたわら) サンヂカリズムの刺戟を受けた一部のイギリス人は,この平凡着実なフェビヤニズムを排して,その一度忘れたウィリヤム・モリスを新たに再び迎えようとしている。かくして,再び国家社会主義の長短得失が頻りに論ぜられることになったのである。(参考:小泉信三「学問芸術と社会主義 」
野間宏「分子生物学と文学」 [『茨城文学』1975年2月] (2012.2.28)* 野間宏 (1915-1991):作家,評論家。
(p.243) ・・・。私はそのうちようやく,散歩に出られる身体になり,神田まで行きつき,一軒の書店のなかで身を休めていたとき,バートランド・ラッセルの『相対性理論への認識』(金子務・佐竹誠也(訳),白揚社) を見つけた。そして私はこの書物が私の救い手となるにちがいないと,この書物の最初の三頁ほどを読んで行くうちに,はっきりと知らされた。このように,微分,積分などの数式をできるだけ使わずに相対性理論を解説するのは,やはりラッセルのような数理哲学より出発したすぐれた哲学者の手によるほかない,ということを私は考えながら,この書物に十分に時間をさいて読みおえた。 時間をさいてといっても,私がこの書物を読むのにさいた時間は,他の相対性理論の解説書にさいた時間よりも,はるかに短かったのである。そのような類いまれな力 がこの書物には備っていた。しかも私はこの書物を読みながら,自分もまた,大地の上に立って,何故に自分は地球の重力によって,ぎっしりつまっているように見えるがほとんど空虚な空間である地球の中へ,落ち込んでゆかぬのかという疑いを一度なりとも出すことなく,今日まで過ごしてきたのかと,自分自身のうちにまだ生きてとどまっている自然主義的な要素を認めさせられた。何故,地上に立つとき,私は地球の中へと落ちていかないのか。このことについてラッセルは次のように説明している。
「地上に立つときのあなたは,電磁力の作用をうけます。なぜなら,あなたの足下の電子や陽子には,ちょうど地球の重力に打ち勝つにたるだけの斥力があるからです,これがあなたを,ぎっしりつまっているようには見えるが,ほとんど空虚な空間である地球の中へ,落ちてゆかぬようにささえているものなのです。」
ただ,このラッセルの書物を読むうえで注意すべきこと は,この書物の訳者が「あとがき」で述べているように,解説者のラッセルとアインシュタインの間で,物理学を物質ではなく事象の上に建設するということについての考え(方)のうえで根本的なちがいがあるということ である。ラッセルのこの事象の考えにアインシュタインは反対する。ほとんど同じところにその考えが位置しているように見えながら,その二人の考えのちがいはじつに大きいといわなければならない。
「アインシュタインの考えでは,<事象の諸性質の束(Sens data)>のようなもので物質(物理的物体)を置きかえてしまったら,どうやってまったく同じ諸性質の束が二つあったとしても,たとえばパリのエッフェル塔とニューヨークのそれとを区別できようか,という反論で,それを区別するには束同士の時空的配置の差 を考えざるを得まい,ということです。そしてその時空的な点は,拡がりをもった日常的な事象の性質の束から,理論的に導くのはむりであり,事象では説明しきれない,というのですが,これにはラッセルの方でも異論があるはずです。事実,ラッセルは,事象の束の交錯によって時空的な点(事象は測地線そのものであり,多くの測地線の交わるところを"点"と呼ぶ )を論理的に考えています。 もっともこのような論理的操作を量子力学的レベルに適用するとなると,位置と運動量についての不確定性関係 によって,これらの事象を一点で交わらせることは不可能になるはずですが,ラッセルはその点についてどう考えていたのか不明です。」
測地線とあるのは,彎曲(わんきょく)した時空における惑星その他の運動の最短距離に相当するものである。無機物世界と有機物世界の連続性,あるいは連接 が分子生物学の発展によって,サルトルが『弁証法的理性批判』のなかで仮説として成立させていたところを越えて,仮説の境を脱することが可能となり,実在として,引き出されることとなった全文を閲覧する!
『矢部貞治日記-銀杏の巻』(読売新聞社,1974年5月刊) (2012.2.24)* 矢部貞治(やべ・ていじ,1902-1967):政治学者,政治評論家。東京帝国大学法学部教授,拓殖大学総長などを歴任。従三位勲一等。編者あとがき 」から: 先生は「私は中学生の時から,毎日,日記をつけている」と時々言っておられた。旅行のおともをしたときに,先生が早朝,日記を書いておられるのを見せていただいたこともある。そして,よくわれわれは「あとで出版します」と申し上げると,先生は笑っておられた。大学ノート百冊にわたる日記 の現物を見て,大変びっくりした。多忙なご生活の中で,よくも,こんな克明な記録を書かれたものである。事業は,先生の三回忌の席上での中曽根康弘さんの発言から発展し,多くの方々の御援助で,少しずつ進行した。 ・・・。
(p.30) (1937年)9月15日(水)曇改造(注:雑誌『改造』の発行元) に頼まれたり,国家学会の講演などのこともあるので,その材料に,バートランド・ラッセルの次の戦争(注:即ち,勃発が懸念される「第二次世界大戦) に関するところを読み直した。 (p.31) (1937年)9月16日(木)大雨研究室に行って,ラッセルを読む。これは面白いのだが,現下の時局でこれを公けに言ふことがどうかといふのが問題だ。併し今日も宮沢君に強引に頼まれて結局国家学会で話しをすることにしたのでこれをしゃべり,その上で改造の約束を果すことにしようと考へる。 瓦斯電 からは又二三名卒業生を世話してくれと言って来た。
ロビン・ギル(著),E.O.ライシャワー(序文)『反日本人論』(工作舎,1985年2月) (2012.2.18)* ロビン・ギル(Robin Gill, 1951~ ):著作家。/ロビン・ギルの本
[pp.81-:第二部:日本人と自然,西洋人と自然](p145)
日本人の一般の印象では ,狩猟採集や遊牧の生活より定着生活をする農民のほうが安定している。日本の社会を「農耕型」とし,日本人を世界無比の偉大な百姓思想の民族とする渡部昇一 氏は,弱者も飢えないという'安心感'を「農耕型発想の基本」とさえ断言する。(『日本,そして日本人』) だが,実際には反対かもしれないのだ。 今日,あちこちに国境が引かれ自由な移動が不可能になったアフリカ,そして現代医学(経済,教育などの改革に先立って)の「恵み」や貿易のおかげで人口過剰を来たしたアフリカは,農民におとらず苦しむ遊牧民を生み出した。だが,これは異常な例である。昔から,遊牧民や狩猟採集民族 は,移動するという生活様式と,頼むに足る'大きなクッション'のおかげで,移り気な天候にほとんど左右されずに来た。私が言いたいのは,国によって程度の差はあるにせよ,農業すなわち安定,といった発想はまちがっているということだ。 農業の「成功」は同時に,人口過剰や不安定 という失敗をもひきおこした。だから,その不安定をこえようと,豊作を必死に神々に祈る農民 はイケニエという神との交換物を必要としていた。こういう仮説はありうるし,アメリカ人のフェミニスト派の解釈になると,この農業に起因する不安は,自然を治めよう,支配しようという要求や,農業以前のヨコ型の社会的関係に代えてタテ型の新しい秩序の形成 を促進したということになる。(The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, 1983)。また哲学者のB. ラッセルも『幸福論』(The Conquest of Happiness, 1930)の中で「・・・。農業の開化とともに,人類はその後永く続くことになる meaness(みじめさ・残忍)や misery(苦痛)や madness (狂気)の時代に入ってしまった」ということを一九三〇年に述べている。(『ラッセル幸福論』該当箇所 )
岡一男『古典の再評価 -文芸科学の樹立へ-』(有精堂,1968年6月刊) (2012.2.17)* 岡一男 (おか・かずお,1900-1981):(故)早稲田大学名誉教授。
(pp.8-13:日本文学の思潮) 夏目漱石 は文学の内容を焦点的観念(F) とそれに付着する情緒(f) としたが,そのFおよびfが歴史的社会的に変化することを論じたのや,バートランド・ラッセル がその名著『西洋哲学史-古代より現代に至る政治的・社会的諸条件との関連における哲学史』(市川三郎訳)のまえがきにおいて,その書が西洋哲学史上のそれぞれの哲学者を,「各人の環境の所産として,また各人の属する社会というものにアイマイに拡散した形態で共通している思想や感情がそのひとの中に集中し,結晶したのだというような人間として,哲学者を呈示したい」,あるいは,また「哲学者は結果であるとともに原因である。すなわち彼はその社会環境やその時代の政治・制度の結果であり,また(もし哲学者が幸運に恵まれれば)後世の政治や制度を形成してゆく諸信念の原因となる。」といったのに,深い共鳴 をおぼえる。そしてラッセルのこの文章の中の哲学および哲学者を文学および作家にかえ,夏目漱石の文学論をはじめ,現代の尖鋭で多彩なさまざまな文芸理論を批判的に適用すると,ほんとうにすぐれた,世界文芸を媒介とする日本文学思潮史が生まれるのではないかと思う。
『講座家族3 婚姻の成立』(弘文堂,1973年12月) (2012.2.12)* 上野雅和 (うえの・まさかず,1931~ ):本論文執筆当時,岡山大学教授(民法専攻)。
[pp.183-202:上野雅和「市民的婚姻観の成立と展開--イギリスを中心として--」] (p.199) ・・・。しかし,これに対して,ラッセルは,性愛を婚姻内に閉じ込めること は個人の健全な発展を妨げることになるから,個人は自由な性愛によって幸福を追求する権利をもつべきだという前提から出発する。そこで,婚姻の本質 は,性愛に基づく夫婦の幸福追求にあるのではなくて,子を生み育てるという社会的目的 にあることになる。社会は子供に関係する限りで婚姻に関心をもつものであり,その限りで婚姻は制度化さるべきものとなる。したがって,性交を妊娠と切り離しうる現在では,夫婦が貞操の義務を負う必要はない。彼にとって,夫婦の貞節(marital fidelity)とは,夫は妻以外の女に子を生ませない,妻は夫以外の男の子を生まないという義務にすぎない。 ラッセルの提案 が現実化されるためには,いくつかの前提条件 が要求されるであろう。第一に,男女の完全な社会的平等が達成されていなければならない。第二に,独占欲と嫉妬が性愛から除去されなければならない。第三に,子を産み育てる共同事業としての婚姻を公的行為として公示し,その他のすべての男女関係を私的なものにしなければならない。第四に,夫婦の双方または一方によってもたれる婚姻外性愛は,婚姻関係を損うものではなく,かえって夫婦生活を豊かにし婚姻を深めるものでなければならない。このためには,まず出産・養育が婚姻の中心的かつ最高の義務であって,他のすべての関係は,その性質上,第二次的な意義しかもたないという相互理解が要求されよう。もし,こういう条件が満足されれば,性愛の自由を認めることによって,子を生み育てる社会的共同事業としての婚姻に対する理解と尊敬 は,現在よりもより深いものとなるであろう。なぜなら,自由な合意に基づく性愛と共同生活の経験によって,夫婦として幸福に生活できる確信をもった場合にのみ,子を生み育てることになる だろうからである。婚姻に対する個人の要求 に社会が適応する以外に道がないことを示しているようである。現状のまま進めば,子の養育を,婚姻から分離して親子関係だけの問題として,嫡出子と非嫡出子を区別せずに処理せざるをえなくなるだろう。そうすると,婚姻について国家がすること は,その生死を登録して,親族関係確認の資料を用意することだけになる。婚姻は,当事者が約定した内容によって共同生活を営むだけのものになり,これに対して法が介入する余地はなくなる。 しかし,これは現在の婚姻が優越的・独占的地位を失うことを意味するだけで,それが少数派になることも消滅することも意味するものではない。
木村大治『括弧の意味論』(NTT出版,2011年2月) (2012.2.9)* 木村大治 (きむら・だいじ,1960~ ):京都大学大学院アジアフリカ地域研究研究科准教授。
(p150) ・・・。λ計算 ラッセルのパラドックスが生じない世界 であった。集合という概念を無制限に使い「○○であるようなすべての集合の集合」などというものを考えることを許すと,「「自分自身を要素に含まない集合」の集合」などという妙なものが出てきて,そこから解決不可能な矛盾が生じてくる。これをラッセルのパラドックスと呼ぶのだが,この深刻な事態に対処するため,「『集合の集合』などというものを無制限に考えるのは許さないことにしよう」という原則のもとに数学体系を再構成することが試みられた。言い換えれば,ある集合そのもの(クラス)と,その要素(メンバー)を混同せず,分けて考えようというわけである。これがラッセルの「階型理論」であり,この理論を下敷きにして考えられたのが,先に紹介したベイトソンの「論理階型」である。・・・。
『近代日本文学の諸相- 安川定男先生古稀記念』(明治書院,1990年3月) (2012.2.8)* 有島武郎 (ありしま・たけお,1878-1923.6.9):小説家。志賀直哉や武者小路実篤とともに同人「白樺」に参加。1923年,軽井沢の別荘・浄月荘 で波多野秋子と心中。代表作として『或る女』や『(評論)惜みなく愛は奪ふ』がある。
[pp.135-150:大里恭三郎「「宣言一つ」論 -- 階級への挽歌--」] 有島武郎にあったもの,それは無類の誠実さと迸る激情,及び,時代の思想的動向を逸早く捉える知的な直感力である。そして,それ以外に何もない。・・・。 宣言一つ 」発表後も,有産階級出身 であることに,意味もないコンプレックスを抱き続け,その思想と生活の乖離に悩み,潔癖に,その一体化を目ざした。彼はやがて,農場解放と財産処理 によって,その「生活」を「思想」に接近させるべく,痛々しい努力を続けるのである。・・・。一度その迫害を跳ね返すと,今度は「人間生活の支配者」になる ,「単に主義の人がさうなるばかりではなく,制度そのものが支配者になります。」と語っている。そしてさらに,「私はこの考へを如何なる種類の制度であれ,苟も制度と名の付くものには押拡めて考へることが出来ると信ずる」とも付け加えている。「それが国家主義的制度であらうが,社会主義的制度であらうが,決して除外例となることは出来ません。」と。たしかに,「主義」が制度化されたとき,いかに苛酷な迫害を他民族の上に,また同胞の上に加えるものであるかは,有島死後の歴史も,繰り返し実証してきたところである。有島はおそらく,まだ制度化されていない「主義」から無言の圧迫を受けていたのである。彼の良心的思想はその圧迫を不当なものと退けることはできなかったであろうが,少なくとも,彼の無意識の中では,重苦しい迫害と感じられていたに違いない。それは彼が,ラッセルの「露西亜訪問記」 に,「一つ心を打たれるものを発見しました。」と告白していることからも推測できる。
ラッセルがレーニンやトロツキー を訪問すると,二人とも今露西亜が経過しつつある更新運動に対して絶対のヂャスティフィケーションをなし,世界を救ふの道はこの革命の外にはあり得ぬと確信してゐるのを知ることが出来ます。処が其後マキシム・ゴルキー(ゴーリキー) を訪問した時の記事によると,(略)ゴルキーは(略),お前が英国に帰つて露国の実情を世界に披露する時,露国の人民がこの革命の為めにどれ程痛烈な苦難を嘗めてゐるかといふ事を,強言するのを忘れてはいけないといった言葉が,ラッセルを殊に動かしたやうに見えます。(「ホイットマンに就いて」)
有島武郎にとって,「棄教 」(注:キリスト教の信仰を捨てること) が第一の宣言であったとすれば,「宣言一つ」は第二の宣言であったと言えよう。棄教によって思想の自由を手にした彼は,この「宣言一つ」によって社会「主義」からの思想的自由を自分のものにしようとしたのである。「宣言一つ」は,自ら「良心」,及び,時代の「思想潮流」によって,その思想をがんじがらめにされて,いわば自由の酸欠状態に陥っていた有島の悲痛な叫びだったのである。このように想像するとき,声高で無味乾燥な彼の社会的「発言」などに大した意義は見出せなくとも,「決して自らが迫害者に転じない者があるとすれば,それはただ「独り行くもの」だけなのである」という,有島の苦い「呟き」だけは,私の耳に重く響いて消えないのである。
桑原武夫(編)『中江兆民の研究』(岩波書店,1966年2月) (2012.2.5)
* 中江兆民 (なかえ・ちょうみん,1847年12月8日-1901年12月13日):明治の自由思想家,政治家(第1回衆議院議員選挙で当選)。上山春平 (かみやま・しゅんぺい,1921~ ):哲学者。京都大学名誉教授。
[pp.38-68:上山春平「兆民の哲学思想」] (p.38) 啓蒙哲学者は,洋の東西を問わず,政治色が濃厚である。中江兆民 も例外ではない。彼は多量の政治評論と新聞論説を残したが,まともに哲学のテーマと取りくんだ書物は,翻訳や訳編を除けば,『続一年有半 』だけである。これは,ガンの診断を受けてから一気に書きおろされた一種の遺書 であり,巻末に,「他日幸に其人を得て此間より一のナカエニスムを組織することが有るならば,著者に取て本懐の至りで有る」と記されている。(『一年有半・続一年有半』(岩波文庫)一二六ぺージ。)兆民の多年の念願で あったのに,わずか十日か二十日の間に,しかも一冊の参考書もなく,病苦をしのんで書き上げねばならなかったのは,まことに気の毒なことであった,と『続一年有半』(博文館版)の「発行者序文」に書いているが,こうした一見最悪に近い執筆条件が,思想の核心を何のかざり気もなくぎりぎり決着の形で表現させるというある意味で幸運な結果を生んだのではないか,と私は考えている。兆民の哲学思想の基本的な立場 を示すものとして注目に値する。つまり,彼は,西洋の哲学,とくに観念論哲学の共通の前提をなす神の存在と霊魂の不滅の思想と対決 することを通して,自らの独自な唯物論哲学の立脚点を明らかにしようとしたのである。兆民は,欧米の哲学者たちが,母乳とともに吸いこんで肉体のすみずみにまで浸みわたった迷信に支配されて,神や霊魂の存在を否定すると大罪を犯したように言うのは笑止千万である,と書いているが,これは,西洋哲学思想の根幹にずばりと斬り込む鋭い指摘だと思う。神の存在と霊魂の不滅は,西洋の思想史において,私たち非キリスト教国の住民には想像もできないほど重要な位置をしめている。 アウグスチヌスやトマス・アクナスのような僧侶哲学者の場合はもちろんのこと,近代哲学の確立のために神学思想との対決を余儀なくされたデカルトやカントの場合でさえも例外ではなかった。すくなくとも観念論哲学は,前世紀まで,神の存在と霊魂の不滅の思想を軸として旋回していたといっても過言ではない。・・・。(p.41) 西洋におけるすぐれた哲学思想とキリスト教思想との閑係について,さらにバートランド・ラッセル の場合を検討してみよう。彼は,近著『私の哲学の発展 』(原著:My Philosophical Development,1959/邦訳書:『私の哲学の発展』(みすず書房,1960年)) という哲学的自伝の中で,哲学的思索の出発点にふれ,「私の思考を促した感情的推進力は主として宗教の根本的な教理についての疑いであった 」と書いている。「根本的な教理」とは神の存在と霊魂の不滅の思想に他ならない。一八八八年三月三日から六月三日(注:ラッセル16歳の誕生日前後) にかけての日付のある手記からの摘録によれば,彼は神の存在をニュートン的な仕方で辛うじて肯定し,霊魂の不滅を否定している。私たちには想像もつかないことだが,当時のイギリス社会ではこうした考えでさ危険思想 であった。「私は私の神学上の疑いを気に病んだ。というのは,私はそれまで宗教の中に慰めを見出していたためばかりでなく,また,もしこれらの疑いを人にうちあけるなら,人に苦痛を与え,またその嘲笑を招くであろうと感じたためでもある。そこで私は大変孤立し,孤独になった。私は十六歳の誕生日の直前と直後とに,自分が信ずることと信じえぬこととを書き記した。人に知られぬようにギリシャ文字と発音通りの綴りとを使って」とラッセルは書いている。 彼は当時まだ神の存在を否定する所まではいっていなかったが,まもなくその地点に到達する。「私は神の存在を信じなくなり,十八世紀フランスの哲学者たちの主張にちかいものに進んだ。私は合理主義の熱情的な信奉者であるという点で彼らに一致した。ラッセルの哲学思索の山発点 であった。それは兆民の『続一年有半』の見地とほぼ一致するが,兆民にはラッセルの場合のような神学思想との血みどろなたたかい が欠けている。おそらくこうしたたたかいを通してはじめて,ラッセルのたくましい理論的な思索力がきたえ上げられたのに相違ない。
今田高俊『自己組織性と社会』(東京大学出版会,2005年3月) (2012.2.3)* 今田高俊 (いまだ・たかとし,1948~ ):東大文学部卒。現在,東京工業大学社会理工学研究科教授。2008年に紫綬褒章受賞。今田高俊研究室のウェブサイト
[pp.1-44:序章 自己組織性論の射程] 言葉の世界での パラドクスであり,論理のそれではない. けれども,このパラドクスは論理学の問題 にも通じており,<自己非決定の矛盾>を導く. たとえば,バートランド・ラッセル は集合論を用いて嘘つきのパラドクスの論理学版を発見した. また,クルト・ゲーデル は形式論理の世界において,真偽判断ができない命題がつくれるという「不完全性定理」を証明し,形式論理が自己を検証できない,すなわち自己非決定に陥ってしまうことを証明した. これら両者に共通しているのは,論理の世界に自己言及作用 が入り込むと,自己非決定の矛盾が発生することである. 自己組織 というからには,自己が自己を変える論理 を構築できなければならないが,形式論理においてはそのような自己を決定できない. 自己言及のパラドクスに ,いわば「臭いものには蓋をせよ」の原則で対処してきた.自已言及の問題は近代科学にとって始末におえない悪霊であり,墓場に葬り続けておく必要があった. けれども,自己組織性の問題が持ち上がるとともに,この悪霊が墓場から抜けだして徘徊し始めた. この悪霊を退治しないかぎり,自己組織性はわれわれの射程に入ってこない。
近畿化学協会(編)『化学の未来へ-ケミカルパワーが時代をつくる』(化学同人,1999年6月) (2012.1.26)* 有本卓 (1936- ):立命館大学名誉教授。1988年~1997年まで東大工学部教授。
[pp.19-35:有本卓「脳からみた未来のロボテックス --人間にどこまで近づきうるか」] チューリング機械のアイデアの源泉 は,そもそも1900年にパリで開催された国際数学者会議 におけるヒルベルトの講演にまでさかのぼることができる。その講演では,20世紀の数学が解決すべき重要問題 が提示されたが,そのなかの10番目 がディオファントスの問題 整数を係数とするn変数の多項式について,その値をゼロにする整数解が存在するかどうかを判定するアルゴリズムを求めよ 」,という問題であった。その背景には,数学の体系を形式化・公理化して,すべての定理を機械的に証明する構想(これをヒルベルトのプログラムという)があった。それはやがて,ホワイトヘッドとラッセルの大著 Principia Mathematica(『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』) で具体化され,自然数の体系の公理(ペアノの公理)と一階の述語論理と呼ぶ論理体系を用いて,数学の命題を表す論理式が公理から導かれる(定理として証明できる)かどうかが注意深く論じられた。1931年 ,ヒルベルトの弟子ゲーテルが衝撃的な定理(不完全性定理)を証明する。すなわち,この論理体系が無矛盾であれば,命題として論理式が整っていても,定理として成立するかどうかの証明も反証もできない命題 が存在しうることを示したのである。チューリングはこのことから逆に,理論的に証明できることは手続的に書き下せるはず であり,機械がこれをシミュレートできないはずはないと確信したのであろう。よく考えると,無限長のテープと機能表(シンボルの変換則)をもつチューリング機械は,自然数に関するペアノの公理と一階述語論理の公理をツール化したものと見なせる。人間が論証しうることは機械もたどれるはずであり,こうして人工知能の思想的基盤が与えられた のである。 以来,人類が共有できる論証(これをアルゴリズムといってもいい)はすべてチューリング機械の機能表で書き表せるのだが,現在は(恐らく将来も)逆に,チューリング機械によって記述できるものをアルゴリズムと呼んでいる。
島崎藤村『感想集 春をまちつつ』(アルス,1925年3月刊) (2012.1.25)* (島崎藤村 , 1872年3月25日-1943年8月22日):詩人,小説家。春を待ちつつ /YouTube:「初恋」朗読 /小林旭(歌)「初恋 」)
『島崎藤村集』p.280) カーライルとホイットマン(『春をまちつつ』の一節)
人は愛情の厚薄によって非常に異なって見えるものだし,同じ人でも時によっては非常に異なって見えるものだ。この点に関して,カーライルとホイットマン とは両極端の例を見せて居る。カーライル に取っては,殊にその晩年には,多くの男や女が厭わしいものであった。それが彼を導いて人間生活の著しい破壊者にのみ満足を覚えさせるようになった。彼が戦闘と強暴とを好んで,弱きもの・虐げられたものを排したのもそれに基いて居る。晩年に於ける彼の道徳も彼の政治論も,殆どすべての人間に対する憎悪によって鼓吹された。そこへ行くと,ホイットマン はその正反対で,男や女の大衆に対して,広い温かい感受性をもって居た。彼の想像の前にはすべてが歓びの対象であった。多くの人が唯美しく愛すべく思うもののみに感ずるような歓びをホイットマンは殆どすべての人間に感じた。この広い,愛好の念から楽天主義が生まれ,デモクラシーの信念が生まれ,平和と愛とに共存する道も容易であるとの確信が生まれた。彼の哲学も,彼の政治論も,カーライルと等しく,普通一般の男や女に対する直角的な態度に基づいて居る。』と。
この言葉は面白いと思った。そればかりでなく,新しい理解の方法によって人間の生活を見直そうとする温かい心が分かって来てから,それまであまり注意する気にもならず,何となくとげとげした英吉利人(イギリス人)のように思って居たラッセルという人が異なって見えて来た。 <原文: カアライルとホヰットマン>
八木沢敬(著)『分析哲学入門』(講談社,2011年12月/講談社選書メチエn.517) (2012.1.18)* 八木沢敬(Tobias Dantzig , 1953~ ):カリフォルニア州立大学ノースリッジ校哲学科教授。ソール・A・クリプキ(著)『名指しと必然性』の訳者
(野家啓一との共訳)。
[ラッセルについてはなんども引用・言及されていますが,ここでは1ケ所だけ,ご紹介(引用)しておきます。 ](p.93) 4の6.分析哲学史的な補足 文と命題をはっきり区別し ,現代論理哲学,言語哲学の基礎を築いたのは他ならぬフレーゲとラッセルである。フレーゲの1879年の著作『概念表記』はアリストテレス的論理学から決別する画期的な論理学の著作であると同時に,文学的,社会科学的,あるいは心理学的なアプローチとはまったく違う ,概念的に厳密な方法で言語の現象を分析する土台を与える非常に重要な著作である。1892年の論文「意味と指示対象」では,「フレーゲのパズル」として知られる意味論の問題に独自の解決案を提唱した。ふたつの異なった「意味」の概念を体系的に理論化したこの提案は,「フレーゲ主義」として今なお広く擁護,論議されている。ラッセルは1903年の『数学の原理』(The Principles of Mathematics, 1903/Principia Mathematica, 3 vols.とは別)という本で,フレーゲの理論と共通点は多いが重要な相違点もある独自の命題理論を提唱した。また,「丸い四角は丸い」に関する問題の解決は,1905年の論文「指示について」(On denoting, 1905)で披露している。2005に出版百周年の行事が世界各地でおこなわれたほど有名なラッセルのこの論文は,英語の定冠詞「the」の画期的な分析だけでなく,命題構造についての広い論証を含む。・・・。
トビアス・ダンツィク(著),水谷淳(訳)『数は科学の言葉』(日経BP社,2007年2月) (2012.1.18)* トビアス・ダンツィク(Tobias Dantzig , 1884-1956):ロシアのラトビア生まれの数学者。アンリ・ポアンカレの下で学ぶ。
(p.17) ・・・。具体的な事柄の後には抽象的な事柄が続く。バートランド・ラッセル は,「キジ の'つがい'と2日間がどちらも2という数の実例であることが発見されるには,いくつもの時代が必要だったに違いない」と言っている。今日,2という概念を表現する方法は,'Pair'(一対),'coup1e'(一対),'set'(一組),'team'(一組),'twin'(双子),'brace'(つがい)など数多くある。(注:2011年12月28日にご紹介した足立恒雄(著)『数とは何か,そしてまた何であったか』では「キジ(雉)」ではなく,「カラス」となっています。ラッセルの Introduction to Mathematical Philosophy, 1919 では「キジ(雉)」となっていることから,「カラス」は足立氏の勘違いか?) (pp.98-99) ・・・。『プリンキピア・マテマティカ 』は今後も長い間,苦しい努力と並はずれた意志を示す金字塔でありつづけるだろう。はたして著者たちは,純粋な推論に支えられて人間の直観に汚されていない構造物を見事に組み上げられたのだろうか? 私にはこの問いに答える資格はない。その全三巻を読み通した数学者に出会ったことがないからだ。数学界に広まっている噂話 によれば,『プリンキピア・マテマティカ』を最初から最後まで読んだことがあるのは,二人しかいないという。その二人の中に著者たちが含まれているかどうか,私には確かめる術はない。この自分の無能さが私の意見に影響を及ぼしているのは間違いなく,だからこそ,ここで自分の偏見に満ちた考えを公言すべきではないと思う。 数学的記号体系の役割 を低く見てはいない。私にとって,この記号体系が持つ計り知れない重要性は,人間の思考の領域から直観を追い払おうという不毛な試みにあるのではなく,新たな形の思考を作り出す上で「直観の手助けをする」限りない力にあるのだ 。(p.212) ・・・。'形式主義者'の側にはヒルベルト,ラッセル,ツェルメロがいる。カントールを擁護した彼らは,カントールの「最小限綱領」を救おうとしたという意味で'メンシェヴィキ'(ロシア社会民主労働党で大衆政党路線を主張した少数派)と言える。彼らは,'全て','集合','対応',そして'数'という言葉を無制限に用いるのは認められないと主張した。しかし彼らの解決法は,集合論を完全に否定することではなく,集合論を純粋な理性に沿った形で作り直す ことにあった。だとすれば,理論の基礎をもたらす一連の公理を考案しなければならず,しかも二度と直観に惑わされないよう,純粋に'形式的'で論理的に一貫した一連の公理の図式を,内容を含まない単なる骨組みとして作り上げなければならない。そうした包括的で一貫した体系を組み立てれば,それに基づく無限の算術を一つの基礎に据え,心の平安を乱すパラドックスや矛盾 は二度と起こらないという信念が手に入るはずだ。ヒルベルト日く,「カントールが作ってくれた楽園からは,誰も我々を追放できない」
J-C.ブランギエ(編著),大浜幾久子(訳)『ピアジェ晩年に語る』(国土社,1985年9月) (2012.1.9)* ピアジェ (Jean Piajet, 1896-1980):20世紀において最も影響力の大きかった心理学者(スイス人)の一人。
(pp.194-203:新しい可能性) 可能なことは先行するものの中に予定されているのか,それとも,これは実際に新しいことの創造であるのか 可能なことというのは,仮説の集合であって,その中には偽のものも,真のものもある のです。とすると,これらの誤りは,もし予定 ということばで語りたいのであれば・・・。バートランド・ラッセル です。ラッセルは,生涯の初めには プラトン主義だったのですが,あらゆる論理,数学的観念は何らかの形でずっと以前から先在しており,知覚によって,感性的な現実の所与に到達するのと同じ仕方で,主体はその外側から概念作用によって,それらに到達するのだと考えていました。とすれば,間違った観念はどうすればよいでしょうか。--ラッセルは,偉大な論理学者でしたから,次のように答えました。「間違った観念は,ずっと前から正しい観念と同様,この可能なことのがらくた箱の中に存在しています」。そして次のように付け加えます。「ちょうど白いバラと赤いバラとがあるように」と。その後,ラッセル自身もこのばかげた説は撤回した のですが,これをあげたのは,可能なことの予定 ということが不可能であることを示すためです。これは実際に新しい何ものかへの開放 であって,ごらんのように,四,五歳に始まる骨の折れる開放なのです。・・・。
逸見久美(編)『与謝野寛・与謝野晶子書簡集成』第2巻(八木書店,2001年7月刊) (2012.1.8)* 与謝野鉄幹 (よさの・てっかん,1873年-1935年):日本の歌人。本名は寛,鉄幹は号。与謝野晶子の夫。後に慶應義塾大学教授。文化学院学監。
(p.56) 大正9年1月21日 白仁秋津宛の寛(鉄幹)書簡 (ママ/「梧朗」は「悟朗」の誤記か?) 。
(同じ書物の翻譯に高橋五郎氏の譯本あれども,まちがひだらけの由に候。) )
(p.57) 大正9年1月22日 渡辺湖畔宛の寛(鉄幹)書簡 (ママ/「評」は「譯」の,「梧朗」は「悟朗」の誤記か?) 。内外の形勢,急轉直下し,おもしろキなかに可なり心配な鮎も有之候。新しキ組織や新しキ秩序が短時間にてハ山来上がらず,破壊の時期が長引キ候ことハ面白からず候。維新の変化のごとく圓滑に速に推移させたきものに候。
善積京子(編)『結婚とパートナー関係--問い直される夫婦』(ミネルヴァ書房,2000年5月刊 (2012.1.4)* 大橋照代 (おおはし・てるよ,1941年~ ):麗澤大学教授。足ページ
(pp.40-41) 大橋照枝「進む「結婚の経済学」の議論(1):'子供を生むことを金の儲かる職業とせよ'と訴えたバートランド・ラッセル」 [注: (pp.27-55の)大橋照枝「未婚化・晩婚化・シングル化の背景」の一節から引用したもの。ラッセルは,「予想 」したのであって,'子供を生むことを金の儲かる職業「とせよ」'と訴えたわけではないのでニュアンスの違いに注意する必要あり。] 子育てで経済的不利益 を被ってはならないとする経済的支援が,少子化防止 に最も利いていることがわかる。そして,その経済的支援の乏しい日本で,未婚化・晩婚化・シングル化,そして少子化が加速していることも事実だ。・・・中略・・・。結婚と道徳 』(松下補注:江上照彦(訳),社会思想社,1955年12月刊/現代教養文庫n.128) という著書の中で,次のように述べている。
「子供を生むことが金のもうかる職業だと思えるくらいに報酬を与えない限りは,将来高度の 文明は維持できなくなる公算が大きい。もしそうなったとすれば(子供を生むことが金のもうかる職業となれば)大部分の女性がこの職業(子供を生む職業)につく必要はなくなる。それは職業中の一つだからだ。確かだと思える唯一の点は,女性解放論の今日的発展で,有史以来の男性の女性への勝利を表わす家父長制家族を破壊する上に甚大な影響を与えるであろう。」
バートランド・ラッセルのこの主張こそ,まさに日本女性の今の実態を正確にいい表わしているといえるが,当時の欧米でも,この主張は早すぎたのか,非難を浴びて,ラッセルはニューヨーク市立大学教授就任の約束を取り消されるほど過激であったらしい。しかしその後,1950年にラッセルはノーベル文学賞を授与され,名誉を十分回復している。
足立恒雄(著)『数とは何か,そしてまた何であったか』 (2011.12.28)* 足立恒雄 (あだち・のりお,1941年~ ):早稲田大学理工学部教授,理工学部長を経て,早稲田大学名誉教授。専攻は,代数的整数論及び数学史。足立恒雄のページ
(p.8) 数 を事物の集まりの類 であると明言したのは,イギリスの数理哲学者バートランド・ラッセルが最初ではなかろうか。少なくともラッセルは何度も何度も繰り返しそのように述べている。たとえば,「ある物の数は数の一例 ではなく ,ある数の例 である 」,「数は与えられた個数の要素をもつすべての数を一つの束にまとめるための手段である」,「ある集合の数とはその集合に対等なすべての集合の集合である」など(『数理哲学序説』,1919年刊)(「すべての集合の集合」が矛盾を生じることはラッセルは一番よく知っている人だが,「序説」と銘打った本なので,敢えてこういう表現をしているのであろう。後述の例(ラッセルのパラドクス)参照。)カラス(注:ラッセルの『数理哲学入門』では「雉」となっている。)の2羽も2日も同じ2という数の例である」と書いている。カラスやサルが「数」を知ってるとはしばしば言われることだが,今話しているような意味で言えば,数の実例 を知っているだけで数 を知っているわけではなさそうである。 ・・・。すべての集合のなす集合 を考えると矛盾を生じる」という事実(「ラッセルのパラドクス 」)を指摘したことにより,フレーゲは自分の生涯をかけた仕事は無駄であったと嘆いた(第4章4.1.1項参照)。カントルらも矛盾が生じることに気がついていたというが,とりわけ悩んだ様子もないのは「論理」にかける思い入れの深さ が違っていたのではないかと思われる。 フレーゲは生涯沈痛な面持ちで書斎に篭って矛盾を避けるための研究を続けたとされている。・・・。The Principles of Mathematics '(1903年刊)をほぼ書き上げた時点でペアノを通じてフレーゲを知った。自分の仕事(と等価値以上の研究)がすでにフレーゲによってなされていたことを知ったのだが,一方いわゆるラッセルのパラドクス に気づき,フレーゲに質問の手紙を書くことになる(注:1902年)。簡単に言えば,ある性質 P の外延,すなわち P を満たす対象 x の全体,がいつでも集合をなすとすれば,矛盾が生じるというのである(第1章1.2節参照)。フレーゲは『算術の基本法則 』の第2巻の印刷を終えたところであったが,大いに驚き,呆然自失といった態であった。あわてて修正案を書き加えた「後書き」は次のように書き出される。
学問的著述に従事する者にとって,一つの仕事が完成した後になって,自分の建造物の基礎の一つが揺らぐということほど,好ましくないことはほとんどないであろう。
ラッセルは数学基礎論の歴史アンソロジーを編纂したヘイエノールトに宛てて,フレーゲをまじめに読んだのは自分が最初であったとし,さらに次のように書いた(野本和幸『フレーゲ入門』 )による):
彼のライフワークが完成しようとしており,彼の仕事の大部分は能力において彼に無限に劣る人々のせいで無視され続けてきて,彼の主著の第2巻がまさに出版されようとしている,その折も折に彼の根本的想定が誤っているということがわかったとき,彼は個人的な失望といういかなる感情も押さえ込んで,(注:真実を知るという)知的な歓びをもって応答してくれたのです。
実際には,フレーゲ自身も指摘しているように外延,あるいはクラス,あるいは集合という概念を用いてきた(たとえばデデキントやカントルなどを筆頭とする)すべての人の研究の基礎に疑惑が生じたのであるが,論証の隅々まで厳密な推論に還元することを目論んできたフレーゲにとっては痛手はとりわけ著しかったようである。たとえば,神学にのめり込んでいたカントルはパラドクスの発生を集合論の深遠さを示す新たなる神秘と前向きに受け止めていたらしい。しかし,フレーゲにはそうした感性はなかった。その後矛盾の回避に打ち込んだが,隣人たちにはその姿は暗鬱なものとして映っていたようである。こうしたこともあって,フレーゲには悲運の人というイメージがつきまとっている。(松下注:ギリシヤでベストセラーとなっている Logicomix; a Epic Search for Truth Wikipedia の説明 公式」ホームページ 関係動画 関係画像
「(YuTube 掲載の抒情詩)Spinoza - Lika 8yanagi(八柳李花 スピノザのうた:「ラッセル(著)『西洋哲学史』から」 (2011.12.19)* 八柳李花 (やつやなぎ・りか,1986年5月15日-):日本の詩人で,旧姓は伊藤李花。
八柳李花 という人物についてはまったく聞いたことがありませんでしたが,ウィキペディアによれば,日本の若手の詩人とのことで,現在,同志社大学の哲学科に在籍しているそうです。There is no such thing as free will in the mental sphere or chance in the physical world. Everything that happens is a manifestation of God's inscrutable nature, and it is logically impossible that events should be other than they are. This leads to difficulties in regard to sin, which critics were not slow to point out. One of them, observing that, according to Spinoza, everything is decreed by God and is therefore good, (ここで途中で終わっています。) 自由意志 といったものは存在しないし,物理酌世界 には偶然 というものはない。すべて生起することは,測り知るζとのできない神の本性 の顕現であり,さまざまな出来事が実際にそうであるものと異なることは論理的に不可能 だという。このような考えは,罪 という問題に関してさまざまな困難を導びき出すのであり,批判者たちはいち早くそのことを指摘するのだった。その一人は,スピノーザ によればすべてのことが神によって定められ,したがって善 である,・・・]VIDEO
R. K. マートン(著),森東吾(他訳)『社会理論と社会構造』 (みすず書房,1961年9月第1刷;1990年10月第17刷発行) (2011.12.18)* ロバート・キング・マートン (Robert King Merton, 1910-2003):米国の著名は社会学者で,1956年にアメリカ社会学会会長,1994年にはアメリカ国家科学賞を授与される。
(pp.416-445:第12章「知識社会学」) 科学に対する社会構造(social structure)の影響 は,ただ単に科学者の注意を或る研究問題に集中させることだけに尽きるものではない。この意味で,すでに言及した諸研究以外に,文化的,社会的脈絡が科学的問題の概念的定式化の中にまで入りこむ仕方を取上げた研究もある。例えば,ダーウィンの陶汰説は,競争的な経済秩序という支配的観念をモデルとしているが,この観念たるや利害の自然的同一性という想定をもつが故に,一つのイデオロギー的機能を付与されてきた。また動物の学習に関する研究には国民性が認められるというラッセル の半ば真面目な主張は,国民文化と概念的定式化の関係に対するもう一つ別のタイプの研究を示している(注87)。 ・・・。(注87) Bertrand Russell, Philosophy (New York: Norton, 1927)ppl29-30.(松下注:英国での書名は An Outline of Philosophy , 1927) ラッセルは言う。心理学研究に使用された動物は「何れも観察者の国民性を発揮した。アメリカ人の研究した動物は信じられない程の乱暴さと元気さを示して,気狂いのように走り廻り,最後にうまくチャンスを掴んで希望の結果を達成する。ドイツ人の観察した動物はじっとして思索にふけり,最後に内的意識から解決を導きだしてくる」と。この洒落 を無意味だと考えては誤りであって,科学的問題の選択と定式化に国民的差異がある のではないかということは,これまで繰返し気づかれたが,組織的に概研究されなかったのである。・・・。

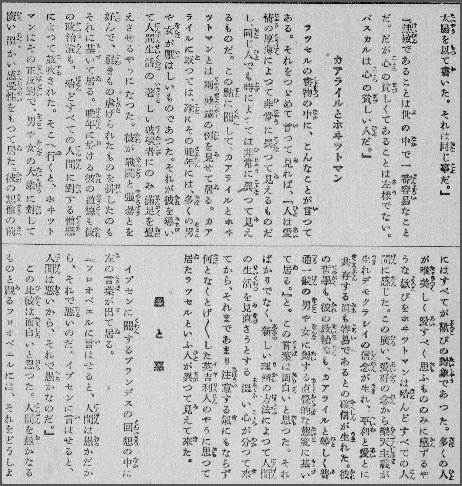 『人は愛情の厚薄によつて非常に異なつて見えるものだし,同じ人でも時によつては非常に異なつて見えるものだ。この點に関して,カアライルとホヰットマンとは両極端の例を見せて居る。カアライルに取つては,殊にその晩年には,多くの男や女が厭はしいものであつた。それが彼を導いて人間生活の著しい破壊者にのみ満足を覚えさせるやうになつた。彼が戦闘と強暴とを好んで,弱きもの虐げられたものを排したのもそれに基いて居る。晩年に於ける彼の道徳も彼の政治論も,殆どすべての人間に対する憎悪によつて鼓吹された。そこへ行くと,ホヰットマンはその正反対で,男や女の大衆に対して,広い温かい感受性をもつて居た。彼の想像の前にはすべての歓びの対象であつた。多くの人が唯美しく愛すべく思ふもののみに感ずるやうな歓びをホヰットマンは殆どすべての人間に感じた。この広い,愛好の念から楽天主義が生まれ,デモクラシーの信念が生まれ,平和と愛とに共存する道も容易であるとの確信が生まれた。彼の哲学も彼の政治論も,カアライルと等しく普通一般の男や女に対する直角的な態度に基づいて居る。』と。
『人は愛情の厚薄によつて非常に異なつて見えるものだし,同じ人でも時によつては非常に異なつて見えるものだ。この點に関して,カアライルとホヰットマンとは両極端の例を見せて居る。カアライルに取つては,殊にその晩年には,多くの男や女が厭はしいものであつた。それが彼を導いて人間生活の著しい破壊者にのみ満足を覚えさせるやうになつた。彼が戦闘と強暴とを好んで,弱きもの虐げられたものを排したのもそれに基いて居る。晩年に於ける彼の道徳も彼の政治論も,殆どすべての人間に対する憎悪によつて鼓吹された。そこへ行くと,ホヰットマンはその正反対で,男や女の大衆に対して,広い温かい感受性をもつて居た。彼の想像の前にはすべての歓びの対象であつた。多くの人が唯美しく愛すべく思ふもののみに感ずるやうな歓びをホヰットマンは殆どすべての人間に感じた。この広い,愛好の念から楽天主義が生まれ,デモクラシーの信念が生まれ,平和と愛とに共存する道も容易であるとの確信が生まれた。彼の哲学も彼の政治論も,カアライルと等しく普通一般の男や女に対する直角的な態度に基づいて居る。』と。