高橋正雄「バートランド・ラッセルのSPD論-紹介と今日的意義」(1)-(3)(日本フェビアン研究所『フェビアン研究』所収)
(1)(v.19,n.9:1968.09, pp.1-9)(2)(v.19,n.10:1968.10, pp.1-11)
(3)(v.19,n.11:1968.11, pp.1-11)
*(故)高橋正雄(1901.11.12~?):東大経済学科卒、九州大学名誉教授。本論文執筆当時は、東北学院大学教授、日本フェビアン研究所理事。因みに、日本フェビアン協会の代表理事は有沢広巳氏。また都留重人氏も理事の一人。
*『日本フェビアン研究』は、v.20,n.3(1969.3)が最終号で、廃刊となったため、本論文のn.4は出版されなかった。
*SPD:Sozialdemokratische Partei Deutschlands)→ https://www.spd.de/">
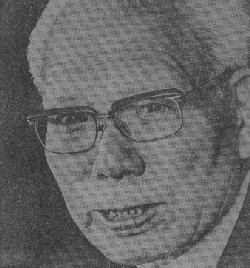
まえがき
いつか、(東京)日本橋の丸善で次の本を見つけた。Bertrand Russell: German Social Democracy; a new ed. of his first book. London; George Allen and Unwin Ltd., 1965(バートランド・ラッセル著『ドイツ社会民主主義(党)』、著者の最初の著書の新版)
最初というのはいつのことかと思って扉をみると「初版は、1896年(明治29年/ラッセル24歳)、Longmans Green 社によってとある。初版から新版まで70年である。著者は「1965年版の序」で次のようにいっている。
ラッセルは、1872(明治5)年生れだから、1896年には25歳(満24歳)である。 (ついでながら、労働党に入党した1914(大正3)年には43才(満42歳)である。そして、労働党政府の向米一偏倒?の外交政策に'あいそ'をつかして、労働党を脱党した1966(昭和41)年には95歳(満94歳)になる。/松下注:「?」は著者が挿入したもの。またラッセルが労働党を脱党したのは1965年10月のこと。)「この本は約70年前に書いた。この70年間に多くのことが起り、多くのことが変った。わたしがこの本を書いたころは、ドイツ皇帝カイゼルが栄光の頂点にあった。かれとかれの政府は、ドイツ社会民主党(SPD)に対し極度に敵対的であった。SPDの方も敗けていずに、利子をつけてその返礼をした。党の人々は、当時は、完全に正統派マルクス主義者だった。かれらは、ドイツを社会主義国に転化させる革命がドイツに起ることを希望していた。わたしがこの本を書いた立場は、正統派リベラリストのそれだった。わたしが労働党のメンバーになったのは、1914年になってからである。わたしはこの本を現在のわたしの意見と矛盾しないものにするために、手を加えることはしなかった。わたしは、この本を、1人のむかしの著者が、1つのすぎ去ったむかしの世界について述べた1つの歴史上のドキュメント(記録)として、そのままにしておくことにした。
わたしがこの本を買ったのは、1966(昭印41)年12月である。「SPD(ドイツ社会民主党)がCUD(キリスト教民主同盟)と大連立政権をつくったことの意味を考えるために」と、わたしは扉のウラに書いている。いま、これを書きながら思うのだけれども、ラッセルが新版を出したのもそういうことと関係があるのではなかろうか。西ドイツの大連立政権について、現在のラッセルがどう思っているか、わたしは知らないが、たしかに「多くのことが起り、多くのことが変った」ということになるからである。
ところで、わたし自身の関心はといえば、この本を読むことによって、「1つの過ぎさったむかしの世界」のできごとについてのラッセルの見方、考え方を知ることだけではない。ラッセルが「ドキュメント」を残している「一つのむかしの世界」と今日の世界がどうつながっているかを知る手がかりを得よう、さらに、日本のむかしと今日とをよりよく理解できる助けを得たいということもあるのである。
1 この本の成立・性格・構成
このように考えながら、わたしは、この本を紹介すること、そして、その今日的意味をさぐること-そういう課題と取りくもうとしている。まず、この本の成立と性格を知るため「初版の序」を見ておこう。
「(この本におさめられた)6回の講義は、1896年2月と3月に London School of Economics and Political Science (松下注:1900年にロンドン大学の一部となる。)で行われた。それはドイツの社会民主党全史を意図したものではない。むしろ今日のドイツの政治情勢を生みだす上でもっとも重要だと著者に思われた歴史の諸局面を浮きぼりにすることをねらったものである。したがって、選択の基準は、終始、現在のドイツにみられる険悪な感情関係をもたらした事件や思惑を強調することに置かれている。それで、マルクス(Karl Marx, 1818~1883)を扱う際にも、わたしは、かれの著作のうちで、主としてドイツの社会主義思想に影響を与えた部分だけに限った。『資本論』第2巻と第3巻には、ほんのちょつぴり触れるだけにした。この両巻は、わたしが見当つけることができた限りでは、第1巻が与えた影響を修正するという点では目だった作用を及ぼしていないからである。」この本の全体を理解する上で有益だから、目次を紹介しておこう。次のようである。
「また、ラサール(1825~1864)についての講義では、わたしは、かれがロードベルトス(1805~1875)に負うところよりも、マルクスに負うところをはるかに強く力説している。ラサール自身に対する、ロードベルトスの影響が重要度の点で小さいからではなく、ラサールの政治上の行動に関する限り、かれがロードベルトスから得た考え方は、あまり果を結ばなかったからである。これに反してマルクスから出ている考え方は、直接にも間接にも、その後のSPDの成長過程で大いに成果をあげた。・・・」
|
第1講 マルクスと社会民主主義(党)の理論的基礎 1 マルクスの修業 (a)ドイツ哲学-へーゲルとフォイエルパッハ (b)フランスの社会主義者、とくにプルードン (c)イギリスの社会主義者。ブレイ、トムソン、その他は主としてイギリスに住んでいたエンゲルスとの交友関係を通じて、おそらくマルクスに影響を与えたであろう。 2 共産党宣言(1848)と史的唯物論 3 1867年の『資本論』で展開されているマルクスの経済理論 (a)価値論と剰余価値論:解説と批判 (b)資本集中の法則:解説と批判 第2講 ラサール 1 マルクスは学徒であって、扇動家ではない。かれの考え方は、はじめは、ラサールによって勤労者諸階級に持ち込まれた。 2 ラサール煽動活動開始までのドイツ情勢の概観 (a)イエナの戦役と農奴解放。解放戦争(1813) (b)1848年の革命。はじめはブルジョアジーとプロレタリアートの統一運動、しかし、プルジョアジーは、プロレタリアートの要求に直面してびっくりした。そして、多くの収穫が得られないうちに反動の時期はじまる。 (c)1850年代のドイツの経済発展。自由放任主義が広まる。シュルツ・デリッチ(1808~1883)の協同組合運動。 3 1863年と1864年のラサールの著作と煽動活動。全ドイツ労働者同盟。ラサールの死(1864年)。 4 ラサールの思想の源。ロードベルトスとマルクス。 5 ラサールの性格とかれの活動の成果。かれの行動は主として情緒的。 第3講 ドイツ社会主義の歴史-ラサールの死から社会主義者鎮圧法(1878年)の通過まで 1 いろいろの組織。それがマルクス主義を指向して発展。 (a)ラサールの全ドイツ労働者同盟は、1871年まで。フォン・シュワイツアー委員長のもとで、ビスマルク(1815~1898)と終始なれあい。その後、より民主的そしてマルクス派的になり、1875年、マルクスの追随者と合同。 (b)1864年、ロンドンで設立された国際労働者協会(インタナショナル)は、マルクスの指導にしたがい、主として、マルクスの友人リープクネヒト(1826~1900)を通じ、ドイツで大きな影響力を持つ。 (c)ドイツ労働者団体連盟-自由主義の立場からラサールに対抗するため、1863年、ライプチヒで設立された。連盟の指導者べーベル(1840~1913)に(「は」の誤記?)、リープクネヒトの影響を受けて社会主義者となり、自分の追随者の大部分を同調させた。 (d)1869年、連盟はインタナショナルのメンバーと合同して、社会民主労働者党を結成。これに、ラサールの同盟が参加。こうして、マルクスの影響が絶大となった。 2 プロシヤ・フランス戦争。その結果、SPDへの弾圧強くなる。 3 1871年制定のドイツ憲法。 4 社会主義に対する敵意高まる。1878年の例外法(SPD鎮圧法)通過。 第4講 例外法(1878~1890)下のSPD 1 社会民主党に対する一般的反感の主な動機。 (a)無神論 (b)結婚と家庭の考え方 (c)国際主義 (d)革命の弁護 2 例外法の主な条文 3 例外法の実施及び、党の正式の指導者たちの態度 4 ビスマルクの国家社会主義、その結果として党の指導昔と大衆の間に抗争が起る。 5 社会主義に対する警察官の見解と例外法 6 例外法のもとでの煽動。SPDへの投票数の増加。例外法の廃止期限の到来(1890年) 第5講 社会主義者鎮圧法廃止以来のSPDの組織、煽動、戦術および綱領 1 1890年の年次大会できまった組織。近年の警察による、いく度かの解散。その結果として組織の変更。 2 煽動の方法 3 1891年次大会での戦術論争。国家社会主義と革命という2つの対立する傾向。 4 1891年の年次大会で採用されたエルフルト綱領 第6講 SPDの現状 1 ドイツの諸政党、その綱領と勢力。農業関係人口は少ないのに多くの議員が出せる。その結果、農民票の重要性が大きい。 2 農業問題のむずかしさ。 (a)マルクスの経済理論の帰結として (b)1894年と1895年の党大会での討論 3 結論 |
目次からも知られるように、索引まで入れて200ページにならないのに、この本(の扱う主題)は広い範囲にわたっている。扱われてる項目は、どれもがわたしには興味がある。その全部にわたることはできないが、さきに述べた方針で、この本を紹介しながら、その今日的意味を考えてみることにしよう。しかし、正直なところ、73年前の、25才(満24歳)の青年著者の博識と自主的な考え方にわたしは圧倒されている。まちがいなく紹介できるようにつとめることがせいいっぱいということになりそうである。
(注)ごく最近、わたしはある国際学生ゼミで、イギリス労働党員という青年と話す機会があった。その博識と自主的な考え方にやはり圧倒された。「年は?」と聞いたら、「21才」という答だった。大して知識もなく、自主的でもないわたしが感心してもどうということはないが、アチラの人々の青年時代の才能におどろきながら、いわゆる全学連の学生諸君のことなどを考えさせられている。
2 SPDの理論的基礎としてのマルクス主義
(1)哲学と方法論
「われわれドイツの社会主義者は、サン・シモン、フーリエ、ロバート・オーウェンの子孫であるだけでなく、カント、フィヒテ、へーゲルの子孫でもあることを誇りとしている。ドイツの労働運動は、ドイツの古典哲学の後継者である。」というエンゲルスの言葉を引用して、ラッセルは、
「マルクス主義を理論的基礎とするドイツ社会民主主義党は、ただの政党ではない。また、社会民主主義は、ただの経済理論ではない。それは、世界と人間の発展に関する完全自足の哲学である。一言でいえば、それは1つの宗教であり、1つの道徳原理である」といっている。
こうして、かれはマルクスその人の哲学を取り上げる。フォイエルバッハの影響や、当時のフランスの哲学者たちとの接触によって、早くからマルクスは、徹底した唯物論者になっていたことを述べた後、かれは『資本論』第2版の序文を引用する。
「私の弁証法的方法は、根本的にへーゲルのものとは違っているだけではなく、それとは正反対なものである。へーゲルにとっては、彼が理念という名のもとに1つの独立の主体にさえ転化している思考過程が「現究的なものの創造者」なのであって、現実的なものはその外的現象をなしているだけなのである。私にあっては、これとは反対に、観念的なものは、人間の頭のなかで置きかえられた物質的なものにほかならないのである……。」これにすぐつづけてラッセルはいう-。
「その神秘化された形態では、弁証法はドイツのはやりものになった。というのは、それが現状を光明で満たすように見えたからである。しかし、その合理的な姿では、弁証法は、ブルジョアジーやその空論的代弁者たちにとって腹だたしいものであり、恐ろしいものである。なぜなら、それは、現状の肯定的理解のうちに、同時にまた「その否定」、その必然的没落の理解を含み、いっさいの生成した形態を運動の流れのなかでとらえ、したがってまたその過ぎ去る面からとらえ、なにものにも動かされることなく、その本質上、批判的であり、革命的であるからである。」(岡崎次郎訳)
「こうしてマルクスは、論理学的には弁証法的合理主義者であり、同時に、形而上学的には独断的唯物論者である。この2つがいっしょになって、SPDの政策の基礎である "唯物史観" の主な特色を説明してくれる。弁証法はマルクスのように解択すると、そこからこの史観の2つの注目すべき特色が出てくる。すなわち、一切の事物の発展の革命的性格とその不可避性(-ほとんど宿命性-)という待色が。革命的性格は、弁証法的過程の論理的な性質(-生物学的または心理学的な性質とは対立した-)から出てくる。1つの観念と他の観念との間には、父と子の間の場合と同様に、漸進的な移行、感知し得ない有機的成長は不可能である。論理上の諸観念は、ハッキリしており、相互に対立的に明確に規定されていて、ダーウィン流の進化は不可能である。それゆえ、継起する社会の諸段階を、論理的に明瞭な観念の継起的実現と見る歴史哲学は、すべての前進、すべての発展を突然の飛躍によって、革命によって、-必らずしも警察当局がこの言葉に持たせようとしている意味での革命によってではないが-、一つの社会形態から、1つのまったくちがった形態の社会への非連続的な変化という意味での「革命」によって-先行されるものとして考えるようにならざるを得ない。こうして、マルクスの教義においては、資本主義的社会形態は、プロレタリアートの抵抗がはげしくなるにもかかわらず、存続する、突如として "表皮がバラバラになり、資本主義的私有財産制の吊鐘が鳴るまで。収奪者が収奪される" まで。」ここで、ラッセルは、証拠としてエンゲルスの『共産党宣言』の序文を引用している。
「マルクスの教義は、こうして、理論的な意味では、それまでのいかなる世界観も到達したことがないほど、徹底的に革命的であった。しかし、実際は、この革命的傾向は、事物の発展過程の他の性質によって、すなわち弁証法的方法にもとづく内在的必然性と宿命性によって中和され、制御される。すべての変化は事物の現実の秩序のなかに潜む内在的原理にもとづく。へーゲルの言葉によれば、この秩序は矛盾を含む、それは、新らしい秩序によって終局的に滅亡させられる。そして、この新らしい秩序もやがて同様の崩壊と安楽死を経験する、というわけである。それゆえ、なにものも、事物の予定されている進行過程を阻止することはできない。現在は論理的に将来を内包する。そして、将来を現在自身の内的不安からつくりだす。この宿命論こそ、他のすべてにまさって、社会民主主義にその宗教的信念と力を与えた。忍耐心を吹き込んだ。猪突的な革命を決行しようとする、無理もない気持をおさえた。資本主義社会の運命はきわまっている。そして共産主義国家の到来は、運命によって予定されている必然であるというこの信念-すべての正統派マルクス主義者がいだいていた信念-には、ほとんど東洋的(諦観的という意味?一高橋)といってもいい匂いが感じられる。SPDは闘争する勢力として、人間の全情緒に訴える主体として、この信念から計り知れない力を汲み取っている。この信念があったからこそ、党はどんな難境にあっても落ちついてもいたし、賢明にふるまってもいた。この信念こそが、党の活動家たちに、かれらの主義が結局は勝利をおさめるという、不動の確信を吹きこんだのである。」
「しかしこれらの特色は、ある程度まで、新興宗教がみな共通に持っている特色である。マルクスが創りだした運動に独特の形態とプログラムを持たせたのは、かれの唯物論である。精神は物質によってつくられたのだから、それが動きだす究極の動機は、物質的なもののなかに求められる。したがって物体の生産が一切の人間現象の基礎にある原動力である。この論法にみられる、一方から他方への移行関係は、マルクスの著作のどこにもハッキリ説明されてはいない。そして、それを論理的に証明することが不可能なのはいうまでもない。しかし、それはそれとして、こういう論法の帰結は、次のようになる。一切の人間のつくる制度と信念は、終局的には、とことんまで分析すれば、経済的諸条件の、すなわち物体の生産および交換の諸条件の産物である。すべての動機が経済的、すなわち物欲だというのではない。全社会が問題となるような場合には、経済的動機が原動力だというのである。…宗教、科学、国家・・・、要するに、人間活動のすべての部門-が、結局において、経済的原因によって決定される。これが、マルクスの歴史観の大きな指導理念である。時間的にも、空間的にも、人類生活の全局面にわたっている1つの宗教であり、1つの哲学であるマルクス主義が、「資本」に関し、とくに経済学的著作の形をとるようになったのは、この歴史観のせいである。」
「すべての歴史上の時代をみると、生産と交換の支配的様式と、それから必然的に出てくる社会組織とが基礎(その時代の政治的および知的歴史がその上につくられ、そして、その上にあるものとしてのみ説明され得る基礎)となっている。……」ラッセルは、マルクスとエンゲルスがかれらの理論の正しさを証明するのに、先験的な論法によっているのではなく、かなりの歴史的研究を基礎としていることは、「マルクスに対し公正を期するため」に認めている。ただし、その研究はほとんどまったくイギリスに限られていること、マルクスは、イギリスを資本主義の「古典の国」と呼び、今日のイギリスは明日のフランスであり、明後日のドイツであると確信していたこと、かれの事実、典拠、経済理論は、ほとんど常に、当時のイギリスに求められていたこと、抜け目のないランカシャーの製造業者がマンチェスター学派にとって全人類のタイプであったが、マルクスにとってもそうであったこと、マルクスはリカードの弟子たちから、経済上の利殖が経済活動の唯一の動機であると考えることを学んだこと、当時のフランスの社会主義者たちとイギリスの社会から、経済活動が時空の点で人間生活の全面にわたっていること、こうしてマルクスは、経済学の点で古典派イギリス経済学者の教義をそのもっとも粗野な形で受け入れたが、人間論の点でもかれは、人間の経済的動機を一般化して、社会生活のすべての部分を包むものと考えたこと-などに触れたのち、次のようにいっている。
「…1840~1870年のイギリスが、SPDにとってはカナンの地(理想郷)となった。そこからすべての例証が引かれた。世界が現にどうするかについてのすべての理論も、世界がいかにあるべきかについてのすべての理論も、この地を基礎とすべきだということになった。・・・。SPDは、かれらの事実と称するものを、現実の世界からよりも、より多くマルクスから引用しているが、イギリスの諸条件が圧倒的な影響を及ぼしたということは、わたしの考えでは、SPDにとって、多くの混乱とまちがった判断を生む1つの源泉となった。もちろん、多くのドイツの経済学者や支配者の、非常に古風な、家父長的な考え方とくらべてはすぐれていたということの源泉ともなったが。」ラッセルは、マルクスの「最初の大著」として『共産党宣言』をあげ、その「簡潔な修辞、人を刺すような機知、歴史的洞察の点で、今日までの政治的文献の最良のものの一つであると思う」といいながら、それをくわしく紹介したあとで、次のようにいっている。
「このすばらしい著作のうちに、唯物史観の雄壮な迫力の一切が、すなわち、その冷酷な、反センチメンタルな宿命観、道徳と宗教の蔑視、一切の社会関係を非人間的な生産力の盲目的な運動に帰着させることが含まれている。ブルジョアジーの残忍な革命に対し、ただの一言も非難の言葉がない。中世紀世界の牧歌的情景を皮肉をまじえて描いているが、それが失われたことに対し、ただの一言もそれをいとおしむ言葉がない。マルクスにあっては、正義とか道徳という問題は存しない。人間の同情とか道徳感に訴えるということはない。力だけが正しい。共産主義は、その不可避の勝利によって正当づけられる。たしかにマルクスは、資本主義が貧困を生み、共産主義が幸福を生んだと信じている。かれは、かれの論理をしばしば台なしにするほどの僧悪の言葉で「資本」をあつかっている。しかし、かれの学説は、・・・歴史的必然性だけを、生産諸力の盲目的発展だけを基礎としている。この生産諸力こそ、それをつくり出すように強制された来た資本家を呑み込んでしまう。『資本論』では、歴史的の発展のこれらの法則を証明しようとして、広い経験と読書から例を引きながら、入念の努力がなされている。しかし、『共産党宣言』では、証明はされていないが、かれの学説の主要な点は、すでに示されている。…」こうして、ラッセルは、「いまやマルクス体系の想像力に富み、詩的で美しい部面を去って、かれの経済理論の無味乾燥な、たいくつな細部の点を検討しなければならない」といって、SPDとの関係を意識しながら、マルクス経済学を検討する。(以下つづく)
2 SPDの理論的基礎としてのマルクス主義(承前)
(2)経済理論
1)価値論・剰余価値論とSPD
マルクスの価値論と剰余価値論を簡潔に紹介した後、ラッセルは、「それがすべての正当派経済学者によって拒否されてきたこと、そして、剰余価値の定立にいたるまでのすべての論旨が少なくとも一つのまちがいを持っていることを述べ、それを説明して次のようにいっている。
「第一に、商品の価値は費やされた労働の量によっては計られない。マルクスの証明は、方法の点でまちがっている。単に差別を捨象しただけで、われわれが多くのモノの唯一の共通の性質につきあたること、または、われわれがつきあたった性質が適切なものであることが確実だということは、決してあり得ない。次に、マルクスの証明は、実質の点でまちがっている。なぜなら、商品は、他の共通の性質、すなわち効用、つまり欲望をみたす力を持っているからである。・・・」こうして、ラッセルは、マルクス価値論の問題点を指摘していく。それは、人間労働を等質のものに還元するのは不可能であること、マルクスを(が?)どこかで「並はずれて強壮な労働者」の「独占的差益(レント)」を認めていること、商品の生産に社会的に必要な労働というとき、それが、ある商品を生産するのに通常必要とされる労働なのか、それとも、一定の需要量みたすのに必要な労働なのか、あいまいであること、ジェヴォンズの価値論を援用するまでもなく、マルクスが需要を無視しているのは許せない。近代経済学者にとって、非唯物論的哲学者にとっても、需要こそ第一義のものである。ものが生産されるのは、それが人間の欲望をみたすと期待されるからである。欲望がものの効用をつくるのだ。効用がなければ、ものは生産されないこと、労働者のコストは社会的に必要なコストだといい、それは、労働者が通常生活できる最低のコストだ。このコストは、労働者を健康に保つために必要な生活資料の最低限から成っているというが、この最低限の生活資料は賃金によって得られるのだから、飢餓水準以上の賃金を得ている労働者たちが現にあれば、この議論はたおれること。賃金が飢餓水準以上である場合は、いつでも労働力の生産費は、それだけの報酬をもらえるなら労働を提供してもいいという水準、すなわちマルサス派の人々のいう「安楽の基準」によってきまるということ。賃金のもとになる生活水準が飢餓線であるか、それより高いかは論理的必然の問題ではなくて、歴史上の事実の問題であること。この点で、マルクスは無視しているが、「資本主義国家」の内部においても可能な労働組合やその他の方法によって、賃金を引き上げる可能性があること。マルクスとその追随者がストライキや労働組合と対立しているものとしての政治行動や国家の行動をきわめて高く評価するのは、この可能性を見落しているからであること。
剰余労働・剰余価値についていえば、企業家は労働しない(-『資本論』第3巻ではちがうことをいうようになっているが-)から賃金を受けず、したがって企業の収入のうちで賃金でないものは不当利得とみなされている。地代と利子については、この見解はかなり真実に近いが、企業家の指導がなんらかの労働を含まない、したがって価値を増加させないという驚くべき想定をマルクスがしていること。-これらのことを述べたあとで、ラッセルは、たいていの社会主義者がマルクスの不滅の功績だといっている「剰余価値の偉大な発見」は、なんらの理論的妥当性を持っていないといっている。
しかし、ラッセルは、マルクス価値=剰余価値論の意義-ことに実践的意義-を過小評価しようとしているのではない。右(上記)のことにすぐつづけて次のようにいっている。
「ここで、自己満足にふけっているドイツのブルジョアは、勝ちほこって歌をうたい、社会主義は自分自身の矛盾によって亡びるままにしておけばいい、というのがおきまりである。しかし、上に述べて来た程度の知ったか振りでは、マルクスの理論によってプロレタリアートという階級全体がその利害関係に目ざめさせられている事態を説明するには、十分でない。社会民主党員たちは、マルクスの衒学的な排撃者のことに触れる際、言葉ではいいつくせないほどの侮蔑の感情を示すのが常であるが、そのことは、マルクスの学説のうちになにほどかの真理があるにちがいないと思わせてもいいはずである。」ラッセルは、こういって、マルクスのために助け舟を出す。ラッセルは、レント(Rent 差益)と独占という概念を持ち出すことによって、自由競争が行われる面とそうでない面とを区別し、自由競争が行なわれる面に関しては、マルクスの学説は通用する、と言っている。ある企業は、資本・技術の点で、他よりもすぐれていれば、独占レントを得る。ある企業家は、管理経営の点で他よりもすぐれていれば、やはり、独占レントを得る。労働者の場合も同じである。ある労働者は他よりも熟練の点ですぐれていればやはり独占レントを得る。その賃金は、かれの生産費または主活費よりも大きい。「しかし」とラッセルはいう。-
「平均的労働者は、マルクスの'産業予備軍'が存続する限リ、独占レントを得ることはできない。生活必需品の限界効用は、かれらにとっては無限大であり、したがって仕事がどんなにつらくても、それをつぐなって余りがある。それゆえ、労働の供給が過剰である間は-マルクスは、この過剰を資本主義に特有な人口法則としてマルサスから取っている- 労働者は飢餓賃金(松下注:生活していく上での最低限の賃金)を与えられるだけであり、かれの生産物のうちで、かれの生活必要品を越える部分は、地代、利潤または利子として資本家のものとなるであろう。…労働の供給増加がその需要増加を超過している限りは、労働者の間に強力な団結がない限りは、賃金鉄則は、不熟練労働者に関しては、当面のところは真実だということになりそうである。」しかし、ラッセルは、貨金鉄則 Iron Law という名称よりは、グタぺルカ法則 Gutapercha Law(Gutapercha: 硬ゴム様の物質・絶縁体・歯科充てん料(「材料」or「材」の誤記?)などに使う)といった方がいいといっている。なぜなら、この法則が意味している事態に影響を与える条件が、非常に多いからである。労働力の供給増加よりも、需要増加が大きければ賃金が上ること、賃金が上ったからといって、労働者は子供を増加させないこと、さらに、労働者自身でコントロールできることとして、労働粗合が労働力の供給を制限すること、こうして、賃金を企業側が認め得る最高限度に高めること、-そういうことも可能だからである。そして、そうなれば賃金は、飢餓線上にあるとは限らないからである。こう述べたのち、ラッセルは次のようにいっている。
「それゆえ、労働力の価格はその生産費できまる。そして、この生産費は生活最低限の必要品から成る、というマルクスの理論は、きわめて特殊な状況のもとでだけ、正しいものであり得る。それにもかかわらず、剰余価値論は次の点では真理である。すなわち、資本主義生産は、地代と利子の受取人を怠惰にしていながらますます富ませ、そして、それだけ労働者から生産物の一部を収奪している、という点では、また、国全体が貧しく、労働者がほとんど組織(化)されていなかったドイツでは、賃金鉄則は、当時は、ある程度の妥当性を持っていた、ということは確かである。それゆえ、マルクスの教義は、それが自明のものであるようにドイツの労働者に思わせるに足るだけの真実味を持っていた。しかし、不幸なことに、ドイツの労働者たちは、ドイツという資本主義国の具体的条件のもとで、明日に必要やむを得ないことだったとはいえ、労働組合に対し、そして、かれらの生活状態の改善に役立つすべて非政治的手段に対し、きわめて気乗りのしない態度を取った。こうして、SPDが一途に政治的性格を持つようになったのは、主としてマルクス主義のせいであるが、それが、ドイツの労働者にとってどれだけの効能があったか、はなはだ疑わしい。しかし、現在の迫害がつづく限り、SPDがかなりの変化を示すことはなさそうである。」SPDがどんなに迫害されていたか、それは後段でみることにするが、ラッセルは、ドイツでマルクス主義が大きな影響力を持つようになったのは多分にその環境のせいだった、といっている。イギリスでは、そうでなかったことも、やはり、イギリスという環境のせいだと、ラッセルはいうかも知れない。
2)資本集中論とSPD
ラッセルによれば、社会主義の合理的支柱または条件となるものは、政治的民主主義 Political Democracy と集産主義 Collectivism の2つだけである。唯物史観も価値論・剰余価値論も、労働者窮乏論も、社会主義にとっては不要である。こうして、社会主義の理論としてのマルクス主義が立つか倒れるかは、いまや集産主義との関係で、そして、いつもながらSPDの基礎理論という関係で、マルクスの'資本集中論'が支持し得るかどうかにかかって来ている。ラッセルはかなりの紙面を使って、この問題を扱っている。
ラッセルは『資本論』から引用する。
「いまや収奪されるのは、独立自営の生産者ではない。多くの労働昔を搾取している資本家である。この収奪は、資本制生産そのものの内的諸法則の作用によって、資本の集中によってなしとげられる。1人の資本家が常に多くの資本家を殺す。この集中過程、すなわち少数の資本家による多数の資本家の収奪と平行して、次のことがらがますます拡大する規模で発展する。すなわち、労働過程の協業形態、科学の計画的な技術への応用、土地の秩序整然とした利用、個々の労働者によって使われる労働手段が共同でしか使われない労働手段に変ること、結合され、社会化された労働のための生産要素として使われることによって、一切の生産要素が節約されること、世界のすべての民族が、世界市場の網の目に編み込まれること、そして、それとともに、資本主義体制の国際的性格-これらのことがますます拡大する規模で発展する。この変化過程から生ずる一切の利益を横領し、独占する大資本家の数が不断に減っていくのに平行して、貧困、圧政、奴隷状態、堕落、搾取が増大する。しかし、それとともに、労働階級(-、常にその数が増加し、資本制生産過程そのもののメカニズムによって訓練され、団結させられ、組織される労働階級-)の反抗も増大する。資本が一部の者に独占されるということが、生産様式(-資本が一部の者によって独占されているという事態にそって、そういう事態のもとで成立し、栄えて来た生産様式-)に対する桎梏となる。生産要素の集中と労働の社会化が、ついにその資本制的包皮と両立し得ない点に達する、この包皮はばらばらにされる。SPDに強い影響を与えたのは『資本論』第1巻である、とラッセルがいっていることはすでに紹介したが、ラッセルは、この項のはじめに述べたような理由で、右(上記)の引用文を非常に重要視している。この引用につづけて、次のようにいっている。
資本主義的私有財産制の弔鐘が鳴る。収奪者が収奪される。」
「…マルクスが主張するように、すべての産業部門において、労働生産性が企業規模の拡大とともに向上するならば、競争が自由に行われるという条件のもとでは、企業の平均規模がますます大きくならざるを得ない。そして、ついには、国家がそれぞれの産業部門でただ1つの企業をおさえればいい、ということになるであろう。また、こういう事態になるのは、生産費が不断に安くなることの結果であるはずだから、そういう事態は、国富を非常に大きくしているということは明らかである。SPDの人々は、集散主義社会を描くとき、日々非常に少ない時間働けば高度に安楽な生活が得られると考えているが、それは右(上記)のような理由による。もしこの資本集中の法則が一般的な形で無条件的に真実であるならば、そして、マルクスがいつも想定しているように思われるが、それぞれの企業がただ1人の資本家の手にあるならぱ、マルクスの経済理論の他の部分がすべてまちがいであるとしても、私的資本から集産的管理への急激な革命的転化は不可避であるように思われる。」では、こういうマルクスの考え方、ここではSPDによって受け入れられているものとしてのマルクスの考え方は、理論的に、また、実証的に正しいだろうか。
「われわれは、それゆえ、資本集中の法則を注意深く検討し、その真実性の限界と例外を発見するように努力しなければならない」とラッセルはいいながら、次の点を指摘する。
- マルクスは、この法則について長々と述べているが、ここでも厳密な証明を試みていない。また、理論的な証明と統計的な証明とをハッキリ区別していない。統計的証明は、資本集中の傾向を示している点で大いに興味はあるが、それだからといって、それは、その傾向が単一企業出現という点までとまることなく進むと主張することはできない。それは、その点が仮りにあるとして、まだそこまで達していないということを示しているだけである。統計的証明には反するが、与えられた技術条件のもとでは、どこかに均衡点があるかも知れない。その点を越すと、それまでとは違った新しい力が作用しはじめ、規模をそれ以上大きくすることを不利益なものにするかも知れない。この可能性をマルクスは無視している。そしてこの難点をマルクス批判者は利用しないでいる。
- われわれは、-マーシャルを権威として、ラッセルは言う- 収奪逓増の法則が作用する産業部門と、収奪逓減(ていげん)の法則が作用する部門とを区別しなけれぱならない。具体的にはインダストリーと農業とを区別しなければならない。
- インダストリー(生産と流通を含む)では、大規模の有利と優位が明らかである。高価で優秀な機械、研究、広告、分業、熟練という点でそうである。マルクスは、筋肉労働を美化し、資本家的経営者の頭脳労働を蔑視していたから、次の点を十分には評価できなかった。それは、大企業ほどその主脳者が余暇を持ち得ること、それを利用して、日常の小事にわずらわされずに、一般情勢や自分たちの企業の技術的可能性を検討する中枢部をつくり得る、ということである。「大企業の最高責任者が忙しくしているのは、その企業がうまくいっていない印だ」とバジョットは『ロンバード街』のなかでいっている。
- しかし、大規模企業にも不利な点がある。それは、規模の拡大とともにひどくなる。したがって、われわれは、理論的には、技術の一定の条件のもとでは、規模の拡大が有利であることには限界があると、考えた方がいい。不利の点というのは、監督の困難、職長などがずるけること、仕事をいい加減にすること、そして、汚職がだんだんひどくなる、ということである。専門知識の点でも、一般の広告や専門誌が発達してくるので、大企業の有利性はそれほどでもなくなる。
- ラッセルは、その他いろいろのことを述べているが、インダストリーに関する限りは、資本集中法則の妥当性を認めている。
「しかし、全体としては、芸術的生産と、あとで述べる原料生産を除いては、マルクスの法則は真実であるように思われる。技術を一定とすれば、輸送や監督が困難だという事情から、企業の適正規模には限度があるが、この限界は技術が進歩するにつれ、また、競争の結果として、組織を有能に駆使する企業が勝利を得るにつれて、不断に後退していく。こうして、そういう大企業は、おそかれ早かれ、国家と同一の範囲にわたるようになりかねない。企業規模がこの発展段階に達してしまえば、一般に国家管理が有利になり、自由競争と政治勢力の結合した作用によって、それは実現されそうである。鉄道、ガス、水道などでは、ヨーロッパ大陸の多くの政府は、すでにこの方向で一歩踏みだした。トラストや市場独占が多くなるから、やがて国家が右(上記)の部門以外の部門でも同様のことをやり、そして、いい成績をあげるかも知れない。」
ラッセルは、このように、マルクスの資本集中論とその帰結に対し好意を示しているが、重要な点では批判的である。それは、SPDとの関係ではとくに重要である。「資本集中の過程は、マルクスが想定した過程とは非常にちがったものとなっているが、この過程でとくに3点を注目せねばならない。」
と前置きして、次のようにいっている。「第1に、大企業は普通は株式会社である。したがって、大企業の勝利は、個人個人としての資本家の数を必ずしも減少させない。」
株式会社制度が発達してからも、「革命的」な経済変動や恐慌があったから、ラッセルの所説は必らずしもあたっていないみたいだが、ラッセルは、企業がすべて個人企業だったらもっとひどかった、というかも知れない。しかし、ここでの問題は、両者の「政治的相違点」を強調するかどうかである。一方において、多数の小株主が少数の大株主の専制下におかれているということ、その意味では少数の大株主は個人企業家みたいなものだということ、つまり多数の小株主は無力であるということ、他方において、それにもかかわらず、多数の小株主が自分を資本家だと思っていること、したがって、反資本主義的にはならないこと、-この2つを混同してはいけない。ことにSPDの立場からはそうだ、とラッセルは警告している。
「『資本論』第3巻では、マルクスは株式会社の重要性を十分に認識し、正当にも、それは資本主義国家内の社会的生産だといっている。しかし、かれは、集産的生産への転化のこの形態と、第1巻で述べられている形態(1人の資本家が企業の所有者・経営者である形態)との間のきわめて大きい政治的相違点を考えていない。株式会社制度の成長によって支配される経済発展は、漸進的、平和的で、少しづつ進んでいくが、『資本論』第1巻でスケッチされている発展は革命的である、ということをマルクスは考えつかなかったようである。」「第2に、大企業と機械の使用によって、新しい中間階級(-たとえば、監督、技師、熟練機械工など-) は、マルクスがあれほど強調した、"労資問題の尖鋭化をはげしくし、対立する"(事態?)をなくした。」
ちかごろ日本でも「労働者の意識調査」がさかんに行われている。その際、労働者の中間階級化の傾向が指摘されている。しかも労働者というのは、ラッセルがあげている種類よりももっと広い範囲にわたっている。しかし、それはそれとして、ラッセルがこの本を書くときにも、そういう傾向が見られたのだろうか。このことについて、資本主義との関係では、または、SPDとの関係では、第1のところで述べたことがあてはまるであろう。「第3に、国家の企業管理が有利であるということは、その企業がある程度の発展をしているということが前提となっている。ところで、すべての部門の企業-ただ1つの巨大企業-が同時に同じ程度の発展段階に達することはないから、企業の国家管理は産業部門別に、別な時点で実施されねばならない。それは、マルクスが考えていたように、ただ一度の革命的転化によって実現されるものではない。この点は、とくに重要である。なぜなら、それは、資本主義から社会主義への転化の全過程を、SPDが期待しているような、非連続的、弁証法的変化としてではなく、漸進的、有機的発展ならしめるかどうかである。」
ラッセルがマルクスの理論を理解しているように、SPDがマルクスの理論を理解し、そして、ラッセルがマルクスの理論について持っている批判や留保をSPDが持っていなかったとすれば、その限りでは、マルクスの理論はSPDの発展にとって、長期的には必らずしもプラスにはならなかった、ということになる。もちろんプラスの面もあるが、マイナスの面がヨリ大きかったということになりそうである。その点、その後70年間の歴史が「勝負あった」という決定をくだしているというべきかどうか、わたしには一つの問題である。それはそれとして、さきごろ、日本の革新陣営の一部でみられた構造改革論争も、ラッセルが第1、第2、とくに第3として述べていることと関連させて考えると、わたしには興味深いものがある。
なお、ここで触れるのはまだ早すぎるかもしれないが、ラッセルのSPD論が出てからの70年を知る意味で、本誌1968年8月号の「ドイツ社民党の"70年代の展望"」を読んでいただければありがたい。
(3)農業問題とSPD
農業という部門では、一般的にいって、収穫逓減の法則が作用する。つまり規模の利益は、インダストリーの場合のようではない。しかし、マルクスは、「かれのいつもの不注意な一般化するくせ」に支配されて、資本集中の法則が普遍的なものであると考え、それぞれの部門を十分に検討することをしなかった、とラッセルはいっている。
社会民主党鎮圧法が廃止されてからのSPDと農業問題の関係はあとで考察するといいながら、SPDの基礎理論としてのマルクス主義について、ラッセルは次の点を指摘する。
マルクスは、利潤と地代とを明確に区別していないが、すなわち、企業経営から生ずる所得と単なる土地所有から生ずる所得とを、どちらも資本家に帰属するという理由で、十分に区別していないが、その結果として、かれは大土地所有者と大農業経営者を混同している。かれが大規模農業? 農場(ママ/「農業」と訳すべきか、「農場」と訳すべきか躊躇?)としてあげている例は、狩猟用とか、自分の所有地で故郷の空気を吸いたいとかいった、非経済的な動機にもとづくものばかりである。これらのものが、農業における資本集中の傾向の進行を物語るものでないことは明らかである。とくに農業規模の大小は、土地の面積の大小ではなく、資本の多少であることを考えればなおさらである。
マルクスが右(上記)のように考える結果として、2つの帰結が出てくる。1の帰結は、土地所有者としての国家と、農業経営者としての国家を混同すること。土地国有ということは、SPDの他のどんな集産主義的政策よりも説得力を持っていたはずである。ところが、右(上記)に見て来たようなマルクス経済学にとらわれて、SPDはこういう政策を論理的に採用できなかった。なぜなら、土地国有を農業国営と混同すれ、それは、長期にわたる資本集中の傾向が進んだあとではじめて可能になる政策だからである。
もう1つの帰結は、SPDが小農または中農の意義を十分に評価できなかったこと。『共産党宣言』や『資本論』の文面に忠実にしたがって、これらの人々を「亡びゆく階級」としてしか考えなかった。まして、大農場が分解して、経営とともに所有の点でも小中農化が進む傾向がみられることなど、かれらの視野には入ってこなかった。
この点は、土地国有を主張しなかったこととともに、あとでくわしく触れるが、SPDにとって、深刻な意義を持つことになる。ドイツの政治情勢、とくに選挙制度との関係でそうである。
3)結論
ラッセルは、SPDの理論的基礎としてのマルクス主義を結論的に評価して、次のようにいっている。「われわれは、マルクスの経済理論のもっとも根本的な点をすべて検討した。そして、そのどれもが、現状および将来の理論としては厳密な批判に耐えないことを知った。唯物史観は、マルクスが主張しているような精密な形ではどうしても真実だとはいえない。それはまた、生産及び価値を決定する1つの要素としての需要を無視することになる。価値は労働時間だけできまるという理論はあやまっている。とくに、資本家が買うのは労働力であって、労働時間ではないという理論と一致しない。賃金生活者は、資本主義生産がつづく限り、飢餓賃金に釘づけにされるという理論は、完全にまちがっている。イギリス、アメリカ、そしてドイツのサキソニアでさえ、賃金の動向が -経済理論の世界のことはいわないとして- 十分にそのことを証明している。次に、自由競争は必然的に資本の集中を不断に促進するという理論は、農業ではまったくまちがっているし、インダストリーではある程度まで正しいだけである。しかし、たとえば鉄道の場合のように、しばしば企業の活動範囲が国家と同一のものになることは認めねばならない。最後に、大企業への資本集積は必らずしも少数の人の手への集積を意味しない。企業は、株式会社の場合には、多くの株主によって所有されているかも知れない。事実、一般にはそうである。こうして、次のような事態が生じやすくなるかも知れない。すなわち大規模生産が非常に進んでいる国で、資本からの配当に関心を持っている人々の数が、したがってマルクス経済の意味では資本家とブルジョア社会の支柱の数が非常に多くなるという事態、その結果として資本に対する反抗が、おそかれ早かれそうなるはずだとマルクスが主張していたようには、決してはげしくはならないという事態-そういう事態が生じやすくなるかもしれない。それゆえ、マルクス主義の社会主義は、証明された理論の体系としては、拒否されねばならない。しかし、だからといって、集産主義 -人間社会がいかにあるべきか、また、政治および経済情勢の発展によってそれがどういうものになりそうかについての理論としての集産主義- が同時に拒否される、ということには決してならない。必然的宿命論としては、人間がそれを促進するため、または阻止するために、どんなことをしようとも、それが真実であることをわれわれが知っているのだという知識の体系としては、マルクス派社会主義は批判に耐え得ない。その点、それ以前に万人に幸福をもたらす福音として伝導された自由放任主義と同じことだ。しかし、集産主義国家の可能性または望ましさを独断的に否定することも同様に立証不可能である。したがって、決定は、それぞれの特殊事情を細密に考慮した上でなされねばならない。
さきにもいったように、この本が書かれてから70年余になる。その間に「多くのことが起り、多くのことが変った。」マルクス主義と社会主義の関係についていうと、SPDのことはまだそのときでないとして、-マルクス主義を文宇通り実践にうつした「集産主義」としてソビエト社会主義がある。共産党が権力をにぎっている国々がある。これを書いているいま、社会主義のあり方をめぐってソ連とチェコの間に「対話」が行われている。それが、ここで展開されたラッセルのマルクス主義批判と関連づけて考えることができるかどうか、考えるべきかどうかを、わたしは、いま考えている。
「マルクスはある意味で、ドイツの偉大な体系建設者の最後の人である。かれが人間の想像力に君臨し、熱列な弟子たちを持つようになったのは、多分にこの体系によってである。しかし、農業に関してのような誤りを犯したこと、かれの追随者たちが、インダストリーのプロレタリアートの利益以外に、だれのそれをも弁護するのを阻止されたことも、かれの体系のせいである。」
それはそれとして、マルクスの理論の検討をすませたラッセルは、マルクス主義がドイツの土壌で、SPDとして、生きた姿をとるようになる過程を次に追跡する。
 3 ラサールとSPD(承前)
3 ラサールとSPD(承前)
(1)ドイツの社会情勢
マルクスの思想が、ドイツにおいて大きな影響力を持つようなったのは、ラッセルによれば、ラサール(Ferdinand Lassalle, 1825~1864: ドイツの社会主義思想家、労働運動の指導者)の活動によってである。ラッセルは一章をあてて、そのことを一説明している。
1)前史
そのころまでのドイツの情勢は、ラッセルによれば次のようであった。
16世紀はじめの宗教改革と30年戦争は、それまで神聖ローマ帝国のもとで存続してきたドイツの統一を破壊した。30年戦争は、1618~1648(徳川時代のはじめ)にかけての戦争であった。ドイツのカトリック派の諸侯と新教派の諸侯の対立、それに目をつけたオーストリア帝室の野望がもとになってはじまり、デンマーク、スウェーデン、フランスも参加。この戦争の結果、スイスとオランダが独立することになったが、ドイツはさんざんな目にあった。
南部と大部分の西部は、ローマン・カソリックのままで残ったが、北部と東部はプロテスタントになった。東方の、文化発展の程度がもっとも低かったプロシヤは、大きなスラブ系の人口を抱え、まったく封建的な社会体制のもとにあったが、フリードリヒ大帝(1712~1786)の治政によって、ドイツのうちでは、最も強力な王国となった。西部ドイツはフランスとの接触によって急激に文化を進めていたが、東部ドイツは人民の訓練と軍事組織の整備を計り、純枠に軍事的な優越を誇るだけであった。
しかし、ナポレオンの時代になって、ラインランドはフランスに併合され、プロシヤの封建的権力は、しばらくの間は、イエナの戦役(1860)によって撃滅された。この2つの事件は、文明の大きな進歩をもたらした。マルクスの生地であり、ラサールの煽動活動の主たる中心地であったラインランドの諸地方は、政治的自由の喜びを学んだ。そして、プロシヤは純粋に貴族専制の社会組織の弱さを学んだ。ドイツ各州の政府は、ドイツの「哲学者や詩人たちの学校」においてではなく、「ナポレオンの学校」で啓蒙思想を学んだといわれている。つまり思想によってではなく、戦火によって改革の必要を認識させられた。
こうして、農奴は解放された。多くの貴族の封建的特徴は廃止された。財政制度は改善された。そして、プロシヤ王は、もし人民がフランス軍をドイツ国土から追い出すのに協力するならば、憲政を布くと約束した。これらの改革と約束によって、それまではナポレオンに敵意を持たず、むしろ好意的だった人民は、国民的情勢(熱?)にかき立てられ、1813年には、民族的解放のためとともに、政治的解放のために戦った。
しかし、フランス軍が追い出されるや否や、ドイツ国民の独立の恩人である当の愛国者たちが、国王にその約束を思い出させようとして動きだすと、改革の希望は窒息せしめられ、きのうの愛国者たちは危険人物として投獄された。
この弾圧政策は、ラインランドを除くプロシアの全土で成功した。ラインランドでは、経済はかなり発展していたし、フランスの支配が文明をもたらし、封建制を打破した。こういうラインランドだったので民主主義運動は生きつづけていた。ここで1842年に民主主義的な1つの地方誌が創刊され、24歳のマルクスがその協力者、やがて主幹となった。マルクスは、雑誌の廃刊ののち、パリ、(それから)ブラッセル(ブリュッセル)にゆくことになるが、マルクスの『共産党宣言』が現われた1848年1月は、フランスの2月革命の1ケ月前であった。
ここでもラッセルは、かれの著書の目的に忠実である。『共産党宜言』とSPDの関係について、次のように述べている。「注目すべきことに、『宣言』の2人の著者(=マルクスとエンゲルス)のどちらもドイツのことは大して知らなかった。マルクスはフランスとラインランドは知っていた。エンゲルスはほとんどまったくイギリスにばかり住んでいた。亡命生活は、かれらにドイツの経済発展の前途についてほとんど予言者的な洞察力を与えはしたが、当然の必要についての政治的洞察力という点ではマイナスであった。そして、今日でもなお、SPDの非実際的、理論的態度の多くの部分はこういう事情から来ている。」
2)1948年革命のころ
フランスの2月革命につづいて、ドイツの3月革命が起った。はじめは中産階級とプロレタリアート、都市と農村が手をつないでいた。運動は抵抗を許さなかった。プロシヤ王は恐怖に駆られた。そして、立憲議会(-その同意なしには新らしい法律はつくらないと王は約束した-)が普通選挙によって選出された。しかし、封建的貢租の軽減だけを望むにすぎなかった農民の要求が急いで認められると、農民の革命に対する関心は消え去り、かれらは旧体制の側についた。他方、プロレタリアートの社会主義的要求(-もっともその大部分は反動的なものであり、一部分はギルドの(同業組合)維持・復活を目ざすものだった-)が、次第にハッキリしてくるにつれて、中産階級(資本家)はびっくりして、急に反動の陣営に移った。王は冷静を取りもどし、民主的すぎる議会を解散した。そして、王の意見に従順な新らしい議会が選出されたが、それでもなお王にとってまったく申し分のないものになるには元気がよすぎた。そこで王は約束を破り、議会を解散し、クーデターによって反民主的な選挙が新らしい議会を選出させた。この新議会はまったく反動的なものであった。この議会が現在の憲法に同意したのだが、その憲法下にあって、プロシヤの人民は今日もなお(-民主主義の自由と権利が認められていないために-)うめき苦しんでいる。この憲法は権力の大部分を王に、残りを富んだブルジョアの手に与えている。プロシヤのクーデターと同時に、プロシヤ以外のドイツにも反動がはじまった。目ざめたプロレタリアートの要求に当面して、中産階級が急に恐怖におそわれたため、革命はごくありふれた公民としての諸権利も実現しないうちに、挫折してしまった。
マルクスは、これよりさき、急進派民主的な『新ライン新聞』の編集長として帰国していたが、やがて国を去るように強制された。人民の指導者たちは、みな投獄されるか追放されるかした。こうして、1850年までは、民主主義運動のすべての名残りが消え去った。この年、結社を禁止または困難にする法律のたいていのものが議会を通過した。それが、今日(=1896年)にいたるまで労働組合やその他の団体に危険で有害な影響を与えている。
ラッセルは、右(上記)のようにいっている。この法律がどんなものであるか、あとで、戦前の日本とくらべて見ることにするが、わたしは、SPDが、さきに述べたような階級構成の社会(圧倒的に多い農民、そんなに勇敢でないブルジョア、そして少数のプロレタリアート)で、これらの弾圧法規に抵抗しながら、活動しなければならなかったことを記憶しておこう。
3)1860年前後
1850年代のドイツ経済は急速に発展していった。職業選択の自由、居住・移転の自由は、1860年代のはじめに、手工業者の猛烈な反対なしに認められることができた。貿易と産業の発展が、自由放任主義的個人主義のチャンピオンである進歩党を強くした。全経済体制が急速に近代的になっていった。経済学者たちは、イギリスとフランスから、リカードの弟子たちの諸原理を、自由競争と自助という社会的万能薬とともに輸入した。この派の一人で、裕福で慈善家だった経済学者シュルツェ・デーリチュ(1808~1883)は、労働者の協同組合を非常に多く組織し、貯蓄と倹約の効果を宣伝した。かれは、上級の職人や手工業者の間にかなり多数の追随者を見いだした。この人々にかれは、自助と自由競争が有益な効果を持つことを説教した。しかし、より進んだ都市では、人々が、シュルツェ・デーリチュの福音は非常に完全なものでないこと、そして、なにかもっといい方法があるにちがいないということに、間もなく気づきはじめた。そこで、何人かの最ももののわかった人々が、進歩党の人々によって、1862年のロンドン産業博覧会に派遣された。ところが、派遣された人々は、疑いもなく雇主たちを驚かしたにちがいないが、イギリスやフランスの社会主義者たちから学んだ異端的な考え方で頭をいっぱいにして帰国した。こうして、ドイツに新らしい運動が起ることになるが、その主な中心はライプチヒであった。そして、「ライプチヒ労働者協会」が、かれらの取るべき方針についての講義をラサールにたのんだのが1863年2月であった。ラサールの煽動活動とドイツの実際上の社会主義はこうしてはじまることになった。『共産党宣言』が世に出てから15年目である。
こうしてラサールの登場となり、本章の主題が展開されることになるが、ラッセルがベルンシュタイン著『ラサール』から引いている「数字」によると、プロシヤでは人口の半数以上が農業、都市の勤労者の多くは手工業者、工場で働らいて生活していたのは人口の10%にすぎなかった。この階級構成は次第に変化していくが、しかし、そんなに急激な変化ではなかったはずだ、ということも忘れないでおこう。
(2)ラサールとマルクス
マルクスの「影響力の増大、産業プロレタリアート大衆へのその漸進的拡大、かれの階級闘争理論がドイツでは富者によっても、貧者によっても採用されたこと、これらのことがドイツ社会主義(SPD)の歴史の課題である」と言いながら、ラッセルはラサールについていう-、「マルクスの学説を人々の間に投げこんだ最初の人、かれらの階級利害を感ずるように、かれらのミゼラブルな境遇に反抗するように、そして、かれらの諸権利のための強烈な政治闘争に立ちあがるようにかれらを目ざめさせた最初の人-要するに、第4階級(プロレタリアート)をドイツの政治における一つの勢力にした最初の人は、ラサールである。」
1)人物
ラサールは、マルクスより7年おくれて、1825年、やはりユダヤ人の、裕福な家庭に生まれた。ブレスラウ(現・ブロツワフ)では、1848年まで、ユダヤ人は解放されていなかった。そういう事情から彼は家業につかず学界、そして、政界の指導者になることを心がけた。およそ民主的でなく、自己中心、専制的な性格の人だった。「もしわたしが皇太子だったら、骨のズイまで貴族だったろう。庶民の子として生まれたから、民主主義を主張するんだ」
と自分で言っていた。堂々たる著書がいくつかある。公安に有害な言論をしたというので、23歳のとき裁判にかけられたが、そのときの抗弁はすばらしいものだった。彼が実際、運動に関係するようになったのは、1862年、さきに触れた進歩党のために講演をしたのがキッカケとなってであった。そのころ進歩党とプロシヤ政府ははげしく対立していた。それで進歩党は、政府が憲法に違反していることを非難してもらうためにラサールを招いた。進歩党は三級制による選挙制度だったにもかかわらず、議会で多故派を占めてはいたが、国王は議会無視の態度をとっていたからである。ところが、ラサールは、「力こそ正義である。」「一国の憲法は、要するに、その国に存在する諸勢力の集合にすぎない。それらの勢力の合成物にほかならない。」 つまり正義とか合法性とかは問題にならないようなことをいった。「まさに正統派SPDの見解を述べた」わけで、進歩党はガッカリし、政府系新聞は喜んだ。
これにつづく第2の講義では、しかし、ラサールは進歩党のすべきこととして、政府が屈服するまで、議会は一切の審議を拒絶し、予算を拒否せよと述べた。この勧告が賢明であったかどうかは別として、ラサールは、一切の政治的アジテーションにおいて、武力革命ではなく精力的な、しかし平和的な行動をとるべきことを主張している。
ラサールを労働運動・社会主義運動に結びつけるようになったのは、彼れの『労働者綱領』である。それは、1862年春、郊外の労働者の集まりで行われた講義であった。はじめは世間の注目を引かなかったが、パンフレットになって出版されると、社会主義的な労働者を強くとらえるようになった。そして、そういうことがモトになって、「ライプチヒ委員会」から依頼状が送られることになった。
シュルツェ・デーリチュのやり方では不十分だと考えるようになっていたライプチヒの労働者たちは、1862年10月、ベルリンに代表者を送り、進歩党と協力できるかどうかを交渉した。代表団を構成していた3人はみな社会主義者だった。交渉は、予期されていたとおり、失敗した。そこで代表団がライプチヒに帰ってから相談の結果、ライプチヒ姿員会からラサールに依頼状が送られた。それは、次のようなものであった。「労働者運動の諸目的、すなわち、労働者の状態を政治的、物質的、精神的に改善するためにはシュルツェ・デーリチュが推せんしている方法とは別な方法」があるにちがいない、と自分たちは考える。ラサールの『労働者綱領』を読んだ上でのことだが、これらの点についてのラサールの見解を非常に高く評価する。そこで、労働者の諸組織をラサールはどう思うか、これらの組織が何をなすべきか、また、これらの組織の価値について、どんな形ででもいいからラサールが適当だと考える形で意見を述べてもらいたい。-依頼状の内容はそういうものであった。これに対しラサールは、1863年3月1日、『公開回答書』を書いた。
『労働者綱領』と『公開回答書』を次に紹介するが、『共産党宣言』(1848年)が出てから15年にもなるのに、ドイツの情勢は右(上記)のようであったということはわれわれが記憶しておいていいであろう。
2)『労働者綱領』
『綱領』は、ベルンシュタインがいっているように、『共産党宣言』を当時のドイツ情勢に適するように再生したもであった。経済の見方や歴史観の点で、社会の唯一の革命的勢力は労働者階級であることを認めた点で、また、この階級のためになることは将来の人類にためになることだと考える点で、それはほとんどまったくマルクス流であった。しかし、重要な点ではマルクスとちがっていた。
1つは、経済史観または唯物史観をラサールはマルクスほど厳格には考えなかった。経済の代りに法律を持ちだすことがあった。2つは、もっと重要な点だが、ラサールは国家の意義を強調する。マンチェスター派が国家を夜警国家としてしか考えていなかったのに対し、ラサールは、「人類が自由に向って前進するのを助けること」が国家の役割であると考えた。ただし、この役割をはたすことができるのは、普通選挙制のある国家、万人の利害を代表する国家だけである。今日の国家では、機械の発明と工場制の発展は賃金労働者を現実にもっとも強力な階級たらしめた。だから、財産にもとづく選挙制を廃止し、純粋の民主主義を導入することによって、労働者階級を法律上、もっとも強力な階級にすることは、自然でもあり必然でもある。経済の進歩は、すでに革命を実現している。右(上記)のことは、それを法律的に認知するだけのことである。「革命をつくり出すことは不可能だ。社会の現実の状況のなかですでに起ってしまっている革命を法律的に認知し、それを徹底的に押し進めることができるだけだ。」そういう意味では、アークライトの綿紡績機は、1つの革命であった。「革命をつくり出そうと念願することは、歴史の法則をまったく知らない未成熟な人々の愚行である。」 フランス革命は封建貴族に対するブルジョアジーの革命、土地所有者に対する産業の革命であった。1848年に始まった革命(-それを推進するのが勤労階級の政治的役割である-)は大資本家たちに対する賃金プロレタリアートの革命である。しかし、これまで階級の勝利とちがって、プロレタリアートの勝利、財産を相続していない階級の勝利は、(-彼らは取りもどさねばならない特権を持っていないのだから-)全人類の勝利である。彼らの自由は全人類自身の自由である。彼らの支配は万人の支配である。「この使命の高い世界史的な重要さは諸君の全思考力を吸収しければならない。圧制された者の不道徳はもう諸君にはふさわしくない。思慮分別のない者の役にも立たない放とう(放蕩)もそうだ。社会から重んじられない者が持つ無害な軽々しい言行も、もう諸君にはふさわしくない。諸君こそ、現代の天国がその上に建設されねばならない岩盤である。
これは、さきにも言ったように、『共産党宣言』の再版(焼き直し)であるが、それが社会に適応するかどうかは資本主義の発展程度にかかっている。ラサールにとって不幸なことに、その発展ははなはだ不完全なものだった。ラサールが話しかけていた「協会」の名称そのもの(-それはオラニエンブルグ手工業者協会というものだった-)が示すように、労資の対立はまだ発展していなかった。近代労働者だけの運動が成功するチャンスはなかったのである。マルクスとエンゲルスが先進国イギリスから得たヒントに基づいて提唱した政策は、ドイツでは近い将来のうちに成功する可能性はまったくなかった。あとになってラサールが、その本来の主張に反して特異な方法で「革命をつくり出す」ようになったのは、右(上記)のような事情があったからである。「特異な方法」についてはあとで述べる。
3)『公開回答書』
次に『回答書』を見よう。そのころ労働者たちは政治に背を向けるか、それとも進歩党に合流するかで迷っていた。それに対し、ラサールは第3の道、すなわち独自の労働者党をつくれと言った。まず、労働者は賃金鉄則を破らねばならないが、それには協同生産組合をつくり、いま資本家が手に入れている利潤を労働者が自分のものにするようにしなければならない。しかし、それには資本が必要だ。それを調整する唯一の方法は国家からそれを借りることだ。国家が普通の利子率でそれを貸してくれればいい。しかし、資本家たちが支配している国家がそんなことをするはずはない。では、どうしたらいいか。かつての英国の穀物関税反対同盟にならって、普通選挙制の実現だけを目標として、労働者は全ドイツにまたがる全国組織をつくるべきだ。89%から96%の国民は貧しい階級だから、普選の結果はそれらの人々の代表者である国家が生れるはずだ。わき目をふらずに普通選挙制の実現のためだけに全力をつくせ。ほかに諸君がすることはまったくないんだ!」
こうしてラサールの宣伝・煽動の結果として、全ドイツ労働者同盟(協会)(SPD:ドイツ社会民主党の前身)が1863年5月23日、ライプチヒに結成され、ラサールがその規約をつくリ、自分で総裁となり、独裁的な権限をにぎった。もともとラサールはそういう人物だった。
しかし、さきに述べたようなドイツの情勢、階級構成だったので、同盟ははかばかしく拡大しなかった。設立3ヶ月後、そのメンバーは900人、しかもベルリンには支部をつくることができなかった。失望とあせりの結果、ラサールは政府に(ビスマルクに)近づくようになった。当時、政府と進歩党との対立は頂点に達していた。だから、ラサールが労働者党の結成を主張したことは、進歩党からみれば反政府勢力を分裂させる裏切り行為であった。進歩党はラサールをはげしく批判した。それは、ビスマルクにとっては、敵の分裂になるわけだから歓迎すべきことだった。
ラサールは1863年から1864年にかけて、進歩党をはげしく攻撃しながら、他方では、ビスマルクに近づこうとしているように思われたので、一般の人々から疑いの目でみられるようになった。事実、彼れは、「ビスマルクは立派な男子だが、進歩党の人々はひとにぎりの老女にすぎない」といったりした。ラサールとビスマルクの間にどんな交渉があったかは明らかでないが、ラサールとしては普通選挙制を実現させること、国家の資金を生産協同組合に出させることを考えていたかも知れない。「ビスマルクはわたしの全権大使だ」などと彼れはある時言ったが、事実は彼れの方がビスマルク全権大使だったかも知れない。ビスマルクが主人で、ラサールはそれの道具だったかも知れない。その後15年、1878年9月、議会で、ビスマルクはラサールとの会談を回想している。そのなかで次のようにいっている。「ラサールとの会談は政治的接衝といったものではなかった。なぜなら、すべての政治的接衝では、ギブ・アンド・ティク、すなわち交換条件がその背後になければならないが、彼れは提供するなにものをも持っていなかったからだ。わたしは、この上なく魅力のある1人の人間として(の)ラサールとつき合っていただけだ。」「彼れほど知的で才能のある人物をわたしは知らない。……」いずれにせよ、ラサールはその希望の実現があやしくなるにつれ、ますます情熱的になり、自己の偉大さに陶酔するようになった。「わたしが火を点じた文明の力強い国民的運動の火が、わたしがこの世を去っても消えないで、ますます拡大するように!…」といった叫びをあげるようになった。
そういう叫びをあげたあと、彼れはスイスにゆき、そこで婦人問題をめぐる(松下注:ある女性との婚約のもつれから挑んだ)決闘で殺された。(1864年)40歳になっていなかった。
3)ラサールの影響
ラサールの伝記や活動を知っただけでは、なぜ彼れがドイツの社会主義運動に強い影響を及ぼしたかが理解できない。彼れの功績は、当面の成果をあげたかどうかではなくて、彼れが人々に与えた精神的影響が大きかった点にある。彼れは人々をいわば強制して政治情勢をあるがままに認識させた。ラサールという名は、彼れの著作が人々のなかに広がるにつれて、人々の熱情を駆り立てる旗じるしとなった。即座の効果をねらって、独得の才能を揮って、理論的で、しかもわかりやすく書かれた彼れの著作は、現在でも福音書的な影響力を持っている。なん十万という人間を社会主義に転向させた。なん十万の人々が労働者の権利のために闘う際の確信を与えられた。彼れの著作は、ドイツの労働者階級に社会的使命を意識させ、自主独立の労働者党の結成を労動者に教えた。ラサールは、ドイツの労働運動の創始者であり、それは今日でも彼れの個性の刻印を残している。彼れの路線が賢明であったかどうかは別としてである。
最後に、マルクス、ロードベルトス両人とラサールの関係について述べておこう。ラサールは、あわただしい書き方をしているということもあって、その著作で出典を明らかにしていないが、彼れの経済論は、すでに述べたように、マルクスにしたがっている。マルクス同様、絶対的な自由競争を前提としている。その点は、マンチェスター派と同じである。社会主義という点になると、ラサールのそれはマルクスとロードベルトスの組み合せである。ロードベルトスは田舎紳士であって農業経営者であり、保守的社会主義を主張した。それがドイツの国家社会主義の生みの親となった。彼れ(ロードベルトス)の経済学はほとんどまったくマルクスのそれと一致しているが、マルクスの光彩を持っていない。しかし、実際間題となるとマルクスとはちがっていた。彼れは、労働者の状況の改善を望んではいたが、それは、労働者自身によってではなくて、上からなされるべきものであった。経済の面では徹底した社会主義の立揚に立ちながら、政治的に保守派、地主、そして、プロシヤ人であった。
ラサールの路線がマルクスおよびラサール(ロードベルトスの誤記?)のそれとちがうのは、生産協同組合を主張する点である。なおロドベルトスは、独立の労働党にも反対していた。(ラサールの)協同組合論に対する批判は、次の点、すなわち協同組合が、競争する資本家的企業に変質すること、職業の性質からいって協同組合に加入できない人々は、現在のプロレタリアートのようにいつまでも貧困な生活を送らねばならないということ、過剰生産(-それは、マルクスおよびロードベルトスによれば恐慌の原因である-)が避けられる保障がないこと、最後に、これらの協同組合から集産主義社会に移行することは不可能でないまでも困難であること-これらの点についてであった。今日のSPDが、その綱領からラサールの提案を除いているのは賢明だというべきであろう。ラサールは賃金鉄則論に固執したので、労働組合運動の意義を評価しなかった。しかし、SPDの指導者はそれを評価するようになっている。なおラサールは、運動を1つの目標にしぼるべきだということを主張したが、SPDは、その全綱領を一挙に実現しようとしているために、かえって、さもなければ得られたかも知れない成果をあげ得ないでいる。いずれにせよ、少数派に属する者は、民主主義の条件のもとでは、多くを望み得ないのに、ラサールは、農民や手工業者が大きな比重を占めている「貧しい人々」(-しばしば反動的勢力となる-)のことを十分に認識していなかった。進歩党を条件づきで支持すべきだったのに、そうしなかった点でも、ラサールの路線は批判さるべきであろう。ラサールが普通選挙制を要求してから3年たって、ビスマルクはそれ(普通選挙)を実施した。しかし、平和的な方法で社会主義が実現する日はまだまだ将来のことである。それは、その後のSPDの歴史が物語っている。
いずれにせよ、ラサールの刻印を十分に理解することなしに、SPDの歴史を理解することはできない。(つづく)
★松下注: (つづく)となっているが、『フェビアン研究』は、v.20.n.3で廃刊となっている。そのこととつじつまあわせをするためではないかも知れないが、この3本目の論文の最初に、全3回分の目次を再編成し、下記のようにして、2本目の論文の結論を、本論文(全3回)の「結論」に変更している。
本論文(全3回)の目次(再調整後)
まえがき
1 この本の成立・性格・構成
2 SPDの理論的基礎としてのマルクス主義
*↑以上、(1)9月号、(2)10月号掲載論文
3 ラサールとSPD
(1)ドイツの社会情勢
1)前史
2)1948年革命のころ
3)1860年前後
(2)ラサールとマルクス
1)人物
2)『労働者綱領』
3)『公開回答書』
(3)ラサールの影響
*↑以上、本号(3)(11月号掲載論文)
1)価値論・剰余価値論とSPD
2)資本集中論とSPD
3)農業問題とSPD
(4)結論
*↑以上、(2)10月号掲載論文
