小池平八郎「ラッセルの外界論」
* 出典:小池平八郎『英国経験論のおける外界存在の問題』(未来社、1967年3月刊)pp.278-408* 小池平八郎氏(1920~ )は当時、愛媛大学教授?。
* 本論分:東京教育大学文学博士学位論文・昭和40年2月10日授与(乙第5号)
第5章 ラッセルの外界論
第1節 論理的構成としての物体
一 センスデータとセンシビリア
外界に関するラッセルの思想は、その長き哲学的生涯において、いく変遷を閲したと考えられるが、その詳細を時間的に跡づけることは、われわれにとってさして重要な関心事ではない。しかしラッセルの外界論を大きく見渡すとき、われわれはそこに、さまざまな変貌にもかかわらず、底流的に科学的実在論とも名づくべき考え方が一貫して流れていることを看取するであろう。しかしてこの科学的実在論の思想を支えているものこそ、知覚の因果説(causal theory fo perception)ないし知覚の物理的起因(physical causation of perception)といわれる理論であると考えられる。そこで、本章におけるわれわれの仕事は、主としてこの理論の検討にささげられることになるが、しかし他方においてわれわれは、科学的実在論の思想とは相容れない思想をもラッセルのうちに見出すのであって、それの代表的なものが『外界に関するわれわれの知識』(Our Knowledge of the External World, rev. ed., 1926 以下『外界の知識』または External World と略称)に現れているところの、論理的構成としての物体論である。これは超経験的なものを否定せんとする経験論の精神を物体的世界に適用して、物体を以てもっぱらセンスデータからの論理的構成と見る現象主義的立場であるといえる。この思想は、右の書物の初版が出版された一九一四年の元日に、突如としてラッセルを襲ったものだと言われ(My Philosophical Development, 1959, p.105)、そののちに出た『心の分析』(The Analysis of Mind, 1921)においても、この立場は強く保持されているが、爾後の思想からは次第にその姿をひそめて、科学的実在論に徹底する傾向をしめしている。しかも注意すべきことは、現象主義的主張の展開されている前記の書物においても、実在論的ないし知覚因果説的思想が全く否認されているのではない、ということである。そのため、それがしばしば姿を現わして、現象主義の主張そのものを不徹底にし混乱せしめているのである。構成論的な物体観は所詮ラッセルの本音ではなく、かれの基調は『哲学の諸問題』(The Problems of Philosophy, 1912)以来、否、それ以前の数理哲学の時期から、その姿を現わしているところの、実在論的傾向であるといえる。構成論的思想は、いわゆるオッカムの剃刀の原理にしたがって、できうるだけ一元論的経験論に徹底せんと努力したにもかかわらず、かれ本来の実在論的思考に妨げられて、それが失敗に帰したことをしめす一時期の産物である、と考えられる。構成論的現象主義的物体論は、ラッセルにとっては単に克服せられ、のり越えられたところの過渡的な思想にすぎないとしても、そのことは、われわれにとってこの思想が、それを克服したといわれるかれの科学的実在論的思想に比して、より劣った思想であることをかならずしも意味しない。のちに見るであろうように、後者はまたそれ自身のうちに、前者には見られなかった重大な困難をともなっていると考えられるからである。そこでわれわれの関心は、ラッセル的現象主義にふくまれた問題点を指摘することによって、かれがその立場にとどまりえなかった所以を明らかにすると同時に、それの解決が、はたしてかれのいう科学的実在論的方向において可能ないし正当であるかどうか、という点を究明するところにおかれるであろう。
 ラッセル著書解題 |
ラッセルをしてこのような論文を書かしめた動機は何かといえば、それは物理学という学問の方法にまつわっているように思えるあるディレンマを解消して、それに統一的な説明をあたえる道を発見せんとするにある。物理学とは一つの経験科学であると考えられている。経験科学とは観察と実験にもとづいて知識を獲得する学問のことである。物理的知識が検証可能でなくてはならないといわれるのはそのためである。ところで、われわれが観察と実験によって検証しうるものというのは、結局われわれが直接に経験するところの種々のセンスデータと、それらの時間的空間的関係以外のものではない。しかるに他方において、物理学の問題とするところのものは、このような感覚的データではなく、それらを越え、むしろそれらの原因と考えられるような世界、すなわち感覚的世界のかなたに横たわるところのいわゆる物質的世界の消息であると考えられている。物理学の教えるアトムやエレクトロンといわれるような存在は、それ自身は無色、無味、無臭、無音のものとされている。したがってそれらはわれわれの感覚的経験の世界のいずこにおいても直接に見出すことのできないものである。しかしそれ故に物理的世界は非実在的な仮構の世界であるのではなく、反って感覚的世界はそれの結果にすぎぬと考えられるものである。すなわち、物理学はセンスデータを逆に物理的対象から説明しようとする。しかしかく、物理的世界は感覚的世界を超越すると考えられるにもかかわらず、物理学が検証可能なる経験科学たることをやめないかぎり、その知識はどこまでも感覚的経験を基礎としなくてはならない。しからば、いかにして感覚的経験からそれを越えた世界の真理が知られうるのであるか。物理的世界は感覚的世界の彼岸にあると考えられるにもかかわらず、両者の間には原因と結果というごとき密接な相関関係が存すると考えられ、この相関を介して感覚的経験から物理的世界への推論が可能となる、といわれるかもしれない。しかし間題は、いかにしてかかる相関関係の存することを知りうるか、というところにある。通常二つ以上のものの間にある相関があるといわれるときには、相関する項のすべてが経験のうちにあたえられえなくてはならぬ。しかるに感覚的経験を超越した物理的世界なるものは、定義によって経験不可能なものであるとすれば、それが感覚的事物に対して相関の関係にあることを経験的に確めることもまた不可能である、といわなくてはならない。しかしかく、物理的世界が感覚的世界への相関を失うということは、物理学が検証可能性という性格を失うことであり、ひいては経験科学たることを放棄することにほかならない。--物理学がもつ方法上のディレンマというのは、この点に存するのである。
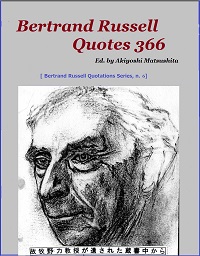 ラッセル関係電子書籍一覧 |
物理的対象をセンスデータの関数として表わそうとする試みにとって、まず問題となることはセンスデータといわれるものの性格である。ラッセルは、センスデータとはわれわれの感官に直接あたえられるものを意味する、という通例の定義をそのまま受け容れた上で、自己の論を進めているように思われる。(尤も、感官にあたえられない、いわゆる内部知覚的なセンスデータについては、おそらく物理学とは無関係と考えたのであろう、かれはなんらふれるところがない。)そこでまずかれの主張することは、センスデータとは物理的な存在である、ということである。センスデータを心的なもの、ないし主観的なものと考えるのは誤りであって、それは正に物理学の現実的題材の一部をなすものにほかならぬ。では「物理的」と「心的」とは定義上どのように区別されるのであるか、という問いに対してラッセルは、「物理的」という語は、予備的な議論においてはつねに、『物理学によって取り扱われるもの』を意味するものとして理解すべきである」と言う(Mysticism, p.144)。これは一見、定義さるべき語を、定義する文章のうちにふくんだところの誤れる定義のように見えるかもしれないが、しかしここにいう「物理学」とは「物理的」なものに関する学問、というような意味にとるべきではなく、客観的な事実として、数学、生物学、化学等とならんで物理学という学問があり、物理学者とよばれる一群の人間が存在していること、かつこの意味の物理学がこの現実の世界を構成するあるものについての学問たることは、だれしも認めるところであって、「物理的」なるものとはこの意味の物理学の題材となるものの総称である、というのである。しかしこれだけでは、たとえば、「生命」とは何か、に答えて「生物学の題材となるもの」と言うにひとしい、肝心なことはその題材がいかなる性質のものかということであり、それこそひとが「物理的」という語の定義に対して求めているものだと考えられるのであるが、しかしこの意味の定義をくだすことは「予備的な議論」の段階では困難であり、また必要でもない、というのであろう。それにしても「物理学によって取り扱われるもの」というごとき形式的な定義を以てしては、「物理的」なるものの本性についてのわれわれの理解はほとんど進展しないであろう。これに反し「心的」という語については、かれは実質的な定義を指向しているのであるが、しかしそれには前者以上の困難のともなうことを自覚し、またそれに立ち入る必要もないとして、さしあたり独断的に、「わたしはある特殊(particular)を、それがあるものを覚知している(aware)時に「心的」とよぶことにする」と言っている(ibid., p.144)。かく、ある特殊が心的とよばれるのは、それがなにものかを覚知するかぎりにおいてであるとすれば、心的なるものと物理的なるものとはいかなる区別と関係に立つことになるか。ラッセルによれば、両者はかならずしも相互に排他的ではないが、しかし両者が重複すると考える理由を自分は知らない、と言う。その意味は、両者は論理的には両立しうるけれども、事実において両立していると考える理由がまだ見出されない、というのであろう。そうとすると、ある物理的なる特殊がなにものかを覚知することによって同時に心的なものでもありうるわけであって、このことはつぎの、センスデータが覚知から独立に存在しうるか、という問題に関係をもっている。
ラッセルはこの論文において、センスデータとならんで「センシビリア」という術語を導入している。センシビリアとは「センスデータと同じ形而上的および物理的地位を有しながら、かならずしもなんらかの心に対するデータたるを要しないような対象」である、と言う(ibid., p.142)。センシビリアは心によって覚知されることによってセンスデータとなる。覚知されぬセンスデータというのは形容矛盾であるが、しかし覚知されぬセンシビリアは存在しうる。両者の関係は男と夫の関係に似ており、男は結婚関係に入ることによって夫となるごとく、センシビリアは覚知の関係に入ることによってセンスデータの地位を獲得するという。しかしこのアナロジーはあまり正確ではないというべきである。なぜなら、男は夫となることによって新しい地位を付加されると考えられるからである。しかるに、心はセンシビリアを覚知することによって、何物かをセンシビリアに付加するのではない。右の定義において、センシビリアがセンスデータと同一の形而上的物理的地位を有するといわれたのはそのためである。それ故センスデータそのもののもつ種々の特徴はまた、そのままセンシビリアのもつ特徴にほかならない。ただその特徴がなんらかの心によって覚知されるか否か、という相違が存するだけである。この意味において、センスデータは心的覚知を超越した客観的存在であるといわなくてはならない。しかるにそれを心的主観的な存在のごとく考える説があるのは、ラッセルによれば、二つの混同を犯した結果であるという。一つは生理学的な主観性と心理学的な主観性の混同である。センスデータが主観的であるというのは、ただ生理学的な主観性の意味においてのみ真実である。その意味は、センスデータが特定の感覚器官、神経、脳に因果的に依存するということである。一般にセンスデータが存在するためには、そのセンスデータを自己の現象とするごとき特定の物質のほかに、種々の仲介物を必要とするが、後者のうちには霧や眼鏡のほかに眼、神経等の生理学的条件がふくまれている。生理学的主観性とは、これら生理学的条件の変化に応じてセンスデータが変化を蒙ることを意味するのである。けれどもこのことは、心理学的主観性とは全く別個のことがらである。なぜならば、かくセンスデータがそれに依存するといわれる生理学的条件なるものは、それ自身物質的世界の一部にほかならないからである。もう一つの混同とは、感覚作用(sensation)とセンスデータとの関係に関するものである。ここで感覚作用というのは、主体がセンスデータを覚知するという事実を指す。したがってそれは主体をその構成要素としてふくむという意味において主体に論理的に依存する、と考えられるのに対し、センスデータとはかかる感覚作用のなかで主体に対して立つ対象である。それ故センスデータは主体とは別の存在であり、主体を自己の内にふくむものではない。この点においてそれは信念や意志と異なるものであり、後者は主体を自己の部分としてふくむ故に主体に依存すると考えられ、主観的といわれるのである。このようにしてセンスデータが感覚作用から区別せられ、他方生理学的主観性と心理学的主観性の意味が区別せられるならば、センスデータが心的ではなくて物理的なる存在たることが確定するはずである、とラッセルは言う。
しかしはたしてそうであろうか。まずセンスデータと感覚作用とを区別し、心、主体の外にセンスデータを位置づける思想は、かれがムーアから学んだものであり、すでに『哲学の諸間題』において明確に打ち出されているものである。しかしこの考えは主として日常的な言語形式の考察からみちびきだされたものであって、深い哲学的洞察の結果とは称しがたい。われわれが「色の感覚」とか、「音の感覚」というごとき表現を用いるとき、「色」と「音」とは異なるけれども、しかしそれらを「感覚」するはたらきは同一である、したがって感覚作用そのものは色や音から区別されなくてはならない、という解釈が生れるのは一応尤もである。というのは、たとえば「色の選択」とか、「音の選択」という場合、選択作用とは別に色や音の存在することについてはまず問題がないからである。しかしこれは言語形式上の類似に欺かれて事態を見損ったものというべきであって、感覚の場合については後の例におけるほど容易に作用と対象とを区別しうるものではない。選択されない色や音はいくらも存在するといえるけれども、感覚されない色や音の存在をいかにして知ることができるか。ラッセルは色や音のセンスデータはそれを覚知する主体の概念を論理的に内包しないというが、これは前の、センスデータとは主体に覚知されたるセンシビリアである、という定義といかにして調和しうるのであるか。おそらくかれの答えは、覚知の作用はセンシビリアの存在的特徴になんらの変更をもおよぼすものでないから、センスデータといっても存在的にはセンシビリアと同一性格のものである、だから、センスデータが覚知の関係をはなれ、センスデータたる地位から退いたのちにも存在しつづけるということを否定するアプリオリの理由は存しない、というのであろう。それではそもそも、覚知の作用がセンシビリアの存在性格に無影響であるというごときことをいかにして主張しうるのであるか。われわれが色や音を感覚するという場合、言語的表現にとらわれることなく事態そのものを直視するならば、覚知の作用と覚知される色や音とは一体不可分のものであって、色や音の存在をはなれた純粋な覚知作用そのものというごときものを考えることはできないというべきであろう。かれものちにいたって、この感覚作用とセンスデータの区別を撤回せざるをえなくなったのであるが、それはまことに当然というべきである。一九二六年の『外界の知識』改訂版においてラッセルは、「ある著者によれば--私も以前はそれにふくまれていたが--心的出来事である感覚作用と、一片の色とか音とかであるその対象とを区別することが必要である。……〔しかし〕わたくしは『心の分析』〈たとえば一四一頁以下)において説かれたような理由によって、この区別を正当でないと看做し、センスデータ(ム)を感覚作用と同一であると考えるにいたった。」と告白している(p.83)。しかるに、この区別にして否定せられるならば、センスデータとセンシビリアとの区別もまたその意義を喪失せざるをえぬであろう。なぜなら、ラッセルがとくにセンシビリアの概念を導入しえた所以のものは、センスデータなるものが心の覚知作用から独立に存在しうるものである、という前提に立つからである。もしこの前提を疑うならば、覚知と無関係なるセンシビリアの概念もまた疑われなくてはならない。
ラッセルは、センシビリアがセンスデータたることなしに存在しうるかという問題と、センスデータが心的か物理的かという問題とを混同してはならない、と言う。かれはセンスデータが物理的たることを主張するけれども、しかし、それはセンスデータたることを止めたのちも不変的に存続するということはおそらくないであろうと言う(Mysticsim, pp.144-145.)。もしもセンスデータが心的であれば、それがデータでないのちも不変に存続することは論理的に不可能であるが、かれはそれを心的とせず物理的とするのであるから、それの不変存続の否定は論理的理由によるのではなくて単なる経験的理由による、換言すれば、経験的な因果法則からの確率的な推理として主張されるにすぎない、というのである。われわれはこのようなかれの主張に対しても疑問なきをえないであろう。まず、かれのいうごとき「心的」の定義から、いかにして、センスデータが心的なるときはそれの不変的存続が論理的に不可能である、といいうるのであろうか。前述したラッセルの定義にしたがえば、心的なるものとは覚知するもの(特殊)を意味した。したがってセンスデータが心的であるということは、それがなにものかを覚知するものであるということである。しかし他方において、センスデータとは(定義によって)覚知されるものであるといわれる。そうすると、「心的なるセンスデータ」とは「覚知するとともに覚知せられるもの」を意味しなくてはならぬ。そこで、心的なるセンスデータがデータでないのちにも不変的に存続することが論理的不可能事であるというラッセルの主張は、言い換えれば、覚知するものは、それが覚知されることを止めても存続すると考えることは矛盾である、という主張となるであろう。が、はたしてそういえるであろうか。われわれは覚知されることによってのみ存在すると考えられるものが、覚知されることを止めてのちも存在する、と考えることが自己矛盾たることは疑いえないけれども、しかし、覚知するものが、覚知されることを止めたのちも存在する、と考えることは自己矛盾である、とかんたんに断定することはできないであろう。しかるにかれは、あたかもそれを自明的な真理であるかの如くあつかっているのである。心的なるものが覚知されぬ時も存在する、ということが明白な自己矛盾であるといえるためには、かれがのちに採用したごとく、心的なものとは直接覚知されるものだ、という定義に改められる必要があるというべきである。
つぎに、センスデータが物理的であるというラッセルの主張を認めるとした場合、それの不変存続が経験的確率的に否定せられる、というかれの主張はいかなる意味であるか。かれはセンスデータが生理学的条件に依存するという意味におけるセンスデータの生理学的主観性を説いた。これは、経験的な因果的依存の関係である。かかる依存関係の存在することにもとづいてわれわれは、生理学的条件が存在しなくてもセンスデータは不変的に存在するということのインプロバブルなることを推論しうるというのであろう。ところがラッセルはすこし前のところで、「われわれは脳、神経、感覚器官でかこまれていない場所から物がどのように現象するかを確める手段をば有しない。われわれは身体を離れえないからである。しかしながら、そのような場所においても物がある現象を呈すると考えることは、連続性にもとづいて不合理ではない」と言っている(ibid., p.143)。これによると、ある現象(センスデータ)は生理学的条件が存しなくても不変的に存続することがプロバブルとされる。ここで「ある現象」と特に断ったのは、おそらく第一性質的な現象を指すのであろう。そこでこの主張と調和的に始めの主張を解すべきだとすれば、そこにおいて不変存続がインプロバブルだとされるセンスデータとは、すべてのセンスデータを意味せず、その一部--おそらく第一性質的なものを除いたもの--を指すということになる。
ところで、かく生理学的条件が存しなくなるということは、センスデータたることが中止されるところの唯一の場合であるわけではなく、そのほかに生理学的条件は存在するけれども覚知する心が存しないという場合がすくなくとも考えうるものといえる。これについてラッセルは、右にあげた文章のあとで、「もし--ありえぬことだが--その内に心をもたない完全な人体が存在するとしたら、身体内に心があったらセンスデータとなるであろうようなすべてのセンシビリアがその身体への関係において存在するであろう」と語っている。すなわちこれは、覚知する心がなければ当然センスデータたることも中止されるけれども、しかしかりに身体だけはそのまま存続すると仮定した場合は、すべてのセンスデータは不変的にセンシビリアとして存続するであろう、というのである。そうなるとこの主張は、先の、センスデータがセンスデータたることを止めたのちも不変的に存続することは、インプロバブルだという主張とは、全く相容れないことになるであろう。
このようにして、センスデータがセンスデータたることを止めてのちも不変的に存続することは、インプロバブルだというラッセルの主張は、かれ自身の思想の文脈内においても、つぎのような二重の制限つき--第一に、身体は存在するが心が存しないためにセンスデータたることを止めた場合は、すべてセンシビリアとして存続すること、第二に、身体と心の双方が存在しないためにセンスデータたることを止めた場合も、一部のセンスデータは不変的に存続するであろうと考えられること--でのみ承認されうるように思われるのである。しかし問題は、はたして、このような制限のもとにセンスデータの不変存続をインプロバプルと考えるラッセルの主張自身が、容認されうるかという点にある。第一に、身体器官さえあれば覚知する心がなくてもすべてのセンスデータはそのままセンシピリアとして不変に存続するだろうというごときことが、いかなる根拠にもとづいて主張されるのであるか。われわれの経験しうるものは、すべて覚知されたセンスデータとしての存在である。覚知されえざるものは経験されえないものであり、しかして経験されえないものを経験によって推論することの不可能なるはいうまでもない。心なき身体は、身体なき心と同様、いわゆる「ありえないこと」に属するとしても、しかしともに論理的不可能と断定するわけにはゆかない。けれどもわれわれは、心なき身体に対してもセンスデータが不変的に存在しつづけるであろうと考えるべきいかなる経験的理由をも有しないのである。第二に、身体器官が存在しなくても、あるセンスデータは存続しうるだろうという主張についても、その際身体器官とともに覚知する心も存在しないものとすれば(そしてそれがおそらくラッセルの真意であろう)、第一に対するのと全く同様の批評が妥当することになる。加うるにこの主張は、かれが現象主義的立場に立とうと意気込みながら、他方においてなおかつロック的な第一性質と第二性質との区別を清算しえないでいるという不徹底を暴露しているといわれても仕方がないであろう。以上は二重の制限そのものに対する批評であるが、かかる制限を通過した後に残ると考えられる第三の主張、すなわち身体器官および覚知する心が存しなければ、あるセンスデータは不変的に存続しないだろうという主張は、いわゆる第二性質的なるセンスデータについていわれたものと解せられるが、既述のごとくラッセルは、この主張を論理的理由によらず、経験的確率的なる推理として提示しているところに問題があるといわなくてはならない。センスデータの身体器官への依存関係が、たんに経験的総合的であると考えられるかぎり、後者(原因)が存在しないときは前者(結果)も存在しないであろうことが確率的に推論される、ということについては一応異論のないところであろう。しかしいまの場合は、身体器官のみならず覚知する心も存しないためにセンスデータたることを止めたのちの不変存続の有無が問われているのである。しかるに、センスデータと覚知する心との関係は右のような経験的総合的な結びつきではなく、むしろ一体不可分の関係にあると考るべきものである。両者の結合は経験的偶然的ではなくて論理的本質的なるそれである。この意味において、センスデータたることを止めたのちにおける不変存続の否定は、ラッセルと反対に、経験的確率的ではなくて論理的理由によるというべきである。しかしてこの相違は、ラッセルのいうごとく、センスデータの性格を物理的と見るか心的と見るかの相違にもとづいている。ところで、もしこの相違がたんに規約的な言葉の定義の問題にほかならないというのであれば、そのどちらを採るかはさして哲学的な問題とならなかったであろう。しかしラッセルがセンスデータの性格をとくに物理的と規定したのは、すでに見たごとく、センスデータとよばれるものとそれを覚知する心(主体)との関係についての哲学的な洞察と分析の結果としてなのである。しかしてわれわれがそれに反対するのも、そのような洞察と分析に賛同しがたいからであって、たんなる定義上の争いによるのではない。これを要するに、ラッセルがセンスデータを以て物理的と規定する思想を支えているものは、センスデータを感覚作用から区別するという誤った哲学的洞察である、といわなくてはならぬ。
ところでラッセルは、センスデータの覚知されないのちの不変存続を問題とする際、心の存しない場合と身体器官の存しない場合とをかならずしも区別せず、しばしば両者を同意味に解しているように思われる。たとえばかれは、われわれが推論を用いて知るほかない存在として、他人のもつセンスデータのほかに、「心がたまたま存在しない場所へ現象するであろうところのセンシビリア」があると言い(ibid.,p.150)、そうして後者に対しては、前者と異なって重大な問題が提起される、なぜなら「物がそれを通じて現象しうるところのいかなる感覚器官も神経構造も存在しない場所においてそもそも物がなんらかの現象を提示しうると主張することは奇怪であると考えられるかもしれない」からと語っている(ibid.,p.151)。この文章からすれば、かれが「心の存在しない場所」と「感覚器官や神経の存在しない場所」とを同義に用いていることは明らかであろう。しかも興味あることは、それにすぐ続いて、自分はこの主張を奇怪だとは感じないけれども、しかし決してそれを物理学の哲学の最終形態における独断的部分として述べているのではなく、むしろ予備的議論における「説明的仮説」として、建築が終ったら取り払いうるような「仮説的足場」として、主張するにすぎない、と断っていることである。そうすると、第二性質的なセンスデータはもちろん、第一性質的なセンスデータについても、心と身体の存在しないのちの不変的存続ということは、たんなる説明的仮説以上の真実性を有しないことになる。しかしそうなると、そのような仮説的な存在とは何か、なぜにそのような存在を認めなくてはならないか、をさらに追求する必要が生じるであろうが、ラッセルはそれについて別に説くところがないように思われるのである。
さらにラッセルの、センスデータを心的と考える思想は、生理学的主観性と心理学的主観性とを混同した結果であるという主張についても問題があろう。かれのいうごとくセンスデータの生理学的主観性を認めることから、それが心的でなくて物理的たることがはたして導出されうるであろうか。ラッセルは、センスデータが生理学的意味においてのみ主観的と考えられ、これはセンスデータが生理学的条件に因果的に依存することを意味するのみであって、それが心的なることをしめすものではない、と説く。しかしながら、かくセンスデータが生理的すなわち物理的なものに依存することが認められるとしても、その故にそれが物理的であって心的でない、という結論が出てくるわけでないことも明らかである。なぜなら、心的とよばれる多くのものが生理的物理的条件に因果的に依存するという事実もまた広く容認されているからである。それ故センスデータの心的でなく物理的なることを主張するためには、たんに生理的条件への因果的依存ということだけでは不充分であって、さらにそれ以上のことがしめされなくてはならぬ。この問題に対しては、ラッセルのつぎのような言葉が一つの手掛りをあたえるであろう。「センスデータが多くの場合主体の身体内にあることは確かだが、しかし主体の身体はテーブルや椅子と同様主体とは別のものであり、事実、物質界の一部にすぎない」(ibid.,p.145)。もし多くのセンスデータが文字通りわれわれの身体の内にあるものであれば、それが物理的なることは争われないであろう。物理的ならざるものが物理的なるものの内にある、とは言いえないからである。ところで、この文章のなかの「多くの場合」という制限は何を意味するのであろうか。おそらくは、それは前述した、身体的器官の存しない所にも存するであろうと考えられる一部のセンスデータを除いて、という意味に解すべきであろう。具体的にいえば、色、音、味、匂等の第二性質的なるセンスデータを指すものと思われる。もしそうであるとすれば、これらのセンスデータがそれを覚知する身体の内にある、というごときことがいかにして可能であるか。たとえばわれわれが茶色のテーブルを見るという場合、茶色のセンスデータがわれわれの脳の内にある、と言いうるであろうか。ラッセルによれば、脳もテーブルと同じく一つの物理的存在であるから、当然一定の色や形をもつはずである。いまかりに脳が灰色をした物質であるとすれば、テーブルの茶色が灰色の脳のどこかにあることになるであろうが、いかにして机の大きさと形をもつ茶色のセンスデータが小さな脳の形をした灰色のセンスデータの内にありうるのか。--しかしこの問題は、一般に物体ないし物質と呼ばれるものが、いかにしてセンスデータから構成されうるか、というつぎの問題を考察したのちにとりあげる方が適当であろう。それ故、目下のところわれわれは、センスデータが生理学的主観性を有するというラッセルの主張に対して、もしも「生理学的主観性」の意味が因果的な依存関係の意味であれば、そこからセンスデータが心的でないという結論は出てこないということ、またもしその意味が、センスデータが身体に内在するという意味であれば、それはそれ自身に重大な困難を伴う思想であるということ、したがっていずれの意味であるにせよ、そこからセンスデータの物理的性格を帰結することは困難であるということ、を指摘するにとどめておきたい。
二 「物」の構成と位置づけ
ラッセルがセンスデータないしセンシビリアの物理的なる性格を強調するのは、それらこそ現実の物理的世界といわれるものの究極的構成要素であると考えられるからにほかならない。しかしわれわれは右において、センスデータを感覚作用から区別し、前者が後者から独立に存在しうるという意味において、センスデータを物理的と考える説の承認しがたいことを見た。しかしながらこのことは、センスデータによって物理的世界を説明せんとする企てがすべて誤りなることを意味するものではない。否、われわれは、物理的世界ないし外界の問題は広義における現象主義的立場においてのみ解決可能であると信ずるものである。問題はいかなる仕方によってそれが可能かというにある。その点において、これから問題とするラッセルの構成論的物体観は、この方向における一つの典型をしめすものとして検討に値するといわなくてはならない。さて、一般に物理的対象をセンスデータの言葉に翻訳しようとする企てにとって第一の障害となるものは、物理的対象が一定の大きさ、形、色を具えてある期間持続するもの、と考えられているのに対し、センスデータは知覚者の位置の変動や感覚器官の変化に応じて変化し生滅するものである、という事実である。たとえば物理的対象としての硬貨は一定の大きさ、形、色をもつと考えられるにかかわらず、それのセンスデータといわれるものは、見る位置によってはもちろん、同一位置においても光線の状態、知覚者の生理的条件の相違、眼の開閉、圧迫等によって、その大きさ、形、色が無限に変化することは、平凡な日常経験の事実である。このような事実にもとづいて、物質的対象はセンスデータとは本質的に異なる存在であり、センスデータを自己の現象とはするが、それ自身は現象の背後にかくれて知覚されえないところの形而上的な実体である、というような思想が生れてくるのも、ある意味で自然といえよう。けれども、かかる形而上的な考え方にともなうと考えられる重大な困難にかんがみ、ラッセルは実体的物体観をしりぞけて、あくまでセンスデータのみによって物理的世界を構成せんとする。いわゆるオッカムの剃刀を用いて、できうるかぎり推論的な実在を減じて、それに代えるに論理的構成を以てせんとする科学的哲学の格率を、物理的存在の問題にも適用せんとするのである。それではセンスデータと物理的対象との間に存するように思われる右のギャップを、かれはいかにして埋めようとするのであるか。れわれはその答を、ラッセルの提唱する「物]の概念の変革と「場所]の区別に関する思想とのうちに求めうるであろう。
形而上的実体の観念を採用することのできないラッセルは、物理的な「物」の概念を結局センスデータに分解してしまわなくてはならない。その際、センスデータの変易的性格が「物」の概念に矛盾するごとく考えられるのは、「物]を以て一定の形や大きさをもった存在と考えるが故である。しかしながらはたしてそれのみが唯一正当なる「物」の観念であるというべきであろうか。もし「物]がそのようなものであるとすれば、言うところの一定の形や大きさも実はあるセンスデータにほかならない以上、そのような特定のセンスデータのみを「物]に属せしめて、それに大なり小なり類似した他の無数のセンスデータを排除するのはいかなる理由によるのであるか、という困難な問題に面しなくてはならないであろう。「物体]を以ていずれのセンスデータとも異なる超感覚的実体とする思想は、かかる困難を避けるために案出された一つの解答であるともいえるのであろう。が、かかる思弁的解答の代りにラッセルの提出したものが、物とは「その現象の全クラスである」という定義なのである(ibid.,p.147)。この定義にしたがえば、物とは特定のセンスデータではなく、無限数のセンスデータの集合を意味する。たとえば一室に居る数名の人間が同一のテーブルや椅子を見るという場合、各人のもつテーブルや椅子のセンスデータは多かれ少なかれ類似するとはいえ、同じであるということはできない。そうして相並ぶ二人の中間に別の人間が入りこめば、かれの経験するセンスデータもまた二人のそれに対して中間的性格をもつであろう。しかしてこのセンスデータのあるものは、かれがその位置に入りこむ以前から存在していたと考えても不自然ではない。(これが問題的な仮定なることはすでに見た通りであるが、いまはかりにそれを容認した上で議論をすすめる。)そうすると、現実の知覚者が経験するセンスデータのほかに、もしその位置が知覚者によって占められたならば存在するだろうと考えられるテーブルや椅子の無数のセンスデータを想定しうるわけであって、これら相類似する無数のセンスデータを総括して、「テーブルの現象]とか「椅子の現象]と称するのである。しかし、「テープルの現象」と言っても、現象とは別に背後から現象を統括するようなものとしてのテープルがあるというのではなく、「テーブル」とはこれら諸現象の集合以外のものではないから、それは「テーブルという現象]ないし「テーブル的現象]の意味に解すべきものである。「テープル]とは相互に類似的な無数のテーブル的現象の全クラスにあたえられた名称にほかならない。(「現象]の語が現象の背後にある「現象するもの]を連想せしめるという危険をともない易いという不利を除くためであろう、『外界の知識』では「現象」のほかに「相](aspect)という語が用いられ、「物」とはあらゆるパースペクティブにおいてあたえられる諸相の体系である、と定義されるp.96)
かく、「物]を定義してある種のセンスデータ(現象)の集合とするならば、物が知覚者の位置の相違に応じて異なった現象を呈するという事実は、これらの諸現象が物の構成要素であるという主張にとってなんらの支障ともならないであろう。というのは、それが支障と考えられるのは、これら相異なる諸現象(円と楕円、大きい円と小さい円、等々)がすべて同一の位置に存するとはいえないから、という理由によるのであるが、しかしそれらは一物を構成すべく同一位置に存しなくてはならないと考える必要はなく、それらはすべて異なった位置において知覚される異なったセンスデータでありつつも、「物]とはかかる異なれるセンスデータが類似の関係によって総括されたものにすぎないのである。この意味において、ラッセルは、「一切の諸相はすべて実在的であるけれども、他方その物とはたんなる論理的構成にすぎない」と言うのである。しかしてかく考えることによって、一物が一人以上の観察者によって同時に見られる、という意味も理解しうるという。というのは、この際二人以上の者が真に見ているのは同一の現象、相であるのではなく、一物を構成すると考えられる諸相の一つ(それぞれ別個の)にほかならないのである。「物]とはこれら諸相のいずれともただちに同一ではなく、いずれの視点に対してもいわば中立的であると考えられる(External World, pp.96-97)。われわれがある位置に立って眺める時、そこにはテーブル、椅子、壁、床等と呼ばれる「物]のセンスデータが一度にあたえられるであろうが、これらのセンスデータはただちに上の諸物と同一なのではなく、たんにそれらの一断面、一現象にすぎぬ。それは他の無数の視点から得られる他の無数の断面、現象と相関的に結合されることによって、はじめて一つの「物]の観念を形成しうるのである。
しかしながら、視点の変動にもとづくセンスデータの変易性ということが別に物の観念を構成する妨げにならないことを一応認めるとして、ではそのようにして構成された「物]の概念を以て、物が一定の場所に存在するということをいかにして説明しうるであろうか。「物]とは無数の異なる位置から知覚されるセンスデータの集合であるとすれば、そもそも「物]が一定の位置を占めるというごときことはナンセンスとなるのではなかろうか。しかしわれわれの常識によれば、テーブルや椅子は特定の場所にあるものであって、決して無数の異なる位置に散在ないし遍在するものとは考えないのである。ラッセルはこの問題に答えるために、一般にものの位置ということついて三つの場合を区別すべきことを主張する。第一は私空間内におけるセンスデータ相互の位置であり、第二はセンスデータがそこから現象する場所であり、第三はセンスデータがそこにおいて現象する場所である。第二と第三は第一と異なり、構成せられた物理的空間における場所であるといわれる。では、かかる区別がいかにして可能であるか。第一の私的空間における場所とは、一つの感覚的世界の内に見られる部分相互の空間的関係のことである。ある瞬間におけるわたしの視野のうちに机、椅子、壁、床等のセンスデータといわれるものがふくまれているとき、これらのセンスデータは相互にある空間的関係において配置されており、それにもとづいて各センスデータの位置が定められるであろう。わたしの隣りに位置する他人もまたこれと類似の空間的関係をふくんだ視野を経験するであろうが、しかし両者がいかに類似的であろうとも、視点の違いの故に同一であることはできず、わたしの見るいかなるセンスデータも他人の見るそれと同一ではなく、その逆もまた真なのである。この意味において「各人はかれのセンスデータに関するかぎり、私的世界に住む」と言わなくてはならないのであって、二つの私的世界の間にはなんらの共通部分も存在しない。したがって二つの私的世界にとって同一なる場所というものも存在しえないのである。というのは、一つのセンスデータの場所を定めるものはそのセンスデータの内または周囲のセンスデータとの関係でなくてはならないが、二つの私的世界はなんら共通のセンスデータを有することができないために、それによって「同一の場所]なるものを規定するということが、始めから無意味であるからである。そうすると、同一物についての異なる諸現象はそれぞれ異なる私的空間の内に位置するものたる以上、それらを「同一の場所]に結びつけるという問題もそもそも生じえないわけである。
私的空間のうちには、視空間のみならず触空間もふくまれている。二本のビンが同時に手の異なる部分に触れるとき、われわれは眼を閉じていても、その二つの部分の空間的関係を知覚すると考える。もしその際眼を開けば、二つの接触点の空間的関係を同時に視野の内において認めることもできるであろう。しかしここで注意すべきは、かくして得られる二つの空間的関係はそれぞれ別の私的空間に属するということである。われわれは、触覚によって知られる接触点が視覚によって知られる接触点と同一の点であるというごときことを、直接に感覚によって知ることはできないのである。私的空間とは、厳密にはつねに同一感官によってあたえられるセンスデータ相互の関係なのである。しかしわれわれは経験によって、触覚的私空間と視覚的私空間との間に、ある相関(correlation)の存することを学ぶことができる。われわれは常識的に、物が手に触れている同じ場所をば眼によっても見うるというけれど、これは正確な言い方ではなく、実際は、触れられる場所と見られる場所との間に密接な相関関係のあることが知られているにすぎないのである。かく経験を通じて種々の私的空間を相関せしめることによって、われわれは、その内に自己のすべてのセンスデータを包含するところの一つの私的空間なるものを形成しうるであろうが、しかしこれは決して感覚において直接あたえられる私的空間であるのではなく、実は同時的にあたえられた異なる私的諸空間の間に経験的に見出されたところの相関の関係にほかならないのである。
第二の、センスデータがそこから現象するところの場所とは、右のごとき各知覚者に固有な私的空間の内における場所ではなく、むしろ、「そこにおいては一つの全体的私的世界が一点として、あるいは少なくとも一つの空間的単位として数えられるところのもう一つの空間」である(Mysticism, p.152)。それぞれの私的世界はそれぞれの視点(point of view)から眺められた宇宙の現象とも見られるとすれば、第二の空間とは、これらもろもの視点においてある空間、すなわち諸視点の空間(space of points of view)ともいうべきものであるが、ラッセルはそれよりも、諸パースペクティブの空間(space of perspectives)ないしパースペクティブ空間(Perspective-space)と呼ぶ方が適当であるという。そのわけは、前者には知覚者が存在しなければ私的世界が実在しないというような示唆がふくまれているので、それを避けるために、知覚者を想定しない私的世界という意味で、とくに「パースペクティブ]の名称を用いるという。(これに対し、『外界の知識』p.95でははっきりと、「わたくしは「私的世界]という表現を現実に知覚されているごとき宇宙の眺望にのみ局限するであろう。かくして「私的世界]とは知覚せられた「パースペクティブ]であるが、しかし知覚されないパースペクティブがいくらでも存在しうる」と主張する。)とにかく諸パースペクティブの空間とは、もろもろの私的空間の成立する諸視点から成る空間のことである。第一の場所がもろもろのセンスデータがそこにおいてある場所をしめすものであったのに対し、この第二の場所とは、一つの私的空間全体が他のもろもろの私的空間とならんでそこにおかれているところの場所、すなわちセンスデータがそこから現象するところの場所である。
ところで問題は、いかにしてかかるパースペクティブ空間というごときものが考えられるか、ということである。ラッセルの中心課題は、センシピリアを以て物理的世界の究極的構成要素と考え、その立場から物理的な「物]や「物質]を説明することであった。しかして「物]を定義して「現象の全クラス]ないし「諸相の体系]とすることによって、課題の第一段階を一応のり越えたとも考えられる。なぜなら「物]は無数のセンシピリアの類似の関係による相関として説明せられたからである。しかるにつぎに、かく定義せられた「物]のおいてある場所を説明する段階にいたり、一つのパースペクティブ内部におけるセンシビリア相互の空間的関係、すなわち私的空間のほかに、無数のパースペクティブがそこにおかれているごときもう一つの空間、すなわちパースペクティブ空間なるものを導入せざるをえなくなったのである。もしこの空間が私的空間とは別種の空間であるとすれば、そのことは物理的世界の説明にセンシビリア以外の要素を導入するものとして、そのかぎりかれの計画の挫折を意味することになるのではないか。もしこれに反し、パースペクティブ空間もまたセンシビリアないし私的空間から構成せられるものとするならば、そのかぎりかれの態度は一貫するわけである。しかしてわれわれの見るところでは、『外界の知識」においては前者の立場が採られているのに対し、『神秘主義』の論文はむしろ後者の立場に立っているように思われるのである。まず、『外界の知識』では、パースペクティブ空間についてつぎのような叙述がある。もしある二つのパースペクティブの内容がきわめて類似的である場合は、「われわれは二つのパースペクティブの視点が空間的に近寄っているという。しかし、その中で視点が近寄っているところのこの空間は、二つのパースペクティブ内部の空間とは全く異なるものである。それはパースペクティブの間の関係であって、そのいずれの内にあるものでもない。なにびともそれを知覚しえない。もしそれが知られうるものとすれば、それはただ推論によってのみ知られうる」という(p.96、下線筆者)。ここにパースペクティブ空間なるものが、知覚されえず、ただ推論されうるのみという性格を付与されることによって、私的空間とは「全く異なる」所以が明示されているといえるであろう。私的空間すなわちパースペクティブ内部の空間は、現実に知覚されていなくても、知覚されうるものであったのに対し、パースペクティブ空間は知覚されえない空間として規定される。したがってそれは私的空間から論理的に構成されうるものではなく、それ自身は私的空間とは別種の空間として、ただ推論によってしか知る途のないものである。これに対し、『神秘主義』の論文においては、すでに引用したごとく、パースペクティブ空間とは私的空間のほかの「もう一つの」空間であるといわれているけれども、しかし右のごとく、知覚されえず、推論によってしか知られない空間である、というような主張はなされていない。このことは前に、ラッセルの許容する推論的存在として、他人の覚知するセンスデータと、心の存在しない場所から現象するであろうセンシビリアの二種類があげられるにとどまり(p.150)、パースペクティブ空間のごときものに言及されていないことからしても当然であるというべきであろう。のみならず、この二種類の存在は他我または自我によって知覚されうるものであるという点において、『外界の知識』における「なにびともそれを知覚することはできない」底(?)のパースペクティブ空間とは種類を異にするといわなくてはならない。では一体、かく椎論を用いず構成によってパースペクティブ空間の概念を獲得するということがいかにして可能と考えられるのであるか。
各パースペクティブ自身のうちに包含される私的空間は、パースペクティブの数に応じて無数に存在するわけであるが、これら無数のパースペクティブを自己の要素とするところのパークペクティブ空間というものは、ただ一つしか存在しない。その故にそれは、「一つの包括的なパースペクティブ空間](one all-embracing perspective space)とか「一つの包括的な物理的空間](one all-embracing space of physics)と呼ばれて、無数の私的空間から区別せられるのであるが、しかし、かかる一つの空間の構成方法に関して『神秘主義』の論文の教えるところはかならずしも明確とはいいがたいように思われる。というのは、われわれはそこにすくなくとも三つの、同一とはいいがたい構成方法が、あたかも同一であるかのごとく--というのは、その間に区別の存することがなんら言及されることなく--順次に述べられているのを見出しうるように思うのである。
第一の方法をしめすと考えられるものはつぎの文章である。「われわれはいまや、いかにして異なる諸パースペクティブが一つの空間に整序されるか、ということを説明しなくてはならない。これは、同一物の、異なる諸パースペクティブにおける諸現象と看做されるところの諸センシビリアを相関せしめることによって実行される」(p.152)。そうしてそれの説明としてつぎのように述べられている。二つのパースペクティブにふくまれるセンシビリアが同一たりえないにもかかわらず高度に類似し、かつ類似の私的空間的秩序を有するということを、われわれは運動や他人の証言にもとづいて発見するが、かくしてあるパースペクティブにおける一つのセンシビリーが他のパースペクティブにおける一つのセソシビリーと相関せしめられるのであり、そしてかく相関せしめられたセンシビリアが「一つの物の諸現象]とよばれるものにほかならぬ、と。しかしながら、このような説明を以て「一つの物理的空間」の構成方法がしめされたものとすることは困難であろう。なぜならここでしめされたことは、いかにして各私的空間にふくまれた類似のセンシビリアの相関によって「一つの物]が構成されうるか、ということにすぎず、しかして「一つの物」の構成と「一つの物理的空間」の構成とが同じであるというような説明は別になされていないからである。否、類似のセンシビリアを相関せしめて「一物」の概念を構成するだけのことであれば、われわれはかならずしも視覚的ないし触覚的な私的空間とは別に一つの物理的空間なるものを必要としないというべきであろう。後者が要求せられた一つの理由は、すでに述べたごとく、類似的センシビリアの相関によって構成せられた一つの物がそこに置かれている「場所]とは何か、を明らかにするためであったのであり、したがってこのためには、たんなる類似的センシビリアの相関ということ以上の説明があたえられなくてはならないのである。
そこでつぎの段に述べられている第二の方法と考えられるものを見ると、その点でやや進んだ説明がなされているように思われる。その趣旨をしめしていると見られる冒頭の文章は、「諸パースペクティブを一つの空間へ整理することは、種々のパースペクティブにおける、ある与えられた物の諸現象の間の相違によって実行される」というものである(p.153)。この文章を、前に引用した第一の方法をしめす文章と比較するとき、異なる点は、前のが「センシビリアを相関せしめることによって」となっていたところが、こんどは「諸現象〔センシビリアと同義〕の間の相違によって」となっている点だけであるように見える。では、両者の間にどのような意味の相違が存するのであろうか。、両者は表現上の相違にもかかわらず実際に意味するものは同じであるようにも考えられる。しかしながら、後の文章につづく説明を注意して読むならば、そこに前の文章にふくまれていなかった重要な主張の意図されていることに気づかれるであろう。というのは、ここでラッセルの主張せんとしていることは、前のように、もろもろのセンシビリアが類似関係によって相関せしめられて「一物]を構成するということではなくて、逆にかく相関せしめられるもろもろのセンシビリアが、相互の間に有する一定の相違にもとづいて異なった場所に配列される、ということであり、かれはそれによって、一つの物理的空間の構成が可能となることをしめそうとしているように思われるのである。ラッセルはこのことを硬貨の実例によってつぎのように説明する。われわれが一つの硬貨を見るというとき、パースペクティブの異なるのに応じて異なる硬貨の現象を知覚する。すなわち、あるものは大きく他は小さく、あるものは円く他は楕円またはある厚さの短い直線(真横から見た姿)であったりする。「われわれは、硬貨の現象が円形であるようなすべてのパースペクティブを集めることができる。われわれは硬貨の見かけ上の大きさの変移にしたがってこれらのパースペクティブを一つの系列に整理して、それらを一つの直線上に置くであろう。硬貨がある厚さをもった短い直線として現れるようなパースペクティブは、同様に一つの平面上に置かれるであろう」(p.153)。この際、大きさを等しくするものが無数にあるわけであって、それらを大きさの別に集めるならばいくたの同心円が形成されるであろう。「このような方法によって、硬貨が視覚的現象を呈するパースペクティブは、すべて一つの三次元空間的秩序へ整理されうる」のであり、硬貨以外のいかなる物をとっても同じパースペクティブ空間が結果することは経験の教えるところである。そうして「この経験的事実こそ一つの包括的な物理的空間の構成を可能ならしめたものなのである」という。
しかし、はたしてこれによってセンシビリアから一つの物理的空間を構成する道が説明されたといいうるであろうか。一つの硬貨を構成するところの相異なるもろもろのセンシビリアを、ある基準のもとに選択し配列するということは、私的空間のうちにあたえられるセンシビリア以外の存在を導入しなくとも一応可能であるといえるであろう。たとえばわれわれはただある運動をすることによって、種々の大きさをもつ円形のセンシビリアをふくむパースペクティブの全系列を得ることができるであろう。しかし問題は、この系列が一直線上に配置される、というごときことがいかにして知られうるか、というにある。われわれの知りうるものは、ただある種の運動の感覚と相関的に変化する視覚的形象のみである、というべきであろう。その運動が直線運動であるとか、変化する視覚形象をふくむもろもろのパースペクティブが一直線上に置かれている、というごときことを、いかなるセンシビリアによって検証しうるのであるか。ラッセルはこれを問題とすることなく、種々のパースペクティブが、あるいは一直線上に、あるいは一平面上に配置されることを自明の理のごとくあつかっているけれども、実はこの点にこそ問題の核心が横たわっているというべきではないか。もしそれが自明の理であるとすれば、一つの物理的空間なるものはすでに前提されているのであって、いまさらそれを構成する必要は存しないはずである。しからずして、あくまでそれは構成さるべきものであるとすれば、右の説明における「直線]や「平面]そのものがセンシビリアの語によって定義されなくてはならない。しかしながら、たんに漸次的に大きさの変化する円形をふくむ無数の視覚的パースペクティブの系列、というごときことのみを以て「直線」を定義することがいかにして可能といえるか。すくなくともラッセルはこの論文ではなんらそれに論及していないのである。しかるにかれはすぐ後の節において、「前に定義せられた意味における諸パースペクティブの線」とか、「硬貨を用いて定義されたパースペクティブの線」というごとき言葉を使っている(p.155)。もしそれが、いうごとく硬貨(的センシビリア)を用いて定義せられた線であるとすれば、それによって一つの物理的空間を構成することは当然可能となるであろうが、われわれはそのような定義がほどこされたと考えることができないのである。物理的空間を構成する第三の方法と考えられるものは、つぎの文章のうちにしめされているように思われる。「われわれはいまやパースペクティブ空間と、種々のパースペクティブに個別にふくまれている種々の私的諸空間との間の相関を説明しなくてはならない。一つの三次元的物理的空間が構成せられるのはこの相関によるのである」(p.154)。ところでわれわれはこの文章の意味をいかに理解すべきであろうか。一般に相関せしめられるものは相関によって構成されるものと同一であることはできない。AとBを相関せしめることによってCを構成する、というのが普通であって、個々の類似的センシビリアの相関によって「物]を構成するというのはその一例である。これに対し、もし、AとBとを相関せしめることによってAを構成する、と説く者がありとしたら、われわれはかれの論理的能力に疑いをいだかざるをえないであろう。しかるに右の文章は、正にこのような疑問を投げかけるものというべきではないか。そこではパースペクティブ空間、すなわち一つの三次元的物理的空間と個々の私的諸空間との相関によって、一つの三次元的物理的空間が構成せられる、という主張がなされているのである。かかる意味の構成が不可解なることは、おそらく多言を要しないであろう。事実、この文章につづいてラッセルのあたえている説明を見るならば、かれがそこで言わんとしていることは、物理的空間の構成ではなくて、その中での「物のおかれている場所]を構成することなのである。このようにしてわれわれは、この第三の構成方法をば、論理的理由にもとづいて否認せざるをえないのである。
以上によって、『神秘主義』の論文において述べられている物理的空間の構成に関するラッセルの議論は、そのいずれも承服しがたいことが認められるであろう。これに対し『外界の知識』(1922年、改訂版)における論述では、右のような欠陥やあいまいさが除かれているといえるが、そのかわり、そこにはもはや現象主義で一貫しようとする純粋性が失われて、のちの科学的実在論的思想が頭をもたげているのである。たとえば、硬貨の円形をふくむ無数のパースペクティブが一直線上に配置される、という問題をあつかうにあたっても、それは前のごとく、物理的空間を構成するためとは言われず、「いかにして個別的パースペクティブの私的空間が、一つの包括的パースペクティブ空間の部分と相関せしめられるかを説明する」ための一例としてであり、したがって「硬貨が円形に見える諸バースペクティブはパースペクティブ空間における一直線上に横たわるといわれるであろう」と明記されている(p.97,下線筆者)。すなわちここでは、物理的空間は私的空間とは別個にすでにその存在が前提された上で、両者の相関が論ぜられているのである。それ故、前者を後者から構成するという問題は生じないわけである。しかしそうなると、いかにしてわれわれは、私的諸空間から区別された一つの物理的空間というごときものの存在を知りうるか、という新たなる大問題に直面せざるをえなくなるであろう。が、それについて『外界の知識』ではただ、すでにふれたごとく、それはなにびとも知覚しえず、ただ推論によって知るほかない、と言われているだけであって、その推論の根拠や方法については別に説くところがない。この問題は、科学的実存論の立場を正面に押し出したところの後の著作において、はじめて主題的にとりあげられることになるわけであるが、しかしここで注意すべきことは、現象主義的態度の最も横溢した『神秘主義』の論文においてさえ、ラッセル本来の科学的実存論的精神はその活動を完全に停止してはいなかった、という事実である。このことを最もよくしめすものが、前述した、「一つの私的世界全体がそこにおいては一点として数えられるところのもう一つの空間」という言葉であろう。というのは、ある延長をもったところの私的空間が、それにもかかわらず一点として数えられる、と言われるところに二つの空間の異質性が端的に表現されていると考えられるのである。そうしてそこに、延長をもった私的空間(センシビリア)を以て、延長を有しない物理的な点や、幅を有しない物理的な線を構成(定義)しようとすることの不可能性が前もってしめされているともいえるであろう。尤もラッセルは、センシビリーがそこから現象するところの物理的空間における場所とは、「その「セソシビリー]を自己のメンバーとするパースペクティブである」というような規定の仕方もしている(p.155,下線筆著)。このような表現は『外界の知識』に見られる、パースペクティブ空間とは「諸パースペクティブ自身がその要素である」とか、「私的諸空間自身の体系である」というごとき表現(p.97)とともに、物理的空間が私的空間のみから定義されるものであるかのような印象をあたえるであろう。が、すこし注意してみるならば、この印象の間違いであることが判明するであろう。まず、センシビリーがそこから現象する場所を、そのセソシビリーをふくむパースペクティブと同一視するということは、もし文字通りに受け取るならば、ひとつの論理的背理というべきであろう。なぜかといえば、一つのパースペクティブとは種々のセソシビリアの集合以外の何物でもない以上、一つのセンシビリーが自分を一メンバーとするパースペクティブ自身から現象するという主張は、言語の意味を不当に曲げないかぎり解しがたき表現であるといわざるをえないからである。つぎに、物理的空間が諸パースペクティブないし私的諸空間自身を自己の要素とする、というのちの表現についても、その意味を、物理的空間とは無数の私的空間の集合にほかならない、という意味に解するときは、やはり理解困難な命題と化するのではないか。というのは、相異なる私的空間そのものを集めるとか加えるとかいうことが具体的にいかなる意味をもちうるのか。たとえばある私的空間に現われた円い硬貨の姿や矩形のテーブルの姿等々の全体と、他の私的空間に現われた楕円の硬貨の姿と平行四辺形のテープルの姿等々の全体とを集めることによって、物理的空間の一部をつくる、というごときことが、はたして理論的に有意味であるといえるであろうか。もしそれが有意味であるというのであれば、それに関する詳細な説明を必要とするはずである。しかしラッセルがそのような困難な意味においてかかる表現を用いているのでないことは、すぐあとの「これらの私的諸空間はそれぞれパースペクティブ空間における一点、ないしはとにかく一要素として数えられるであろう」という言葉からもうかがえるように思う。これはたんに前の言葉を布延した言葉のようにも見えるけれども、実際は逆に、この言葉を基にして前の言葉を解すべきものであろう。換言すれば、物理的空間とは私的諸空間そのものの集合ないし総和であるのではなく、したがって後者をその意味で自己の要素とするものではなく、むしろ私的諸空間がそこにおかれている場所(点)の集合ないし総和と考えらるべきものなのである。しかして物理的空間が私的諸空間を要素とする、ということの真実の意味はここにもとむべきものであろう。
さて、センシビリーがそこから現象する場所をいかにして構成するか、についてのラッセルの説明が、右のごとくにして受け容れがたいとすれば、第三の、センシビリーがそこにおいて現象するところの場所の構成についてはどうであろうか。この場所こそかれによって、「物]の存在する場所とせられるものであるが、この場所の構成については、『神秘主義』と『外界の知識』とで同様の説明があたえられている。それによれば、たとえば硬貨の位置を定めるためには、前述のごとき硬貨の諸パースペクティブの配列される線を用いればよいという。硬貨がその内で円形に見える諸パースペクティブはすべて一直線上に置かれるとして、他方側面から眺めて、硬貨がその内である厚さをもった短い直線として現われる諸パースペクティブを大小の順に配列するときは、それらは別の一直線上に置かれるであろう。しかしてこの二直線がパースペクチブ空間の内で相交わる点を「硬貨のある場所]と定義することができるであろう。もっとも実際はこの交叉点に至らないうちに、硬貨が眼にある程度以上接近する時は、その姿は見えなくなるであろうが、その時は「われわれの硬貨を取り去って、別の二硬貨をより遠くに置き、元の硬貨の諸相が円形であった所ではその一つの諸相も円形であり、元の硬貨の諸相が短い直線であった所では他方の諸相も短い直線であるようにすることによって、二つの直線をそれぞれ交叉点まで延長することができる。そうすると、そこにおいては新しい硬貨の一方が円形に、他方が短い直線に見えるところのただ一つのパースペクティブが存在するであろう。これが定義によって、元の硬貨がパースペクティブの空間においてあった場所であるだろう」(Extrenal World, pp.98-99)。
われわれはかかる議論に対してどのように批評すべきであるか。まずいえることは、この議論は前の議論で主張せられた諸パースペクティブの線についての考えを前提して成立していることである。そしてわれわれは、個々のパースペクティブのみを以てしては一つのパースペクティブ空間(物理的空間)を構成しえず、したがって前者がパースペクティブ空間における一直線上に配置されるということを決定することもできないことを見た。そうすると、第三の場所の構成は第二の場所の構成の上に成り立っている以上、後者の欠陥をそのまま受け継いでいることになるわけである。これは、形式的ではあるけれどもしかし致命的な難点といわなくてはならない。しかし、われわれはそのほかにも、つぎのごときこの議論固有の弱点をも見出しうるであろう。それはほかでもなく、この議論が、定義しようとするものを前提するという誤りを内包するために、読む者に奇妙な印象をあたえずにはおかないことである。たとえばラッセルのつぎのような言葉--「われわれの二つの線がこの場所〔交叉点〕に到達するまでそれらを延長するためには、その硬貨のほかに他の物を利用しなくてはならないであろう。なぜなら、経験によると、われわれがその硬貨が眼に触れるほどそれに接近したのちは、それはなんらの現象をも呈しなくなるからである」(ibid.,p.98)とか、右に引用した文中の「われわれの硬貨を取り去って別の二硬貨をより遠くに置き」(傍点はすべて筆者)を考えてみれば、その奇妙性はなにびとにも容易に気づかれるであろう。かれがここで定義しようとするものは「硬貨の位置]である。しかるに、かれはそれを定義するための文章のなかで、すでにそれを知られたものとして前提し使用している、というべきではないか。上の文中で傍点を付したような個所は、すでに硬貨の位置を知っていなければ使えない表現と考えられるからである。(これらの表現がすべて能動的触覚経験を表わすことに注意せよ。)元の硬貨に「接近」したり、それを「取り去る」ことができるのであれば、すでに硬貨の位置は知られておるというべきで、硬貨の位置を知らずして硬貨に近づくとか、硬貨を取り去るというのはナンセンスであろう。それであるから、いまさら他の硬貨を遠くに置いて(このこともそれらの位置を知らずしては不可能なことである)、元の硬貨の位置を定める必要はすこしも存しないはずである。ラッセルがこのようなバカバカしい複雑な操作を提案しなければならなかった原因はどこにあるかといえば、結局かれが視覚的なパースペクティブのみによって物の位置を定義しうると考えたことにあるといえるであろう。しかし視覚経験のみを以てしては、もろもろのパースペクティブがその上に配置されるところの「直線」を定義しえないばかりでなく、かりにそれができたとしても、硬貨に関する無数の視覚的パースペクティブのなかから、ただ一つを選び出して、それを硬貨の位置と同一視する理由をしめしえぬであろう。ラッセルは、二つの補助硬貨を置くことによって二つの直線の交叉点が獲得せられるならば、その交叉点において補助硬貨の一方が円形に、他方が直線に見えるところのただ一つのパースペクチティブが存在するであろうという。たしかに交叉点以外の場所では、円形と直線を同時にふくむパースペクティブは存在しないであろう。しかしてラッセルは、一般に物はそれが置かれている位置自身においてその全貌を露呈するように考えられているために、二つ(以上)の相をともに含有するパースペクティブを以て物の位置と同視しうると考えたのであろう。けれども、問題の交叉点で同時に見られるという円形と直線形はともに元の硬貨の姿ではなく、別の二硬貨がある不定な距離を隔てて呈示する姿にすぎないのである。とはいえ、物にある程度以上接近する時に物の姿が混乱消失するというのは、われわれの眼球のもつ偶然的制限によるのであって、そのような制限を有しない完全な眼を想定するならば、別に補助的硬貨を用いることなしに、問題の交叉点を決定しうるとも考えられよう。しかしその場合といえども、その交叉点に位置した眼が硬貨の諸相--円形、無限の曲率をもった無数の楕円形、直線形等々--をことごとく見る、というごときことがはたして可能であろうか。むしろ、森の全貌は森の内部に入って反って失われる、というような事態がそこにもあるというべきではないか。それはともかくとしても、そもそも特定の視覚的パースペクティブをただちに物の場所と同一視することは、第二の場所の場合と同様に、原理的な背理をふくんでいるというべきであろう。なんとなれば、いかなる視覚的パースペクティブといえども、自己内部のセンシビリア相互の位置関係を決定しうるのみであって、自己自身の(他のパースペクティブに対する)位置を決定することも、これをふくむこともできないと考えられるからである。--これを要するに、視覚的パースペクティブの変化から物の位置が決定されるのではなく、逆に物の位置から視覚的パースペクティブの変化が説明され、ないしは後者が前者に相関せしめられる、というべきである。ラッセルの説明によって確立されたものは、物の位置ではなくて、実は視覚的パースペクティブの変化と、物の位置から視点までの距離や方向の変化との間に見られる相関関係にすぎない、といわなくてはならぬ。ラッセルは、自己のあたえた物の位置の定義に立って、一般にセンスデータの主観性とよばれる現象につき、つぎのような興味ある説明を試みている。たとえばわれわれが山を眺めている時、自分の眼を閉じたり圧したりすれば、山の姿は消滅したり二重になったりするであろうが、しかしわれわれはその故に山そのものが変化したとは考えない。しかるに前述の、物とはその諸現象のクラスである、という定義を採用するならば、山の現象の一部に生じた変化は、同時に山そのものにおける或る変化を意味しなくてはならないであろう。ラッセルはこのディレンマを克服するために、現象の変化の仕方について二つの場合を区別すべきだと主張する。われわれが眼を閉じた時は、われわれの眼の現象はあらゆるパースペクティブにおいて変化するであろうが、眺められていた物の現象はそのほとんどが不変である。そしてラッセルは定義的に、物の近くの諸現象のすべてが変化する場合は物が変化したというが、反対に物の近くの現象はすべて不変であって、ただ比較的物から遠い位置で見られるその物の現象が変化するような場合は、変化はその物にではなくて、他の中間物に生じたということができる、と説くのである(Mysticsim, p.156)。これによると、物が変化したか否かは、物の近傍におけるその物の諸現象に変化が生じたか否かによって決定されることになる。この定義は、山の姿はそれを見る位置が山から遠ざかるほど、中間に存在する雲や霞等の影響で変動を受け易くなる、というような常識とも調和するように見える。しかし物の姿を変えるものには雲や霞のごとき身体外の中間物のほかに眼や神経等の器官がある。眼を閉じたり圧したりして生ずる物の姿の変化は物からの距離とは無関係の現象ではないか。いかに至近の場処であろうとも、知覚者が眼を閉じれば物の現象はただちに消滅する。ラッセルの定義にしたがえば、この時物は変化した、といわざるをえない。ディレンマは依然存続するのである。もしこの困難を脱するために、「感覚器官の正常な状態]というごとき条件を付加するならば、一つの感覚器官の状態が正常であるか否かを決定するために、それを知覚する別の感覚器官の正常なる状態を必要条件とすることになり、かくして問題は無限に後退するであろう。そこでわれわれは、物を諸現象の集合と考えるラッセル的定義そのものを、改めて根本的に検討しなくてはならぬ。
ラッセルが「物」の定義に関して用いている「現象]、「センシビリア]、「相]、「パースペクティブ]等の語は、すべて視覚的なるものを主な内容とするもの、すくなくとも必須の内容とするものと考えられる。そのことは、もともと「パースペクティブ]という語が「見る]から生れたものであり、つねに視点と連関させて用いられることからも首肯されるであろう。しかして右のごときラッセルの困難は、かれが視覚的センシビリアを要素として「物]を構成せんとしたところに起因すると考えられるのである。視覚的センシビリアは「物]の構成要素ではなくて「物]の現象なのであり、このときの「現象]とは、ラッセル的用法と異なり、現象する物から区別される現象を意味する。われわれが見る山の姿は幽かであると鮮やかであるとを問わず、すべて物体としての山そのものの構成部分ではなくて、それのたんなる現象にすぎぬ。しかしてそれを現象というのは、すでにわれわれが因果的な思考に立ってものを見ていることを意味する。見られる山の姿は「山」を原因として生起した結果である、という意味で、「物]としての山の現象と考えられる。しかしこの結果としての山の姿は、たんに「山]の存在にのみ依存するのではない。そのほかに「光]、「空気の状態]、「眼]、「神経」等無数の「物]の存在を条件として生起したものである。山の姿はこれら諸条件の関数といえる。したがってこれら諸条件のどの一つに生じた変化でも、山の姿に変化をおよぼさずにはおかない。ある場合には、「山]が崩れたために山の姿が変化することもあろう。他の場合には、「山]は不変であるのに、「光」や「霧]や「眼]の状態が変化したために山の姿が変化することもあろう。このように考えれば、右に述べたような困難は全く解消するであろう。しかしかく、山の姿が山以外の無数の諸物を条件として生起したものであるとすれば、なぜにそれを「山の姿]といって、「光の姿]とか「眼の姿]とかとよばないのであるか、という疑問が生ずるであろう。しかしこの問題は、差別的条件と恒常的条件とを区別することによって解決しうること、すでに前章で詳論した通りである。ところでラッセルが、遠くから眺められた物の現象の変化は、その物の変化ではなくて中間物の変化を意味する、というとき、問題は「物]の構成から進んで「物質]の構成にかかわってくるであろう。かれは両者の区別をいかに考えるのであるか。
三 「「物質」の構成と原因的効能」
一つの物の諸現象が変化するという場合、それが物の位置からどれほどの距離においての現象であるか、ということによってその意義を異にする、というラッセルの思想は、すでに述べたところの、「物」とは諸現象のクラスである、という定義以上のものをふくむというべきであろう。かれは右に述べられたごとき物の位置についての定義にもとづいて、一般に物は近くにおいて観察されるほどより精密な情報を提供する、と考える通念をも説明しうると主張する。遠くで見た時は一人の人間にすぎないものが、接近するにつれてそれが太郎であること、さらにかれが笑っていることが判明する。そうしてかかる過程の極限において知られるものが太郎の真相であると考える。物理学においても、至近の場所で観察される物の現象は遠くのそれよりも重視せられる。かかる事実にもとづいて、ラッセルは、つぎのような定義を試みにあたえうるであろうという。「あたえられた物の物質とは、物からの距離が減少した極限の諸現象である」(Mysticism, p.157)。この定義の大きな特色は、「物質」とよばれるものも、やはり一種の現象であって、現象を超越した別種の実在ではない、ということをしめしたところにあるであろう。といっても、この「物質」の定義が完全に経験的な定義とはいえぬという欠陥をもつことは、ラッセルも認めている。なぜなら、そのような極限における現象なるものは、経験的にはあたえられえないものだからである。われわれは物にあまりに接近する時は、その現象を知覚することができない。それ故、物質についてわれわれの経験的に知りうることは、単に近似的たるにすぎぬ。というのは、われわれはただ、ある距離において観察された諸現象からの近似的な推論を通して、それらの極限を知るほかないからである。しかしそれにもかかわらず、物質とはあくまで現象の極限であり、極限における現象であって、現象と異質な実在ではない。この意味において、物理的世界をセンシビリアのみから構成せんとするラッセルの現象主義的態度は、「物」と同じく「物質」に関しても一応貫かれているわけである。しかし問題は、このように定義せられた物質の概念がはたしてラッセルの意図するごとき機能を果しうるか、というところにあろう。かれが「物」とは別に「物質」の構成を必要とした一つの事情は、それによって物の変化とその現象の変化との間に存する区別と関係を明らかにするためであったと考えられる。すなわち、一物の現象の変化かならずしもその物の変化ではなく、むしろ他の物の変化でありうる所以を説明することであった。かれはこの説明が、「物質」の概念を新しく導入することによって果たされると考えたのである。けだしいまや、「物」の変化とはその物を構成する「物質」の変化である、と言い換えうるからである。前に、「物」の変化とは、物の近傍における現象の変化である、といわれたことのより正確な意味はここにあるといわなくてはならない。「物質」とは物に接近した極限に現われる現象にほかならないからである。物質とは物の置かれている位置自身において見られる現象なのであるから、その現象が不変であるにかかわらず他の位置におけるその物の現象が変化するとしても、別に矛盾は存しない。それは他の位置に位するところの他の中間物を構成している物質によってひきおこされた変化であると考えうるからである。遠くに見える山の現象が、山をつくっている物質の変化によらずして、それと観察者との間に横たわる雲、霧等の中間物質の変化によって変ずることもあろう。かくして一般に、「所与のパースペクティブにおける一物の現象は、その物とそのパースペクティブとの中間にある物質によって因果的に影響される」という事実は、「物」から区別せられた「物質」の概念を構成することによって、はじめて十分な解明に達しうるように思われる。けれどもすこし反省すれば、この定義に対しても大きな疑問が提出されうるであろう。ラッセルの主なねらいは、一物の諸現象が、その物と中間的諸物の物質との因果的関数なることを主張することにあると考えられるが、しかしわれわれはいかにしてかかる二種類の物質を区別しうるであろうか。物質とは物の位置において見られると考えられる現象であるから、山の物質は山のある位置において、光や眼の中間的物質はそれぞれ光や眼の位置において現われるところの現象である。ところで山に接近した場所に現われる現象ほど中間物質の影響が減じ、その極限における現象が山をつくっている物質であるというが、それでは光や眼の中間物質の影響を全く受けない山自身の現象というごときものがいかにして考えられるのであるか。われわれは雲や霞の影響を受けない山の姿を見うるけれども、光や眼の影響から独立な山の姿を見ることが、いかにして可能であるか。(知覚者の感覚器官や神経もラッセルのいう中間物に属する〔ibid.,p.158〕)。むしろ反対に、山に接近して得られる鮮明かつ正確なる山の姿といわれるものほど、実は光や眼が特定の状態にあることを必要条件として要求するというべきではないか。かかる条件から解放された山の姿とは、暗夜に見られる幻影にも類するようなものであって、それを以て山をつくる物質と同一視することの不合理なるはいうまでもない。距離を縮めることによって除かれる中間物質の影響とは、雲や霞やガラスや液体等の半透明体のそれであって、光や眼や神経や脳などの中間物質ではありえないであろう。後者はあらゆる視覚的現象を成立させるための必要条件でなくてはならぬ。つぎに問題となることは、「物質」に負わされているところの原因的効能(causal efficacy)についてである。ラッセルによれば、一物の諸現象は一物と中間物とを構成しているところの諸物質を原因として生じた結果であり、「一物の全原因的効能はそれの物質の内に宿る」(ibid.,p.158)といわれるが、いかにして物質というものが、かかる効能を有しうるのであるか。ラッセルは現象主義をつらぬくために、物質をも一種の現象とした。それが他の諸現象と異なるのは、ただ物の位置に接近した極限において見られる、という点にすぎない。そうすると、遠くで見られる現象には他の現象の原因たる能力がなく、ただ近くで見られる現象のみそれを有する、ということになるが、それはいかなる理由によるのであろうか。かれは、「原因的効能」という概念は定義しにくいので、右に引用した命題を正確に陳述することは困難であると断っているが、すくなくとものちに述べるごときラッセル的因果の概念を以てすれば、物質とよばれる現象にのみ原因的効能を付与する正当な理由は存しないというべきである。というのは、あらゆる現象は、規則的に結合されるかぎり、前なる現象に対しては結果と考えられるとともに、後なる現象に対しては原因と呼ばれうるからである。われわれはかかるラッセル的因果観の容認しがたい所以を、のちに論究するはずであるが、かりにそれを認めるとしても、物質に対してのみ原因的効能を帰属せしめる根拠の不明確なる点を指摘せざるをえないのである。ましてや、ラッセル的因果観をしりぞけて、われわれの正当と考える因果観に立つならば、およそ物の現象というものは、それが現象する場所の遠近を問わず、それが現象なるかぎり、原因的効能を有することは不可能なのであって、逆にそれはたんなる結果にすぎぬと考るべきものである。しかし、このような因果観の提唱解明は第三節(二)にゆずることにして、いまはただ、物質にのみ原因的効能を付与するという主張が、ラッセル的体系内部における不整合をしめすと考えられる点を注意するにとどめたい。
かくしてわれわれは、『神秘主義』の論文においてラッセルの試みた「物」と「物質」とを区別する思想は、かれの意図にもかかわらず有効な機能を発揮しえないことを認めざるをえない。のちの『外界の知識』(松下注:1914年初版ではなく、1922年の改訂版)では、もはやかかる区別の説かれなくなったのは、おそらくそのためであろう。ここでは、物理学の物質も山や石やテーブル同様に、センスデータからの論理的構成として説明せられる。ここでも現象相互の間に存する因果関係は重要な意義をもたされているけれども、しかしそれは、『神秘主義』の論文におけるごとく、「物質」が他の諸現象に対して有する一方的関係としてではなく、現象相互の同等な関係として理解されており、この理解に立ってすべての物理的な物を定義しようとする。すなわち、「物とは物理学の法則にしたがうごとき諸相の系列である」(pp.115-116)と説かれる。これに対し、この定義に相当するものを『神秘主義』の論文に徴すれば、そこではつぎのようにやや異なった表現が見出される。「物理的諸物とは、それらの物質が物理学の法則にしたがうごとき諸現象の系列である」(p.164)。ここに用いられている「それらの物質」、すなわち「諸現象の物質」という言葉は、「一物の物質」というごとき表現と異なり、ここだけで突然用いられた妙な表現のように思えるが、前後の文脈から推測すれば、この定義の意味はおそらくつぎのように解せられるであろう。まずここで定義せられる「物理的諸物」(physical things)とは物理学のいう物質を意味することは、この定義が「物理学における物質の持続性という概念」を検討した結果として到達されたものなることからも肯定せられるであろう(p.162)。そこでは、物質の持続性という問題が、既述の意味で物質とよばれる現象の連続性と物理的因果法則への適合性とによって説明せられる。したがってこのときの因果関係とは、物質から他の現象への一方的関係ではなく、いわば物質相互の間に成立するものである。換言すれば、たんなる現象一般ではなくて、物質に属せしめられる現象、つまり物の位置において見られる現象が、物理法則的に結合せられることによって、物理学の物質が構成せられるというのである。それ故定義せられる「物理的諸物」とは、自己同一的に持続すると考えられる物質のことであり、したがってそれを定義する文に現われた「それらの物質」とは、物質に属せしめられた瞬間的な現象を指すものと解せられるのである。が、このような定義が、「物」と「物質」との区別の廃棄とともに、『外界の知識』から姿を消したことは当然である。『神秘主義』の論文におけるごとき「物質」概念の消滅とともに、そこでなされた、一物の変化とその諸現象の変化との関係の問題も、もはや『外界の知識』では取り上げられなくなり、ただ諸現象の変化にもかかわらず、それらが同一物の変化と考えられる所以が、古き実体概念の代りに、変易する諸現象の間の連続性と物理法則への適合性という原理によって解明されることになる。前には物の近傍における現象の変化が問題とせられたのに対し、ここではもっぱら、変化する現象に見られる一定の関係から、自己同一的な「物」や「物質」を構成しようとする。--このような思想の変化が、『神秘主義』の論文における「物質」概念の包蔵する欠陥を除去して、以て思想の整合性と単純化を達成せんとするものであるかぎり、たしかにひとつの進歩であることは争えないであろう。
四 知覚と脳の関係
われわれの知覚し、ないし経験するものは、すべてわれわれの脳の内にある、という思想は、ラッセルの長き哲学的思索を通じて、終始変わることのない信念であるといえるだろう。ただこの信念の理論的な基礎づけに関しては、そのときどきの哲学的立場の変遷に応じて、かならずしも一様でないことは当然である。われわれのここでの問題は、すでに述べたごとき構成論的物体論の立場から、この信念にどのような根拠があたえられるか、を問うことである。ラッセルは二項で述べたような三つの場所の区別にもとづいて、「われわれのセンスデータが属するパースペクティブは、われわれの頭の内側にある」(Mysticism,p.155)とか、「われわれの私的世界はわれわれの頭の内側にある」(External World,p.99)という命題が、意味をもちうることを主張する。そのわけは、一方において、私的世界すなわち個々のパースペクティブの位置する場所、すなわちセンスデータがそこから現象する場所が定まり、他方において、諸物の位置する場所、すなわちセンスデータがそこにおいて現象する場所が定まるときは、当然この二つの場所相互の空間的関係を論じうることになり、そうしてわれわれの身体各部は山やテーブルと同じく一つの「物」にほかならぬ以上、それの置かれた場所と私的世界の属する場所との関係を問うことは、当然有意味であるはずだ、というのである。が、はたしてそうであろうか。
ラッセルは、私的世界が頭内にある、という命題が有意味であると言って、真であると断定しているのではない。ところでこの命題が有意味である、すなわち理解しうるものであるという意味は、この命題の真(または偽)なる場合とはいかなるものであるか、をわれわれが考えうる、その意味でそれが検証可能な命題である、ということであろう。ではわれわれは、私的世界が頭内にあることを、はたして検証しうるであろうか。実例についてこの問題を考えてみよう。わたくしが赤いリンゴを見るというとき、わたくしの直接知覚するものは、ある背景のなかである大きさのほぼ円い赤色をしたセンスデータである、といえるとした場合、ラッセルによれば、このセンスデータがわたくしの頭の内にある、ということになる。ところでこのときの「頭」とは、たんなるセンスデータではなくて、一定のセンスデータのクラスとしての「物」であるから、「頭の内」とはかかる「物」のおいてある場所の一部という意味になる。ところで「物」のおいてある場所とは、すでに見たごときパースペクティブの直線の交又点であるから、「頭の内」とはかかる点の集まりによってつくられた領域の一部ということである。一方、円い赤色等を内容とする問題のパースペクティブもラッセルによれば物理的空間における一点に位置するというのであるから、もしこの一点が右の領域の一部と合致するときは、問題のパースペクティブがわたくしの頭内にある、という命題が真となり、したがってそれは検証可能な、有意味な命題である、ということになるであろう。
しかし、ここで看過してはならない重要な一点がある。それはすでに二項において論じた、個々のパースペクティブと、それが占めるといわれる物理的空間(パースペクティブ空間)内の一点との区別の問題である。ラッセルはこの区別ないし関係について、かならずしも明確ではない。すでに引用したごとく、類似せる二つのパースペクティブの視点は空間的に接近している、とかれが言うときの空間とは、各パースペクティブ内の私的空間とは「全く異なる」ものであって、それは「だれも知覚しえず、もし知りうるとすればただ推論によってしか知りえない」ものである。もしそうとすれば、かかる視点を以て画かれるところのパースペクティブの直線、および直線と直線の相交る場所というものも、すべて知覚しえないものでなくてはならない。そこからして、パースペクティブの視点が知覚者の頭内にある、というごとき命題も、知覚によらず、ただ推論によってしか知りえない命題である、と結論せざるをえなくなるであろう。しかしラッセルが、私的世界は頭内にある、という命題が有意味であると言うとき、かれがこの命題を以て、だれも知覚しえず、もし知りうるとすればただ推論によってしか知りえないような事柄に関する命題であると看做しているとは思われず、またそのような意味の発言も見出せないのである。ラッセルをしてこのような不明確に陥らしめたものは何であるか。
思うにそれは、『神秘主義』の論文以来の、能うかぎり超知覚的なものへの推論を排除せんとする現象主義的要求に駆られて、物理的空間をも私的空間的要素から構成しようとする態度を完全に清算しきれないところから生じた不徹底ないし混乱であるといいうるであろう。そのために、一方において二つの空間を全く異質のものと断定しておきながら、他方では、物理的空間とは個々のパースペクティブを要素とするとか、「われわれの私的世界はパースペクティブ空間における一つの場所である」〔にある、ではなく〕(External World,pp.99-100 傍点筆者)とか、前掲の「これ〔一つのパースペクティブ〕が……元の硬貨がパースペクティブ空間にあった場所であるだろう」〔にあるだろう、でなく〕(傍点筆者)というごとき表現を平気で用いる結果となったのであろう。ところで、もしこのような意味において物理的空間なるものを私的空間からの構成と看徹しうるのであれば、私的空間が頭内にある、という命題を、検証可能な経験的命題と考えることが不可能ではないようにも思われる。が、実際は、そこにまた別の困難がわれわれを待っているといわなくてはならぬ。
もし右の言葉のごとく、一つのパースペクティブがそのままそれの物理的空間における場所であり、例の二直線の交わる所のただ一つのパースペクティブがそのまま物理的空間における「物」の場所であるとすれば、一つのパースペクティブが他のパースペクティブの内に位置する、とはどういう意味になるか。たとえばそれは、リンゴの知覚が知覚者の頭内にあるという命題は、円い赤色のセンスデータをふくんだ一つのパースペクティブが「知覚者の頭」という「物」のおかれた位置において見られる別のパースペクティブの内にあるというような意味であるか。もしそうとすれば、そのようなことがいかにして知られるのであるか。すでに述べたごとく、ラッセルによれば、二つのパースペクティブはどれほどその内容が類似しようとも共通の要素を有しえず、「したがってある心によって見られる三次元的〔私的〕世界は他の心によって見られるそれといかなる場所をも共有せず」(External World,p.96)、「それ故に異なる〔パースペクティブにおける〕現象を一つの場所に結合するという問題は生じない」(Mysticsim,p.147)はずであった。しかるに、わたくしのいま見るリンゴ的なセンスデータをふくむパースペクティブと、他方、わたくしの頭の位置において現象すると想定せられるいわば頭的なセンスデータをふくむパースペクティブとは、明らかに同一ではない。そして両者は別のパースペクティブであれば、共通の場所をもつことができず、したがって一方が他方の内にあるというごとき主張は、全く無意味と化するであろう。
かりに、わたくしが赤いリンゴを眺めている時の頭の状態を、他人が解剖学的に観察しうると想定した場合、かれの見るわたしの頭的なセンスデータをふくむパースペクティブは、ラッセルによれば、わたしの、ではなくかれの頭の内にあることとなるが、しかし同時に、わたくしの頭の位置において現象すると考えられるパースペクティブがあるはずであって、このパースペクティブの内に、はじめのパースペクティブ、すなわちわたしの知覚している赤いリンゴ的センスデータをふくむパースペクティブが存在する、というのが、わたくしの知覚するものがわたくしの頭内にある、という命題の意味でなくてはならない。けれども、この二つのパースペクティブは、いかに類似的であっても同一の場所を有しえない以上、一方が他方の内にあるというような命題はナンセンスといわざるをえないのである。
ラッセルをしてこのような無意味な命題を、にもかかわらず終生的信念として主張せしめているものは、結局、知覚についての因果的な見方であろう。この思想はかれが現象主義的立場に立ったときといえども、実在論的立場にあるときと同様に、かれによって不動の真理と考えられている。そしてかれは、それが現象主義的立場と両立しないかのごとき批評を受けるのは不可解だ、と難じている(The Philosophy of B. Russell, p.707)。この思想は、『神秘主義』の論文にあっては、センスデータの生理学的主観性とか、「物質」のもつ原因的効能というような考え方のうちに現われているが、『外界の知識』においても、かれは「一人の人の経験のなかで生起するものはことごとく、物理学的立場からすれば、その人の身体内に場所をもたなくてはならぬ。このことは因果的連続性を考慮すれば明瞭である」(p.219)と断定する。わたくしの見る星の知覚は、光波がわれわれの網膜に当って、視神経や脳にある過程をひきおこした結果であるから、それは脳の内になくてはならぬ。「わたくしは物理的対象を見ているのではない。わたくしの脳が位置する領域に物理的対象が産出した結果を、わたくしは見ているのだ」とかれは言う(loc. cit.)。しかし「物理的立場」とか「物理的対象」とかいっても、それは目下の立場においては、センスデータからの構成にほかならぬはずであって、それと別種の実在を含意するわけではない以上、「星」、「光波」、「網膜」、「視神経」、「脳」などは、すべて「星の知覚」と同じくセンスデータないしパースペクティブの語によって定義されなくてはならぬ。因果的連続性とは、これら諸種のパースペクティブの生起の時間的連続のことであり、「星の知覚」はその最終項にすぎぬ、というのであろう。しかしながら、わたくしが星を見る時はつねに、もし他人がわたくしの脳を観察したら得るであろうパースペクティブに一定の変化が見られるとしても、そのことがなぜに星の知覚が脳内にあることを意味するのであるか。両者はそれぞれ別の私的空間に属するものである。したがって、星的センスデータをふくむ私的空間が、脳的センスデータをふくむ別の私的空間--後者のうちには星的センスデータに対応するもの(同じものではなく)がふくまれるであろうが--の内に存在する、というのは論理的誤謬以外の何物でもないであろう。思うに、ラッセルの根本的な誤りは、わたくしが見る星の姿と、わたくしが星を見る時に(厳密には、直前に)それに対応して、わたくしの脳内に刻印されていると想像されるある変化(ないし星的な痕跡)とを同一視しているところに存すると考えられる。が、後者は、もしそれが存在すれば--存在するか否かは解剖学的な観察によって確めればよい--当然わたくしの脳の内にあるといえるであろうが、それはわたくしの見る星の姿とは同一ではなく(痕跡は星の知覚の条件である)、両者が別のパースペクティブに属する以上、相互の場所的関係を問うことは論理的ナンセンスにほかならぬ。
右のような背理を避けるためには、結局パースペクティブとそれの物理的空間における位置点、すなわち視点とをはっきり区別するほかないであろう。そうすることによって、一つのパースペクティブが別のパースペクティブを内にふくむ、というごとき背理を犯すことなくして、パースペクティブを一つの場所に結合することが可能となるであろう。その際とくに二つの場所に結合すると言って、一つの場所にあると言わないことに注意すべきである。一般に二つのものが場所的関係に立つためには、両者が同一の知覚的世界においてあたえられなくてはならぬと考えられるのに、'われわれは、そこにおいてパースペクティブとそれの視点とが合わせふくまれているような一つの世界を知覚することはできないのである。両者は次元を異にした二つの世界に属している。パースペクティブは自己の視点をふくみえず、視点は自己のパースペクティブをふくみえない。その意味で、「パースペクティブが視点にある」というごとき表現は、実は誤解をまねき易い表現であるというべきである。人が家にある、というごとき意味で、パースペクティブが視点にあるのではないからである。正確には、「あるパースペクティブがある視点と(因果的に)結合している」というべきである。この意味に解するとき、二つ以上のパースペクティブが同一の場所に結合される、というようなことも当然可能となるわけである。
それでは、かくパースペクティブから区別せられる視点とはいかなる性格の存在であるか。それはラッセルのいうごとき、なにびとも知覚しえず、推論によってしか知りえない底の存在であるか。(もしそうとすれば、一体知覚不可能なる存在をいかにして推論によって知りうるのであるか、という難問に逢着せざるをえぬであろう。)視点とはかかる形而上的存在ではなく、むしろなにびとにも知覚されうる存在でなくてはならぬ。なぜかといえば、それとパースペクティブとの因果的結合を、われわれは経験的に確かめうるからである。とはいえ、それは決して幾何学的な点のごとき存在ではない。広がりをもった私的空間が広がりをもたない一点上に位置する、というごときことは、もし文字通りにとるならば、理解不可能というべきであろう。かかる背理を回避する道は、視点と呼ばれているものが、実は幾何学的な一点ではなく、また私的空間が文字通りそこにおいてある場所でもなく、それはあたえられた私的空間の存在を因果的に制約するところの、それ自身ある大きさをもった物理的対象としての知覚者の身体的器官(眼、神経、脳等)の位置である、と解する方向に存するというべきではないか。しかしてそれが私的空間内のいずこにも見出せないのは、それが視覚的ではなくて触覚的なる対象たるためであって、点的ないし形而上的なる存在たるためではない。そもそもわれわれが、あたえられたパースペクティブについて、その視点を問題とするというのはいかなる意味であるか。観想的受動的立場に立つかぎり、ただ所与のパースペクティブとその自然的変易とが存在するのみであって、視点というごときものはどこにも見出せず、また考えられもしないはずではないか。これに反し、われわれが行為的制作的立場に立って所与のパースペクティブの意図的変革を意志するという立場に立つときに、そしてそのときにのみ、所与のパースペクティブを因果的に制約する条件としての感覚器官の位置が問題となるのである。視点とはこのような立場において見出されるところの、パースペクティブ変更の条件としての感覚器官の位置と考るべきである。が、このような行為的制作的立場に立って触覚的なるものと視覚的なるものとの区別をするのではなく(ラッセルももちろん、視覚と触覚との相関の重要性を説いているけれども--たとえば External World,pp.85088. --しかしわれわれのごとく触覚に物理的対象の構成のための必須的条件としての特別的地位を付与することなく、たんに視覚や他の感覚と同列において、それらの間の相関を論ずるにすぎぬ)、視覚的なるパースペクティブのみによって物理的対象を構成し、しかもその立場で知覚の因果的説明を展開しようとするラッセル的構成主義に立つかぎり、右に指摘したごとき困難からの解放を期待することはできないと思われる。
